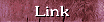(前略)
最近では、水泳部の男子シンクロナイズド・スイミングをテーマにした映画『ウォーターボーイズ』の舞台として知られる県立川越高等学校(川越市/1899年創立/第三中学―川越中学)。制服もない同校は、このような「本気の遊び心」が生徒のモットーで、そのあたりが浦和高校との違いだろうか。
川越中学に学んだ平和運動家吉川勇一(1931~/旧制浦和高―東大・文)は、共産党を除名後、65年のベ平連(ベトナムに平和を!市民連合)結成に参加、事務局長をつとめ、ベ平連解散後は予備校の教師をしながら、盟友小田実らとさまざまな形で平和運動に関わっている。現在の連合会長笹森清(1940~/明大中退)も同校出身である。
作家では、「浅見光彦」シリーズなどの旅情ミステリーで知られる内田康夫(1934~/東洋大・文)が筆頭に挙げられる。内田はコピーライター、CM制作会社社長を経て、四〇代半ばでデビューと遅咲きながらも、今では超人気作家として不動の地位を築いている。
1994年に『石の来歴』で芥川賞を受賞した後、『「我が輩は猫である」殺人事件』『鳥類学者のファンタジア』など純文学のジャンルに留まらない作品を手がける作家で近畿大学教授の奥泉光(1956~/国際基督教大―同大学院)、2004年4月、高遠菜穂子さん、今井紀明さんとともにイラクの武装勢力の人質となり、三日間の拘束の後に解放されたフリージャーナリストの安田純平(1974~/一橋大・社会―信濃毎日新聞)も同校の出身だ。
放送界には、日本テレビ系『ウェークアップ!ぷらす』司会の読売テレビ報道局解説委員辛坊治郎(1956~/早大・法)、サッカーへの深い愛情に裏打ちされた確かな実況を聞かせると評判のNHKアナウンサー山本浩(1953~/東京外大)、テレビ朝日アナウンサー小久保知之進(1970~/早大・政経)がいる。川越高校野球部のエースだった小久保は、〝伝統儀式〟ともいえる卒業式におけるパフォーマンスで、卒業証書を受け取る際、校長の目の前でお尻を丸出しにしたという逸話が残っている。
この野球部からは、プロ野球へも何人か人材を輩出しているが、なかでも現在ヤクルトスワローズに所属する杉本友(1973~/筑波大)は、97年にオリックス・ブルーウェーブ(現・オリックス・バファローズ)に入団する際、国立大出身初のドラフト一位として注目を集めた。
合格実績は、東大9名、一橋大7名、東京工大10名、早大104名、慶大30名、上智大36名と、県下の公立高では浦和に次ぐ位置を占めている。
(中略)
県立川越女子高等学校(川越市/1906年創立/川越高女)もまた人材の宝庫だ。東京外国語大学英米語学科からプリンストン大学大学院を経て、フジテレビのアナウンサーとして活躍、現在はTBS系『報道特集』のメインキャスターをつとめる田丸美寿々(1952~)、『ニュースステーション』から『スーパーJチャンネル』と常にお茶の間の顔でありつづける小宮悦子(1958~/都立大・人文)という二大女性キャスターを生んでいる。
雑誌『olive』などのファッションページや、家庭用台所洗剤のキャラクターなども描くイラストレーターの上田三根子(1949~)も同校の出身だ。
合格実績は、京大2名、一橋大2名、東工大3名、お茶の水女子大4名、慶大9名、上智大18名の一方で早大81名、明大83名、法大53名と、わりにバンカラな気風の私学への合格実績が高い。