|
(表紙)
「 先登録
川越図書館蔵 」
弘化三丙午年閏五月二十七日朝五ツ時頃、異国船三崎城か島沖江程近く乗込来る趣、三崎町久野又兵衛手代安五郎と申者大音に御陣屋内往来触廻る、其時御陣屋一統三島浜江面々手鎗にて押出し、直様船の仕度致し乗出る、即〔予〕乗合の士十二人、城か島沖江乗出し候処、風波強く進も〔水主〕手間取り、や(よ)ふやふ三里半程も南の方へ乗出し候処、異船二艘近く乗込来る、予乗上り候船ハ先ニ(江)乗込来りた(ケ)る、近くに相成見るに異人一統白装束にて小筒の先ニ剣を付、鎗のことくして立並ひし有様ハ稲麻(摩)竹葦のことく何のこともなく、白装束故白鷺の集りしことくなり、予〔か船〕異船へ乗付、されとも未た二間程へたゝり居候得共、異船より腕木二間程も出居候に、高さ二間程高く鎖張りて有之に、予飛付とひ上らんとする処に、右の鎖ゆるみて海中江両足踏落し、されとも身をかへし異船の大筒足たまりとして二番乗の内予壱番に乗上る、続いて作(佐)治政記・片手たんみ(片平克美)押上る、其余ハ次第次第に押登る、二番乗の面々壱番乗の船に三尺も予か船後れ乗付候を残念に存、二番乗の面々の抜身の下をかいくゝり無理に飛入申候、一番乗の(り)面々ハ上る場所より多く上る、二番乗ハ大筒の矢さまより飛込申候、予直様大壱番に膝の御船印もち上り四方を見廻し候処、東方松下総守様御人数三方より押来る、又北に当て浦賀御人数押来る(候)、右の御船印持上る処、異人大勢集り〔来り〕、異船よりおろせおろせと申手真似にて、何れ(か)ハア(はう)ハアバアバア申、予か持居候御船印に取付大勢大さわきに候間、予片手に御船印を持、片手にて手真似に親指を出し候得ハ異人静まり申候に付、猶又親指を出し○う(ヲ)と申手真似いたし〔候〕、予か鼻へ指差、壱番に上り候印に(を)建ると申手真〔似〕いたし候ヘハ、早速異人承知致候に付、異船のみよしの方へ罷越し右の御船印をふり廻し申候、直様異人共御船印を手伝ひ、みよしに(へ)立呉申候、予異人に向ひ世話に相成候と申手真似いたし、これハ手伝呉候間挨拶也、其時異人御船印に指差日本法と申候、予親指差出し頭分ハ何方に罷在哉と申手真似致し候へハ、異人予か(の)胸を取候に付、打捨置一覧致居候得ハ、其侭異船のともの方江召連、高き処へ案内致し、頭分とおほしきころものことき衣服を着し罷在候男の前江連行(召連)候処、亦々同様予か(の)胸を彼の頭分の男取り候に付、前書の通り打捨置候処、上座の方江座し候様頭分の男手真似いたし、頭分の男挨拶の礼ニ相(と)見江、手を合右の手を差上け申候に付、此の方にても日本通り挨拶致し候、頭分の男横文字を認め出し候に付、予不知と申心持にて頭をふり申候、乗船致し候面々、予をはしめ一統手拭をまき、帆をまけと申真似致し、或ハ陣羽織ぬきてまく真似致し、帆をまきし(候)様大勢にて〔度々〕申聞候得共、一向に異人相集り居候ても取合不申候、先方にてもかてん不参様子にて有之候、予をはしめ四五人申合、頭分の男の手を取り帆柱の側に(江)召連参り、帆をまく真似いたし、観音崎の方江一統指差、亦異船の大筒江指差、数々並へ有之、彼(あの)地江乗込候はゝ、此船みちんに打破ると申手真似、其上我々共(等とも)腹切候、果てすハ(半てハ)不相成と申手真似致し候へ共、〔左候得者〕腹切よりハ片はしより切倒し申候と手真似いたし候得ハ、頭分の男驚き候様子にて、やふ(よふ)やふ(よふ)の事にて先方承知致し、彼の男大船の方江指差、大船に帝居の旨、大船〔の方〕止候はゝ、此船供(友)ふねに付留り可申〔候〕旨手真似致候て、早々(く)大船の方江誰なり日本人の内罷越、右の訳申呉候様子(ママ)手真似にて申聞候、並に日本〔人〕腹切と有、夫より異人を片はしより切候と日本人申候間、早々大船止り候様申呉候様にと頭分の男頼有之〔候〕に付、直様船手組を大船の方江差遣し、右の様子(右之場)を日本人乗船の面々江申遣候ヘハ、先方乗船の日本人承知の旨答有之、間もなく大船の方帆をまき、野比浜沖江船を止、右に付此方の異船〔の〕頭分の男先の船止候間、此船帆をまき留る間安堵いたせる也(と)申手真似致し、日本人の気を休め居(候)様にと申手真似致し候、彼〔の〕男船奉行ともおほしき男を召呼、何れ(か)下知致し申伝候ヘハ、船奉行の男短き笛を吹き候ヘハ、水手の人々帆柱又〔ハ〕帆縄〔縄〕ばしこ江登申候、右の船奉行日本にて相用(申候おら)ふると申様なる銀にて拵申候 (挿図あり) ことき此(如此)の二尺計の物を口江当て、色々申差図致し候ヘハ、早速に帆をまき申候て、同様野比浜に船を止る間もなく、亦々頭分の男横文字其外色々わかり不申手真似いたし候間、此方にてハ相知れ不申と申〔候〕手真似、横文字も同様不知と申手真似にて頭をふり候得ハ、頭分の男何れ(か)外〔之〕異人に申付候得ハ、間もなく人物も違ひ候人下より〔三人来り、頭分之男に何か礼とおほしき様子にて〕手を合、両の手を差上〔申〕候得ハ、頭分の男頭を少し動し〔申〕候て、文字認め候真似致候ヘハ、右三人の内二十二三歳の男、此方江向〔て〕日本と認出し見せ候に付、夫て(ニて)ハ相知れ〔申〕候と申手真似一統にて致し候得ハ、右の三人頭分の男に向何れ(か)申候、右三人はけし坊主にて髪の長き事、三四尺ともおほしき右の毛を三〔ツ〕よりに致頭をまき居候、右の二十二三歳の男、紙と白箸の様なる物を持来り、右の白箸の様成物を小刀にて四方をけつり、筆の様に致し、右の品にて文字を認め申候、右の箸の中より墨出申候、予軍船何如と認、右の男の前に(江)差出す、右の男認るハ蘭地花旗軍船、水手壱百五十〔余〕人、帝名ハ日本不敵と答ふ、予又問、皆同国か〔ト〕申手真似にてとふ、右の男南京〔人〕三人、亜利加五人、あとハ同国外黒ん坊と申手真似にて黒ん坊江指差す、予又問、名ハ何と申、国ハ何と云と申心にて国と認め出す、南京人と右の男答、〔予〕又問名と認出す、南京人答名ハ信と答、予又問、位〔ハ〕と認め出す、南京人答〔に〕大夫下々と答、予又亦問、孔子を不知哉と申心持にて問ハ孔子と認め出す、南答ハ万国聖と答、南京人日本の婦人人形をひいとろの鏡の内ニ絵書有を持出し為見〔申〕候、其髪形島田の女ニ眉なく、歯を黒く染し女の形を出し、南問、歯を染め眉を落し候ハ何如(義何故)ぞと〔問〕、予答二と不嫁印と認出す、南聖国と認出し右の手を差上る、予大筒に指差、人の国江武器をかさり大面にて罷越候ハ(義)格外不礼なる儀と存候に付、南京人に向不礼と認出す、南答〔に〕大筒江指差不動と申手真似致し候、南京人赤面の体ニ有之、且亦日本人乗船致候面々一統ニ腰兵糧を遣ひ候処、異人大勢相集まり見物致し居候て、其節異人日本〔之〕米宜きと申手真似いたし、先方の米を持出し見せ申候処、此方一統にて一覧致し候に(所)、異国の米細長くしてしゐな米のことく有之候、此方〔一統〕兵粮〔を〕遣ひ仕舞候節、異人きやまんの湯桶の様なる器を台にのせ持出し、同しきやまんの桔梗の花のことき茶碗を、是又(亦)台に載せ持参り、此方の面々江向、食事致し〔候〕て後ハ水を呑候ま(半)てハ落付不申と申手真似致し、自分(ら)毒味致し候間(て)、日本人一統にて呑み(江為呑申)候、右此方一統兵粮入れの(物)明に相成候時に(ニ付)、兵粮方役人稲田弥次右衛門〔と申者兵粮を持来り、右弥次右衛門又〕申候にハ、兵粮差上可申間、御面ニ(之)入れ物一まとめ〔に〕致、〔異船より〕此方の船に(江)なけ落し候様申〔候〕に付、即ち〔一まとめに致し〕なけ落し〔申〕候処に、早速に右の入物江兵粮を入、又一まとめにいたし竹の棒の先に付、異船に(江)乗込み居候面々江相渡可申と、下より差出し候得ハ、上にて請取候を(申候へ者)、異人以ての外立腹の体にて、何れ(か)不分義をわアわア申、元の弥次右衛門の船へなけ戻し〔申〕候に付、此方〔一統〕相談致し高石園(円)治頭分之男の前ニ(江)罷越し、食事致し候真似いたし候て、何卒右の品を上けさせ呉候様、手を合せ頼み候得ハ、異人大勢打寄頭分の男ニ向、火薬と存候に付、先の船江なけ落し申候旨、異人手真似いたし候、左様致し候と頭分〔の男〕此方一統に(へ)向、手真似にて兵粮をなけ落し候ハ不礼致し候旨手真似にて挨拶有之、其上早速ニ兵粮を為上可申旨、厚く手真似にて呉々挨拶に及、全く火薬と心得申候故、失礼致し候と手真似致し候、此方にてハ予罷出、挨拶も不致兵粮を船中江入れ候〔義〕ハ不宜と申手真似にて挨拶致し候、早速異人縄を下け兵粮を上け呉候、且又菓子の類其外食物〔等〕異人持来り、一統江呉申候、一々毒味いたし呉候事に候、頭分の男何れ(か)外の異人を〔召〕呼申付候て、早速ニ六角の〔形の〕ぎやまんの徳利と、日本にて水呑の形の様なる銀の器を添、台に乗せ持来る、頭分の男右の器に酒の様なる〔一〕物をつき〔込〕毒味致し、浦賀同心江遣候、其節南京人つぎ役ニ〔て〕有之〔候〕、南一物ニ指ざし小酒と認め出す、此方一統一礼す、其節頭分の男右の〔銀の〕器にて三ツ呑み候と、よろけ申と云(ゆ)ふ手真似致し、伏すと申す真似致し候、浦賀同心一ツ呑て頭分の男江戻す、頭分〔の〕男二ツ続けて呑み、一統江と申手真似致し〔一統江〕為呑申候、〔右ニ付〕南京人小酒と認め出し候に付、予考ふるに大酒も有之〔可申〕哉と存候に付、南京人に向ひ大酒と認め出す、左様いたし候へハ、南京人頭分の男に向、何れ(か)不分義を申候へハ、頭分の男承知致し候様子ニ候ヘハ、南京人亦同様〔之入物〕に入持来り、頭分の男の前ニ置く、頭分の男又々毒味致し、銘々江と申手真似致し候ヘハ、南京人銘々江持あるき為呑申候、日本にてみりん酒の様ニ有之候、其後頭分の男箱を持来り、中より猩々緋のふくさに包み有之候一物を取出し候、一覧致し候に、天鏡とおほしき八方に遠鏡を籠の様なる物の内に掛けて有之を色々〔に〕動かし、又下に磁石の様なる一物を台にのせ、合せて見て、予あやしく存候に付、天鏡かと申手真似いたし候へハ、先方手真似にて、しかりと答、予無用にいたし様ニ日本の法と申〔手真似致候〕、手真似にて右の品〔を〕仕舞候様申候ヘハ、其内ニ右之品損〔し申〕候間、異人右〔の〕品仕舞申候、其後頭分の男参りか様(候様に)と申手真似にて、予の(か)袖を引候に付、松下総守様御内後藤五八、並に予の(か)船差配の男千助と申者一同にて下のはしごの側を伝下り候得ハ、南京人先案内致し、夫より〔右〕三人一同(同道にて)罷越候へハ、其後ニ(者)続いて頭分の男附添来る、二段目江下り候入口はしこより〔予〕下らんと致し候得ハ、右入口固め居候異人予に向ひ(て)、予か刀江(に)指差し、長く有之間、定〔て〕しやまに相成るべくと申手真似致し、預けて下江おり〔て〕、見物いたせと申手真似致し候、予も手真似にて、日本〔の〕法と(に)て帯すと申し〔手真似にて〕答ふ、夫より南京人一人頭分の男、並ニ此方三人にて、二段目江下り一覧致し候に、小筒数百挺、帆柱の廻りにかさり有之、鎗も同様数百本立てならへて有之、其節頭分の男小筒を取て打ツ(候)真似〔を〕いたし、打候(て)後ハ鎗に致〔候〕と申真似致候、〔予〕一覧致し候にすりわり無之に付、すりわり無之旨〔を〕手真似致し候へハ、又すりわり有之筒を取出し〔申〕候、玉目二匁五分位と存候、鉄炮の長さ五尺位、火皿の処〔ニて〕火打石・火打鉄有之、引鉄をひき候とすれ合火出る、鉄砲の先江(へ)剣を附、鎗の様ニ致候、剣の長さ二尺位〔に〕有之候、右の剣を平生ハ皮の袋に入て腰ニさし居り申候、右の鉄炮打真似、又ハ鎗にいたしつかひ候真似なと〔いたし候義、誠に以〕色々様々の真似致候、〔此所〕ハ筆にて難及候、殊の外利方ニ御座候様存候、其節側らの鎗一覧致候処、殊の外手薄ニ有之候間、突ク間敷と申し手真似を〔予ハ〕致し候ヘハ、頭分の男、南京人に向、何れ(か)申付候ヘハ、南京人かめのことき一物を持出し、予一覧いたし候に、目はり〔いたし〕有之、右南京人ふく面をかけ、右の目はりを切、中より先つ日本にてきん出し油の様なる物を匕に掛て為見候に付、予側江寄一覧致しに未(候半)と存じ候て近より候処、南京人手真似にて無用々々と申〔手真似致し〕候間、予をはしめ後藤五八並千助、頭分の男の側へ罷越候ヘハ、頭分の男右の品を槍にぬりて突といふ真似致し候、右の一物ハ毒薬と相見江申候、夫より頭分の男並南京人両人にて、廊下の様なる処江案内いたし候間、〔予を始右之面々〕参り候処、大の男五人曲□(録ヵ)に腰をかけ、一人ハ書見いたし居候、二番目の男、予に向、腕を差出し〔手を〕ねちり見候様手真似致し候に付、〔予も〕当惑いたし候へ共、甚残念に〔存〕候間、予の腕を差出し、予か腕をねぢり候得と申手真似いたし候ヘハ、右の男立上り、予の(か)手を金剛力を出しねちり申候、予其時一生一代の力を出してかまん致しこらへ(い)申候仕合也(に)、ねちれ不申候、予格外骨折れ草臥申候、夫にて其処を行過さんと致し候処、右の五人何れ(か)バアバア申〔候〕に付、予足を止め、かへり見候得ハ、末席ニ罷在候男、少々腹立の顔色にて眼玉をいからし、予をさしまねき候ニ付、又〔右之〕五人の前ニ罷越候得ハ、右末席の男、予の(に)〔向予の〕腕〔を〕ねちらせ候様、前(先)の男にねちられす(ねしれざる)〔義〕を残念と申し手真似致候て(者)、是非々々ねちらせ候様頼み度〔々〕手真似致し候、〔予〕考へ候に最初の男に仕合せとねちられず候を、大仕合致候を了簡いたし居候処江、又々末席の男、予か(の)腕をねちらせ候様申かけられ、当惑の至、殊に最初力を出し労れ候事〔故〕、右別て難渋致し候、無是非次第腕〔を〕差出し〔腕〕おれる迄ハかまん致さんと〔存〕、腹中にてハ神仏を頼み居候、右の男最初ねちれす候を腹立故、力声を上、予の腕をねちり〔申〕候、予も又一生けんめいの力を出し、異国の人に腕をねちられてハ残念なりと存、かまんいたし候、既にあやふく候へ共、やふ(よふ)やふの事にてこらへ申候、ねちれす仕舞候〔段〕大仕合致し候、其節最初にねちり候男、手真似にて(致し)、予の事を小男にてもねち〔ら〕れ不申と申手真似致し、右五人の異人をはしめ、頭分の男・南京人大笑ひいたし候、予ハ腕を出して、もつとねちて見候〔様〕、異人の前に(へ)差つけ(出し)候得ハ、異人共頭をふり、ねちれすと申手真似致候、予もあまり腹か立候間、先方にて力ちまんいたし候を(義)、こしやくな奴と存候に付、〔兎角〕子供の(か)人差指をまけ動して、馬鹿々々と申義を〔予〕真似(手真似にて)、先方力しまん致し候ても、此男の腕ねちれすと申手真似〔致〕、右申馬鹿々々と申手真似致し候へハ、異人共頭の上江手をあけ、先方にても大笑ひ、此方にても大笑ひ致候、夫より頭分の男と南京人案内にて、武器蔵とおほしき処江〔召連〕参り〔候ニ付〕、色々の品〔右申三人〕一覧致候処〔江〕、野中猪濃八参り、〔夫より〕処々一覧致候、〔夫より〕予後藤五八江申候ハ、兵粮・玉薬・水一覧致度、何程有之候哉、戦にも及候節ハ心得方にも相成候かと存候旨相談いたし候得ハ、五八も落合〔申〕候に付、頭分の男に両人に(し)て食事致〔候〕真似いたし、何方に有之哉と申〔手真似いたし〕候へハ、頭分の男・南京人、又下の段江案内致し行見候ヘハ(下りてみれば)、番人一人罷在候、頭分の男食事の真似致候て指差候に付、予並〔後藤〕五八・千助三人にて一覧いたし候へハ、何分あけ(上ケ)板の下に有之〔候ニ付〕、積込有之(ニて)場ハ十畳敷位に〔有之〕候、右の兵粮を為見候様手真似致し候ヘハ、南京人取出し見せ候処、かますの様なる入物に有之中より出し候ハ、抹香の様なる食物とおほしき物を持出し候間、〔予并後藤五八両人にて〕南京人に問、食物に致し候哉、何に(と)いたし〔候〕やと手真似に〔て問〕、南京人中段に(江)上り、菓子の様なる食物を持来り、右の品に拵へ食物に致すと申手真似致し候、右積込あれとも深さ知れす候故(不申候ニ付)、五八と相談致し、棒を差込見候ハヽ(江者)、大凡見積も付候か(半)と〔予吾八江申候得者、尤のよし答、予〕南京人に向、棒をかせと〔申〕手真似〔を〕致し候へハ、早速に鎗のおれの様なるを持来候に付、〔予〕かますの間に(へ)差て見候に、四五尺〔棒〕通り〔申〕候、側(脇)を見候得ハ大成樽有之に付、何に候哉と〔申〕手真似いたし候処(江得者)、一覧致し〔候〕様〔先方手真似致候〕に付、樽の内を改め見に(両人にて一覧致候所)、梅すのことき物に有之、此方の(是ハ日本にて)醤油の様なるもの〔か〕と被存候、予又腰の兵粮を取出し、頭分の男に為見候て、此品ハ有之哉〔と〕、又外ニ食物ハ無之(き)哉と問(ゆふ手真似致)候ヘハ、〔早速に〕上け板を為上見せ候処、二斗俵位の入物〔に〕五六俵分も有之候、頭分の男〔手真似にて〕食物此余ハ生物の外(ハ外に生物より外に)無之候(と申)手真似いたし候に付、後藤五八、水と申字を書(認)、南京人の前に差出し候ヘハ(出ス、左様致候得者)、又元の二段目江(へ)案内致し候処(ニ付)、〔五八并千助・予罷越候所〕大樽十七八の内七ツはかりハ水有之候、外ハ並へあるはかり、又重ねて有之樽ハ数多に御座候、(大樽拾七八有之、水七ツ計ニ有之候、水ハ並へ有之計、あるひハ重て有之候、数々にて御座候、)夫より玉薬一覧致し候に(致度旨手真似致候得者)、二段目のともの方に六畳敷程もあるへき(可有之)蔵の様なる処に〔案内いたし候ニ付、罷越一覧致候所〕、かますのことき物に焔硝を入、其数二百余も有之へくやと被存候、又玉〔を〕と申〔手真似致〕候得ハ、大筒玉ハ日本人見る通上段に有之外ハ(に)無之〔と申手真似致候〕、大筒玉ハ五六百可有之やと被存候、小筒玉ハ(小筒の玉と申手真似致候得者、案内致候ニ付罷越一覧致候所、)素麺箱のことくなる入置(箱に玉有之)、箱数三ツ、其内壱箱ハ半分程有之候、夫より以前の上段の高き処江(へ)〔予を始両人打〕登り候、〔予下の方を見るに〕佐治政記一二三より十迄書認、南京人に向、右の一二をよみ問〔に〕、一二(イチニ)と〔段々政記〕よみ候得ハ、南〔京人〕かふり(頭)を〔横に〕振〔候へ者〕、又一二(イチジ)とよみ候ても、かふりを振候、南夫より読み聞かせ候ハ(又政記一二(イツジ)とよみ候得者、先方同様頭を横にふり候て、南京人政記によみ聞せるは)、一をイッケン、二をリヤンと、拳の言にて有之(段々日本にてけんとか申事と同様に南京人申候と)、側に野中猪野八罷在〔候〕て、〔猪野八〕南〔京人〕二(リヤン)迄申し〔候を〕、三より十迄〔猪野八ハ〕指を折りて、〔日本にてのけんの言葉を〕彼(南京人)より先に早くよみ(先へ申)仕舞候ヘハ、〔南京人〕恐れ候様子に御座候、夫より〔野中〕猪野八と〔予〕両人にて黒ん坊の側へ(に)罷越、〔両人にて〕能々見(一覧致)候処、頭ハ〔一面に〕ちゝれ毛にて、耳に金の○(輪ヵ)をはめ居候、〔能々見るに〕黒きハ油薬の様なる物をぬり付居候様ニ見受け〔候間、猪野八ニ余向、黒ん坊ハ〕何れ(か)〔ぬり居候よふ申候へハ、猪野八〕ぬりたるかと〔申〕手真似致し候へハ、黒ん坊ハ笑居候〔ニ付〕、猪濃八〔自分〕指を口中にてしめし、黒ん坊の手をこすり候得ハ、〔右の〕油薬の様なる物はけて白く相成〔申〕候、黒ん坊をはしめ異人共大勢大笑ひ致し候、何のためにぬり居る(候)哉解せ不申候、〔兎角〕異人共此方一統江(に)向、ダチンコと申し(候)、色々の品を持出し〔申〕候処、〔此方にてハ〕其訳一向〔に〕相分不申候処、南京人来りて売買と書認め候(出す)、それにて取替呉候と申事と〔一統〕承知致し、取替の義ハ日本の法にて不致趣を手真似にて〔先方へ此方一統〕相断〔申〕候、〔左様いたし候得者〕南京人セツベン(ぜつへん)と〔申候〕大金銭等を取出しゼツヘンゼツヘンと申し(ハ)、日本人に遣し候と申手真似〔致候〕に付、是又同様不貰旨相断〔申〕候、〔其後〕南京人丹下左市に向、おしいおしい(おじいおじい)と申、〔南京人左市の〕歳を問に、右の手をひらき、左の指にて右の指の通りを横にはらひ、五十〔歳〕位かと云(問)、左市〔自分の歳の数を〕手真似にて答、南〔京人〕健と申真似致し、又南〔京人〕下曽根董に向〔歳を問〕、両手をひろけて〔又〕片手をひろけ、十五〔歳〕位かと問、董手真似致し(にて)、年の数を答、南〔両人手真似にて〕誠にちさし(ちいさい)と〔申〕手真似いたし、側の董の歳位の異人を指し(其側に異人董位に歳ともおぼしき男罷越候か、南京人右之男に指取(差ヵ))、又董に指差し、両手にて同しと申〔手〕真似致て(候)、是ハ同歳と相見え申候、右の異人(男)ハ予より七八寸も身の丈高く候、乍去(御座候得共、)面形ハ子供の様に有之候、夫より異人〔大勢〕夜分に相成候間、寝ると申真似致し、首を(にても)かゝれ候も計り不知と〔申〕真似致し、此方一統江異船より下り呉候様、是ハ用心の為と〔申〕手真似致し候、其内又二段目の方(かた)より鉄砲〔の〕先へ剣を付、大勢参り此方一統の後江(へ)廻り、右の鉄炮を横になし、〔日本人を〕押出さんと致候に付、〔此方一統色々の手真似いたし〕乗上内(り候)人数計ハ此船に(江)置呉候様〔一統手真似致し、此方にても〕此船夜の内に沖へ乗出し候も難計(計不知)に付、成へく〔ハ〕乗船致し居度と、色々手真似〔にて〕致し候ても一向に〔先方〕聞入申さす、其内〔に〕先方少々荒立る様(候)に付、御番頭江右の段申遣し、如何可致哉と聞合(申遣)候、〔其〕内、猶々異人あら立候に付、一統異船より下り申候、予と藤井新八郎両人残り、異人頭分の男に向(の前へ罷越)、両人計りも(にても宜有之間、)此船に為居呉れ様申〔手真似にて致〕候得共聞入不申、荒々敷はアはアと申候、〔其時に〕外の異人予に向、〔手真似にて〕今朝御船印を持上り候〔手真似致し〕、此船江入(人の)国の器を上け候ハ法に無之、されとも日本の法にまかせて上けさせ候〔と手真似致し、予に指差日本にて申せは〕、其様申(候)事ハ聞訳〔勘弁いたし、御船印を為上候間、此方申事をと申手真似いたし、唯今異人申事を聞分〕呉候様船の法ニ無之旨手真似致し候、〔右ニ付両人共下り呉候様手真似にて申候、予も〕右の〔理〕利を被申当惑致し候内、(其内に)御番頭より異人荒立候てハ不宜〔候〕間、異船より下候様申越候に付〔両人異船より〕下り候、後にて〔予〕自分の陣羽織を見候得ハ、見返ニ刃物にて切候様〔成るあと有之、少々計〕切れ居〔申〕候、〔予考へ見るに〕是ハ定めて異船へ飛乗り候節か、又予と新八郎〔に〕異船より下り候様にと〔異人〕申〔候〕節、鉄炮の鎗横に致し押し候時(節)、穂にて切れ候義〔か〕と被存候
一異人共日本日本と申、鏡一面持出し為見〔申〕候、並の鏡に御座候、裏ニなんてんの図あり(有之)、藤原政清と銘有之(名あり)、〔日本の鏡〕如何して所持候哉〔げせ不申候〕
一日本日本と〔申〕日本の絵図と〔も〕おほしき〔図〕を持出し〔為〕見〔申〕候、横文字〔故誰にも〕不知申(知れ不申候)、只〔々〕日本日本と申〔候ニ付、日本の絵図存候〕絵の形も日本の国の様に覚え候
一歳取り候人をおぢい〔おぢい〕と申〔候〕、又日本と申〔事を申候〕、又物を見せよ(候へ)と云ふ(申)事を見せへと申〔候〕、法式〔なとの事〕を法と申候、此の(等ハ)日本の言葉と同様に有之候
河越藩 内池武者右衛門記(書)之
是ハ異船江乗上り候に付、船中か有様を文字文章をかさらす、其侭に書記し、家江蔵し子孫に残し置かんと欲するのミ
(これハ異船江乗上り候ニ付、文字文章をかさらす、子孫へのこし置んと存るゆへ記し、家に蔵せんと欲すのミ)
|
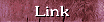 川越市立図書館のデジタルアーカイブで画像を公開しています。
川越市立図書館のデジタルアーカイブで画像を公開しています。
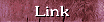 国立公文書館デジタルアーカイブから画像をダウンロードできます。→「川越藩内池武者右衛門異国船風聞」または「内池武者右衛門」で検索。
国立公文書館デジタルアーカイブから画像をダウンロードできます。→「川越藩内池武者右衛門異国船風聞」または「内池武者右衛門」で検索。