
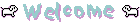


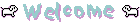


●江戸幕府に重んじられた川越
東京の近くにいくつか興味深い城下町が残っている。 いずれも、幕府が頼りにする親藩大名や譜代大名の小藩をおいたところである。
川越は「小江戸」とよばれる小ぢんまりした町で、関東平野の外れに位置している。もっとも、近年の開発によってそのあたりまで住宅地になってしまった。
川越を代表する観光地に五百羅漢の石像群で知られる喜多院がある。 そこは、関東の天台宗の総本山で、徳川家康の関東入国のときに、彼の補佐役であった天海僧正が来住したところである。
現在の建物の多くは、寛永16年(1639)につくられたものである。後で述べるように、川越の町の発展と新河岸川の水運とは切っても切り離せない。
喜多院の建物の中の庫裏、書院、客殿は、江戸からわざわざ新河岸川を使って運んだものである。 徳川家光は、寛永16年の喜多院の再建にあたって、江戸城紅葉山にあった慶長期(1596-1615)の建物を解体してわざわざ川越に移築している。
このときの客殿の中に、家光誕生の間といわれる12畳半の部屋がある。また、喜多院の中に徳川家康を祭る仙波東照宮があり、それは久能山、日光とならぶ三大東照宮とされる。 こうしてみると江戸幕府が川越を重んじたことがつたわってくる。
川越は、戦国時代には関東平野を押さえる要地とされた。 この地をめぐって川越夜戦が北条氏康と両上杉氏とのあいだでくり広げられたこともある。 これは、川越の水運の便と、そこが荒川沿岸を押さえうる位置にあったことにもとづくものだ。●水運とともに栄えた川越の城下町
川越藩は、家康の江戸入城が行なわれた天正18年(1590)以後まもない時期に、酒井重忠によって開かれた。 ただし、重忠は1万石の大名にすぎず、彼の詳しい経歴は明らかではない。
酒井重忠は慶長6年(1601)に、上野国に移っている。 その後、重忠と別系統の酒井氏と堀田氏をへて、寛永16年(1639)に、松平信綱が川越領主になる。
彼は、長く老中職をつとめた。信綱が伊豆守の官名をもっていたため、信綱は「知恵伊豆」とよばれた。 四代将軍徳川家綱が最も頼りにした補佐役が信綱であった。 松平信綱のときに川越藩の領地は7万5000石になった。
松平信綱は、正保4年(1647)に新河岸川に河岸場を設けた。これは、川越藩の領内の米を江戸に運ぶ船着場として大いに役立った。
のちに、河岸場は上下に分かれ、上新河岸、下新河岸とよばれた。さらに、新たに寺尾、牛子、扇河岸の船着場がつくられ、それらは、「五河岸」とよばれ、いずれも川越藩の外港として繁栄した。
藩の物資だけでなく一般荷物が輸送されるようになったおかげで、川越の町が大いに繁栄することになった。
川越の市役所の庁舎が、江戸時代の川越城の西大手門にあたる。そして、その東方がかつての川越城の本丸で、中心部には本丸御殿が残っている。
その建物は、嘉永元年(1848)に建設されたものである。このころの藩主は松平斉典で、当時の川越藩は、17万石にまで成長していた。 斉典の系統は、松平信綱とは別の家筋である。川越藩主の家は何度も交代している。
本川越駅から約500メートル北方の仲町が、かつての城下町のはずれである。 その北方の元町、幸町、仲町の一番街の通りには、いまでも蔵造りの建物が数十軒ある。 もっとも、その多くは明治時代に立てかえられたものである。江戸時代の建物は、明治26年(1893)の大火で焼けてしまったものが多いからだ。
札の辻の近くの大沢家旧宅は、寛政4年(1792)に建てられた、川越でもっとも古い蔵造りである。
札の辻は、城下町の中心街として、高札が立てられたところである。ここから北を喜多町、南を南町という。 江戸時代の川越の町のほぼ中心に、時の鐘の塔が残っている。それは、時刻を知らせる鐘を打つために松平信綱が設けたものだ。
ただし、いまの時の鐘は、明治の大火の直後に再建された新しいものだ。 再建にあたっては、もとの形式を忠実に踏まえた高さ約16メートルの木造の塔が建てられた。
川越の西方に、川越館跡がある。それは、平安時代末にそこを押さえる武家、川越氏がつくったものだ。 現在、一辺約200メートルの土塁が館跡の西側に残っている。北側と東側にも土塁の一部がみられる。
時の鐘
高さ十六メートル余の古風な櫓が、蔵造りの町に立っている。現在の櫓は明治二十六年の大火のあとで再建されたものだが、時の鐘は三百五十年前の寛永年間からこの場所にあって、城下町に時を報せつづけてきた。
幸町と名は変わっているが城下町の頃の町名は箍町、桶作りの職人たちが住んでいた町で、当時の川越十ヵ町のちょうど中心に当たり、鐘の音は四方へまんべんなく響いたという。
時の鐘が鳴らなくなって、もう久しい。→(現在は日に4回鳴ります)
川越城址
城内の三芳野天神の裏に大杉があった。毎年初雁が、その真上で三声鳴きながら三度回って飛び去るところから、別名を初雁城というやさしい名前で呼ばれてきた城である。
室町時代に太田道真・道灌父子が築き、江戸時代の寛永十六年(1639)、松平信綱が大拡張をしたが、現在はわずかな濠跡と本丸御殿・富士見櫓などの遺構を残すだけになっている。
本丸御殿は幕末の嘉永元年(1848)に松平斉典が建てたもので、当時の十六棟の建物のうち玄関と大広間の一棟が、十七万石の格式をしのばせている。
江戸幕府にとって重要な城地だったことは、城主から大老二人老中七人を出していることからも判る。それだけに維新後、破壊されるのも早かった城だった。
蔵造りの家
川越には「江戸」が残っている。
間口四間の蔵造り、一文字暖簾に屋号を染め抜いたこの菓舗(亀屋)は、江戸時代創業の老舗である。厚さ二十センチに及ぶ土を使った重厚な造りの店蔵――浅葱色の朝空を初燕が切って、どこかで苗売りの声が聞こえそうだ。
喜多院
正月三日は、元三大師良源の入寂した日に当たる。天台の古刹喜多院ではこの日が初大師、境内には縁起物のだるまを売る店が並んで、新春らしい華やぎの中にひねもす人波がひきもきらない。
喜多院は平安初期に創建された寺だが、戦乱に荒れはてていたのを、徳川家康のブレーンの一人といわれた天海が復興した。庫裡・書院・客殿その他、重要文化財に指定された建物が多く、狩野元信筆の「職人尽絵」があることでも知られている。
山門をはいった右手には、江戸後期の天明年間から五十年がかりで完成したという石造の五百羅漢像、五百三十五体がある。表情の豊かな羅漢たちの中には、囁きあったり、腰をもんだり、掃除をしたり、うららかな陽の下に好き勝手なことをしている羅漢もいて、微笑を誘う。
新河岸川
川越の下新河岸に、「伊勢安」斎藤家という旧家がある。
江戸時代、川越城の東の伊佐沼から流れ出る新河岸川が、乗客や荷物を載せた川舟を通していた。武蔵野の穀倉地帯と江戸とを結ぶこの水の動脈が生きていた頃、川越には五ヵ所の河岸場が設けられて、三十軒の船問屋が軒を並べていたという。「伊勢安」は、そのたった一軒残った船問屋なのである。
正保四年(1647)、新河岸川の舟運を開いたのは、川越藩主松平信綱だった。以来二百八十余年、舟唄を流しつづけた新河岸川だったが、昭和の初めに通船が不可能になって長かった舟運の歴史を閉じた。現在はその水路さえも廃滅しようとしている。
古い船問屋の帳場や三棟の土蔵を残す「伊勢安」は、消え去った川が舟を浮べていたことを覚えている唯一の証人なのである。
武蔵野の小江戸
江戸時代の初め頃、川越の家々では、ふだん畳の上に渋紙を敷いておいて、客が来るとそれを巻いてから迎え入れた。土地が乾いているところへ風がよく吹くので、畳の上がすぐ土埃で真っ白になったからだという。
明暦元年(1655)三月、野火止用水に水が通ってから、その必要がなくなった。土が潤うようになったのである。畑作さえ不適とされていた川越南方の荒野で水田耕作が可能になり、「城下のちりほこり昔の様に侍らず」と記録されている。この野火止用水を掘らせたのは、川越藩主で〝知恵伊豆〟と謳われた松平伊豆守信綱である。
毎年十月十四・十五の両日に行われる川越総鎮守氷川神社の祭りは、一名〝天下祭〟ともいわれて、十数台の華麗な飾りつけをした山車が町を練り歩く。京都の祇園祭、飛騨高山の高山祭とともに、山車の豪華さで三大祭りに数え上げられている祭りだ。この祭りの起こりは、「川越ほどの城下に、祭りらしい祭りがないのは情けない」といって、慶安四年(1651)信綱が神輿や獅子頭を寄進してはじめさせたのだと伝えられている。
新河岸川を改修して、川越から江戸浅草の花川戸まで舟運の便を開いたのも信綱だし、川越の名物になっている時の鐘の櫓を建てたのも信綱である。→(時の鐘を創建したのは酒井忠勝です)
信綱は寛永十六年(1639)に武蔵忍から移って来て、寛文二年(1662)六十七歳で亡くなるまでの二十四年間、川越七万五千石の藩主として在城した。城下町を整え川越街道を整備したのも信綱で、江戸の後背地の中心都市として川越が繁栄していく基礎作りをした人だといってよい。
信綱はかねがね、「自分はこの先どこへ移封していくか判らないが、川越を立派にしておくことは公儀への奉公の一つ」と洩らしていたそうだ。生涯を通して将軍の良き補佐役だった信綱は、自分の領地にも同じ役割を果たさせようと考えた。江戸はすなわち将軍であって、川越はその補佐役というわけである。
このように性格づけられた川越は、信綱の歿後も江戸に奉仕をしつづけた。新河岸川の川舟が運んだ江戸積みの荷は、穀物・醤油・炭・杉皮・建築用材など、急膨張をつづける江戸が要求した消費物資ばかりだ。また、江戸に大火が起こったとき急場の役に立てるために、城下の扇河岸にはいつも、秩父地方から伐り出した材木が貯木してあったという。三百数十年経った現在でも、川越はベッドタウンとして、やはり東京に奉仕をつづけているのである。
川越祭に出る手古舞や鳶職は江戸の祭り文化の直輸入だったし、町そのものも江戸を手本にして造られた。現在、川越に歴史的な景観を残している蔵造りの建物なども、その顕著な例の一つで、文化年間に川越を訪れた人が、「江戸の今川橋通から神田須田町筋によく似ている」と感心をして書き残している。
たびたび大火に見舞われた江戸では、享保の頃から蔵造り建築を積極的に奨励しはじめた。火事に見舞われたのは川越も同様だから、財力のある商家はこの頃から競って蔵造りの家を建てたのだろう。川越の旧市街地には、塗り家も含めて六十四の蔵造り建築が残っているそうだが、確認されている最も古い建物は、寛政四年(1792)のものだという。
蔵造りの土壁の厚さはふつうで十七、八センチ、土蔵だと十回あまり塗って二十センチを越えるから、防火の機能は絶大なものがある。
川越は明治二十六年三月に未曾有の大火にあって、十六町千三百戸が被災したが、その中で蔵造りの建物だけが焼け残った。再建のときは蔵造りが大流行したそうで、今残っている重厚な蔵造りの家々は、だいたいこの時期に建てられたものが多い。
西武鉄道川越線(新宿線)の本川越駅からまっすぐに北へ延びる道は、かつての城下町の中心街だった。この道の仲町の交叉点をすぎると、両側にその蔵造りの家が見えはじめる。
階下の正面は、それぞれ商種に応じて現代風な装いをしているが、二階の観音開きの部厚い窓扉や、三段にせり出す軒蛇腹、黒光りする壁は、〝小江戸〟と呼ばれたこの町のかつての繁栄ぶりを語りかけるかのようだ。
「小江戸」はショウエドにあらず
東京が首都圏を拡大してゆく過程で、地方の中小都市は首都の模倣を繰り返してゆく。
このことは江戸時代以来の延長である。土蔵造りの町屋が並ぶ埼玉県の川越が「小江戸(こえど)」と呼ばれたように、明治以来、首都圏の中小都市には、盛り場に銀座が出現した。
その首都圏の銀座には東京の銀座のような時代の前衛性-分りやすくいえば、銀座の資生堂が女性文化や流行の発信地であったような活力を持っていない。それは文化を持たない単なる盛り場に過ぎない。実は問題はそこにあるのだが、「小江戸」という言葉が出たので、ついでに話して置く。
テレビキャスターやタレントたちが「小江戸」を「しょうえど」と平然と呼んでいるが、「小江戸」「小京都」の訓みは「こえど」「こぎょうと」が本来、正しい。
これは大(だい)に対する小(しょう)ではなく、明治初期の新聞業界用語の「大新聞(だいしんぶん)」「小新聞(こしんぶん)」の慣用に見る例に通りである。新聞業界用語としての「大」は政治、外交、経済、論説を中心とした硬派の新聞であり、サイズではない。「小」は主に市井の噂・芸能界情報を主にした、イエローペーパーがこれに当る。現代ならばスポーツ芸能紙である。従って「大(だい)」と「小(こ)」は決して誤用ではないのだ。
百万都市の大江戸に対して、せいぜい二、三万の城下町が小さな江戸、「こえど」と呼ばれた。そこは江戸の街並みのように蔵造り、瓦葺きの街並みがある。江戸の街並みに似た小規模な城下町が「こえど」なのである。その代表的な町が川越の城下町であるが、「小江戸」は川越ばかりではない。関東地方には各地に「小江戸」があった。
首都圏の中小都市に「○○銀座」があるようなものである。しかし、「しょうえど」、どうもこのことばはことばとしてはこなれていないが、二十一世紀には正訓となるだろう。
その例は、東京神田の電気街、秋葉原にある。この神田川の北岸、筋違門(後の万世橋)と和泉橋の間の防火地帯に、遠江国(静岡県)の防火神である秋葉神社を勧請した江戸の火除け地「秋葉ヶ原」が正しい地名であった。日本鉄道を買収した鉄道院はここに広大な貨物駅を設営して、神田川の水運と直結させる物流拠点とした。やがて、この貨物駅は山手線全線開通とともに旅客駅を兼ねるようになると、駅名プレートに「秋葉原」と書かれた。漢文の慣用に即して秋葉ヶ原の送り仮名を入れなかった。そのため、送り抜きで「あきはばら」と誤読され、そのまま正式に駅名となった。
同様に「しょうえど」「しょうきょうと」の発音しにくい日本語もそのまま流通するだろう。
長禄元年(1457)、上杉持朝の命によって太田道真、道灌父子が川越城を築いて以来、川越の町は城下町として栄え、特に江戸時代になってからの川越は、江戸のすぐ隣に位置して重要な役割を果たしてきた。だから、歴代のお殿様たちも譜代、親藩の有力な大名ばかりで、なかには幕府の要職を務めた者も少なくない(赤穂浪士を切腹させた柳沢吉保は有名)。
そういうわけで、江戸と交流の多かった川越の町には、江戸の町民文化がそのまま流入し、江戸の香りが色濃く残っている。
仲町の交差点から、札の辻交差点までの約400㍍、「一番街通り」の両側にまるで土蔵みたいな店が並んでいる。他所の町では見られない珍しい風景だ。
黒塗りの分厚い壁大きな鬼瓦と箱棟、どっしりと大地に根を下したような力強い造りは、よく見ると、大切な商品を災害から守ろうとする商人の心と、これを作り上げた職人達の心配りが生かされていて、造作はもう美しくさえある。
最も目につきやすい店蔵造りの菓子舗「亀屋」は、天明三年(1783)の創業とかで、代々川越藩の御用商をつとめ当店の古い文献を研究して育てあげた銘菓〝小江戸の味〟はこの町の名物でもある。昔のブリキの湯タンポが軒先で風に揺れている「荻野金物店」は、格子戸のある蔵造り。「松崎薬局」の右読みの大きな古い金看板も見事。骨董品屋では川越で二番目に古い「本陣」は、屋根の鬼瓦に金具をヒゲみたいにくっつけた風変りな造り。大正時代のロマンの香りがする「埼玉銀行」(現あさひ銀行)の白いタイル貼りの洋館は、どことなく気品があっていい。
「蔵造り資料館」に入るとすぐ目の前に、蔵造りのミニチュアがあって、蔵造りの建築の急所がことこまかく説明してあって興味ぶかい。
醤油の焼ける香ばしい臭いに誘われて右折すると、二百年も続くダンゴの老舗「タナカダンゴ」があって、その隣りの「時の鐘」は、寛永年間城主酒井忠勝がはじめて建てたといわれる。
現在のものは明治二十七年、江戸時代そのままの構造で再建されたもので、昔も(早鐘で火事を知らせることもあった)、今も(電動式で日に四回)時の鐘は、川越の人々にその美しい音色で時を知らせ、「この鐘なしではもう暮しちゃいけないヨ」(ダンゴ屋のおばあちゃん)と言われるほど市民に親しまれている。
履物小松屋という白壁の店蔵造りが、国指定の「大沢家住居」である。
他の蔵造りの大半は、明治二十六年の川越大火以後に建てられたものらしいが、大沢家は寛政四年(1792)の造りで当時のものとしては全国で唯一の例である。
十坪ほどの店に入ると、黒光りする太い鍼の上に〝文化財指定〟の額が飾ってあり、色白のふくよかな感じのオカミさんが親切に語ってくれた。「神社仏閣や町家で国の重要文化財というのはありますが、商家で指定を受けたのは全国にも例がないそうなんです」
さて、正月の〝だるま市〟で有名な「喜多院」は、慈覚大師が開いたという天台宗の古刹である。寺域のたいていのものがすべて重要文化財だが、特に本堂右側の「宮殿、書院、庫裡」は、江戸城の紅葉山(皇居)にあった別殿をこの地に移築したもので国宝である。
入り口(庫裡)で二百円払って拝観コースの順に従って行くと、この書院式のすばらしい御殿のすべてが見学できる。
この寺の「石像五百羅漢」も有名だ。50㌢㍍から70㌢㍍程の羅漢像は坐っているもの、立つもの、横になるもの、笑うもの、泣くもの、瞑想するもの、書を読むもの……、あらゆる姿勢のあらゆる顔の表情がみな違い、一つ一つ見ていくと、自分の知っている誰かさんに似ているような親近感が湧いてきてまことに興味がつきない。
本丸御殿の目と鼻の先に、「三芳野神社」がある。祭神素盞男尊、稲田姫、菅原道真。土地の人は〝天神様〟とよぶ。
それほど大きい社ではないが、権現造り入母屋銅版葺の本殿は均整のとれた美しさを持っている。ここは城郭の中にあったわけだから一般の人は立ち入ることはできなかったのだろうか。
参道入り口の左右は大銀杏二本。細い道が、お社と鳥居に向かって真っすぐのびている。立木の間を走りまわる二、三人の子供達。どことなく人恋しげで静かなたたずまい。
通りゃんせ、通りゃんせ、
ここはどこの細道じゃ、
天神さまの細道じゃ、
わらべ歌『通りゃんせ』の発祥地と伝えられているのが、素直にうなずけるのである。
子どもたちが大好きなコアラの公園
釣りで有名な伊佐沼のほとりにある伊佐沼公園は入口のコアラマークの看板が目印。コアラはいないけれど、「コアラの公園」として子どもたちには人気だ。冒険の森と呼ばれるアスレチック広場が公園の中心にある。城下町川越をイメージした名前のアスレチックが20種類。城のぬけ道、城壁わたり、城壁のぼりなど忍者になった気分で挑戦したい。川越城はやぐら造りのかなり高いもの。子どもたちは身軽にひょいひょい登ってしまうけど、高所恐怖症のお父さんは気をつけて。夏は公園内の水遊び広場で遊ぶのも楽しいよ。
【INFORMATION】
●所在地/川越市大字伊佐沼字沼田町584 ●TEL/049-222-1301(公園管理事務所) ●交通/JR&東武東上線川越駅よりバス(川越グリーンパーク行)伊佐沼冒険の森下車徒歩5分 ●車/国道16号線を川越方面から大宮市方面へ直進。伊佐沼入口交差点を左折すぐ。 ●駐車場/無 ●開園時間/終日開放 ●休園日/なし ●入園料/無料
かわいい遊具がいっぱい!
いわゆる大きな遊園地にはないおもむきがこのまるひろ百貨店の屋上遊園地にはある。屋上の端をゆっくりと回る1人乗りのてんとう虫型のモノレール、ミニ観覧車、3人乗りのメリーゴーランドなど小さい子どもたちにぴったりの遊具たち。色といい形といいどことなくレトロっぽくて、大人は「ああ。もう、かわいい!」とうれしくなってしまう。買い物の後、休憩がてら立ち寄るのもいい。行く前に「乗り物は2つまでね」の約束を忘れずに。まるひろ店内は子どもや赤ちゃん連れへの配慮も行き届いているので安心してでかけられるよ。
【INFORMATION】
所在地/川越市新富町2-6-1 ●TEL/049-224-1111 ●交通/JR川越線&東武東上線川越駅より徒歩10分または西武新宿線本川越駅より徒歩5分 ●車/関越自動車道川越ICより国道16号線川越市内方面へ。川越駅をめざす。 ●駐車場/有(1500台)有料(まるひろ店内で2000円以上購入の場合2時間無料) ●開店時間/10:00~19:00 ●休業日/毎週水曜(開店の場合もある)
子どもにもうれしい小江戸の町
蔵造りの町並みが続く観光地は全国各地いろいろあるが、川越のいい所は大人も子どもも親しめるあめ玉や、せんべい、駄菓子などお菓子の数々を売る菓子屋横丁があることだろう。「このお菓子、見たことある!」小銭を握りしめ、親に隠れてっこっそり買ったなつかしい駄菓子に遭遇するはず。口の大きなガラス瓶に手を突っ込んで10円、20円の菓子を1個ずつ買うなつかしさ。スーパーで箱のお菓子を買う子どもたちにとっては、ちょっとどぎまぎしてしまう、新鮮な体験になるだろう。名産のサツマイモを使った、イモアイスを始めとするイモ菓子もぜひ食べたい。田中屋には胸の奥をくすぐるような、セピア色の情景そのままのレトロなおもちゃや小物が揃った喫茶室もある。「お母さんの子どもの頃はね」なんていつもと違った気分で親子で向かい合うのもいいね。 そこから2~3分の小江戸横丁には、心ひかれるお土産や、漬物、焼き鳥屋と並んで簡単な食事ができる店が連なっている。名物のいも釜めしはお昼にぴったり。バタバタと慌ただしく過ぎる日常をちょっと忘れて、のんびりした1日を過ごすことのできる、心のふるさとになるはずだ。
【INFORMATION】
●所在地/川越市脇田本町39-19(川越観光案内所) ●TEL/049-246-2027 ●交通/JR川越線&東武東上線川越駅または西武新宿線本川越駅よりバス(神明町車庫行)札ノ辻下車 ●車/国道254線より川越市内へ入るか、関越自動車道川越ICより国道16号線に入り川越市内へ ●駐車場/有(初雁公園内70台)無料 土日曜は市役所・あさひ銀行の駐車場が解放される
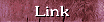 小江戸川越七福神
/呉服かんだ(川唐って何?) (川越インターネットモールの中にあります)
小江戸川越七福神
/呉服かんだ(川唐って何?) (川越インターネットモールの中にあります)