川越の歴史(7)
<目 次>
その他
(史実江戸の母川越
/川越の歴史散歩
/川越歴史渉猟
/川越文化ものがたり
/城下町川越の今昔
/くらしの風土記
/瓦版川越今昔ものかたり(1-12)
/瓦版川越今昔ものかたり(13-24)
/瓦版川越今昔ものかたり(25-36)
/川越灯籠絵 夢まぼろし百年
/川越ご訪問
/埼玉事始
/思わず人に話したくなる埼玉学
/明治・大正・昭和の郷土史
/川越市今福の沿革史
/芳野村郷土誌稿
/川越市菅原町誌
/柿本人麻呂と川越他
/(歴史謎物語)
/大袋新田 内田家文書目録
トップページ
サイトマップ
→
歴史(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
年表
写真集
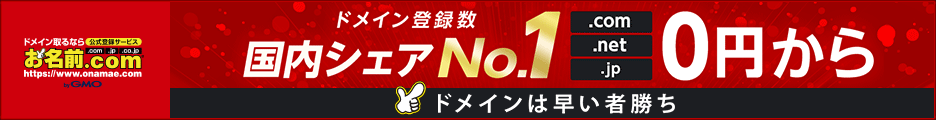

- ●その他
- ・「史実 江戸の母川越 改訂版」 飯島謙輔 1974年 ★★★
- -目 次-
- 川越の発祥と起源
先住民族居住の地/河越氏と皇室御領
川越城の築城と変遷
平野城としての名城/東明寺合戦/上杉氏の略系図/北条氏の系図/徳川時代となる/川越城主一覧表/名城…川越城廃城まで/松平伊豆守の手腕顕著/今も残る知恵伊豆の治績/松平大和守文教政策につくす/築城の研究をした筆者/哀れ明治初年の川越城/川越地方の住民について
昔時の交通と産業
川越と江戸の交通/兵法戦略で出来た道路と町/川越芋(さつまいも)の由来/名物素麺と箪笥/川越平と川越双子/市日に繁昌の城下町/東の方筆頭/川越地方住民の名字/屋号や呼名の調べ
数多い川越の神社仏閣
(神社の部)
川越総鎮守氷川神社/三芳野神社/東照宮/日枝神社/川越八幡神社/川越の神社紹介
(寺院の部)
喜多院/長徳寺/養寿院/蓮馨寺/本行院/川越の寺院一覧表/社寺は戦時への備え/武将と僧侶と寺の思考/川越の寺について/川越の大火に茶目っ気たっぷり
川越市の文化財
国指定文化財/県指定文化財/市指定文化財/国、県、市、文化財の数
川越市の歴史を年代に見る
明治二十六年川越大火による焼失戸数調べ
川越が生んだ知名な人
名医田代三喜/天海僧正/榎本忠重 その他の人/川越に画家の歌麿と雅邦/俳人高山麋塒(幻世)/黒船一番乗り=内池武者右衛門/蔵書家新井甚太郎/勤王の志士西川練造
史実から見た観光の川越
往時が今も生きる/古墳と出土品/現代の川越の山車/関東三大祭り/精巧な山車の構造/山車の人形とはやし/各町引き廻し/豪華山車のひっかわせ/幕末に栄えた川越/山車の略年表/名物川越の蔵造り/時鐘楼について/川越のささら獅子/本丸御殿
明治時代の町政と交通
県下一高い地代/芸妓の数をもって量る/びっくり仰天岡蒸気/時代を知らなすぎる/川越の名所を点と点で結べ
藩主の行政組織と家臣構成
昔の方位と時刻十二支の見方
川越市の主な祭り
【付録】
川越の伝説いろいろ
喜多院と仙波町一帯の伝説
千芳仙人
喜多院七不思議
(1)明星の杉と明星の池/(2)潮音殿/(3)山内の禁鈴 その一、その二、その三、その四、その五/(4)小坊主と狐の物語り その一、その二、その三/(5)琵琶橋/(6)底なしの穴/(7)お化け杉 その一、その二、その三
喜多院鐘楼門の鷹
五百羅漢
双子池
川越城七不思議
(一)初雁の杉/(二)霧吹の井戸/(三)人見御供/(四)夜奈川の小石供養 その一、その二/(五)七つ釜と片葉の葦/(六)天神洗足の井戸/(七)城中蹄の音
冑首の夜盗虫
妻の殺し田
梵心山の民部さま
小坊主/民部さまのお越し/その翌日/民部稲荷/広済寺の石仏/人の気配/石仏/喜多町小町/願をかけて見ましょう
ささら獅子を彫った半右衛門
雪塚稲荷
窪稲荷
川越城は二ヵ所かの質問に答える
江戸城築城裏話と江戸の母川越の題名について
川越が江戸の母たるゆえん
- ・「川越の歴史散歩」 川越民報編集委員会 1999年 ★★★
- -目 次-
- 1 城下町川越と町名変更
- 2 蓮馨寺
- 3 蓮馨寺と多門伝八郎重共
- 4 連雀町と立門前通り
- 5 川越の門前町
- 6 三芳野の里と天神社
- 7 三芳野天神社
- 8 職人の城下町と市
- 9 川越の大火と蔵造り(一)
- 10 川越の大火と蔵造り(二)
大沢家住宅/川越市蔵造り資料館/原家住宅(店蔵 やまわ)/滝島家住宅(店蔵)/岡家住宅(元近常酒店)/松崎家住宅(店蔵 運道具店)/山崎家住宅(店蔵袖蔵 亀屋和菓子店)/山崎家住宅(店蔵袖蔵 茶問屋)/原田家米問屋住宅(店蔵)/田口家住宅(店蔵松江町二丁目)/福田屋/蔵造りの保存と活性化について → 写真:蔵造り
- 11 米(穀)の市とダンゴ屋
- 12 法善寺の奴の墓
- 13 喜多院の〝飯食い鐘〟
- 14 大神楽横丁
- 15 松江町の反戦的落書
- 16 明治初期の交通機関
- 17 西武新宿線と本川越駅
- 18 東武東上線と川越駅
- 19 チンチン電車と久保町の駅
- 20 新河岸川の舟運
- 21 舟と水車にも税金
- 22 赤間川
- 23 菓子屋横丁の匂い
- 24 川越の洋風建築
あさひ銀行/武州銀行(現商工会議所)/川越のキリスト教会/日本団体生命保険 → 写真:洋風建築
- 25 川越街道 九里よりうまい十三里は本当か
- 26 川越街道と大名行列(一)
- 27 川越街道と大名行列(二)
- 28 川越街道と助郷
- 29 川越街道と武州一揆
- 30 川越街道と岸町・高階
- 31 川越街道と明治の夜明け
- 32 お雇い外国人川越街道を行く
- 33 川越街道 藤間流発祥の地
- 34 川越街道 寺尾貝塚と勝福寺
- 35 伊佐沼
- 36 川越東部低地の古墳―古谷・老袋地区
- 37 沖積地の古谷神社古墳
- 38 承久の乱と河越の武士
- 39 古尾谷庄と内藤氏(一)
- 40 古尾谷庄と内藤氏(二)
- 41 川越の次郎兵衛
- 42 赤米に合の手を
- 43 河越氏と太平記
- 44 米と川越の殿様
- 45 挑戦通信使と川越
- 46 川越藩と江戸湾警備
- 47 地球儀は証明した
- 48 川越の映画館 花のパリかロンドンか
- 49 山車の原点
- 50 警察官急募中
- 51 川越の万作
- 52 筒がゆの神事と弓取式
- 53 領民の生活調査
- 54 孝行者の豆腐や
- 55 五重塔
- 56 戦火の川越
- 57 川越・戦火の証言
- 58 古城の月
- 59 川越競馬場始末記
- 60 正確だった川越時間
- 61 河越館
- 62 仙波氏とその館
- 63 入間宿禰物部広成
- 64 高麗福信
- 65 川越が生んだ名医「田代三喜」
- 66 春日局の建物
- 67 荻生徂徠と川越
- 68 芭蕉の門人
- 69 墨池庵尾海
- 70 歌麿の出生考
- 71 広重・安治・清方
- 72 橋本雅邦の左手
- 73 橋本雅邦の最期
- 74 赤沢仁兵衛
- 75 礎 岸野光蔵
- 76 福沢桃介
- 77 西条八十と手紙
- ・「川越歴史渉猟」 新井博 西田書店 1987年 ★★★
- -目 次-
- Ⅰ 川越の歴史を歩く
- ●旧川越市域
- 供出をまぬかれた時の鐘
- 高山家に伝わる出世の絵
- 焼け残った川越城の菱櫓
- 大泥棒を捕まえた地蔵さん《養寿院の泥棒地蔵》
- 御神体に目がくらんだ泥棒《氷川神社の人麻呂神社》
- 明治維新の亡霊
- 新田義貞の一騎坂・駒止めの原
- 六軒町の山車に今福の囃子連が乗るわけ
- 墨池庵尾海
- 川越城の三角芝地
- ●福原地区
- 没収された今福の神輿
- 今福の蔵無尽
- 荒野を開拓した知恵伊豆
- 大根で入植者を集めた羽生又左衛門
- 川越藩の飢饉対策と狂歌
- ●芳野地区
- 芋っ葉地蔵
- 禁止された丑寅正月
- ●霞ヶ関地区
- 杉の木で仲なおりした笠幡村と的場村・鯨井村
- 寺のない安比奈新田
- 的場の百姓野
- ●名細地区
- 名細村の由来
- ●山田地区
- 流れついた観音様――寺山観音堂の聖観音――
- 浄国寺の夜泣き地蔵
- ●南古谷地区
- 友山先生と榛の木
- Ⅱ 川越の歴史を読む
- 幕末川越の一商人――中島久平の生涯――
- はじめに/一川越地方の織物/二川越双子織の成功/三その他の業績
- 川越市における指導者の一類型 安部立郎氏の業績によせて
- はじめに/一、同志会の結成とその発展/二、政治活動と公友会の結成
- 中島孝昌の墓誌銘と「三芳野名勝図会」
- 一、「三芳野名勝図会」成立の前提/二、「三芳野名勝図会」の内容について/三、中島孝昌の墓誌銘について
- 歌人 尾高高雅について
- 古尾谷八幡社の俳句募集の版木
- 中世詩歌文に現れた川越 宗長と「宗祇終焉記」「宗長日記」
- 宗長について/宗祇終焉記/宗長手記
- 中世詩歌文にあらわれた川越 「廻国雑記」と「梅花無尽蔵」
- はじめに/一、道興准后と「廻国雑記」/二、万里集九と「梅花無尽蔵」
- 川越市における昭和史の一コマ 救国埼玉青年挺身隊事件
- はじめに/一/二/三
- 武蔵国川越市城下『時鳴鐘』孝
- 松平信綱の鋳造/秋元氏時代の鐘/松平直恒の鋳造/長喜院の鐘借用/行伝寺の鐘を借用/松平斎典の改鋳/再度行伝寺の鐘を借用/大蓮寺・広済寺の鐘借用/松平直候の新鋳/明治二十七年の新鋳
- ・「証言と記録 川越文化ものがたり」 川越文化会編 さきたま出版会 1993年 ★★★
- -目 次-
- わたしの城下町
- 1 菓子屋横町のおかみさんたち
懐かしい匂いのする庶民の通り/菓子屋横町の歴史/菓子づくりと物資の統制時代/川越の駄菓子あれこれ/菓子屋の一日風景/菓子づくりのおかみさんと旦那/おかみさんたちの楽しみ/職人と小僧さんたちのこと/時代の変遷の中のおかみさんたち
- 2 南田島の足踊り
民俗芸能のルーツ/南田島の足踊り/南田島のお囃子と足踊りの由来/足踊りのやり方について/保存会とチビッコお囃子連/南田島の足踊りと狭山の足踊り
- 3 川越の剣道具
日本における防具の歴史/弘武堂の変遷/弘武道の経営方針/中学で武道が正課となる―剣道の普及へ/扱い防具の多様化/戦後武道の復活/剣道具材料の今昔/防具職人
- 4 川越の剣道
川越の剣道の歴史抄/私の剣道歴/明信館に入門/明信館創設のころ――高野先生のこと/川越中学時代の活躍/わが生涯の最良の時――全国優勝/試し切りのこと――剣道余話/戦中、戦後/望ましき剣道家像
- 5 川越鉄道の開通
川越鉄道の建設/鉄道敷設出願の要旨/川越鉄道の敷設に消極的だった川越の財閥/路線決定の経緯と柳瀬川橋梁のトラブル/川越鉄道と凱旋門/最高速度五十キロのユックリ列車/単線だった川越鉄道と危険な連結作業/細いレールに木の枕木/鉄道草と杉菜のこと/のどかな保線作業/信号機左側の由来と西郷隆盛/女の踏切番と無難信号/高かった汽車賃と川越駅の乗降人員/陸蒸気と駅前風景/新橋・横浜間を走った同形の蒸気機関車
- 6 川越の左官職
徒弟となった日/徒弟の生活/学ぶ/左官の仕事/左官の道具/職人のくらし/親方になって手がけた仕事
- 7 川越高校(中学)の野球
川越高校(中学)の野球/伊丹監督を招聘/家村監督指導の成果/待望の甲子園出場――強豪鎮西高校に勝つ/甲子園に集うベテランチーム/良い選手は頭の良い生徒――野球部員確保に苦労/野球部の選手気質――道具を大事に/野球部育成の恩人/まんじゅう事件/野球部の予算
- 8 関東大震災を語る
日本がひっくり返る日/古老に聴く「関東大震災」/川越市の被害状況(川越震度6、歩行困難/地震はいっぺんに来るのではない/地震と満員のチンチン電車/三十人くらい非難してきたわが家/蚕室いっぱいの蚕がたくさん死んだ/七輪の上の薬鑵が自然の火消し/「火を消せ」と言われても歩けない/地震を予知した利口な馬/〝驚天動地〟この世の終わりかな/地震襲来直後の西武鉄道川越線/震災当日の東上線の状況)/震災発生後の川越市の対応/新聞は大震災をどう報道したか/ひと足遅かったラジオ放送/大震災発生と戒厳令の宣告/大震災余話/朝鮮総督府からの贈り物と孔子様の国の曽さん
- 9 仙波東照宮
東照宮創建の由来/廃仏毀釈と東照宮の管理/伊勢湾台風と社殿の修理計画/重要文化財の指定について/東照宮大権現の勅額と宝物の修理/サイレンが鳴ると身震いした/東照宮への昇殿と絵額の序列/隼の絵額と県博物館への引き渡し拒否/修理を担当した櫻井洋氏と川越市立博物館/三十六歌仙たった七日の里帰り/顎を突き上げて返礼した東照宮の守り神/虎の旦那と早稲田大学総長高田早苗/柳沢吉保奉納の灯籠と石積みのこと/天海と家光の出会い/東照宮の創建と寛永の大火/天海が勝った東照権現説と朱子学者林羅山/泥棒橋の由来と濠の鯉/東照宮の賽銭と奉加帳のこと/結婚式場に狙われた東照宮/アベックがしでかした東照宮のぼや/権現さまと登校拒否児/大嘗祭と東照宮の警備
- あとがき
- ・「城下町 川越の今昔」 えと文/松本茂雄 1967年 ★★★
- -目 次-
- 江戸の母・城下町川越
- 秘められた川越城本丸御殿絵図
- 「お供寺」と川越転封秘話
- 外務卿を断わった殿様
- 煙草が登城した本丸御殿
- 富士見櫓とあんころ餅
- 城内にあった士族の家
- 大坂城代と信楽焼の因縁
- 江戸につながる喜多院
- 天海の前身は光秀?
- 大隈候を迎えた山門
- 将軍の厠もある紅葉山御殿
- 七不思議の一つ「山内禁鈴」
- 三位稲荷と逆さ箒
- 泥棒が落ちた富士見橋
- 晴天祈願の川越だるま
- 首が落ちた五百羅漢
- 明治時代の百花園競輪
- 試胆会の場所となった東照宮
- 江戸へ分祀した日枝神社
- 天神さまの細道
- 氷川神社春宵怪異譚
- 東明寺夜戦と囚人の墓
- 亀が遊ぶ不動尊の池
- 「おびんずる」のある呑竜堂
- 義経の内室となった河越氏の息女
- 大本営となった中学校
- 小学校の大銀杏
- たくわんの香り漂よう教室
- 七面鳥と遊んだ幼稚園
- 大火から守った蔵造り
- 山車の出る川越祭り
- 相撲興行もあった市役所附近
- 火事を知らせた「時の鐘」
- 倉庫もある銀行
- 江戸文学者がほめた亀屋の菓子
- 霞ヶ関ゴルフと山屋
- いせ清と金時計
- 夢枕で宣伝した「かたきだんご」
- 「山の団子」という名の料理店
- 洪水で流された「めがね橋」
- 縁起のいい「ささら獅子舞」
- 「時の鐘」を作った「なべしろ」
- 明信館の寒稽古
- 正午のポーは石川製糸
- モーターに譲った石原の水車
- 急行便もあった舟運
- 乗合馬車と兵隊の位
- チンチン電車と伊佐沼
- およねさんの「小石供養」
- ・「くらしの風土記 ―埼玉―」 野村路子 かや書房 1983年 ★★
- 春 ここに住む人々のくらしは、次の代へと引き継がれていく
- ・大火にこりての家づくり
- 夏 衣・食・住すべてに、その土地、その時代の知恵が生きる
- ・土地の味を生かしたいも菓子
- 秋 人々は、稔りの季節を夢見て、黙々と働きつづけたのだ
- ・船問屋に嫁いだのに――
- ・小江戸の町の商人気質
- 冬 語り聞かすべき話が、ふるさとにはたくさん残っている
- ・女医一・二号にみる埼玉の女
- ふるさと 風土とこころ
- ・「瓦版 川越今昔ものかたり その一からその十二」 龍神由美 幹書房 2003年 ★★★
- も く じ
- はじめに
- その一 春をことほく あさひ銀行川越支店の建物とその歴史(横田五郎兵衛)
川越の豪商「横田家」/幕末の川越藩/川越が日本の相場を動かした!/第八十五国立銀行
その二 春遠からじ 岩田彦助
川越藩主「秋元喬知」/江戸の大地震と富士山の大噴火/川越の知恵袋「岩田彦助」/「川越いも」と「川越唐桟」
その三 春はあけぼの 川越唐桟
「唐桟」とは何?/安政の開国と織物産業/川越商人「中島久平」/川越唐桟(川唐)/「市川団十郎」と川唐
その四 草木萌ゆ モースと川越
アメリカ人動物学者モース/縄文の名付け親/モースと黒岩横穴/再び川越へ/氷川神社とモース
その五 ひばり囀り 橋本雅邦
橋本雅邦の誕生/雅邦、川越へ/日本画の復興/東京美術学校、教授へ/画宝会(がほうかい)
その六 暁に時鳥 舟津蘭山
川越城の炎上と再建/舟津蘭山とは?/川越城の杉戸絵/木村豊太郎と蘭山
その七 朝顔の花一時 三芳野神社
伊勢物語と川越/三芳野の里/縄文時代の名残/天神さまの細道
その八 夕されば蜩 川越の仙波の地と水
あんたがたどこさ/仙波の名の起こり/日枝神社の無底坑と双子池/家康と清水町の水
その九 虫は鈴虫 喜多院と天海大僧正
喜多院の前身、無量寿寺/随風(後の天海)の出生/随風、北院(喜多院)へ/家康、川越へ/家康と天海
その十 桐ひと葉 江戸と喜多院
家康の死/「東照大権現」/家康の霊柩、川越へ/家光、川越へ/仙波東照宮
その十一 散る紅葉 徳川家光と寛永の川越大火
寛永の川越大火/喜多院・東照宮の再建/「家光誕生の間」と「春日局の化粧の間」/川越城主、松平信綱/城下町の整備
その十二 冬はつとめて 松平信綱と川越祭
松平信綱の始めた川越氷川祭礼/文政九年の氷川祭礼絵巻/氷川神社本殿の彫物/江戸の天下祭と川越祭/文化財への指定/市制八十周年
- おわりに
- ・「瓦版 川越今昔ものかたり その十三からその二十四」 龍神由美 幹書房 2004年 ★★★
- も く じ Contents
- はじめに
- その十三 富士の高嶺に 川越城の富士見櫓
- 河越城と富士見櫓/徳川将軍と川越/家康と林羅山/「江戸図屏風」/明治時代と富士見櫓/富士見櫓の図面の発見/富士見櫓の復元に向けて
その十四 七重八重 河越城の成りたち
- 河越城の築城と時代背景/室町幕府と上杉氏/扇谷上杉氏/大田道真・道灌/道灌の逸話
その十五 弥生の空は お茶の歴史と河越茶
- 中国のお茶伝説/日本の歴史へのお茶の登場/河越の茶園/茶の発展/河越茶から狭山茶/開国と狭山茶/製茶機械の発明者、高林謙三
その十六 太平の眠りを 製茶機械を発明した高林謙三と時代背景
- 江戸時代とお茶/鎖国/ペリーの浦賀来航と開国/茶の生産拡大/川越の医師、高林謙三/謙三と川越の茶園/製茶機械の発明
その十七 草葉も水も 成田山川越別院本行院(お不動さま)
- 「お不動さま」/石川留五郎/成田山新勝寺/石川照温/本行院の再興/本行院本堂造営図大絵馬/開創百五十周年
その十八 夏衣ひとへに 「時の鐘」の鐘楼
- 幸田露伴の『五重塔』/関根松五郎/酒井忠勝と「時の鐘」/明治二十六年の川越大火/「時の鐘」の再建/関根松五郎と「時の鐘」の鐘楼
その十九 朝顔に 「時の鐘」の銅鐘
- 鋳物の歴史/川越の鋳物師「鍋五郎」「鍋四郎」/最初の「時の鐘」の建立/松平信綱と「時の鐘」/秋元喬知と「時の鐘」/時を越えて
その二十 風の音の 蓮馨寺
- 戦国時代/河越城と河越夜戦/蓮馨尼/秀吉の小田原攻め/徳川家と蓮馨寺/蓮馨尼の供養碑
その二十一 月の舟 蓮馨寺にゆかりの深いお坊さん(感誉上人・源誉上人・呑龍上人)
- お呑龍さま/感誉上人/源誉上人/家康、増上寺、観智国師/呑龍上人
その二十二 風さそふ 多門伝八郎重共(浅野内匠頭切腹の立会人)
- 蓮馨寺の宝篋印塔/多門氏/目付、多門伝八郎/元禄十四年三月十四日/将軍綱吉の決断/切腹の場/浅野内匠頭の最期/赤穂浪士の討入り
その二十三 松の齢 今を生きる宮大工、数野友次郎さん
- 数野さんと宮大工・印藤家/印藤親方の家/年季奉公/昭和二年の成田山川越別院工事/彫刻絵の模写/川越氷川神社本殿の図面模写/棟梁としての数々の仕事
その二十四 冬籠もり 幕末の川越城主、松平大和守斉典
- 初代、松平大和守朝矩/松平斉典、川越城主へ/十八世紀末の日本の情勢/