図1-5 安政江戸地震の震度分布 によれば、川越付近は震度5と推定されています。
(安政江戸地震:安政2.10.2(1855.11.11) M6.9)
1703年の元禄関東地震の後、1791年1月(寛政2年11月)に埼玉県南部の蕨や川越・岩槻などで多少の被害を生じた地震が記されています。
「1649年の慶安武蔵地震は、川越の大被害と川越領の地変の伝聞記事が重視されて、川越に近い浅い地震(aの活動、たとえば荒川断層)という解釈が主流になっている。しかし注意深く調べてみると、川越の被害は誇張されているようだし、地変は埼玉県東部の液状化だった可能性もあり、いっぽう江戸では大名屋敷の被害が激しくて死者も多かった。ある程度余震があったことも考慮すると、安政江戸地震と同じbタイプで多少北寄りだったという可能性が高い。」
・1855 安政2 …(1855/11/11:安政02/10/02 35.65°N 139.8°E M6.9)
(大江戸)「江戸地震」発生。下町では特に被害が大きかった。地震後30余ヶ所から出火、焼失面積は、2.2平方キロメートルにおよんだ。江戸町方の被害は、潰れ焼失1万4千余、死4千余、瓦版が多数発行された(地震火事)
(小江戸)江戸地震により被害発生(10月)
・1790 寛政2 …(1791/01/31:寛政02/11/27 35.8°N 139.6°E M6~6.5)
(大江戸)川越・蕨地方に被害を出す地震発生。蕨で堂塔が転倒し土蔵なども破損、川越で仙波東照宮の屋根など破損。
(小江戸)大地震、仙波東照宮の屋根が破損(11月)
・1703 元禄16 …(1703/12/31:元禄16/11/23 34.7°N 139.8°E M7.9~8.2)
(大江戸)元禄地震で武蔵・相模・安房・上総諸国の被害甚大。江戸では37,000人余りが犠牲になる。特に小田原で被害大きく、城下は全滅、12ヶ所から出火、壊家8千以上、死者2,300人以上。東海道は川崎から小田原まで殆んど全滅。1923年の関東大地震に似た相模トラフ沿いの巨大地震と思われるが地殻変動はより大きかった。
(小江戸)大地震発生(11月)
・1649 慶安2 …(1649/07/30:慶安02/06/24 35.8°N 139.5°E M7.0)
(大江戸)川越で大地震、町屋700軒ほど大破、江戸城で石垣などが破損、日光東照宮破損。余震日々40~50回
(小江戸)川越で大地震発生(6月)
第四章 江戸のおもな被害地震
三 慶安二年六月二十一日の地震 子丑刻
江戸周辺の状況は次の通りである。
日 光 東照宮の石垣・石の井垣に破損があり相輪塔が傾いたが御本社御宝塔は
安泰であった。
川 越 町屋七〇〇軒大破。松平伊豆守知行地の五百石の村、七百石の村二村で
田畑とも地形が三尺ほどゆり下る。
東海道 掛川までゆれたが、それより上方はゆれなかった。
上伊那 人体に感じたらしい。
以上のことから、この地震の大体のひろがりがわかる。
江戸の被害で示唆的なものは細川光尚家の上屋敷の大広間の被害は立修理は不可能であるが、下屋敷は少しずつ損ぜざる所はない程であったが立修理可能であったという記録である。立修理というのは、家をとりこわすことなく、そのままで修理することであろう。細川家の屋敷の破損はこの立修理ができるか、できないかという程度の被害であったと見てよいであろう。しかし大名家の長屋には立修理不可という被害や、崩れ程度のものもあった。具体的被害のわかっている長屋は松平薩摩守の長屋など九ヶ所である。死者数ではっきりしているのは約五〇人である。
当時の総括的な調査報告は見当らないのでこういう具体的被害から江戸全体の被害をどのように推定したらよいか戸惑う。しかしこの他にも江戸城の石垣・石壁などの破損は一〇ヶ所に及んでいるというし、見付でも破損した所としない所がある。一方、「殊の外殿中の家が破れたが、町では破れなかったが、土蔵の壁などは皆落ちた」という報告もあるし、また、「民家倒れ、その他諸大名の瓦葺悉崩る、人死多し」というような記録もある。このあとに「此時より瓦葺の分皆々コケラ葺となる」と記している。
以上の記録からみると、町屋は破れず土蔵の壁土だけが落ちたというのは誇張にすぎるとしても、瓦葺の家の被害が大きく、屋根の重いことが被害の原因であったと認識できるほど、町屋(コケラ葺?が多かった)と大名屋敷(瓦葺)の被害の差がはっきりしていたのだろう。こういうことから震度はⅤくらいと推定される。さらに地動の周期が短かく、丈夫そうな家の周期に共鳴して、瓦葺の家がこわれたり、土蔵の壁が落ちたと考えられる。周期の短かい地動があったということは、震源地が比較的江戸に近いということを示している。こういうことを総合的に考えると震源地は東京付近となる。一方、最近にわかった川越の被害は、川越付近の地盤の悪いことによる所が大きいと思われるし、液状化現象らしい点もあるので、このためとくに震源地を変更する必要はないであろう。
また、人体に感じたのが西の方は、伊那・掛川付近までであるとすると、地震の規模は六程度で、とても七に達するとは思えない。
以上は被害を低く見積ったときの場合である。もし以上述べた具体的な被害実例から文書に残っていない他の大名屋敷にも同程度の被害があったと推定すれば、江戸の震度はⅥに近くなり、規模は七・一くらいになるであろう。古い地震で、たとえ史料があってもその記述が当時の様子を網羅的に伝えているのでなければ、震度や規模の推定にこのていどの違いが生じうるということを知る、よい例であると思う。
なお、この地震では余震が多く、六月七回以上、七月二〇回余、八月一〇回余、九月四回の記録がある。また、この地震で上野東叡山の大仏の首が落ちたという記録もある。この点については、ハッキリしないが、前の正保四年の地震か、この地震の何れかで首が落ちたので、二回も落ちたということではないかも知れない。
| 種 別 | 建 物 | 檣塀 石垣 | 人の死傷 | |||||
| 郡 市 | 全壊 | 半壊 | 破損 | 計 | 死 | 傷 | 計 | |
| 川越市 | 43 | 31 | 777 | 851 | 14 | 8 | 1 | 9 |
| 北足立郡 | 3,263 | 2,631 | 18,809 | 24,703 | 529 | 103 | 206 | 309 |
| 入間郡 | 397 | 300 | 3,485 | 4,182 | 92 | 3 | 11 | 14 |
| 比企郡 | 306 | 217 | 1,941 | 2,464 | 49 | 1 | 5 | 6 |
| 秩父郡 | 1 | - | 6 | 7 | 8 | - | - | - |
| 児玉郡 | 3 | - | 16 | 19 | 23 | - | - | - |
| 大里郡 | 41 | 42 | 945 | 1,028 | 70 | - | 5 | 5 |
| 北埼玉郡 | 640 | 213 | 6,509 | 7,362 | 327 | 7 | 51 | 58 |
| 南埼玉郡 | 2,181 | 1,328 | 16,834 | 20,343 | 198 | 72 | 139 | 212 |
| 北葛飾郡 | 1,198 | 884 | 7,011 | 9,093 | 485 | 22 | 99 | 121 |
| 合 計 | 8,073 | 5,646 | 56,333 | 70,052 | 1,795 | 217 | 517 | 734 |
九月一日夕刻前後から各地で発生した流言を紹介しているが、そのなかに川越に関するものがある。
一日、その夜はいずこの家もことごとく屋外生活、しかるに午後九時ごろ警鐘が乱打され不逞鮮人来襲の飛報がもたらされた。川越市民はことに老幼はほとんど近村に避難した(埼玉県芳野村) (『かくされていた歴史』)
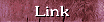 日本地震学会
/防災気象情報サービス
/東京大学地震研究所
/京都防災研地震予知研究センター
/地震本部(地震調査研究推進本部)
/日本地震マップ
/地震のリンク集
日本地震学会
/防災気象情報サービス
/東京大学地震研究所
/京都防災研地震予知研究センター
/地震本部(地震調査研究推進本部)
/日本地震マップ
/地震のリンク集