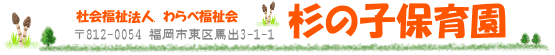
杉の子保育園のご案内
保育園の歴史
いちばんぼしとおつきさま-時間延長保育の実践-
父母の要求は色々ありますが、切実な入所問題をくぐってからは「保育時間」に関する要求が一番大きなものになりました。
病院内の父母の労働条件は、保育園からみていても、次第に厳しくなっていることが実感されておりました。
1982年2月には厚生省から『延長保育』の実施が通達されました。これは、保育時間を1時間延長するというのもでしたが、職員の配置は「残業で・・・」子どもたちに与えられる軽食の内容は「せんべい1枚程度・・・」等という説明で、全く不十分なものでした。杉の子保育園では、市内の保育者で組織された組合と共同で福岡市と交渉を行い、「厚生省と同額の補助金を福岡市が出す」ことで合意して実施にふみきりました。
1990年代にはいると、「1時間だけの延長では、父母の労働実態に合わない」「もっと長い保育時間を」という父母からの要求が出されてくるようになりました。保育所専門委員会を開いて検討し、90年1月に杉の子保育園の職員と父母で「馬出地区に夜間保育所を作る実行委員会」を結成しました。ここでは福岡市に積極的な請願運動をしました。子どもたちの立場、父母の立場、保育者の立場と、いろいろな長時間保育の問題を討議しました。市への要求を出し、具体的な実現の方法の論議を繰り返しました。
1992年になって厚生省から、『長時間保育サービス事業(22時までの保育)』の案が提出されてきました。
これは「厚生省の案通りに(福岡市の単独補助は無し)モデル的に杉の子保育園で実施します」という内容の一方的な通知でした。この長時間保育サービス事業の実施をめぐって現場は大混乱になりました。園と職員、理事会と組合、お互いの身を削るような話し合いの末、5月末から杉の子保育園での実施が始まり、翌年からは本格的に全市内の指定園で実施されるようになりました。
1995年からこの事業は『時間延長型保育サービス事業』と呼ばれるようになり、タイプ別の名称が「特A型(19時まで)」「A型(20時まで)・・・夕食」「B型(22時まで)・・夕食」となりました。
1時間の延長保育を始めてから15年にわたる時間延長保育の実践を経た現在では、職員体制や処遇、保育内容の工夫も次第に充実してきました。