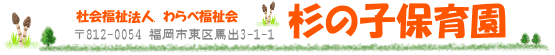
杉の子保育園のご案内
保育園の歴史
社会福祉法人わらべ福祉会「杉の子保育園」と「若杉共同保育所」
共同保育所「若杉保育所」
社会福祉法人わらべ福祉会「杉の子保育園」として、新しくスタートした保育園は、関係者の期待に応えて、充実した活動がはじまりました。従来は保育園の運営をどうするか?財政は?と、父母・保育者とも大変でしたが、認可を受けてからは、しっかりと『子ども達を中心に親と保育者が手をつなぐ保育園』となり、互いの要求を話し合い理解しあいながら『子どものしあわせ』で一致できるようになりました。
このことを反映してか、入所希望者が急増しました。
しかし、福岡市の条件は、入所時生後四ヶ月であること、定員空きがなければ入れないこと、緊急入所の対象となる園は自由児が零であること等、厳しいものばかりです。これらにより年度途中に生まれた子どもの入所は極端に制限されてしまっておりました。
一方、大学当局は「当分の間、保育所要求には応じない」という認可時の約束を盾に、学内の保育所設置は「絶対にダメ」という態度でした。
そこでこの切実な入所問題や、宿題として残されている『産休明け保育』の問題の解決のため、広い視野での話し合いが必要になり、組合代表(2名)、杉の子保育園(園長、担当理事、職員2名)と利用者代表による構成でした。
そこではまず、「共同保育所」を設置することが当面必要である事を確認し、この事業からスタートしました。発足に当たっての確認は以下の通りです。
(1) 入所希望者の受付は医学部組合で行う
(2) 実務は共同保育所の父母と保母による運営委員会で行う
(3) 杉の子保育園はできるだけの援助を行う
年度途中の産休・育休明けなどで保育所の必要な父母を中心にして、学外の場所を探し、資金を出して全くの自主運営での無認可の共同保育所が開設されました。しかし、入所者は一定ではなく、三月には認可園に入ってしまうので、四月はほどんど毎年、子どもが零の状態になるのです。従って、この保育所は慢性的に経営が不安定でした。収入としてはわずかの入園料と保育料だけなので、保育者はパートで支えてもらうしかありません。献身的な若杉保育所の保育者を四月には杉の子保育園の臨時職員になってもらったり、絶えず物品販売をしたりの苦労が続きました。場所も家主の事情等で転々と変わりました。
当時、九州大学職員組合・婦人部で行っていたバザーでは、『共同保育所の支援』という目標が、毎年高く掲げられておりました。これは医学部の保育所だけではなく、本学地区、教養部地区それぞれの共同保育所を含む全学的な取り組みでしたから、医学部では独自のバザーも毎年行いました。『保育所の為ならば・・・』という雰囲気が盛り上がって、協力的な楽しい年中行事になっておりました。
「若杉保育所」と名付けられたこの保育所では、年度の初めには深刻な予算の検討を行い、赤字を絶対に出さない計画を立てました。前述したように保育者の雇用を工夫したり、調理ができない(設備も人もない)ので離乳食は各家庭から作ってきたり、遊具や事務用品等を集め合ったりと苦肉の策が練られ、実行されました。
本当に厳しい共同保育所「若杉」の取り組みでしたが、この運動に関わった父母は子育ての中での楽しみや社会参加の意義を毎日肌で感じ、確かめ合う事ができて、お互いの強い絆ができてきました。
若杉保育所は、1977年度から1985年まで続けられ、一時、入所希望者がいないので閉鎖され、1985年5月から再開されておりました。1993年『育児休業法』の成立とほとんど同時に再び閉鎖され、今に至っております。この若杉保育所に保育者として深く関わってこられた堀江昭子氏は、長期に渡る当時を振り返りながら、「7回もの引っ越しをしましたからねぇ」としみじみ語っておられました。