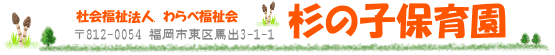
杉の子保育園のご案内
保育園の歴史
認可後の園舎の建て替え運動---父母と職員の力を合わせて
保育所専門委員会では、認可時に理事会が福岡市に対して「出来るだけ早急に建物を自己財産に切り替える」という約束を行っている事に対して、その実現に向けての活動を開始しました。
当時はやっと認可にこぎつけた安堵感の中でしたから「この建物は、みんなの力でつくりあげたもの、これで充分」という意見が強くありました。けれど、園舎全体がプレハブ建築で3歳以上は混合保育でしたから、園舎建て替えは切実なものになってきました。
藤野園長の〔より良い環境の中での保育〕という熱のこもった説得がまわりの重い腰を上げさせました。委員会は知恵を絞り、理事会や父母の会と協力しながら、一つ一つ問題を解決していきました。1979年9月には九州大学へ、12月には福岡市への「移転増改築申請書」を提出する運びになりました。
園内では「園舎設計学習委員会」をスタートさせ、九州大学工学部・建築学科の協力で具体的な土地の条件に合わせた設計に取り組みました。夜遅くまでの大変な量の資料や図面との格闘、休日返上、時間をやりくりしての見学等は、文字通り産み出すことの苦しみと喜びに満ちた活動でした。
零に近かった資金も、補助金や借入金のことを調べ、担保の調達で理事会を開き(理事個人の邸宅を担保にした)、父母の会に協力を依頼して、次第に実現可能な額になっていきました。
当時の父母の会の資料を読みますと、その苦労が偲ばれて感動させられます。毎週色刷りの宣伝ビラが発行され、病院内外に配布されました。以下、日付順にこれらの内容(見出しだけ)を追ってみます。作者は父母の会保育所運動部長であった小西あや子氏です。
| 1980.11.06 | 杉の子保育園が新しくなります。 90名定員に。移転先は薬学部裏の旧機関場跡。 今設計検討中。 |
| 1980.11.13 | 大学病院にはそれなりの保育所を・・・。杉の子保育園は今・・・こんな人が利用。 こんな内容。困っていること。 |
| 1980.11.20 | 建て替えにカンパを! そりゃ政府の仕事ダヨ。 法律もある。他の市の場合。 今の計画は。 カンパをどうぞよろしく。 |
| 1980.11.27 | 子どもらに、もっと緑と太陽を。 今子ども達は。大切なものは何でしょうか。 協力と援助を大切に。 |
| 1981.09.17 | 杉の子保育園いよいよ新園舎着工!資金カンパありがとう-317万円に-。 病院長列席の起工式9月19日。 |
| 1982.02 | お礼のことば。 落成式のごあんない。 募金総額3,191,456円。1982年3月6日落成式。 20日第5会卒園式。 |
この園舎の特色はいくつか挙げることが出来ます。その一つは、デイリープログラムの展開の大きな活動である遊び-昼食-午睡-おやつ等の行為の転換がスムーズに行われるようにそれぞれの空間をレイアウトしており、それにともなって行う排泄や手洗い、更衣等が整然と行われるように、便所や手洗いロッカーの位置等に充分配慮していることです。もう一つは、具体的構成として乳児ゾーン、幼児ゾーン、管理ゾーン、コミュニティゾーンに分け、これらのゾーンで中心の「中庭」を囲みました。この「庭」は、各保育室への日照や採光、通風を確保し、その上に野外での遊び、昼食やおやつの場などとして、日常の保育室では期待できない効果的な活動を行えます。このため多くのガラス屋根を配置し、きわめて明るい雰囲気を創り出しております。
唯一の難点は、思い切った平屋建てを創ったことから、大変に狭い運動場になってしまったことでしょう。
特徴的なこの園舎は大学工学部、建築、保育など角界の関係者から多くの注目を受けました。各学会や各研究会での発表を要請され、研究・実践発表したり、見学者を多数迎えたり致しました。
これによって、保育内容が、飛躍的に充実したことは言うまでもありません。 この頃「男女雇用機会均等法」が施行されました。婦人の労働条件が変化する中で保育園の必要性はいよいよ大きくなり、杉の子保育園への入所希望者は増え続けました。この勢いに押され、福岡市の指導もありましたので、保育園としては再度の定員増に踏みきることを決定しました。大学当局は度重なる要求が今後も続くことを警戒して、渋い態度を崩さず「これ以上の定員増は行いません」という念書の提出を理事会に求めてきました。理事会の理解と大きな努力によって、1984年度には定員110名にするための増築、1985年には定員増を伴わないテラスを保育室の中に取り込む増築を行いました。この他にも、各クラスの人員を年度半ばに移動させる(進級する)ことや、自由児の入園を行うなどの工夫で、深刻な入所難に必死の対応を続けながら、今日に至りました。
長時間保育開始の92年~98年までは、圧倒的に特A型(7時まで)の延長保育型が多く7時からの食事も3歳未満児、3歳以上児が一緒に食事できる程度でした。が、年々、A型・B型増え、ついに2000年度は、A・B型(20時~22時)が、特A型(19時まで)を上回り、園児の半数近くが登録しています。労働時間の長さは医療の現場で働く親にとっては避けがたいものです。が、一方で子育ての時間が、大変に短いものに成らざるを得ません。その現実をふまえ、長時間保育の間に子どもたちが、家庭的な暖かい雰囲気の中で過ごせるように、細かい配慮が必要であることを実感しています。 子どもたちの生活リズムが夜型になりつつあるのも、将来学校に通う子どもには厳しいものがあります。大人の働く条件が厳しいからこそ、乳幼児の大切な時期を園と家庭が一緒になって育んでいきたいものですね。