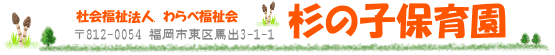
杉の子保育園のご案内
保育園の歴史
保育運動の飛躍を! 認可運動へ向けて
その当時オイルショックを伴う激しいインフレは、今までの運動の成果を完全に反古にするほどのひどさで、保育所財政を襲いました。保育料とわずかの病院からの補助金で運営している保育所財政は危機に襲われ、年毎に大幅にアップする保育料のために利用したくても利用できない人が増加していました。財政は足りない、施設は貧弱であり、また、無認可ですから、きちんとした責任者(園長)がいないのも保育内容を豊かにしていく面で厳しいものがありました。が、全国的に大学内保育所は次々に認可を認めさせる運動が始まっていましたし、実現されていきつつありました。
組合からは、これまでにも「認可」の問題をたびたび提起されてはいたのでしたけれども、差し迫った問題にはならず、いつもうやむやになっておりました。今度は保育所の存在をかけて真剣な議論が始められたのです(1950年度)。
先に認可保育所としてスタートしていた京都大学の話を聞くなどの動きをしながら、話し合う中で、両地区保育所運営委員会は、より強力な「保育所協議会」を結成しました。これは九州大学の父母、保母、組合の代表が集まって認可問題を話し合うための組織でした。ここではまず最初に三項の認可の意義が確認されました。
(1) 福岡市民としてきちんと納税している九州大学職員なのに、その保育所が認可され措置費で運営されていないのはおかしい。福岡市の予算のもとで、市民の子どもとして保育される権利がある。
(2) 子どもの保育条件を豊かにしたい。三歳児まで行っている保育を就学前まで保障していく。
(3) 保育者の労働条件が改善され、保育に専念できるよう保障する。
というものでした。
認可保育所の問題を学習していく中では、良いことばかりではない、今までの自由な運営にかなりの制限(市共通のきまり)があることなどがわかりました。その中で認可にむけての合意に達するまでに、とても時間がかかった問題がありました。「産休明け保育ができなくなる」ということでした。当時は育児休暇の制度が無い時代で、産後休暇明けにはすぐから出勤しなければならないという状況でしたから、特に医系地区での論議は厳しく「認可保育所になって、自由に入所できなくなるのなら、認可はしない方がよい」という意見が多く出てきたのでした。保育所協議会ではねばり強く討議して、このため認可の際には別に産休明けのための共同保育所を併設するという条件をつけて、認可への合意をしていきました(これが「若杉共同保育所」です)。
敷地も園舎も借り物のまま(職員休憩室のまま)という条件でしたので、国の(文部省=貸す方、厚生省=借りる方、共に)許可が難しいというような事情がありましたが、直接の自治体である福岡市が、九州大学内の存在を大きく評価したということもあり、地元国会議員の協力を得たりしながら、なんとか認可へ到達することができました。1977年(昭和52年)4月のことでした。
定員60名、0歳から6歳までを保育する認可保育園の誕生でした。やっと文部省からの借地手続きが完了してほっとしていると「この敷地は(500坪位あった)厚生省の基準に合わせてみると広すぎる」といわれて300坪に減らされたり、台風で壊れた入り口の屋根の修理を工営係に頼んで修理の後で「しなかったことにする」と断られたり、いろんなことがありましたが、認可によっていろいろなことが確かに前進しました。
まず、措置費という収入がきちんとしましたので、財政的に基盤ができました。このことによって保育者は子どもを中心とした保育の話し合いが十分にできるようになりましたし、父母も運営に関する深刻な話し合いから解放され、子どもの成長をみつめることができるようになりました。これは園長というこれまでになかった職務者が配置された事で、各人がそれぞれの職務に専念できるようになったからでした。杉の子保育園の初代園長には、西南学院舞鶴幼稚園の主任教諭であった藤野登志子氏が招聘、就任致しました。
高かった保育料は、収入によって決められるようになり、若干の不公平感は残りましたが、妥当な額になりました。
以上述べてきましたように、九州大学に働く職員の福利厚生施設として出発し発展してきた共同保育所は、認可を期に独立することになりましたので、九州大学には「当分の間、保育所に関する要求は出さない」ことを協約致しました。当時の病院長は「保育所は、お嫁に出した娘のようなもの・・・」と言われておりました。