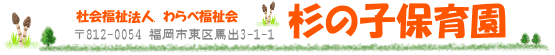
杉の子保育園のご案内
保育園の歴史
病院職員の切実な保育要求を出し合って保育所の実施、その名は「職員休憩室」(1960年代前半~)
改めていうまでもありませんが、病院職員は、毎日が「生命」と向き合っての仕事です。医師や看護婦は勿論のこと、技師や事務、学生も含めて、毎日が現場で「生命をまもる」仕事に取り組んでいます。九州大学で働く仲間の多くは「自分達働く者の権利を守れないで患者の人権を守ることはできない!」と考えていました。当時の病院看護部では、月の半分(12~13日)は夜勤、しかも一病棟に一人で勤務するという厳しい労働条件でした。これを改善し、人間らしい生活がしたい「そのためには看護婦の増員を!」という要求が激しく出されて、労働組合を中心にその実現を求めて闘っておりました。
病院内で安心して預けられる保育所の充実・拡張の要求は、これらの働く者全体の要求の中でも認められ、支持され、セットになって取り組まれていった運動でした。
1963年頃、病院の旧い病棟が改築されることになりました。当然、小児科も新しくなりますが、その計画のどこにも「保育所」のことがないので大騒ぎになりました。ここで、医系支部を中心に父母が「利用者の声を聞く集会」を行ったり、「乳児観察室(小児科保育所)」に見学会を行ったり、準備を重ねて「保育所専門委員会」を結成しました。
当時、「保育所専門委員会」が行ったアンケート(保育所がいつまでに必要ですか?)に対して「今すぐ欲しい。一年以内に欲しい」と答えた人が40名もありました。保育所にも現在23名の子ども達の申し込みが殺到している事も併せて保育所問題の重要性をあらためて認識しました。
このようなたくさんの要望を背景に、看護部長や小児科の保育所主任に協力を要請しながら、街頭に出て「市立の保育所設置・現在あるものの拡充」「市当局への保育所設置を要求する署名」などにも取り組みました。
病院に対しては「(1) 希望者全員を収容できる設備を(2) 小児科の新館移転に伴う観察室の確保を(3) 保育所に関する病院の計画を示せ」という切実な要望で病院長事務部長交渉を重ね、誠意ある話し合いをしました。「保育所をよくするためには父母が組合の一緒になって要求しなければ問題を解決しない」ということが父母の中で認識され、その後、いろいろな闘いのドラマを経て、1967年第二の保育所への移転になりました。
50坪の「皮膚科研究室」をそのまま移設して、現在の変電所の隣の駐車場の場所に「職員休憩室」という名の保育所ができたのです。九州大学付属病院という文部省施設の中に「保育所」という厚生省管轄の施設は建てられないという事情の中での、病院の好意ある苦肉の策であった事と察せられます。旧い建物の利用ですから、外観は変えられませんでしたが、中は新しく、保育所としての機能を持つ空間に区切られた新園舎に生まれ変わっていました。小児科発育観察時代をくぐりぬけてきた父母と職員達がともに祝った「開所式」のあの喜びの日は、わすれられない一日になりました。
念願だった給食室が実現し、専任職員が配置されて給食がはじめられました。毎日の暖かな給食はほんとうにうれしいものでした。
乳児室・幼児室・浴室・よく陽のあたるテラス・ぴかぴかの床・トイレのドアも明るく塗られています。園庭にはジャングルジム・ブランコ・すべり台・鉄棒が設置され、園児定員41名、3歳までの保育がはじまりました。これも念願だった年齢別編成の保育を実現し、大陽の光をいっぱいにうけて、戸外で思い切り土や草、花などにふれての保育がはじまりました。学内で自由に遊べること、散歩に出かける場所に恵まれていること(この当時、学内での規制は少なく、県庁はまだ現在地に建てられていなくて広い東公園でした)等のうれしい条件を発見しては、これまでにはできなかった運動会や合宿など新しい行事に取り組み、保育を充実させていきました。
他の園とも交流して保育内容を考え合うことができるようになったのもこの頃からです。
これらの取り組みの中で、保育所が小児科の手をはなれると同時に、父母と職員と医系支部、それぞれの代表で「保育所運営委員会」が構成されました。そして、保育所の問題はすべてここで考えられていくという民主的な運営がされるようになったのです。