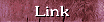| 丂愳墇擭戙婰丂堦枃悹丂屻曇嶰朏栰嵒巕丂丂屆摴傕愮戙傪側偔偝傓壴栰嵠丂奀庻 | ||||
| 丂捔庣昘愳戝柧恄丂丂嬙柧揤峜擇嵨恏撗嬨寧廫屲擔姪惪丂揤柧尦擭枠愮擇昐巐廫堦擭 | ||||
| 悽懎偵偦偺偐傒愳墇偺屼忛偼丄忋僴屗偵桳偟傪丄崯抧傊堷偟屘愳墇偲偄傆偲丄惀戝偒偵岆栫丄崯忛傪抸偟懢揷摴恀偼柤彨偵偰丄抧偺棟傪傛偔偟傟傝丄忋屗偼杴妷澺壓偺抧栫丄崱偺屼忛偼梫奞柤彑偺抧栫丄慠傪嬤偒傪嵎抲偰壗偦澺嫠偺抧偵抸傫傗丄怱桳傕偺巚椂偡傊偟丄寴屌偺抧宍傪埲偰徹偲偡傊偟丄忋屗偺忛偲偄傊傞傕偺媽婰偵側偟丄杒忦壠偺巑媨忛旤嶌庣愰岲偺壆晘栫丄媽婰偵尒傊偨傝 | ||||
| 丒挿榐擇擭巐寧丄愳墇偺屼忛棫丄懢揷帒惔朄柤摴恀抸偔丄懢揷摴燇偐抸偟偲偼岆栫丄摴恀偼摴燇偐晝栫丄柧墳擇擭幍寧擓屲擔偵懖丄懘屻嫕榎嶰擭幍寧廫堦擔丄杒忦巵峧偲忋悪嵍嬤偲戝崌愴桳 | 丒挿榎尦撗偺擭傛傝丄揤惓廫敧撔擭枠杴昐擇廫堦擭偺娫
丂懢揷摴燇丄忋悪娗椞丄戝摴帥弜壨庣丄杒忦垻攇庣丄塃巐戙愳旍偺忛庡栫 |
丒揤暥廫屲擭巐寧擓擔丄杒忦巵峃丄忋悪寷惌偲摃乮搶乯柧帥栭孯
丒揤惓廫敧擭敧寧丄庰堜壨撪庣條愳墇屼擖忛丄宑挿榋塏擭巐寧丄忋廈塜嫶傊屼強懼 |
丒宑挿榋塏擭巐寧丄庰堜旛屻庣條弜壨揷拞傛傝愳旍傊屼擖忛
姲塱廫堦擭丄庒廈彫昹傊屼強懼丄愳旍偵嶰廫嶰擭屼嫃忛丄晇傛傝憡攏屨擵彆條屼忛斣 崯擭峕屗塇嵍儜栧幣嫃棫僣 |
丒摨廫擇擭丄杧揷壛夑庣條愳旍傊屼擖忛丄摨廫屲擭怣廈徏杮傊屼強懼丄惀傛傝悈扟埳惃庣條屼忛斣丄崯帪傛傝愳旍傪愳墇偲彂夵丄梴庻堾忇偺柫偵傕愳旍彲偲偁傝丄尦墳尦擭傛傝揤柧尦擭枠巐昐巐廫敧擭側傝 |
| 丒姲塱廫屲擭丄徏暯埳摛庣條愳墇屼忛攓椞丄梻擭揤憪傊屼弌捖
丒尦榐幍擭丄憤廈屆壨傊屼強懼丄愳墇偵屲廫幍擭屼嫃忛 丒姲塱幍擭丄撿惣戝庤偺娵掞挰拞傊傝愇弌棃傞 |
丒摨廫敧擭仩乮抾亄屼乯壆晘弌棃丄怷壓恟塃儜栧偲偄傆恖惀傪梐傞丄屻偵庽栘壆晘偲塢丄壨撪庣條屼帪嶰廈偺棿奀堾傪唰偵偆偮偟媼傆丄崱塜嫶傊堷偗偨傝丄杒挰峀嵪帥偟傗傇偒偽乀偺愇憸偼丄姲塱廫敧擭偵壗幰偐帩棃傟傝 |
丒宑埨擇擭丄戝偁傜傟傆傞丄戝僒拑榪偺擛偟
丂彨孯壠岝岞擔岝屼幮嶲 丒彸墳擇枻擭屲寧丄懡夑挰偵怴忇偐乀傞丄栬岺捙柤暫屔丄崯崰傛傝崅戲挰偼椉懁奆慺阷傪嶌傟傝丄愳墇偝偆傔傫偲偄傆 |
丒墑曮尦塏擭丄崯帪枠懡夑挰栻巘偼杮挰拠掱墇屻壆偲偄傆偗傫偲傫壆偺偆傜偵桳丄枖柇徆帥偼崱懡夑挰搾壆偺強側傝偟偐丄傦偝偟挰愺塇懛暫塹偲偄傆恖偺壆晘傪攦偰堷傝偟栫 |
丒掑嫕巐塊擭惀枠昘愳嵳楃偼偁傗偮傝嫸尵偲妏椡偲堦擭偍偒栫丄崯擭傛傝抧偍偳傝彮乆巒傞丄懘帪偺塖偲偰崱恖偺岥偵巆傟傝
丂傕偟偺戃偵峠愗擖傟偰偮乀傔偲偄傠偵弌怽偨丂傓偐傆偺旻嵍偼偑偮偰傫偐 |
| 丒尦榐榋撗擭惓寧廫榋擔丄偐偫挰朄慞帥偵悾愳壝嵍塃塹栧愇旇棫丄夲柤忩摽丄惀傪搝偐曟偲塢丄崯帪枠杮挰傛傝懡夑挰傊峴敳偺拞摴桳
丒崅戲挰戝楡帥偺栧慜偵栮墊塛墊偲偄傆桳丄愗偨傞幰晽傎傠偟惗偡 |
丒屲儢懞撶壆栴戲壗朸丄尦榓偺崰傛傝昐梋擭丄媨偺壓戙姱挰偺峀彫楬偵廧嫃偣偟偑丄崯愡屼梡抧偵栫丄戙抧傪栰揷壓偵偰旐壓偨傝丄崱偵撶怴揷偲偄傆丄敤傛傝愜乆揝偔偢傪孈弌偡偼惀備傊栫丄惀傛傝屼戦晹壆傊堷墇丄枖崱偺強傊堷偆偮傝偟側傝 | 丒尦榐幍滫擭嶰寧丄徏暯旤擹庣條愳墇偺忛屼攓椞
丒曮塱擇擭丄峛晎傊屼強懼 丒摨敧擭丄愬攇怴揷傊椃恖偺廻旐嬄晅傜傟偨傝丄崯帪峕屗嬥嬧悂懼 丒摨嬨擭丄嶰搶彫巗偲偄傆恖埩傝傪棫儖丄屻偵桞怱偲塢憁廧儉丄崱偼屼戦彔廻偲側傞 |
丒摨廫堦擭丄崯帪偺嵳楃傛傝崅戲挰偵壆戜巒傞丄愇傗偨偄偲塢丄崯帪丄徏峕偺巗傕偼偟傑傞
丒崯帪偵丄娵攏応捸悢擇愮昐廫榋捸奆敤偵偰崙桭嵅屲塃栧梐傝丄掜巕巗暯嫃戭側傝丄崯帪峕屗塱戙嫶偐乀傞 |
丒曮塱擇撗擭擇寧丄廐尦扐攏庣條愳墇屼攓椞
丒柧榓屲巕擭嶰寧丄塇廈嶳宍傊屼崙懼 丒摨嶰擭丄尦寢偲偄傊傞暔柍丄銅偵偰敮傪傓偡傂偟栫丄懘崰擭曢偺廽媊偵丄捁偺塇傪偺偣偰摛晠傪攝傝偟側傝 |
|
丒姲塱幍撔擭丄斾帪枠奆抝彈妚懌戃栫丄彈偼崶楃偺帪巼偐傢偺偨傃栫丄崅戲挰暁尒壆壗朸栘柸懌戃攧巒傓
丒惓摽擇扖擭丄懘崰巐僣捯屼敾宍偺曈偵傫偵偔巗棫丄壗幰偐岥偡偝傒偗傫 丂愳墇偼偵傫偵偔巗偱嬨偝偄嵠 |
丒嫕曐廫巐撗擭擇寧廫敧擔丄戙姱挌嬺偪偐偄偺搚庤弌棃傞丄崯帪枠廫擮帥唰偵桳
丒摨廫屲擭滫榋寧丄忋徏峕傛傝挅旲挰傊捠傝旐嬄晅丄揝鄘挌偲塢 丒姲曐尦撗擭廫堦寧廫擔丄怣擹慞岝帥杮挰墊杮巵偵偰奐挔 |
丒曮楋嶰撗擭丄崯擭傛傝撿挰帥揷巵丒搱揷巵偵偰偒偸傂傜傪怐丄惀挰偵偰愳墇傂傜偍傝巒栫
丒柧榓屲巕嶰寧丄徏暯戝榓庣條愳墇屼嵼忛 丒愳墇偺屼抸忛偟挿榐擇擭傛傝崱擭揤柧尦擭枠杴嶰昐擓嶰擭栫 |
丒柧榓榋擭丄壓挰偲榋尙挰搾壆弌棃傞
丒埨塱敧堝擭廫寧幍擔丄奃偺偙偲偔偺嵒傆傞 丒揤柧尦恏塏擭巐寧巐擔丄怣擹崙慞岝帥擛棃丄杮挌墊杮巵偵偰奐挔丄憏偰崯杮懜懎壠偵偰奐挔墊杮巵寁偺傛偟 |
崯愳墇擭戙婰偵塳傟岓屼忛撪揤恄丄屲儢懞恄柧丄捠挰敧敠媨丄埥偼榋捤堫壸偺桼棃丄帥乆偺媽婰丄懘奜柤強丄嫿暘偺媽愓丄瀽怱嶳偺暔岅丄愬攇惎栰嶳偺墢婰丄愳墇偵巗恄側偒帠丄奆屻曇嶰朏栰嵒巕偵埾偟偔尠偟怽岓 |
| 杮挰丂丂挿昐嬨娫 尦棃杮廻偲偄傊傝丄偦傟偵懳偟偰偆傜廻偺柤偁傝 |
撿挰丂丂挿擇昐嶰廫擇娫 尦棃奃巗応偲偄傊傝丄懘崰奜偵巗偲偄傆帠側偟 |
婌懡挰丂丂挿昐榋廫榋娫
墲屆摃乮搶乯柧帥挰偲塢丄尦棃嬤懞偺撪帥偺帤晅偨傞偼丄搶柧帥偺抧栫偗傞傛偟 |
崅戲挰丂丂挿昐廍娫巐広
抾戲塃嫗椇椶媊抾戲嬨榊偲塢恖婲棫偺挰栫丄抾戲挰偲塢傪崱偐偔塢傊傝 |
峕屗挰丂丂挿昐榋廫榋娫
偄偵偟傊搶挰偲偄傆丄尦榐廫擇擭榓揷棙暫塹庢帩偵偰偆傜揦桳傝偟偐崱偼側偟 |
| 巙媊挰丂丂挿擇昐幍廫嶰娫
幇慞懢偺庢棫傜傟偟挰屘巣塢丄崱媣曐挰偵幇撪彔偲偄傊傞桳丄懘枛媊栫 |
徏峕挰丂丂挿昐廫敧娫嶰広
愄傛側愳擖崬丄戝偒側傞殓忋傝偟傪丄傕傠偙偟徏峕偺柤偵傛偣偰偐偔偄傆 |
懡夑挰丂丂挿嬨廫敧娫
傓偐偟奆壉壆栫丄崱傕懘樰巆傝偟偼崯挰偼偐傝栫 |
抌栬挰丂丂搶懁榋廫屲娫
丂丂丂丂丂惣懁屲廫嬨娫 偄偵偟傊壠悢廫擇尙奆偐偫傗栫丄崱傕嬥嶳尃尰桳丄嵳楃枅擭擇寧廫屲擔 |
巙懡挰丂丂挿榋廫榋娫
姲塱嶰擭滫敧寧廫擇擔丄婭崙壆壗朸偺棤傛傝懪暔懘奜摢崪巐屷昐孈弌偣傝丄惀屆愴応側傝 |
| 屆恖偺彂偍偐傟偟鐗嶰朏栰傑偔傜偲偄傆憪巻桳丄枖拞嫽愳墇偦偆傔傫偲偄傆彂偁傝丄偐傟傪尒惀傪堏偟偰偆偨偐傢偟偒傪棦榁偵恞偹丄擭偆偮傝悽偐傢傝偰巬愜偵傕側傜傫偐偟偲
丂偄偵偟傊傪崱偵偆偮偟偰傒傛偟栰偺丂婂傢偨傞栭偺桭偲傗偼偣傫丂丂丂丂奀庻挊 | ||||