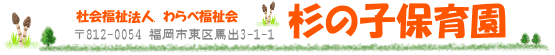
園便り
おおきいなかま、あつまれ~!
保育者と父母を結ぶ雑誌「ちいさいなかま」の紹介をします。
「ちいさいなかま」を読んで感じたこと、思うことを伝えたい! そんな気持ちをお届けする連載です。

12月号をめくると1ページ目には、「せんせい みてみて! どんぐりさん パジャマ着ているねー」と、子どものつぶやきからはじまります。子ども達ならではの目線で、とてもほっこりしますね。以前、どんぐりのぼうし(かくと)が取れているものを見つけた子どもが、「どんぐりさん寒いから」と、そっと被せていた光景を思い出しました。子ども達の感性って素敵だなと思いますね。
さて、今月の特集は~幼児の「イヤ」をどう考える?~です。読者からの一言では、「保育園行くのイヤ」「お風呂に入るのイヤ」「まだ寝たくない」など保護の方は、こんな場面あるあると共感できるような事が沢山書かれています。その時の対応方法として、「○○したかったんだね」と、子どもの気持ちを受け止める。子どもの気持ちが落ち着くまで待つ。「○○しようね」など、子どもが気持ちを切り替え、気持ちよく行動が出来るような声の掛け方、対応が記載されていますが、もちろんいつも上手くいくわけではなく、「○○しないなら○○しないよ」「○○しなさい」と、子どものイヤが更に激しくなってしまった場面もたくさん書かれています。分かってはいるけれど、大人もイライラしてしまったり、むきになってしまう事ってあると思います。私もついつい「なんで?」と、むきになってしまうことがあります。吉田真理子さんの小論には、そんな子どもの「イヤ」にどのようにして関わって行けばよいのか?子どもの「心の成長」について書かれています。乳児期の「イヤ」と幼児期の「イヤ」とでは、子どもの想いも複雑になり、大人の関わり方も違ってきますよね。私は特に『「イヤ」から見えてくる子どもの心の成長、どのようにイヤを表現するようになってきたのか、注目すると面白いかもしれません。』と、最後の文が印象的でした。その時の状況やその子一人ひとりによって「イヤ」の出し方は違いますが、大人が「イヤ」をどうとらえていくのかが大切なんだと思いました。
私のクラスでは、1歳半を迎えた子も多く、ちょうど「イヤイヤ期(乳児期)」が始まってきました。自我が少しずつ芽生え、「○○したかった」「ジブンデ」という思いも出てきました。洋服をジブンデ選び、大人が手伝おうとすると「イヤ、しないで」という場面もあります。これから成長するにあたり、いろんな表現をしていくんだろうなと思いながら読みました。「イヤ」を出すことは、子どもの成長にとって大切なことであり、大人は子どものイヤに隠された想いを受け止めて理解していくことで一緒に成長できるのではないかと思いました。また、大人の心の余裕も持っておきたいですね。
毎月連載、平松さんの「きょうもほっかりスイートで」を読んで「そうだよね。」と気づかされたと同時に、2月の子育て保育のつどいにも是非参加したいと思いました。保護者の皆さんもご一緒に参加されてみませんか。