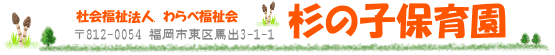
園便り
おおきいなかま、あつまれ~!
保育者と父母を結ぶ雑誌「ちいさいなかま」の紹介をします。
「ちいさいなかま」を読んで感じたこと、思うことを伝えたい! そんな気持ちをお届けする連載です。

『ちいさいなかま2月号』では、本の紹介に目がとまりました。本のタイトルは「赤ちゃんからはじまる便秘問題」です。少し長いですが、引用します。
著者は小児外科医。さいたま市立病院で排便外来を開いています。目からうろこなのは、便秘には食物繊維などと食事のことを考えますが、それは大腸までの話。子どもに多いのは本来からっぽの直腸にたまってしまうもので、浣腸などで1~2日で出し、伸びた大腸を元に戻すことが必要、浣腸が癖になるということはない!「溜まっているなら出せばよい、幼い子どもに精神論はやめて出せるように手助けすればよい」とのあとがきに拍手
そうなんですね。「排便外来」という科があることにも驚きましたし、浣腸した方がいいのだということもわかりました。我が家の息子も4歳くらいのインフルエンザの季節に熱を出し、出張先から呼び戻されたのですが、百道の救急センターに連れて行ったら、「便秘」の診断でした。便秘って大変です……。
☆「赤ちゃんからはじまる便秘問題」中野美和子著 言叢社 ¥1500+税
連載の中で、いつも気になるのは、岩川直樹さんの『ことばからみる今』です。今回のタイトルは「評価の対象はひとじゃない」です。
教育といういとなみの中で「評価」ということばは、たいていは「ひとを評価する」ときに使われる。「子どもの成績の評価」とか「教員の力量の評価」だったりする。だが、教育といういとなみの中で評価が果たすもっとも重要な働きは、ひとを評価する事ではなく、ひとと出来事を評価する事にあるのではないか。1学期の終わりになって、声のかぼそい小学2年生のミキさんが、はじめてみんなの前で音読をした。工藤直子の『のはらうた』の中の「はきはき」という詩だ。トンボから「あそぼう」と誘われたのに、何も応えられなかった「みのむしせつこ」が、その晩、「はい!あそびましょ」という「へんじ」の練習をするという詩だ。ミキさんが小さな声で読み始めると、遠くの席から近寄ってくる子ども達の姿がある。息をのむように見守りながら、一言、一言、ミキさんといっしょに読んでいる子どもたちの表情もある。読み終わったミキさんが溜息をつくとみんなが拍手し、その中でミキさんの顔にはじめて笑顔が浮かぶ。こういう小さなかけがえのない一つひとつの出来事によって、教育といういとなみは織りなされている。それは、ミキさんと教室のみんなと担任の教師のこれまでがあったからこそ生まれた出来事であり、これからの教室をつくる起点になる出来事だ。担任の教師は「これがこの教室の1学期の成果だと思います」という一文を添えて、その出来事を学級通信に書いた。それを読んだミキさんのお母さんが「ミキは読んでくれました。蚊の鳴くような小さな声で堂々と」こうした小さなかけがえのない出来事の意味や価値を分かち合うこと、それこそが、教育といういとなみの中で重視されるべき評価だったのではないか。
こんな実践ができるといいなあと思います。一人ひとりの子どもに寄り添い、それがクラスの子ども達に伝わり、あったかい雰囲気を創り出すことがステキだなあと思います。点数の評価ではない、中身の充実した教育や保育が認められるといいなあと思います。
特集は「もっと豊かな保育がしたい!!」これは、私たちの切実な願いです。ミキさんの実践のような、ていねいな保育がしたいです。保育園はいま、深刻な人手不足の状態です。福岡市内では、ここ数年で新しい保育園や認定こども園、新制度での小規模保育園など保育園の数自体は増えました。しかし、そこで働く職員の確保が難しいようです。また、テレビや新聞などで職員の処遇の低さが、あらわになり、その影響もあるようです。給食室からの「あと一人いればいいのに……」という話も共感することがいっぱいです。かつて出来ていた事が、今はできないというジレンマがあります。でも、この話の最後の一文・・・「私たちは微力だけど無力ではありません。」という言葉に勇気と元気をもらいました。