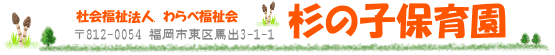
園便り
おおきいなかま、あつまれ~!
保育者と父母を結ぶ雑誌「ちいさいなかま」の紹介をします。
「ちいさいなかま」を読んで感じたこと、思うことを伝えたい! そんな気持ちをお届けする連載です。

梅雨に入り、お部屋で過ごすことが多かった6月、晴れた日は嬉しそうに外であそぶ子どもたちの姿が見られました。外に出ると、子どもたちだけではなく、草花や虫も夏に向けて、元気に活動を始めています。
7月号の「ちいさいなかま」は、『子どもと虫』という特集です。私が担任をしているれんげ組の子どもたちは、外あそびの際に、ちょうちょうが来ると、目で追ったり、指をさしたりする子がいたり、追いかける子がいたりします。虫に対しての興味は持っていますが、一人一人反応が違います。
お子さんは虫を見るとどのような反応をしますか?
この特集を読んで、私の子どもの頃を思い出しました。子どもの頃は、園庭にいるダンゴムシを丸くさせようと人差し指で突いていた思い出があります。れんげ組の子どもたちもダンゴムシが好きで、捕まえては容器にいれて観察したり、つまんでみたりしています。子どもたちのダンゴムシに対する関わり方を見ていると、私が子どもの頃と変わらないなと、童心に返って、子どもたちと一緒にダンゴムシを探しています。
父と一緒にカブトムシを捕まえた思い出もあります。父が高いところにいるカブトムシを虫網で捕り、虫かごにいれますが、当時の私は、カブトムシのたくましい姿に圧倒されて、虫かごを持てませんでした。
好感をもたれているチョウ・ホタル・カブトムシなどの昆虫に接する体験や文化を体験してきた子は虫をすき煮なり、ハエ等の嫌悪的な虫に接する体験や文化を体験してきた子は虫嫌いになると、特集の中で、高家さんはおっしゃっています。ダンゴムシのような小さな虫なら保育園から帰るときや、帰る途中の草地でも見つかると思います。子どもと一緒に探してみてください。触れなくても接する経験をつくれたらいいですね。7月号の「ちいさいなかま」では、ちょうちょうを呼ぶ方法や、虫の飼育方法が載っています。ダンゴムシの飼育方法など知っているようで知らない飼育方法もあり、とてもためになりました。7月号の「ちいさいなかま」を読んで、お子さんと一緒に見つけた小さな虫を飼ってみるのもいいと思います。
ツマグロちゃん(ツマグロヒョウモンというちょうちょうの幼虫)を飼った保育の実践コーナーもありました。子どもたちは充分に命や死をとらえられる年齢ではないですが、虫が何を食べるかということから考え始めて、実際に飼ってみて命が絶えたときに、命の大切さから、自分や人を大切にすることを学びます。すぐに答えを見つけるのではなく実際に飼ってみてじっくりと考え、学んでいくことで子どもたちの理解が増していくということが分かりました。命について書かれてあると思うと重い内容ですが、子どもたちがツマグロちゃんを可愛がったり、落ちた蛹をボンドでくっつけたりする姿が書かれていて、とても可愛らしいです。
『子どもと虫』という特集だけではなく、『おいしいヒミツ教えます!』のコーナーでは、アレルギーを持つ子でもおいしく食べられるレシピが紹介されており、朝・夕ご飯に持ってこいです。今日から使えるような内容ばかりですので、是非ご覧ください。