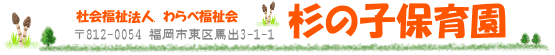
園便り
おおきいなかま、あつまれ~!
保育者と父母を結ぶ雑誌「ちいさいなかま」の紹介をします。
「ちいさいなかま」を読んで感じたこと、思うことを伝えたい! そんな気持ちをお届けする連載です。

8月は全国合研から始まり、暑い(熱い!?)夏になると思いきや、後半は雨ばかりでなんだか物足りなさを感じています。夏の終わりは寂しいですが、これから過ごしやすくなるので、子どもたちとたくさん散歩に出掛けて楽しんでいこうと思っています。
今回は、子どもの発達と遊び“ごっこあそび”(8月号の続編)の記事について書こうと思います。
この記事を読みながら、自分の子どもの頃のごっこを思い出してみました。おそらく、年長の頃だと思いますが、“ムササビごっこ”をよくやっていました。園庭にあるBOXが重ねてあるような大型遊具を住居にして、ムササビの家族の役割を決め手は、住処から飛び立っていき(両手を広げて走っていく。)お父さんムササビは仕事へ、お母さん(大体私はお母さん)は料理(泥団子など)を作ったり、子どもは自由に過ごすという、なぜ“ムササビ”だったのかはなぞですが、楽しかった思い出があります。
今、私は2歳児の担任をしていますが、“みたてあそび”“ふりあそび”が“ごっこあそび”へと変化していきます。最近楽しいのは、“保育園ごっこ”です。保育士になっている子どもは、くま人形を寝かしつけながら「アカチャンネテルノデ、シズカニシテクダサイ。」と言ったり、お母さんになっている子は、くま人形を保育士のところに持ってきては「オハヨウゴザイマス。キョウハ、プールバツニシテイルノデ ハイレマセン。ヨロシクオネガイシマス。」とくま人形を預けていったりと、まるで本当の大人みたいな会話を楽しんでいます。毎日、“子どもたちはよく見てるな~”と感心しつつも笑わせてもらっています。
今は、それぞれのイメージで遊んでいる子どもたちが、言葉を介して友だちとイメージを共有したりして、より“ごっこあそび”が楽しくなっていきます。ごっこ遊びを通して、友だちのイメージを受け入れたりする中で、人との関わり(コミュニケーション)も学んでいきます。想像力でなりたいものになれるごっこあそび、大人になった今ではできないこの遊びを保育園の時期にたくさんさせていきないな~と、改めて感じました。子どものイメージ遊びを豊かにするためには、子どものイメージに共感していくこと、子ども同士のイメージのずれを上手く大人がつなげていくことが大切なようです。子どもと一緒にイメージの世界で遊んでいきたいと思います。