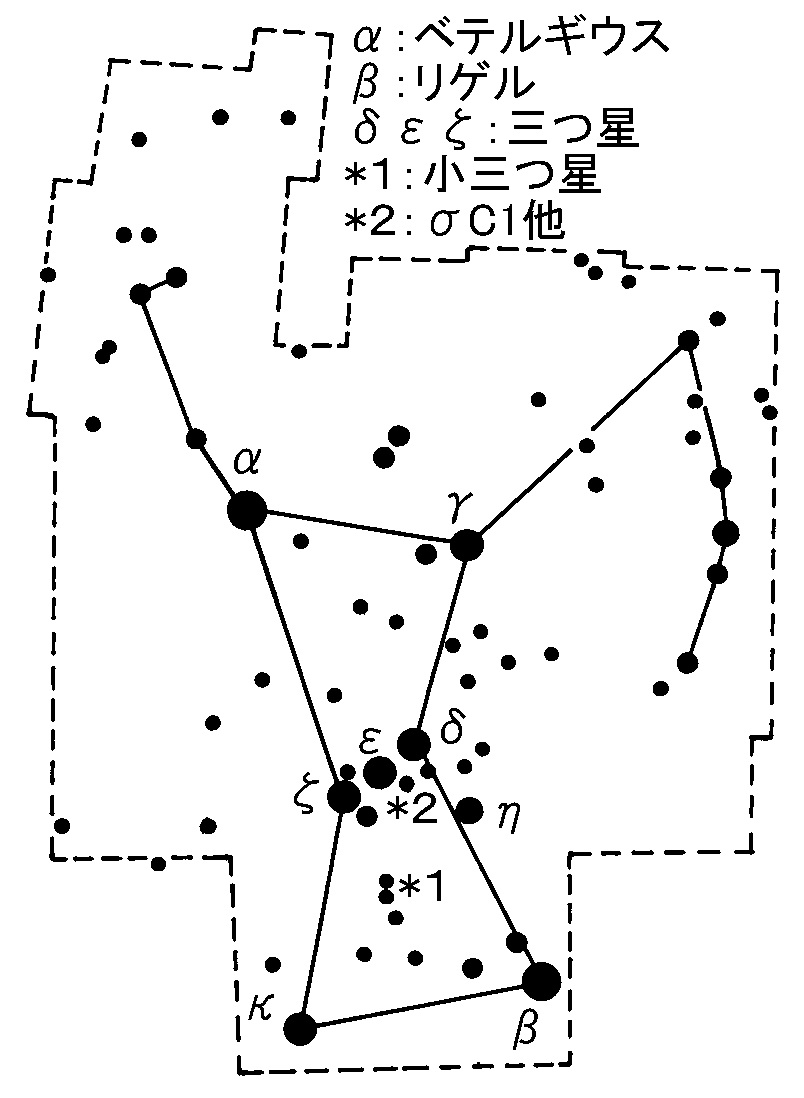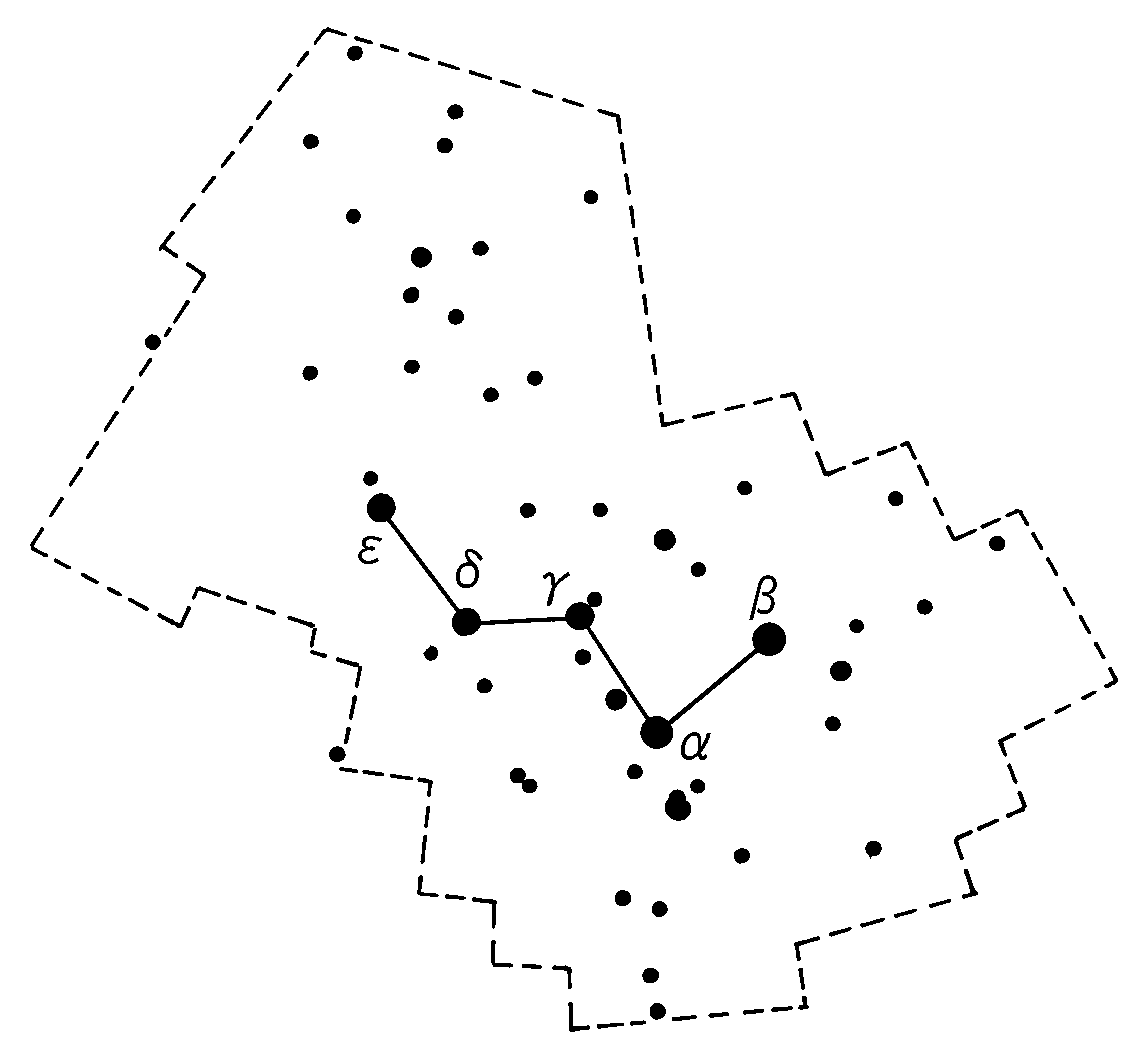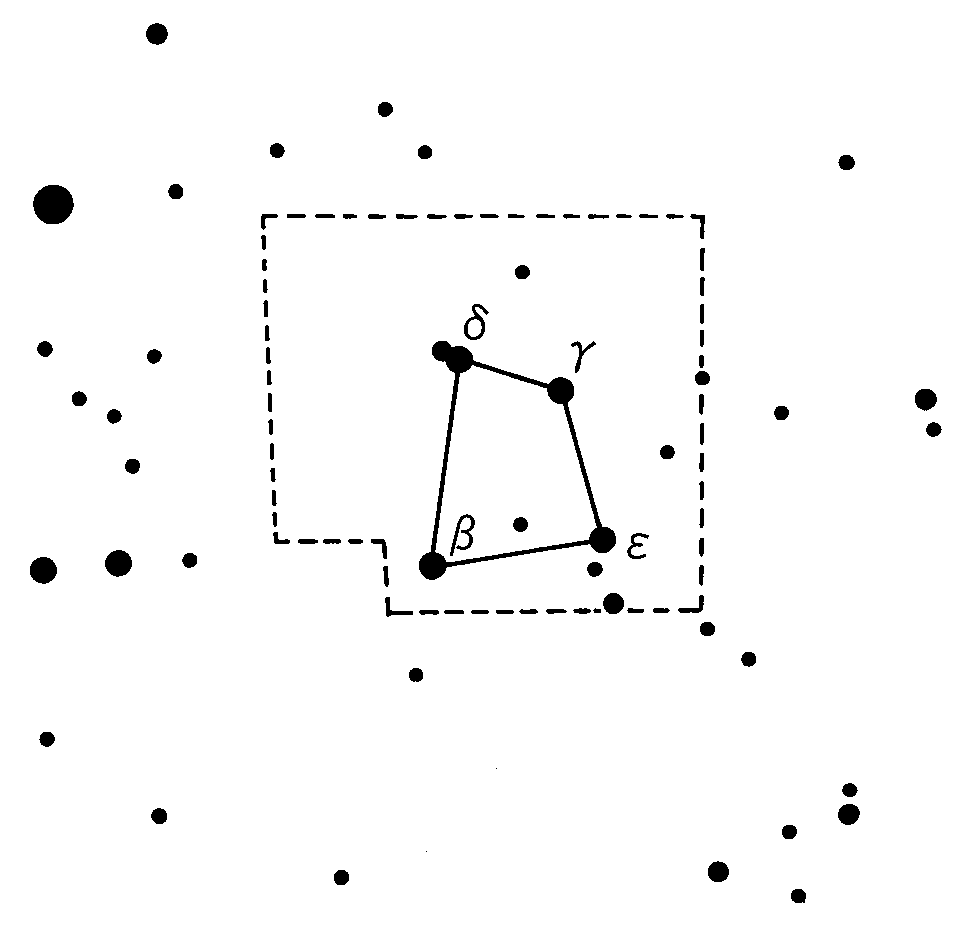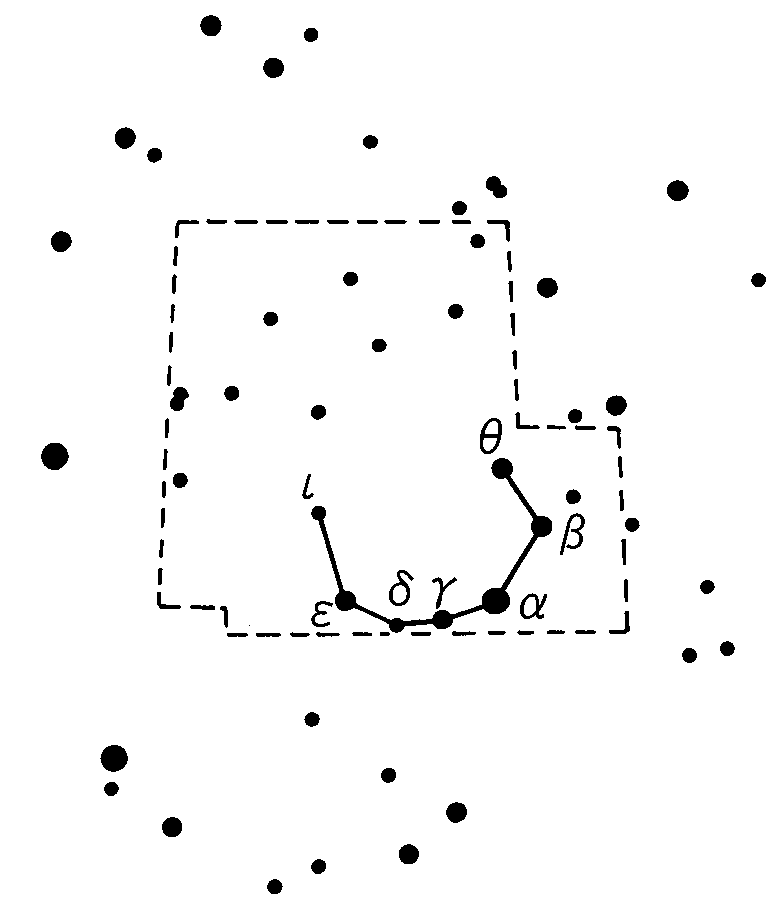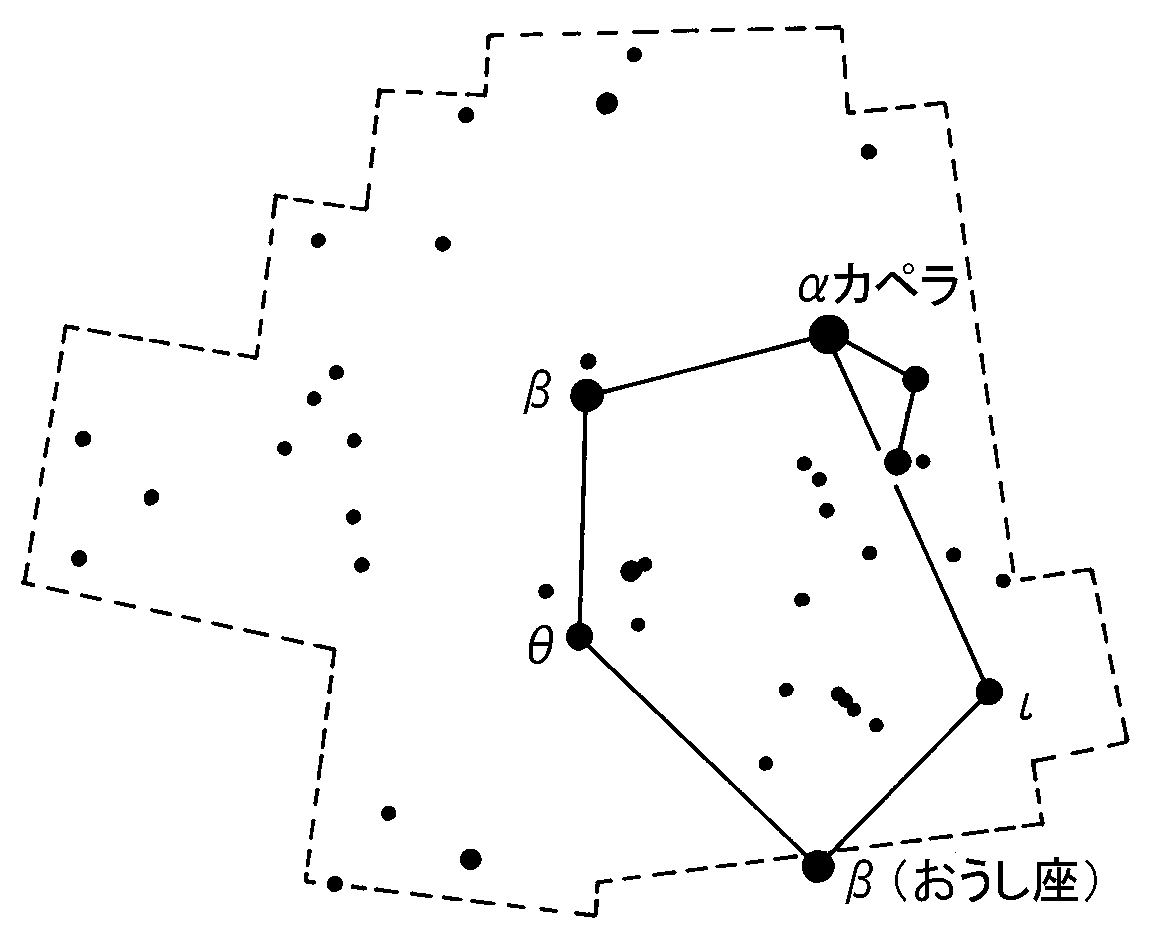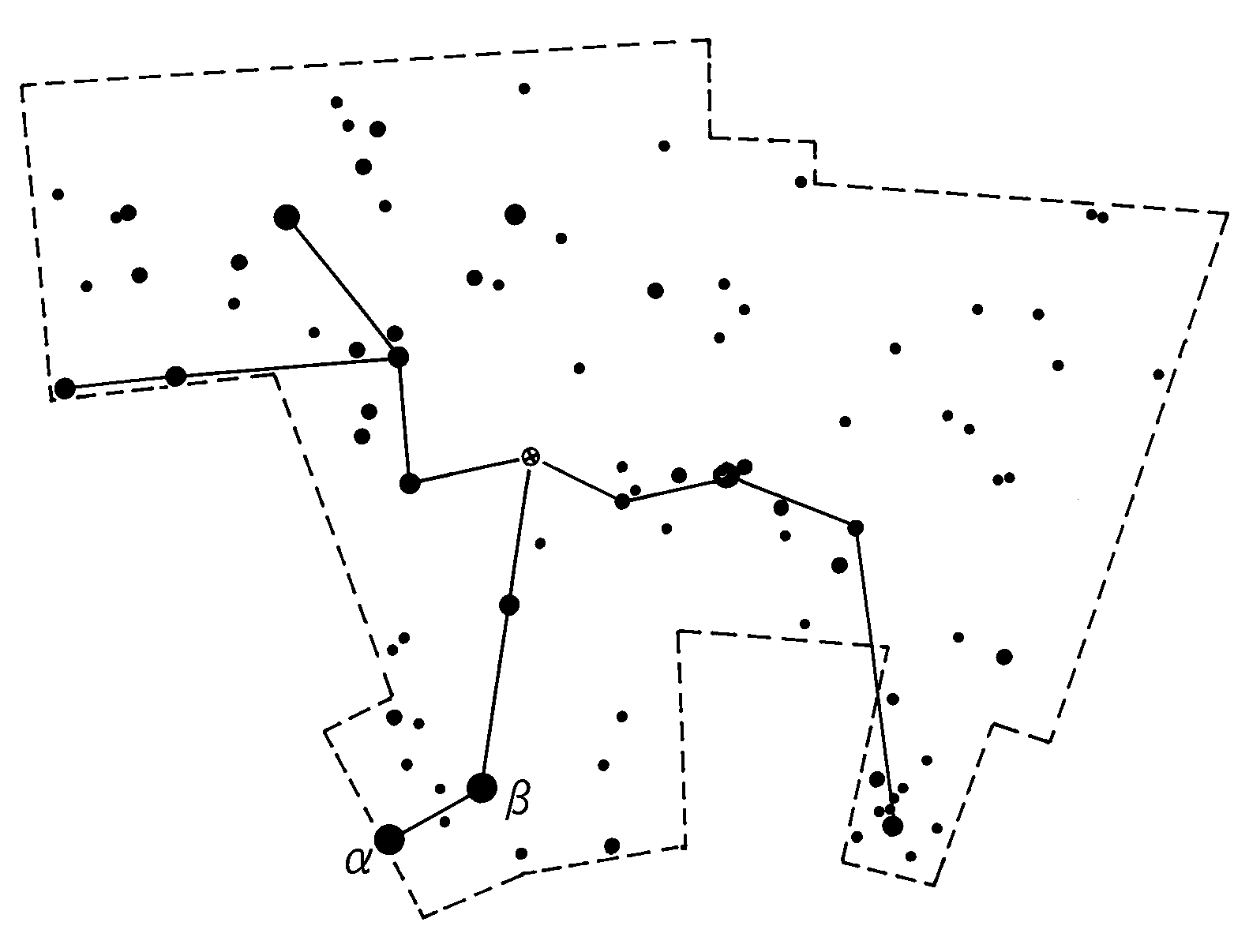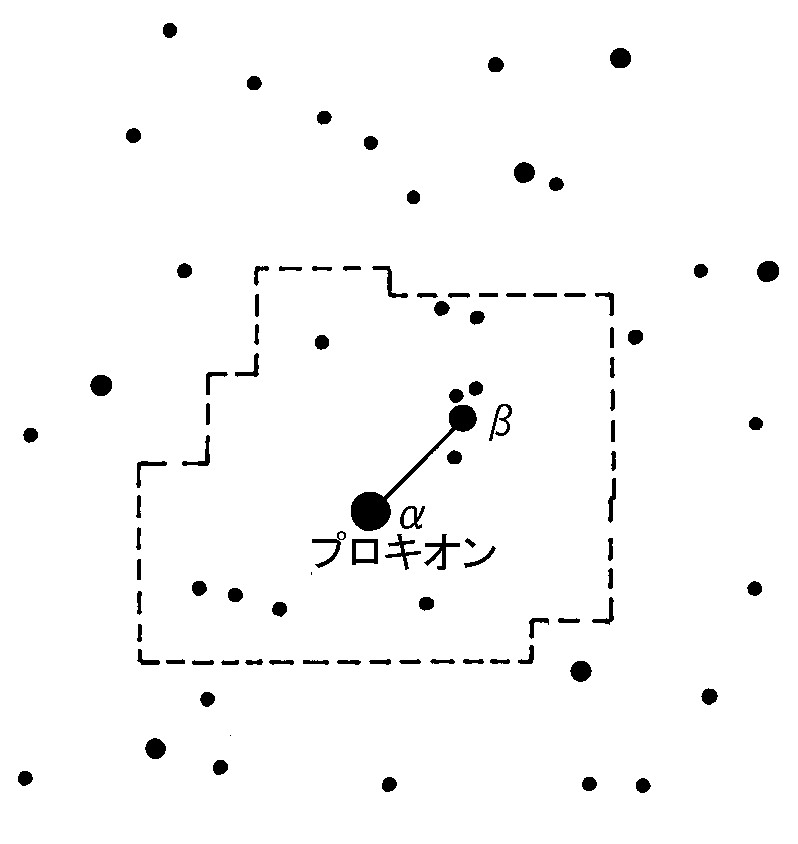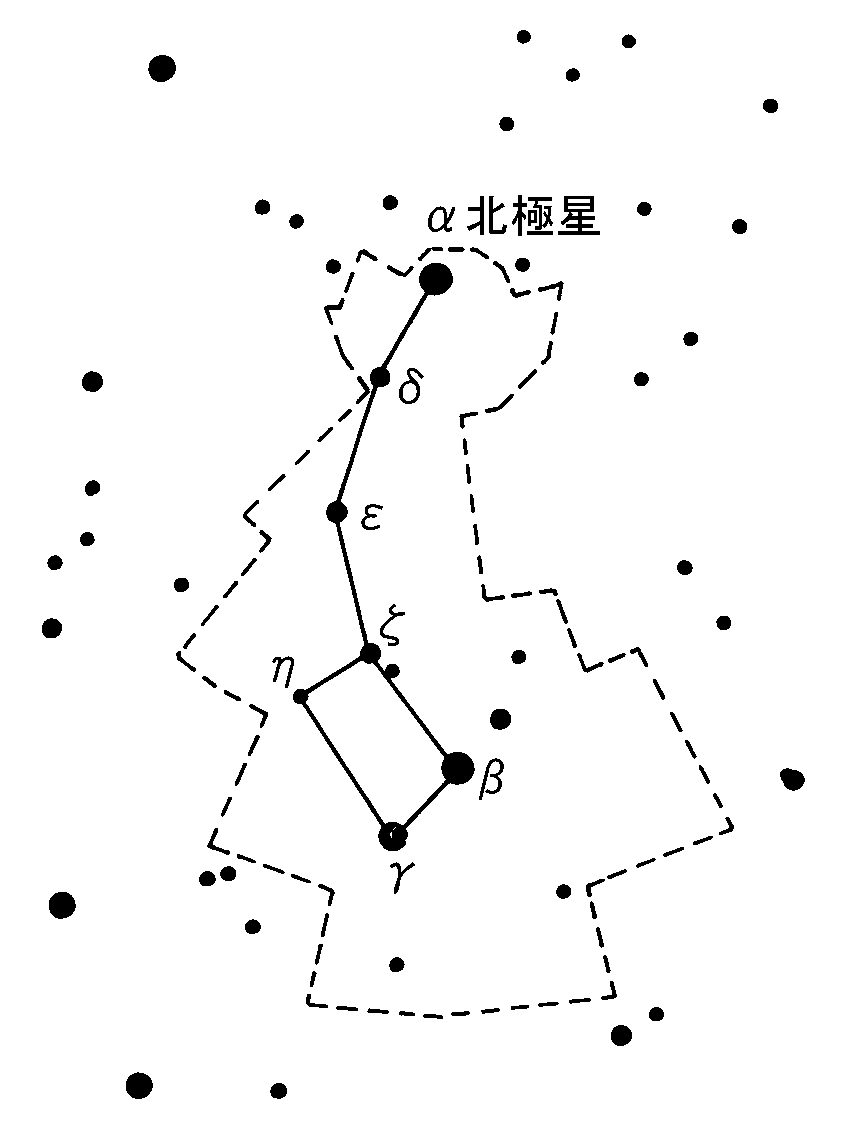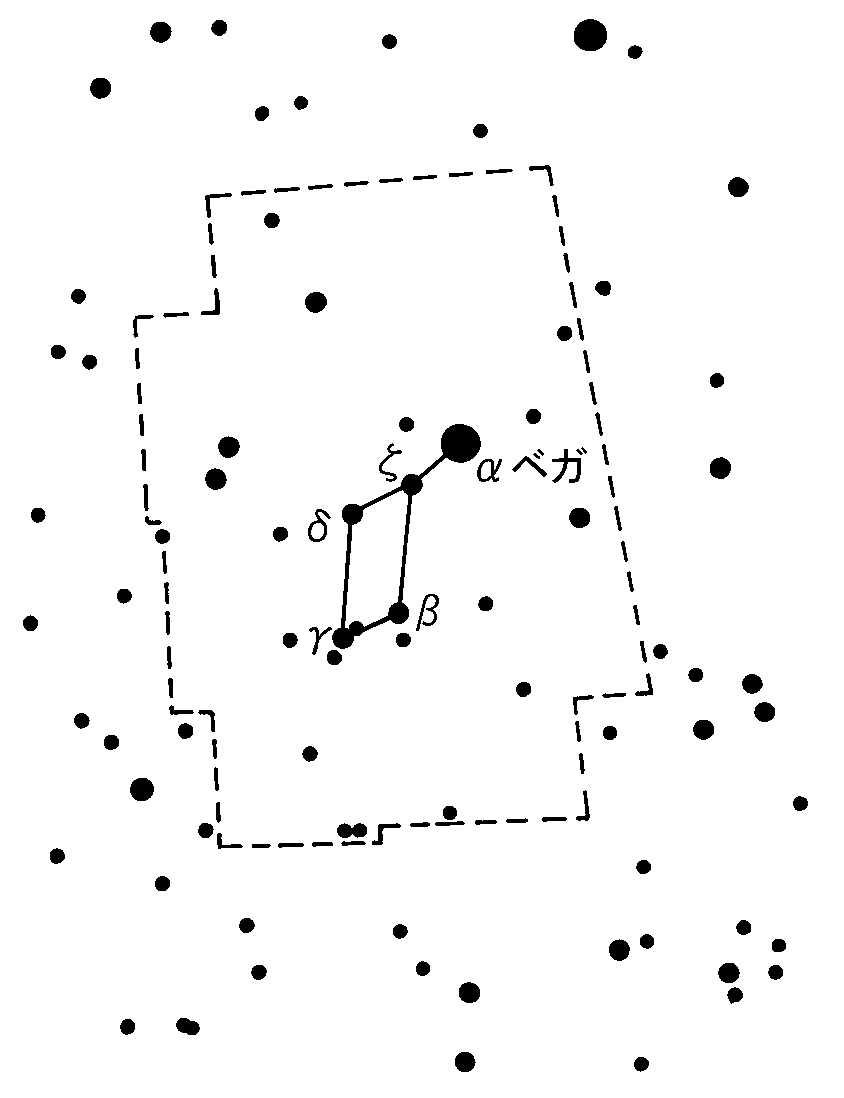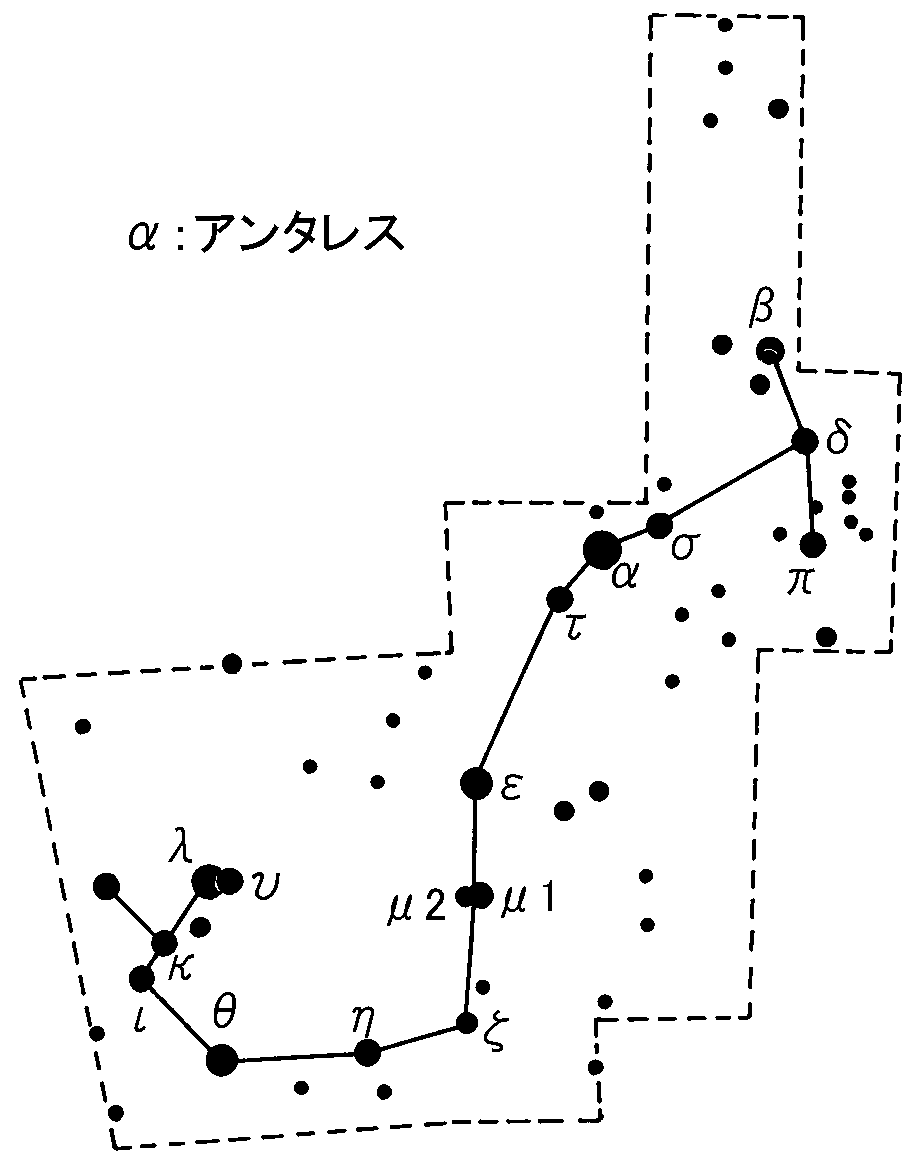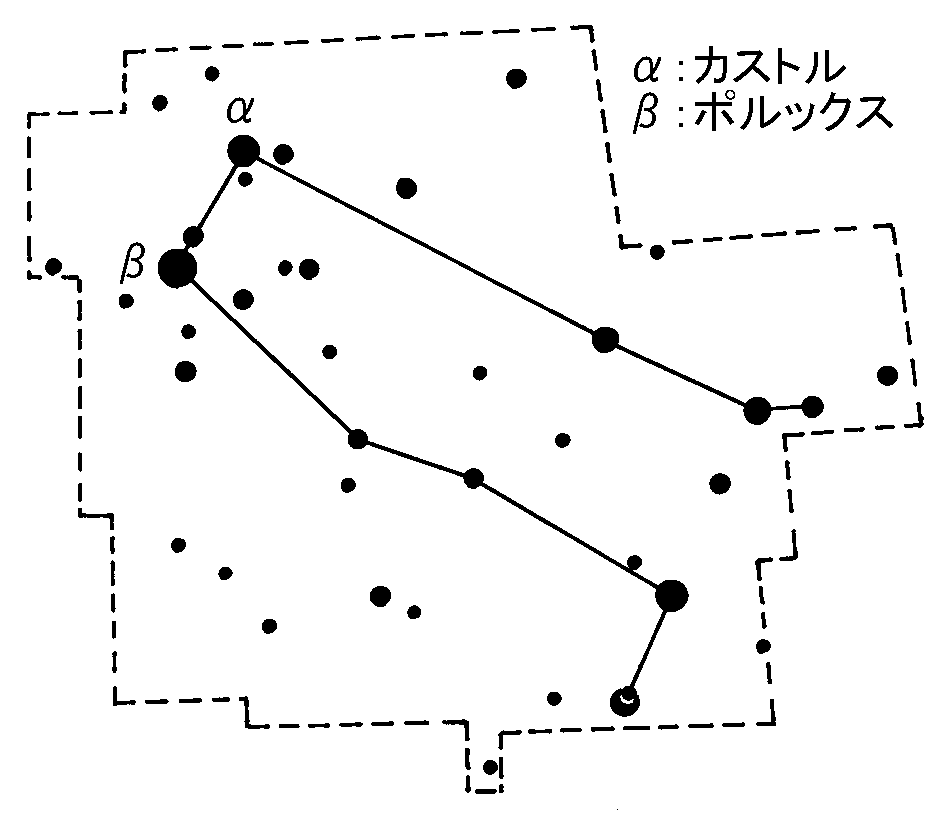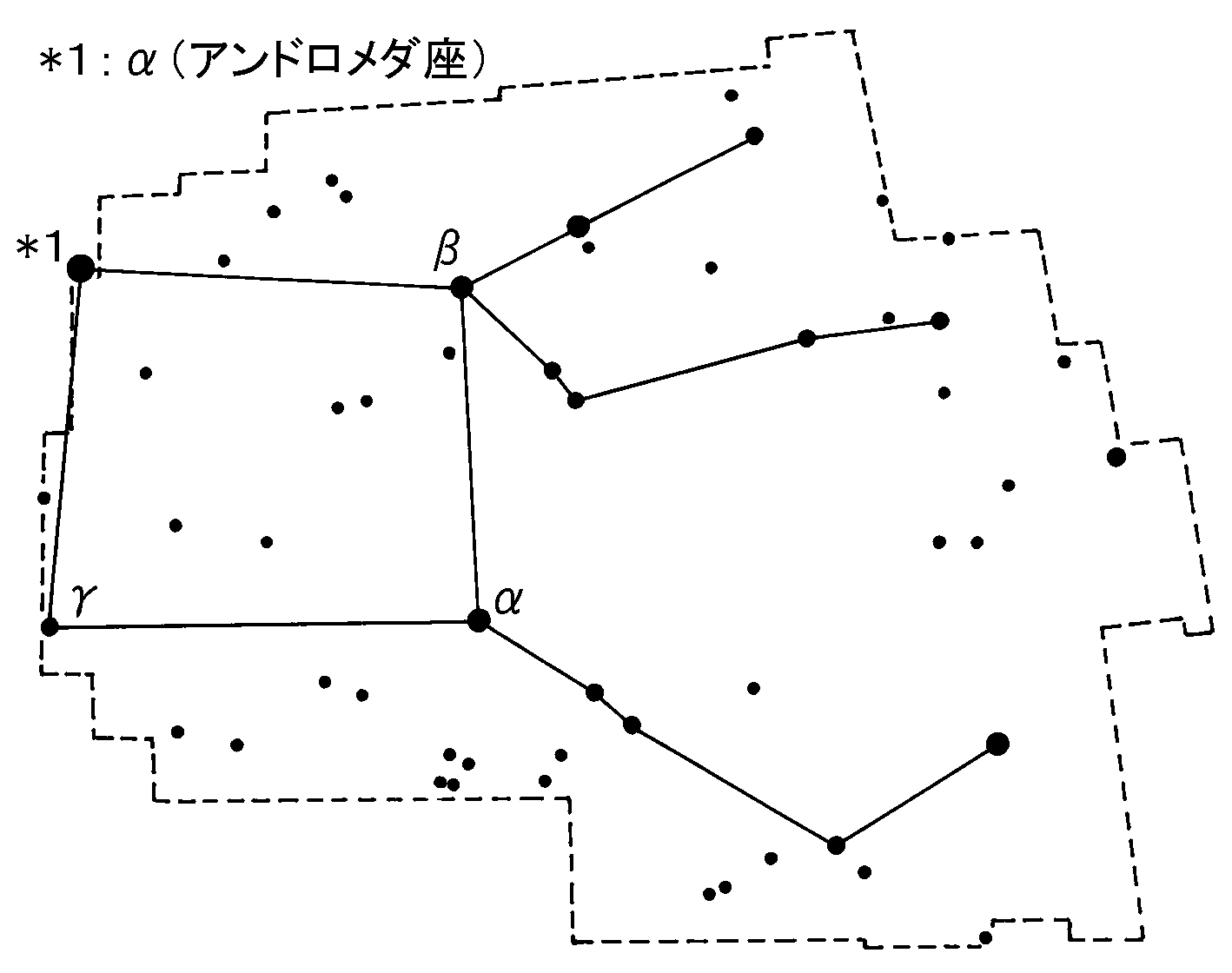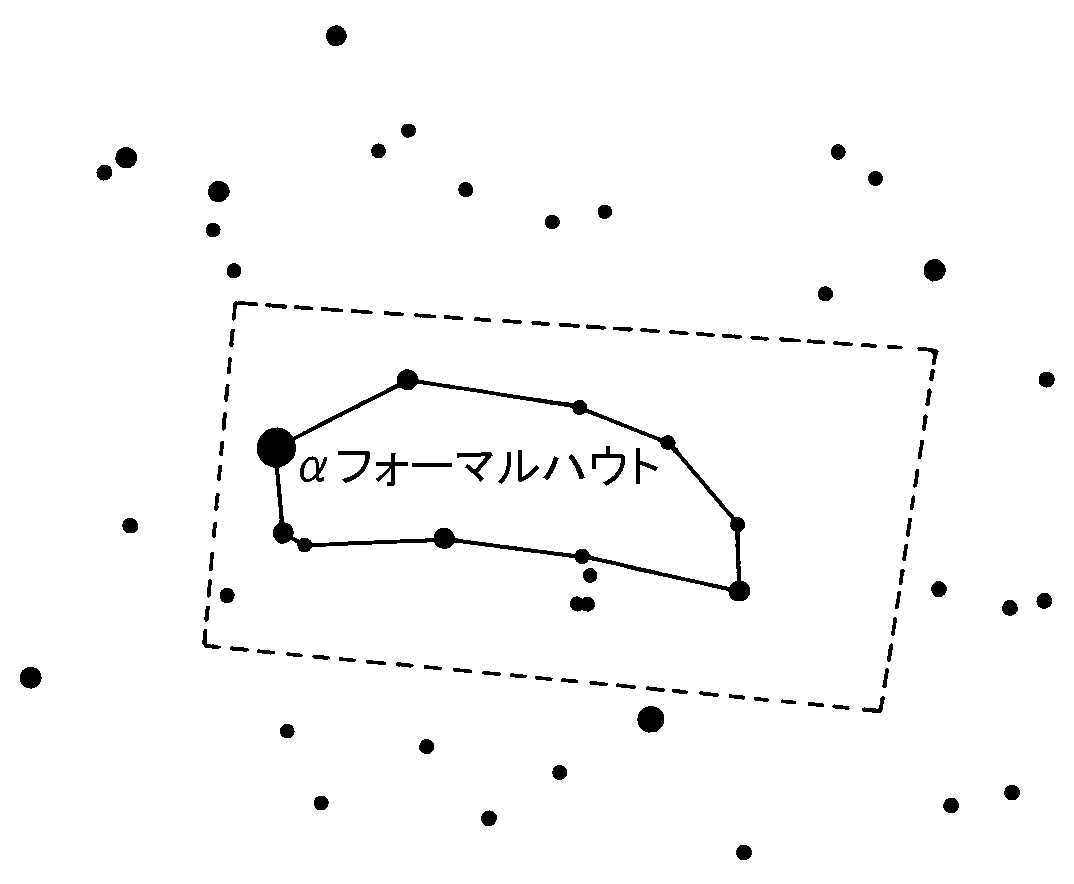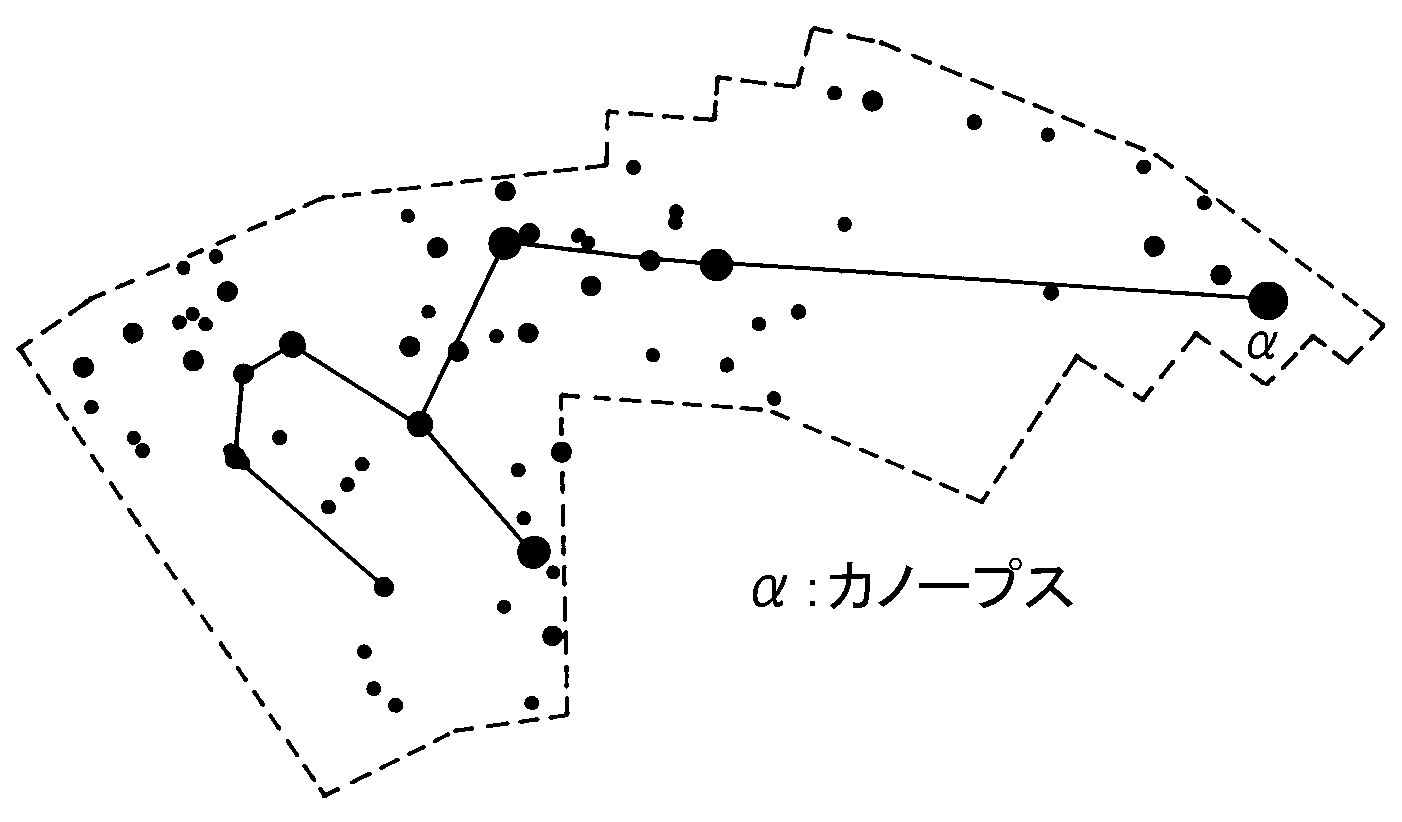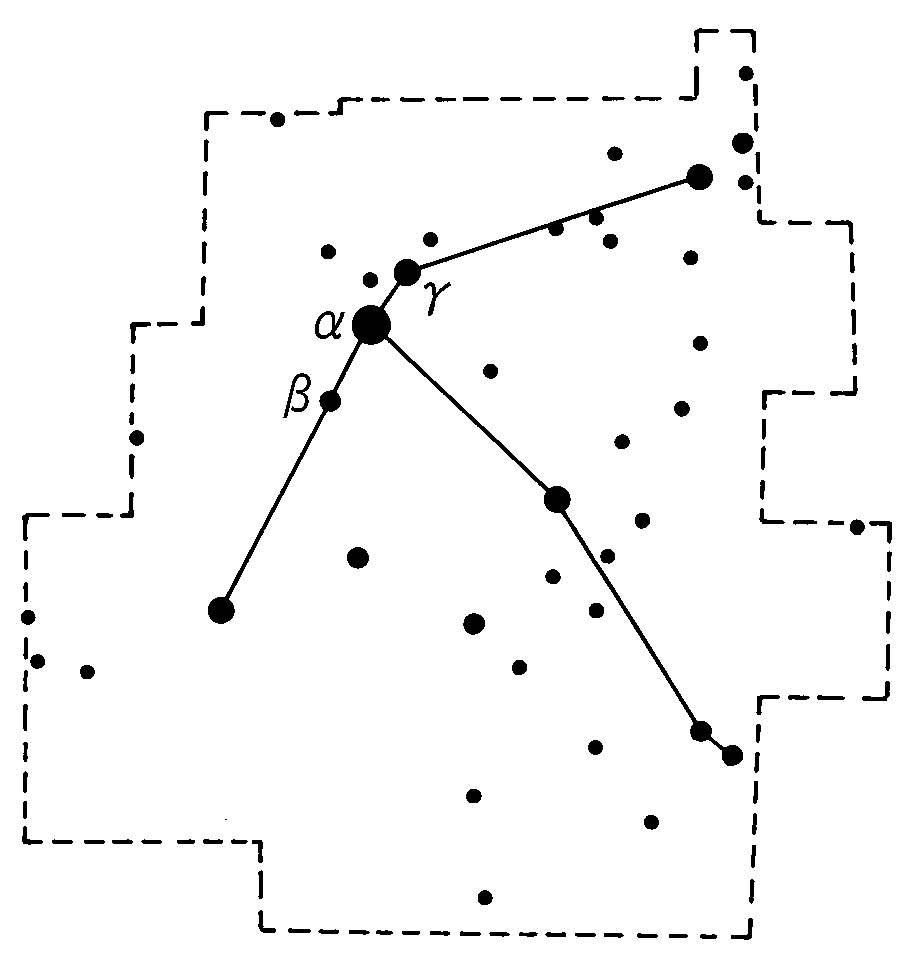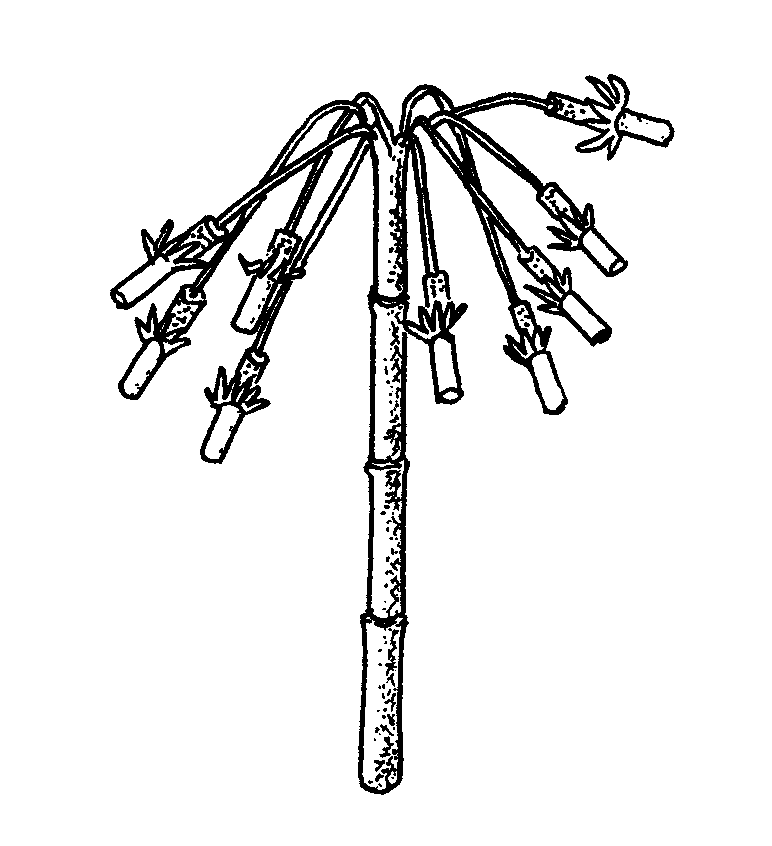いて座
2013/06/23
|
| いて座は、銀河系の中心方向にあたり、天の川がいちだんと輝いて見える
場所に位置しています。ギリシャ神話では、半人半馬で弓を構える姿として伝えられ、このうち弓の上端から矢じりを持つ右手
へと連なる六つの星は、小さな柄杓を形づくっているのが大きな特徴です。中国では、これを北天の北斗七星に対する南斗六星とし、
生と死にまつわる伝説が知られています。星の名が記録されているのは、やはりこれら六つの星(ζλμστφ)ですが、総じて
生業との結びつきはそれほど強くない星座の一つです。
|
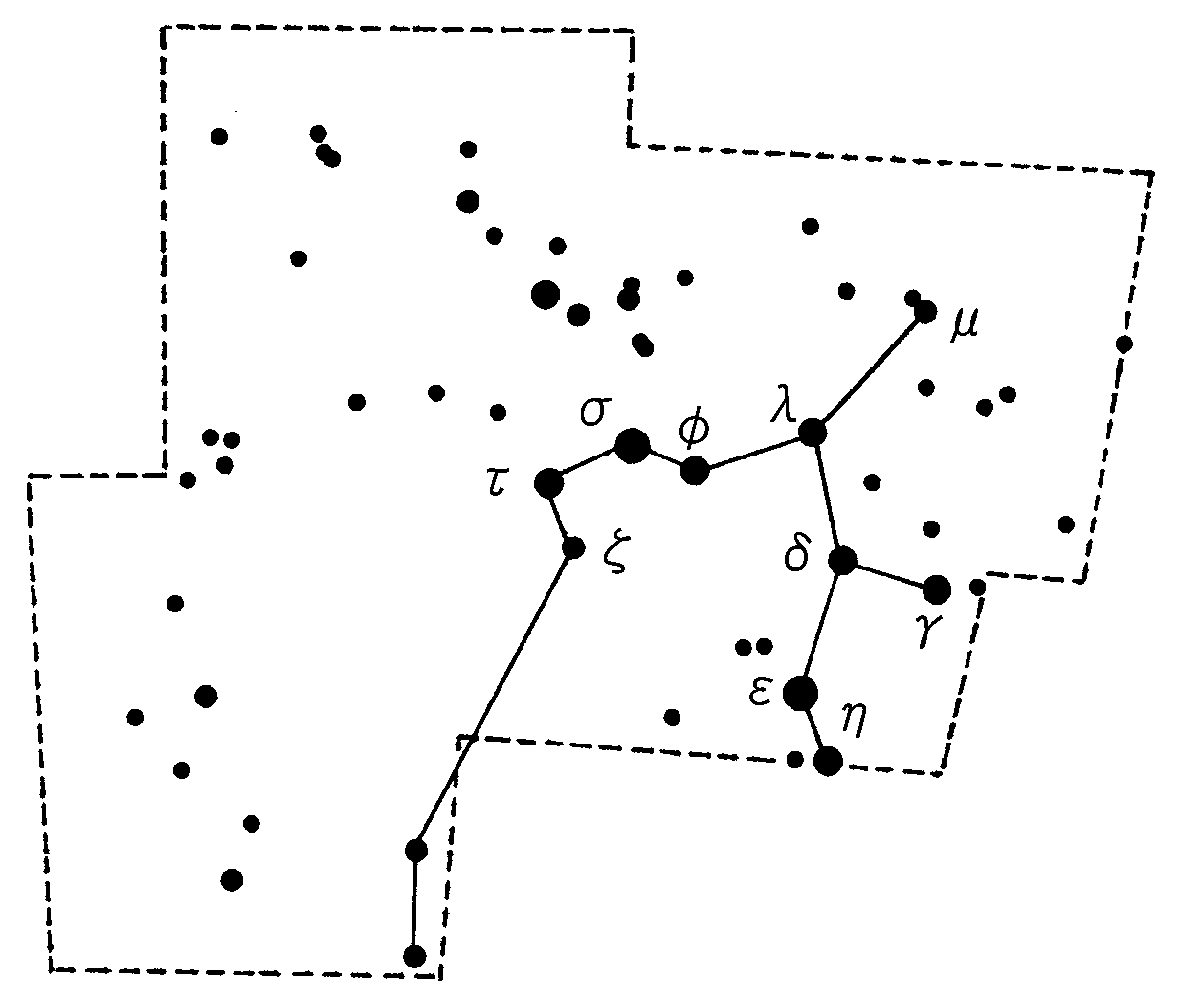
| 南斗六星(ζλμστφ) |
|
|
おうし座
2022/06/25
|
| おうし座は、猟師オリオンに向かっている牡牛として知られています。
この顔の部分にあたるヒアデス星団からβ・ζの両星に延びる線が勇壮な角を表しています。星の名の対象になっているのは、
ヒアデス星団と唯一の1等星アルデバラン、それに有名なプレアデス星団です。アルデバランの場合は、ほとんどがイカ釣り
の指標星としての命名であり、他の星との位置関係を端的に説明した呼称が主流といえます。この星の周辺に集まっているの
がヒアデスという散開星団で、アルデバランとともに「>」形あるいは「∨」形の配列を構成しています。この形が、魚網や
イカ釣り具、釣鐘など、さまざまな発想の原点となっているわけです。 さて、おうし座といえばプレアデス星団があまりにも有名ですが、夜空の宝石といわれるこの星団には、もっとも多くの星名 が記録されています。地域的な特色が顕著に表れている事例も少なくありません。由来となる見方は主に3タイプあり、 〈Ⅰ〉星の集まりによるもの、〈Ⅱ〉星の数によるもの、〈Ⅲ〉星の配列によるものに分類することができます。〈Ⅰ〉型は スバルやスマルなどに代表されるもので、多様な転訛がみられます。〈Ⅱ〉型は肉眼の星の数に基づいて6という数字を基本と しますが、なかには7や9にまつわる呼称もあり、多様性に富んだ星名系列といえるでしょう。また〈Ⅲ〉型では、漁具や 炭焼き用具、生活用具などの形状を星の配列に模した見方が一般的です。生業や地域を問わず、もっとも広く利用された星座と して位置づけられます。 |
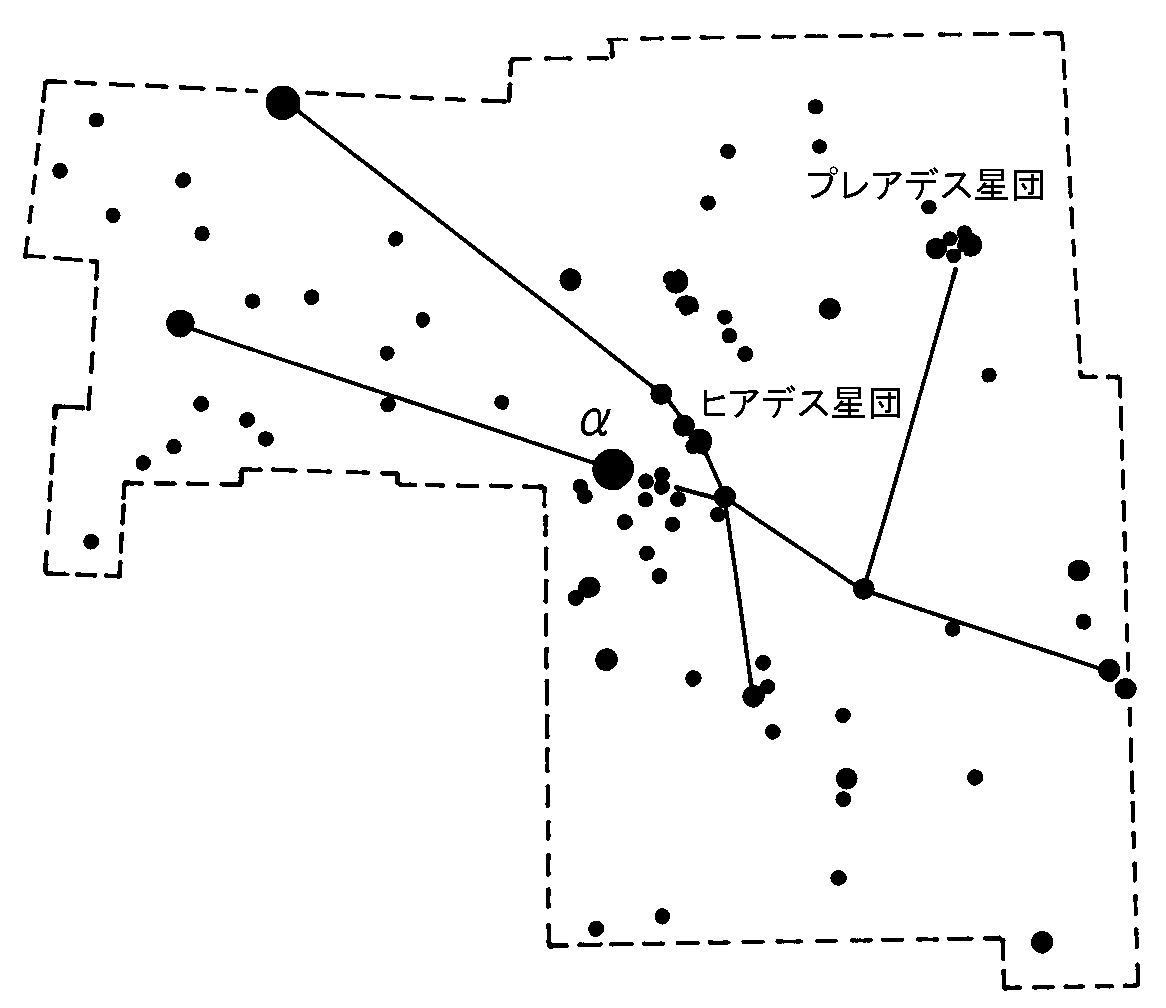
| アルデバラン(α) | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ヒアデス星団 | |||
|
|
|
|
|
| プレアデス星団 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
おおいぬ座
2020/09/25
|
| おおいぬ(大犬)座はオリオン座の南東に位置し、全天一明るい恒星
シリウスを擁する星座です。オリオンに続く猟犬として知られますが、シリウスがちょうど口の部分にあたり、δ・ε・ηの
3星でつくる三角形が胴体から尾の部分に該当します。星の名もシリウスと三角形の星に集中し、前者は北国を中心としたイカ
釣り漁において、重要な指標星の一つでした。呼称としては星の色に基づく呼び名がいくつかあります。しかし、主流はあくまでも
イカ釣りにおける指標星としての存在であり、アルデバランと同様に、他の星との位置関係に星名の多様性が表れています。 |
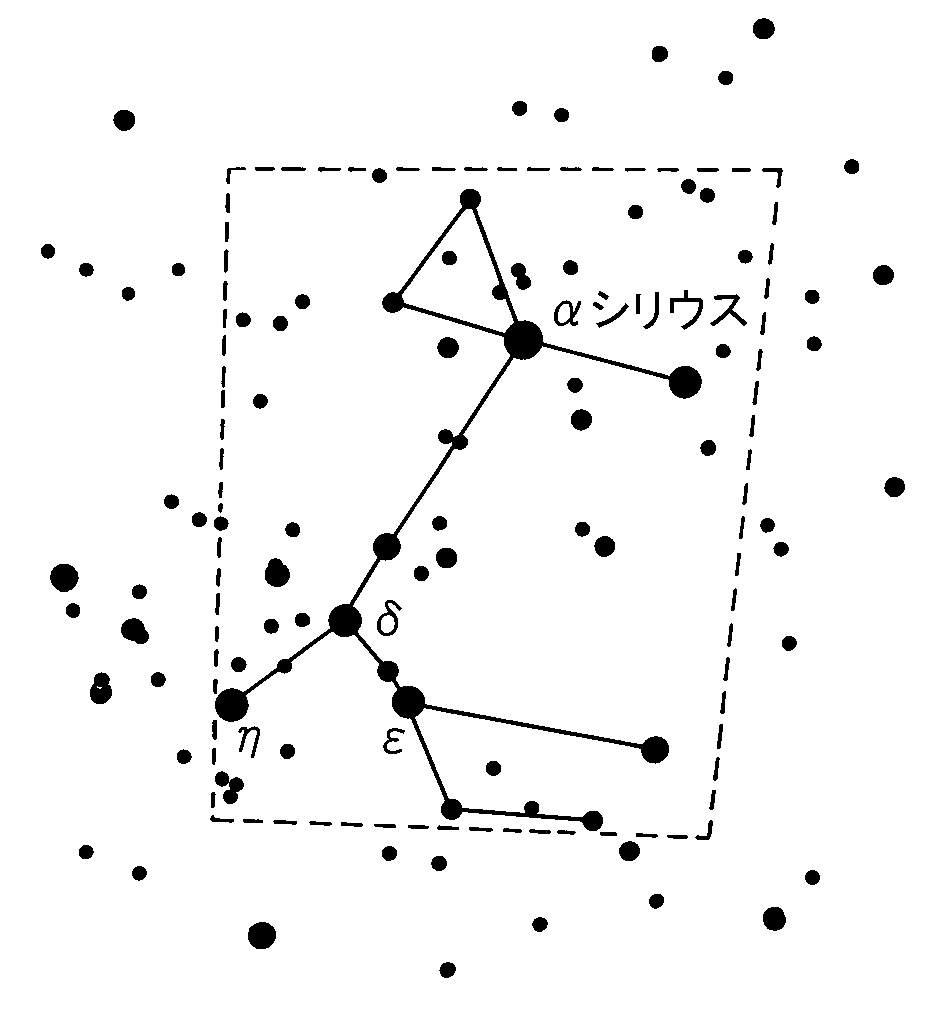
| シリウス(α) | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 三角形の星(δεη) | |||
|
|
おおぐま座
2023/05/25
|
| おおぐま(大熊)座は北天をめぐる星座で、勇猛な熊として知られています。
この熊の背中から尾の部分を構成するのが北斗七星で、北半球の中緯度地方から北では周極星として沈むことがありません。
したがって、この星の位置によって季節や時刻を知ることが、利用に際しての主な役割を担っています。星の名は北斗七星に集中
しており、「七」という数字に基づく命名が主体です。これには単純な星の数をさすものと、そこに信仰的な要素が加わったタイプの
二つがあり、いずれにも多くの転訛形がみられます。もう一つの特徴は、北斗七星全体あるいは一部を生活用具などの形に喩えた
呼び名の存在で、身近な炊事用具から漁労関係の装備にまで及んでいます。夜空では、北極星をさがす目印の星(指極星)としても
よく知られていますが、こうした位置関係や星の動きが、説話や俚謡となって伝えられている事例もあります。特異な星の配列と
七つの星という組み合わせは、多くの民族に注目されていました。
|
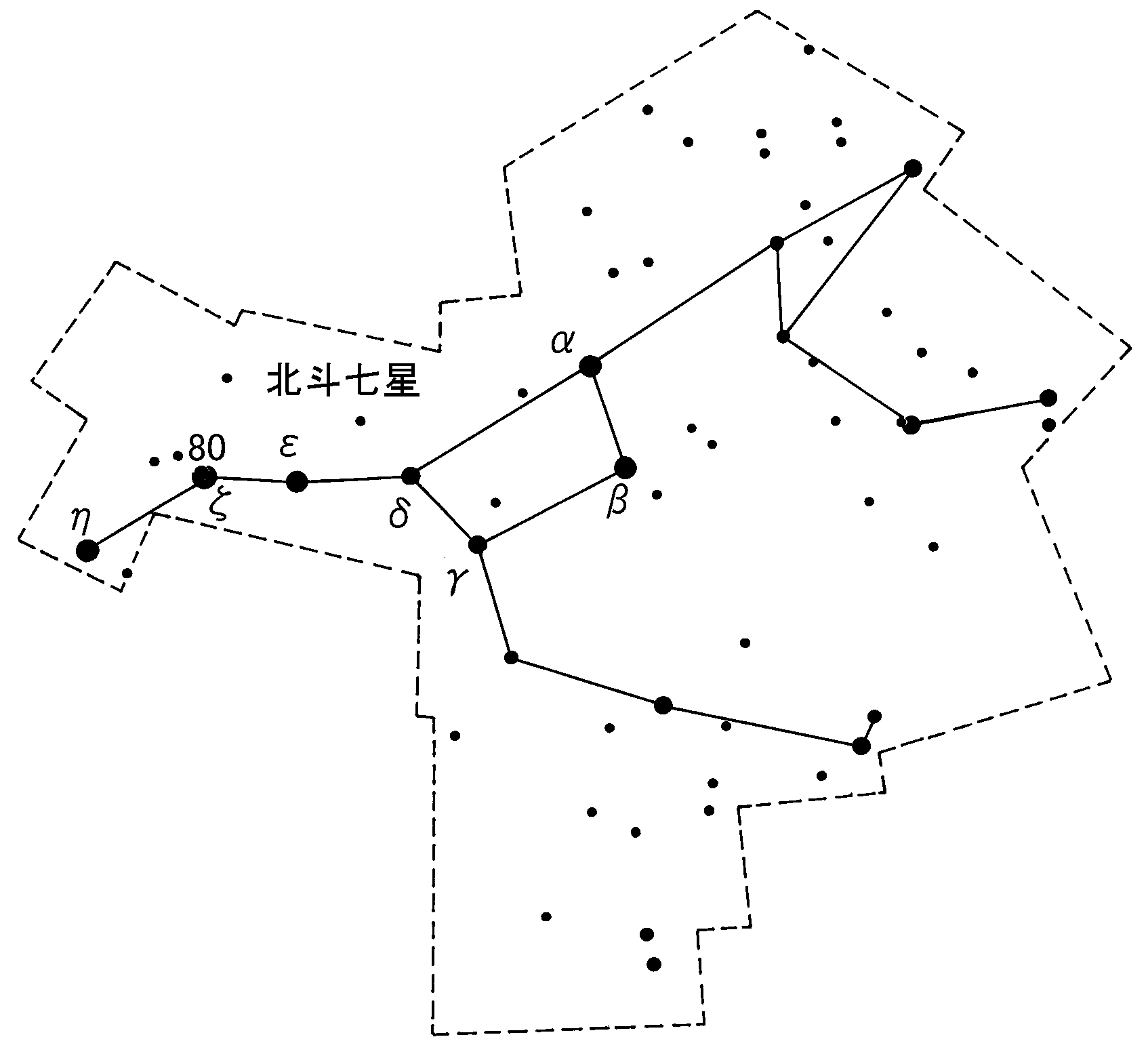
| 北斗七星 (αβγδεζη) | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (γδεζη) |
|
|
オリオン座
2023/05/25
|
| オリオンはギリシャ神話に登場する狩人で、冬の夜空を代表する星座と
してよく知られています。その雄大な星の並びは、賑やかな冬の夜空でもひと際輝いた存在感を示し、日本の各地で農業や
漁業を中心に広く親しまれてきました。したがって、この星座はたくさんの呼び名をもっています。特にオリオンのベルトに
あたる3個の2等星は、日本でも古くから注目されていた星であり、この三つ星とすぐ近くにある小三つ星を中心とした範囲は、
まさに星名の宝庫といえる場所となっています。
呼称が集中しているのは、やはり三つ星の部分で、多くは星の数や配置に由来する名が主体になります。同様の見方は小三つ星
にも向けられており、三つ星との呼び分け事例がいくつか記録されています。両者を併せると6という数字に変わりますが、
これをおうし座のプレアデス星団と同様に捉えた星名もあります。地域によっては、同一呼称で対象の異なる星の利用が
行われていた経緯があり、日本の星の名をめぐる多様性が、意識的な曖昧さのうえに成り立っていたことをよく表していると
いえるでしょう。この六星やη星を加えた星の配置は、計量器を中心とした用具に喩えられていますが、稀な事例として信仰に
由来した呼称もあります。また、三つ星を囲むように位置する四辺形に注目した星名もいくつかあり、いずれも他に類例のない
見方として注目されます。
|