
ガー:からだの特徴
初期の硬骨魚類が登場した古生代。海水域では被食者な立場にいた彼らは、捕食者から逃れるように大陸内部に移り住みはじめました。 そこは豊かな海水域とは異なり、天候や環境などによって水量や水質が激変する過酷な淡水域。より安定した遊泳をするためにヒレを鰭条と鰭膜で構成する条鰭類と、ヒレを手足のように使い遊泳する肉鰭類に分岐進化をはじめます。
鰭条のヒレで活発的な遊泳力で繁栄する時代の幕開けです。 これまで硬骨魚類とは名ばかりで内骨格が軟質で構成されていましたが、古生代後期には硬骨化が進んだ全骨類が登場し、中生代中期には全骨類から魚形も体内構造も洗練された真骨類が登場しました。現在も大繁栄を続ける魚類の登場です。 ジュラ紀が終わるころ軟質骨類と全骨類は、この真骨類に圧され衰退の道を辿りました。
少しずつ時代がずれて繁栄した3系統の条鰭類のうち、ガーは衰退した全骨類に含まれています。
ウロコ
ガーの学名由来に骨や牡蠣のように硬いウロコと付けられているように、とても丈夫な硬鱗(こうりん)で体表面を覆っています。 初期の硬骨魚類は俊敏な遊泳力も攻撃性も低く、捕食者からの防御手段として、体表面を生体で最も硬度が高い歯と同様の構造と硬さのあるウロコで覆い保護することでした。このウロコは古い系統の特徴の1つです。

Lepidotes sp.
歯と硬鱗の構造の違いは、歯の構造は表面層から硬くて光沢のある半透明なエナメル質、中層に多数の象牙細管が走行する象牙質、その内層に血管や神経からなる軟組織の歯髄で構成されています。 一方、硬鱗は表面層にガノイン(硬鱗質)とよばれるエナメル質に似た光沢のある透明で硬いエナメロイド層、中層に脈管系が走行する象牙質層、基底層は多数の脈管がからなる層板状骨質で構成されています。 この構造の硬鱗は表面層に由来してガノイン鱗ganoid scaleとも言いいます。
全ての魚類の起源となる無顎類にはアゴも歯もありませんでしたが、歯と類似構造のウロコ化石から、歯の起源はウロコが口内に入り込み変形したものと考えられています。 軟骨魚類のトゲザラなサメ肌。サメの楯鱗もやっぱり歯と同じ構造なので、化石からみる魚類進化の過程では硬骨魚類の硬鱗だけが特別凄いものでもありません。

ガノイン鱗1枚の形状は、厚さ2mmほどの菱形で前縁に関節突起があります。この突起でウロコ同士を強固に連結し、その表面を粘膜質の表皮が重なって皮膚と同化しているため、剥がれることのない一続きの重厚構造となります。 またウロコの成長は内層と外層の全体が同心円状に大きさを増していくので、ウロコ乱れは治らないようです。
ヒトの永久歯はモース硬度表すと7らしい。鉄の硬度は4。数値的にみると頑丈なガノイン鱗を持つガーを、鉄の包丁で捌くのは厳しいですが、火を通すこと鎖帷子を脱ぐように あっさりズル剥けできるらしい。
背ビレ・臀ビレ

体の中心部より後ろにある背ビレと臀ビレは、体の横揺れを防き安定させると共に方向舵にも使われます。 尾ヒレも合わせ3つを平行に動かすことによって力強く泳ぐこともでき、ときには敏速に行動することができます。
マイナス面はスピーディな小回りや急激な方向転換には不向きで、一般的な魚類なら体の中心部にある背ビレを軸に旋回するところ、ガーの背ビレは後部にあるためどうしても大きく旋回してしまいます。
尾ヒレ


Paramblypterus sp.
尾ヒレの上半分である上葉が下半分の下葉に対し長い上下非対称の異尾(いび) 特に稚魚期に顕著にみられます。
この異尾は古生代に登場した魚類の起源となる無顎類、その後進化した棘魚類や板皮類、サメやエイなどの軟骨魚類、ガーと同時期に派生したチョウザメなど 数多くの古い系統魚類との共通点です。初期の条鰭類も、脊椎が尾ヒレ上葉まで延長していることが確認できます。
脊椎が尾ヒレ上葉まで延長してることにより、後ろ下方へ力強く押し出す推進力と、前と上へ泳ぎだす浮力の効果があります。 進化した真骨類はウキブクロを浮力として完成させたので、尾ヒレは楽に速く泳げるよう、脊椎を中心に鰭条だけで構成したシンプルな上下対称形の正尾(せいび)になりました。
内骨格

最初期の魚類は脊索が頭部~尾を支持していましたが、やがて柔軟な動きを可能にしたまま軟骨の脊柱が筋肉を支えて遊泳効率を高めるよう進化しました。 しかし硬骨魚類は淡水域へと生息圏を移したことによって、塩分濃度による浸透圧の問題だけではなく、海水に含まれるマグネシウムやカルシウムなどのミネラルがその時々の環境で変動、ときには不足する問題に直面することになります。 ミネラルはタンパク質合成を調節、筋肉の動きを調整、神経の鎮静化など生存するうえで必要不可欠な存在です。そこで補填させる貯蔵庫として内骨格を硬骨に置き換えてミネラル不足時の問題を解消しました。
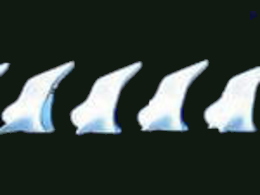
また大陸内部は天候など何らかの条件によって水量が激変、必ずしも水中にいられるとは限りません。干潟になりやすい汽水域、雨が全く降らない乾期の河川など、大気にさらされる危険が付いてまわり、突然 浮力のない陸上の生活を強いられます。貯蔵庫としての硬骨質は重力に耐え内臓機能を守る利便性もありました。
条鰭類の椎骨形状は、前凹・後凹型の鼓状をしていますが、ガーは前部分が凸型 後部分が凹型でをしており、太くて丈夫に支えあい強固に連結して陸上の重力にも耐える椎骨構造をしています。 この構造は波打ち際で ほぼ陸上生活をする真骨類のイソギンポ科 ヨダレカケ属や陸上生活に進化した爬虫類の一部に共通しています。