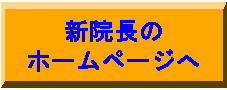|
「医は食に学び、食は農に学び、農は自然に学ぼう」「症状即療法」「心身一者」「一物全体主義」等とよく言われる。
私の好きなことばである。
人は食して明日の生命をいただくのである。「朝日の如く、この世に迎えられて、そしてやがて夕映えの如く沈んでいく」姿であ りたいと思う。
先ず医療、医学の歴史を把握して、人類が健康を守るために地域、食性、食文化などにおいて、どのような工夫や戦いをして いたか、
そうした長期にわたる営みの蓄積の上に今日の保健、医療活動が存在しているというこtを考えてみたいと思う。
医学には薬学、薬理学はあっても、その中には食学、食理学はない。そこに「病い」があつて「治療」が生まれ、
「病む人」 がいて「医者」が存在するのである。 決して、この逆であつてはならない。
医療は人が生まれ、育ち、やがて順調に死んでいくごく自然の営みの中であくまで補助手段であってほしいと思う。
しかし現状は人の一生の`始まり`と 終わり `即ち「出産」と「死」は主に病院`なのである。
(生まれるところと死ぬるところが。)
医学を学問の中にだけ押し込めて、壁を作り、そこから出てこないと言うのでは意味がない。
そこには哲学や宗教や芸術があってもよいし、 生活、教育、遊びなど、 私たちの日々の一挙手一投足が
すべて「医学」であり「治療」になると思う。
生まれて、食べて、死ぬるまで、生きていることは時にどろどろと生々しくもあり、しかし時には湧き出る水に
身体を清めるように清々しくもある。 人生は陰と陽、正と負など両面を背負って旅する旅人なのだ。
大宇宙の中でしばし生命をとどめる・・・・・。様々なのが人生で、様々なのが人間だから、
嬉しくもあれば悲しくもあり、
歓喜があれば悲観もある。 大切なことは人間であることで、人間の心なのである。
いかに喜びや幸福をどれだけ感じることができるかが、人生の熱さであり、厚みである。
生き方には人それぞれ規則はない。そして人生は一つしかない。だからたったひとつの人生を精一杯生きてみたいと、
時に思う。 働くときも、休むときも、 食べるときも、遊ぶときも・・・・
わたしの実父(★)のように・・・。
厳しさの中にも、こよなく母や子や孫たちを愛し続け、太平洋戦争に六年間従軍し、四十有余年仕事一筋に生き、
黄綬褒章をも授かった父は 平成八年二月中旬 八時間にも及ぶ大手術にも耐え、人工膀胱を付けた。
そして、1997年2月中旬自宅にて一時危篤の状態に陥った。
以来診療の仕事を終え実家へ行き 在宅酸素療法と共に自宅に加療中の父の看護に当たっていた。
私の著書が発刊されることを人一倍心より待ち望んでいた。 「お父さん、もうすぐ僕の本が出来上がるよ!」
「一冊・お・い・と・い・て・くれ・・・」 いままでの父には考えられないような弱々しい低い声で・・・。
「花には水を、人には愛を、人生にはユーモアを!」地で行くような父です。
介護のとき何時も「 皆、忙しいのに世話してくれてほんまにすまんなアー
、あの世に行ったら、たくさん土産を送るからなアー 」
又、あるときは「あの世へ行ったらまず。わしの父親に会いに行きたい!・・・」と楽しげに??言う。
父が満二歳の誕生日には(私の祖父は)他界していなかった。
実に七十六ぶりに再会するかもしれない。
いつも瞼に亡き父の姿を描いていたのだろう。往時のの太い大きな声の力強い逞しい父の姿を思い出すのか、下肢、腹部は
浮腫でむくみ、上半身は日々やせ 衰えていく姿を見ると、時々瞼が熱くなるときがある。「世話が出来るだけ幸せかもしれない
なアー」と思いながら・・・
いとおしさがこみあげてくる今日この頃である。
★ 寝屋川市 東香里園町の自宅にてこよなく愛した母や子や孫に看取れられながら、平成九年五月二十五日午後九時二十分
「樹齢78年の大木」が枯れて倒れていくが如く・・・ 「永久の国(よみのくに)」へ旅立ちました。
合掌・・・。
野暮用で、時折、一人中国自動車道運転して走っていると、太く大きな声で「ひとし〜!」と父の声が聞こえるときがある。
瞼に父を想像するのだろう。
目頭がジ〜ンと熱くなり涙が出る時がある。父も人にはいろいろと言えない大きな苦労をしたのだろうと思うと。
時に、私もいろんなばめんが重複して・・・。
いろいろと、ささえられる過去、考える現在、誇れる未来・・を聞かされた・・・
家族を愛し、仕事を愛した父・・・2008.8 亡き父を想う
PS; 2013年,5月
Dr武田の死生観:
人は死ぬ。同じ死ぬのなら「死にがい」のある死を死にたいし、「死なれがい」のある死を死なれたい。死に行く死に際のガイド役
、
死にゆく者を「看取り役」をする「助死者」という発想が望まれても良いと想う。
人生とはある童話に、王様が家来に「人生とは?」と問うと賢い家来たちは十数年調べ分厚い報告書を出すと、「もう少し簡単に分か
らないのか・・・。」又数年かかつて調べ報告すると、「もっと簡単に・・・。」又しっかり調べ直して報告すると「いやもっともっと簡単に」・・
・・そして1冊の本にして渡すと、「もっと、もっと・・・もっと簡単に」・・・とうとう年老いてしまった王様は曰く
「人生とは、生まれて、生きて、死ぬることか」・・・と言った、逸話があります。
医学は人の病に触れることで、人の肉体と生をいじるだけである。
生まれてくるとき、産婦を助ける「助産婦」がいるように、死にゆく者には死の床に侍る臨死者の助けとなる「助死者」がいてもい
いと想う。
助死者は妻や夫や子やケアーマネジャーや医者や友人・・・であってもいいと想う。充実した意味のある人生であったといえる
人は「死にがい」のある生き方をした人である。
又自分が家族に「申し訳ない」と思い続けるだけで終わるなら、辛い寂しい死になるが。「ありがとう」と感謝の念を持って迎えられ
る死は、本人だけでなく、 家族にとっても、終わらせ甲斐ががあり、看取り甲斐のあった死としてあたたかい、幸せな死を死んだこ
とになる。
寿命、寿(ことぶき)のいのち、ほんとうにおめでたいのである。皆、寿のいのちを迎えたいものである。
大自然の動物は自力で食べ物を食べることが出来なければ 「死ぬる」ことを意味するのである。意義ある「生」を貫きたいものである。
没歯とは死ぬることを言う。
「いのち(生命)の器」にある色々しがらみを引きずった歯も「慈歯のこころ」でしっかりと看取りたい。
あなたのいのちを育んでくれたのだから・・・。感謝の気持ちを持ち歯に有り難う・・・♪〜。と合掌・・・。
ハイテク医療に依存する心情は、いまや「生命至上主義」から「延命至上主義」に移り人の生命の引き延ばしに躍起となっている。
そういう場合`生け贄の癒し`とか`治療`という名目で、延命方針が医学の実力を示すバロメーターになってしまい、
生かし続けるだけの医療が、 延命至上主義のため、しばしば人間性を無視しがちなのは残念である。一日でも長く生きたいと
いう願いは尊重されるべきだが、それは「みじめな生」 「ぶざまな生」をながびかせることではないはずである。医療にとって時に
「人の死」は敗北なのである。
人は生きる限り、病むことからも,死ぬることからも、解放されることはない。医学から見ると死であっても、人間的に見ると
生だということがあるように、医学から見ると生であっても人間的に見ると死だということがある。
人は生物であり、「人間は人間だから死ぬ」人は病気でも死にますが、 病気だから死ぬのではないのです。
人は病気にならなくても、いずれは死ぬはずの存在なのです。天地宇宙、森羅万象・・・100%。
ヒトは大自然の中では無力である。台風だ地震だ大雨だ・・暑い・寒い・・・。どうすることも出来ない。
私は約28年前約1ヶ月程(急性肝炎;GPT、GOTが2000以上・・・)入院の体験をしました。
看護婦長に「武田さん。3ヶ月は入院・・・。」と言われましたが、まだ開業して間もないは、銀行から多額の借入金があるは、
愛しい可愛い4人の幼子はいるは・・・・カルガモの子どものように。肝機能も20日ほどで正常値に戻り、無理を言ってつらい体
を引きずり1ヶ月で退院。
私事で大変恐縮ですが・・・退院後、別人?のようになりました?めまいはするは、吐き気はするは、・・・・痔になるは・・・。。「入院後、毎日毎日
点滴(700cc)で20日で点滴を止め、あくる日の夜11時頃「パッと目が覚め天井がぐるぐる飛行機のプロペラのように回っている
ではないか!!脳卒中かメニエール病か前庭神経炎か。・・・・漢方で言う、「水の異変」か?そして何かうまく言葉が話
せなかったり・・・ 変な感じ・・・。
皆さんからのお見舞いでは「武田君、別荘でも行ったつもりでまあ〜ゆっくりしいや〜。」といわれましたが・・・・。
元気に入院??しましたが病気(おおきく気が病んで)になって退院したようです。
入院するにもつくづく体力、気力がいるなあと思いました。
(詳しくは拙著に掲載しています。)
医学は病気を治すように見えて、逆に病人を増やすようにも想う場面が多々あるようです。
医学が原因で患者になる様々な「医原病」を無くしたいものです。
この世の健康なDr もおおよそ1ヶ月ぐらい病院での体験入院が是非必要だと思います。
人が人生の最後を迎えるとき・・・。
あ る学者(カールベーカー)の調査では80%が家で近親者や友人が側にいて、山や庭、草花、森林、青空、海、河・・・
を見ながら、
鳥、虫、飼い犬の鳴き声や風の音、河のせせらぎ、音楽を聞き、そして最期の1週間、草花、森林、きれいな空気、大地の臭い、
潮風を嗅ぎながら・・・
妻の手、子の手、孫の手、友人の手に触れたいといわれています。
朝日の如く生まれ、夕映えの如く・・・・。この世を去りたいものである。
母を看取って ( 2010.12月、No 1038号 「月刊保団連」
全国保険医団体連合会 雑誌に掲載 )
私事恐縮ですが、 2010年8月28日土曜日午後9時55分自宅にて愛する母を看取りました。
享年89歳。全く痛みも訴えず・・・。
午前中から下顎呼吸が始まりました。
その日も日本列島は気象台観測史上113年の歴史では初めて猛暑の続く日々でした。
気温37〜39℃近くまで14日間以上の暑さが続きました。
同居していた母は一昨年の12月頃からやや体調を崩し、毎日杖をついて6〜800m家の周りを 散歩していました。
「今日はやめとくわ〜」と言う日が段々増えていきました。
8年前に心臓の手術をしステントが1カ所入っています。所作によって何となく負担がかかるようでした。
時々、足湯につけ、洗いながら「お母さん。80歳も過ぎてガンになっても当たり前やから、おでき みたいなもんやで。
そら中にはヤクザみたいなものもあるかもしれないけれど。 どんなドラ息子も娘でも自分で産んだ子やから
殺すわけにもいかず、捕るのはいいけど、身内やから共生せなあかん」
「 闘病`病と闘う。時として大変疲れる。抗ガ ン剤、放射線などでガン細胞が小さくなったけれども、
ガンも生物として生きる権利がある。時に反撃して転位してくる場合もある ・・・。」また「お酒をお猪口一杯で酔う人
もおればコップ二杯でも酔わん人もいたはるし、人様ざまやな・・・。」と度々話をし たこともありました。
「入院したら?いろいろ面倒みてくれはるけど・・・。」「どう?」「入院はしたくない・・・。」日々は
過ぎ・・・「延命はいらん」と小さな声で呟きました。「お母さんさ、ここでゆっくりしたらええわ・・・。」
私もふと点滴や、胃婁など経管栄養に走る日本の状況に疑問をもっていました。
高齢になって胃婁で何年も生かされることは果たして本人や家族にとって幸せだろうか。
今の医学は「病気」を治しているが結果として「患者」を増やしているかもしれません。
病気に対する攻めの姿勢が強く、守りの姿勢には不慣れなように想います。病を見て人を見ない ことが多い、
忙しくゆとりがないのか・・・。
これでいいのか、かくいう私も昔は赤ん坊でした。お世話になりました。独り歩きが、つかまり歩きになり、
支え歩きになり・・・。
人は凸凹があり、十人十色かな?人の数だけ死にゆく形も又様々かなと、日々想う日がありましたが、
3歳児が2歳児になり1歳児になり・・・新生児になっていく様子が手に取るように一挙手一投足・ ・・
日々刻々と分かりました。
4人の子育てはしましたが、正に陽と陰、正と負です。母がマイナス成長していくのが分かりました。
これは命あるもの、天地宇宙、森羅万象の法則だと思います。
生命あるものやがては99%でなく100%永久(とわ)の国へ旅立つのです。
日々からだが衰え、体重は25kgを割、自力でトイレに行けない、目の前のものが取れない、入浴は出来ない、・・・。
軟食がとろみの流動食に水差しやスプーンで水分を口元までもっていたり、口腔内にカビなどが 発生しないように
気を付けたりしていきました。
又 、トイレ、廊下、部屋などに手すりや太いロープを張ったりしました。 かかりつけ医の対応、
特に土、日、祭はどうするか,,,。
ケアーマネジャーを通じデイサービス、介護ベットなどの手配、訪問看護センターの看護師の往 診
各種書類の提出・・・。と日々刻々と過ぎていきました。
要支援2が介護4となり旅立つちょっと前には介護5の認定。
育児と同様、体力、忍耐力がいりました。
母の人柄、母の人生を考え内心、普通の心理状態でないこと、無意味な屈辱や苦痛を与えないように
思い心掛けましたが・・・?
大阪船場で生まれ大正、昭和、平成と小4,5年で両親を亡くした母は叔母に引き取られ高女を出してもらい、
上海駐在の叔父を頼って上海、南京などへ行き(英文タイピストの職に従事)、異国の恋を稔らせました。
3人の 男の子(長女は病死)、9人の孫、2人の曾孫に恵まれました。
人、人間として答えようのない問いにも力を尽くし、答えようとしてくれた母でした。
共に生きた愛する母「武田 明子人生物語」89年で終演となり幕を閉じました。
生前ある朝「日の出の餅20個注文したからな、皆で食べて」「黒豆炊いたのがあるから、取ってきて〜」
「ホントありがとう・・・?」相手を拒否せず、絶えず`抱き込み言葉`を心掛けました。
「のりこ(妻)さ〜ん。ひとしさ〜ん。ありがとう・・・」とよく言ってくれた母の声が聞こえてくるようです。
臨終時、右手の指先がむくんだ母の手をしっかりと握りしめ「ありがとう、ありがとう」と心で何回となく
強く呟きました。
止めどもなく涙があふれ出てきました。
赤ん坊が母の胎内で吸い込んだ空気をこの世に吐き出す時の産声に対して、肩と唇でゆっくり
吐いて吸うて、吐いて吸うて、、、の繰り返しの間隔が段々遅くなりました。
最後の息は吸い込むけれども・・・吐かないで、息を引き取りました。呼気は死を、吸気は生を意 味するのかな・・・。
仏前の前でケアマネジャーに赤ちゃんが産まれるとき助産婦さんがいるように
永久に旅立つ人のため助死者?「死の受容」を助け、家族の「死者の受容」を助けるようなの役割の一部
をしっかり担って欲しいと言いました。
合掌
未だに時折、父、母のことが走馬燈のように思い出されます。 2013(平成25年)年.5月〜
あのときこうしてあげたらよかった、こうしたのになぁ〜・・・・。とくに母親に対して・・・。
主に父は母が、母は私と家内が看取りました。
10数年ぶりに、2005年の暮れ映画「Always 三丁目の夕日」を観ました。
昭和33年頃の日本の風景・・・・・、
懐かしさのあまり久しぶり・・・涙、涙。。。光陰矢のごとし、うまく言ったものです。
「 おくりびと」も感銘しました。 「武士の家計簿」・・・。「アース」もいい映画かな・・・。
3人の可愛い孫たちをみていると「人生おしめに始まり・・・おしめで終わり・・・おしめ〜」か
とふと思います。森羅万象、自然の摂理・・・。
朝、起きて希望に燃え、昼は考え、努力して、夜は一日に感謝して
床につきたいと思います。
千数百年以上、蕩々と、皆、生きるために午前中は主に自然を相手に、畑を耕したり、川や海で魚を捕ったり・・・
などの仕事をしていました。
明治維新以降 120〜30年で今日の社会が生まれるとは、誰もが思って?いなかったかも・・・。
多量生産、多量消費、多量廃棄、多量情報・・・・。
2013年4月19日 ふと思います。
|