 |
武田歯科医院 武田 一士(たけだ ひとし)
 |
| 1948年生れ |
大阪府出身 私が子供の頃( 昭和20年後半から30年代 )、寝屋川の香里園(第5小出身)の周辺は、生き物であふれていました。 春や夏には、ブリキのバケツと網を持つて近くの小川や池に、メダカやフナ、モロコ、カメ、ドジョウ、タガメ、 ミズスマシ、ヤゴ(トンボの幼虫)・・・ などを採り(獲)に行きました。 夏等、朝4時30頃に起きて、小さな心を ワクワク` させながら近くの山へカブトムシ、ゲンジ、カミキリ、 カナブン などを捕りに・・・「木を揺すると、カブトムシが、数匹、木から落ちてきました。」「生命(いのち)の輪」が無数にありました。 そして彼らの小さな生命を必死に育てた記憶があります・・・ しかし大人になった、今は・・・多量生産、多量消費、多量廃棄・・・・・・・・・・多量情報・・・時に切なく、 辛く、悲しく 思う 時があります。 ( 私も、高機能携帯電話(IPhone6)などを持っていますが・・・。いろいろ便利ですが・・・? ) 最近ふと汚染が三つあるのでは?と、思います。 三つの汚染とは・・・環境の汚染 ・ 制度の汚染 ・ 心の汚染・・・・も深刻・・・・・。 又、最近は家族内の不幸な事件が多く・・・つらく、悲しく、切ない・・・です。家庭の崩壊?家庭は国家の細胞・・・ このままだと国が日本国が滅びるかも?ふと思うときがあります。 こどもの頃は祖子供母や父母や周りの人々から ・・・ 仁:人には思いやって優しくあれ。 義:弱い者ををいじめるな。 礼:敬意を持ってふるまえ。礼儀を守れ 智:相手を理解せよ。卑怯なことをするな。 信:正直であれ。 嘘をつくな。友を裏切るな。など・・・教えられたと思います。 清貧の思想 、鴨長明の「方丈記」、吉田兼好「徒然草」、良寛和尚をじっくりと・・・味わいたい。 著書「清貧の思想」で有名な中野孝次は、 「無いことが常態であれば、人はものが少しだけでも得られれば、無常の満足と感謝を覚えるものだ」と述べている。、 又私の母親(大正11年生まれ)の小学校の校庭の隅には 有名な二宮金次郎(尊徳)の銅像(薪を背負って本を読む少年)がありました。 尊徳は先ず、孝行 ・ 勤勉 ・ 学問・ 自営 ・ 親の恩 ・ 兄弟仲良 く・ 勤倹 ・ 至誠 ・ 正直 などが人生大切だ述べています。・・・。 子育ての基本は、家庭にあり。 江戸時代、寺子屋(庶民が学んだ塾)では「童子教」という道徳を教えた子供用の教科書がありました。 内容は親や目上の人を敬う。きちんと挨拶。感謝の気持ち。立派な行い・・・。 子どもを育てる上で一番大切なことは、 わがままな気持ちを抑える意志力をつけさせること。人を思いやる気持ちを持たせる。 子どもを厳しく育てるのが父の慈悲、 父の厳しさを悪くいわないように道理を言い聞かせるのが母の慈悲。 と言われていました。 さて現代は?? 財布の中をみて『えっ、1000円 しか ない?」と思うより『あっ1000円 も ある』と・・ も・・の生き方の方が楽なように思います。[ しか] の助詞より[ も] の助詞の方が好きです。 また「私ははこれだけ、している、やったってんのに、のに・・」「私はこのために、こんだけしている のに・・のに・・・」 [のに」という助詞も あまり好きにはなれません。 しかし「でもの助詞は好きです」「あなたに でも 出来るよ」「でも あきらめないで、やってみ ようよ」 「 でも 明日があるさ・・・」・・・ やはり人生いつでもプラス思考で行きたいなあ〜思うんですが・・・。 「上り坂、下り坂、まさかの坂・・・」にくじけず。 明るい顔がまわりを明るくし、 暗い顔がまわりを暗くする。」 身体も元気! 心も元気! 歯も元気(歯もきれい)!!〜笑顔が一番!!! 笑顔の極意は、 生き方の極意。 感じの良さは、笑顔に集約 されます。相手に対して「受容」や「親しみ」「興味・関心」「好感」 「 思いやり」のサンインです。 人は、幸せだから笑顔になるのではありません。笑顔だから幸せになるのです。 仏教の「無財の七施」の中の一つに`顔施`がんせがある。ほほえみによる施しです。 顔施 がんせ ( 七施の内の一つ )自分の一つしかない顔を「柔らかい心」「優しい心」で人に接する。 無財の七施・・・ 自分にして欲しくないことは、他の人にもしないし、自分にして欲しいことは他の人にしてあげる。」 自然の生命(いのち)を大切に。 良く噛んで食べる。歯は「身体を守り」 「脳を守り 」そして 「心を守る」 すなわち 「慈歯の心」。 食をはぐくむことは命、心、愛、絆、信頼、人間関係・・・を育む。 食育は健全な社会をつくる分母です。 「口腔は全体(身体)の縮図」「歯は命の関門・病は口から・先ず食べて耕す人生街道」・・・ (拙著「歯から始める健康医学」にも述べています。 一いつも、患者さんとお話しするときにはー 「 歯は、見て、眺めて、育てて、楽しむんですよ。そう虫歯はないか?」 歯ぐきが腫れていないか? 自然治癒力のない歯( 脳の細胞 と同じように)悪いところは治し、予防に力を入れて下さい。 自分の歯に惚れて下さい。一歯一生・一生一歯 美味しいものをいただくと、心が明るくなり、自然と身体が動きますよ。 歯は生命(いのち)の入口ですからね。 この世に生まれて食べ(飲む)初めて、あの世へ行くまで食べ続けるんですよ。いのちを育むために。 」 よく噛む。 お手軽なダイエット。一口30回以上・・・理想ですが?消化吸収を高めて胃腸への負担を 減らし顎の発達を促し、歯並びをよくして、虫歯や歯周病などを防げる。 咀嚼による顎のポンプ作用により 脳の血流を増し、記憶力アップや痴呆予防を助ける。唾液をよく混ぜることで食べ物に含まれる添加物などの 化学物質の毒性(発ガン性)を低下させる。 唾液の働きには 1 .消化作用 2.抗菌作用 3.溶解作用 4.洗浄作用 5.円滑作用 6.Ph緩衝作用 7.保護 作用 8.再石灰化作用 などがあります。 ( 詳しくは、下記のDr武田のプレゼンを参照して下さい ) リラックスした状態で食事をすると副交感神経が働いて、サラサラした唾液が出て スムーズに食事が出来ます。 反対にイライラ、ドキドキ、感情に起伏があるとネバネバした唾液が少し出ます。緊張すると食事が 喉を通らなくなります。 例えば、ストレス(人間関係、お金、病気など)が多いと唾液中のコルチゾールが増えたり、 免疫グロブリンAが減ります。 よっ ていろんな病気に罹りやすくなります。穀物や野菜はよく噛んでこそ滋味があふれ、心が落ち着いてきます。 自律神経とは自分の意志に関係なく働く神経です。「はい、汗をかいて下さい、脈拍を速くして、体温を下げて、 胃 液を出して、来週まで髪の毛を5cm伸ばして・・・。」なんて言われたら、出来ますか?? 交感神経と副交感神経があります。 車のアクセルとブレーキの如く・・・。車の整備(身体)はしっかりしていきたいものです。 感謝の心 多量生産、多量消費、多量廃棄・・・多量情報・・・。欲しいものが次々出てくる現在です。 好きなものがすぐ手に入りやす く、好きなだけ食べられるようになりました。又あふれんばかりの情報が・・・。 それほど豊かな社会ですが一方では環境破壊、Co2問題、病気などマイナスの面の問題も数多く抱えています。 当たり前ですが「食べ物は全て命」です。命が生まれ、育ち、収穫されて家庭の食卓に上るまで永い営みと その間に費やされた尊い労力を考えれば、食べ物は粗末に出来ません。 日本に住む人全員がたった1粒のお米を残すだけで・・・0.02g×130,000,000.人=2,600kg 即ち10kg入り米袋260袋分のお米を捨てることになります。米1粒約0.02g」。 全世界64億人の内約8億5千万人が 飢餓で苦しんでいます ( 2010年 農林省白書など参考 ) 「好き嫌いは不幸の出発点」・・・。感謝や祈りの心は、自律神経の副交感神経を優位にして、 消化管機能を高め、 食物の消化吸収がよくなります。 「いただきます〜♪」 「ごちそうさま〜♪♪」 「ありがとう・・!!。」 最近、徳のある人がいなくなりました??。 徳とは「無私の責任感の重さ」とも言われています。例えば「線路でお年寄りの方が倒れた。我を顧みず、 その方を助けた。が助けた人は片足を失ってしまった。」 小さな徳を少しでも積みたいと思います。 穀物菜食 人の歯は全部で32本、臼歯20本、門歯8本、犬歯4本に分けられます。臼歯は硬い穀物をすりつぶす ための歯、門歯は野菜や果物を切るための歯、犬歯は肉や魚を食いちぎるための歯です。 ということは、人は穀物を主食として野菜を中心にした副食という食生活が理想といえます。 玄米や豆腐には良質のタンパク質やカルシュムがたくさん含まれています。 特に古来から農耕民族でやってきた わが国です。  一物全体 食べ物の命を丸ごと食べたいものです。 例えば大根、人参など葉には根以上に栄養素が多く含まれています。 ご飯は 、白米よりも蒔けば芽が出てくる生命力あふれた 「玄米」 を勧めます。Ca、Mg、VitB1、 Fe、食物繊維などに富んでいます。 玄米には 「糠」(ぬか)」、があります。漢字で書けば 「糠」。「米」 と健康の 「康」です。逆に米を白くするとそれは 「粕(かす)」 になります。 「もったいない」と感じることで、食べ物を大切にしようと想う心が、ひいては健康作りに繋がるのです。 1粒の米粒を大切 に。 身土不二 国内産、季節の旬の味を大切に。昔は「三里四方のものを食べていれば長生きできる」といわれていました。 食べ物の産地が遠くなればなるほど私達の口に入るまで時間がかかります。 輸入生鮮食品には鮮度を保ったり、腐らないよう、収穫後もう一度、農薬を散布するポストハーベストによる 残留農薬の他、添加物などの問題が指摘されています。 私の医院では近年、乳歯の下から、永久歯が生えてこない子どもたちが多く見られます。 永久歯が4本、5本、と・・・ 犬歯、小臼歯など・・。岐阜大学の先生が仮説として農薬の除草剤ではないか?との見解?を出されています。 また20数年前余り考えられなかった乳歯の歯列不正が、最近よく見られます。 身土不二とは、からだ(身)と 土(土地)は 不二(分かちがたく結びついているもの)であるという意味です。 「地産地消」という言葉もあります。 夏に出来る野菜は陰性で、身体を冷やし、冬の野菜は、身体を温める陽性のの働きがあります。 春は芽を、夏は水もの、秋は実になるもの、冬は根、のもの、を季節の旬の味は、自然のリズムに順応した状態を つくりだしてくれます。旬にこだわるのもいいかもしれません。旬にこだわろう。
愛について
「もったいない」最近よく言われますが、食べ物を大切にしたいと思います。
生涯の自分自身の命の源であり 生きていくためにも。粗末にすると人は滅びます。歴史が証明。
陰の声「中学二年の夏、大阪、日本橋買った卓上式の蛍光灯、今も診療所の私の机のうえで、耐え、53年近く、
20wと5wの灯を灯し、刻み活躍してくれています。」 2014年9月現在も
他の存在も大切にすると自分も安らかに生きていけます。これが生命の秘密。そのため「愛」が。
愛すると言うことは、自分の分を与えて、他が生きることを応援することだと思います。
昔、渇水の夏、木を見ていたら枯れそうです。その時に思いました。
「今日は風呂に入るのはやめよう。 入ったつもりで・・・」その日はシャワーにしました。
倹約した分の水を木にやりました。
その時気づいたのです。自分の分である水を少し削って相手が生きるのを応援する
「 この木を愛している 」相手が生きることを応援する。これが愛することかも?
それを継続していくことが情、 愛 情・・・。
微力ながら、患者さんに「歯は生命の玄関、命を入れる器(うつわ)。極力自分の歯を愛し
、 生かし続ける事を願い、生命(いのち)を、脳を心を、守り続ける歯を応援させていただきます。」
歯を通じ「愛」という「癒し」を「情」をもって・・・・・連綿と築こう。。
最近、日本の国はこのままでいいのか・・?とよく想う。 殺人(特に尊属殺人)強盗・・・・その他。の多いこと。いつの間にか「民主主義」が「勝手主義」 になったように想う。 教育の責任は親にある。確かに正論であり、基本的にはそう考えている。 でも四人の子育て(全員成人)の 親としては大いに違和感を覚える。大半の親は子育てに一生懸命である。 しかし、今の社会はその邪魔 をしているように思える。子どもを消費者に仕立て上げ、 あらゆる手だてを尽くしして、欲望((携帯、パソコン、ゲーム、ファション、グルメ、レジャー。。 など生活物資、電化製品・・・すぐに手に入る )を駆り立てる。自らの欲望をコントロール出来ない 子どもが量産されるのは当然ではないか。いくら親が頑張っても所詮、「蟷螂の釜」 「イヌの遠声」。 我慢や忍耐をこれほど教えにくい世の中はない。 昔の「世間様に申し訳ない」「お天道様」は」 どこへ行ったのか、 子どもの消費行動が日本経済の一部を担っていることも事実。質素倹約、忍耐・・を国是としたのでは 今の資本主義日本は成り立たない。二律背反の中で暗中模索の子育てをしているのでは・ とふと想うときがある。 「工業の目」ではなく大いに「農業の目」を養いたいものである。もっともっと自然を大切にし、 無から有を生み出す心、 いつも風通しよく、作る、造る、創る、そして遊ぶ喜びを子どもたちに教えてあげたいものだ。 教育は「国家なり」 といわれる所以である。 2008.8 記 Dr 武田の徴農制の?の提言 最近、ひき逃げ、親の育児放棄、無差別殺傷事件など・・・が多く見られる社会になってきた。 昔は可愛い子には 旅をさせ、世間やお天道様が見ていてくれた。 特に男性は内面に攻撃性を秘めた生き物だ。妻や子どもや女性たちを守るためにきちんとした男に仕上げて いくためには、女性に対するよりも遙かに厳しい教育、身体の鍛錬ー例えば徴兵からぬ 徴農制( 一定期間、農業、・・・などに従事。)の採用。、 「工業の目」ではなく「農業の目」いわゆる春夏秋冬の自然の厳しさや生き物への思いやり、気配りにが大変必要 ) の採用、 自制心の獲得、強く成熟した男性とのコミニュケーションなどが必要だと痛感する。 それを支えるのが女性の愛なのである。 しかし最近の男女平等教育は「男性」というものを制御し、伸ばす知恵を持たない。「中性的?」な事を価値として、 結局は骨抜きの男と母親になれず、優しさのない女を作る。その結果凶暴な男性を生み出しているように思う。 そんな教育の甘さは語られないまま、犯罪が起きれば精神鑑定で「病気のせい?」として区別をする。 私は大正生まれの親に育てられた。「ヒトには迷惑かlけたらあかんで」「弱い者を絶対、虐めたらあかん」等 とよく言われた。 もし守らなければ父には「足腰たたんようにしたるから。・・・・。半殺しに〜したる。」とか、世の中で怖いものは 「雷・火事・親父」の時代でした。また母からは「人を殺したら、お母ちゃんがあんたを殺し、おかあちゃんもこんな子 を育てて世間様に申し訳なく死ぬわ・・・・?」と、そして「人生取り返しのつかん事はしたらあかんで」とも よく言われました。 フィランドの交換留学生が6年前、拙宅に4ヶ月程、ホームステイをしました。 家族写真を見せてもらったとき「 あれ?お兄ちゃん丸坊主?!」「 2ヶ月前、1年間の、徴兵制の義務を終えて、 から帰ってきた・・・・・。」とか。 彼女も2年後召集され再来日の時に、戦闘服を着た写真を見せてくれました。 教育立国、北欧のフィンランドには男女とも1年間の義務として徴兵制があるのを知りました。 自分の身や自分の家族や自分の国は自ら自分を律し守る気概は大切かも・・・。 家の戸締まりや車や自転車など鍵などしなくて・・・よければいいのですが。国の戸締まりも?? 今や一国、平和主義?人とと同じ様に世界には、様々な国があります。家族を愛するように、 家族の集まりが国です。 当然、国も愛して家族を護り、そして、の衣食住・・・を保証せねばなりません。 断・捨・離 最近、私の周りで「断・捨・離」を実践する人、ダンシャリアン?が増えてきました? そもそも「断捨離」だんしゃりとはヨガの行法哲学の「断行・捨行・離行」を元に生まれた言葉です。 「断」入ってくる要らないモノを断つ、「捨」空間にはびこるがらくたを捨てる。 「離」モノへの執着から離れると言う意味です。モノは使ってこそ生かされる。 不用なモノが無くなると空間だけでなく、時間、エネルギーにもゆとりが生まれ、 それが気持ちのゆとりにつながるようです。 西式甲田療法の「仙人食、第2号」 私が敬愛する故甲田光雄先生。西式甲田療法を実践された患者さん「2人目の仙人」 森美智代(鍼灸師)さんが著された 「食べること、やめました」には感嘆しました。 彼女は21歳の時、神経内科の医師から「次第に進行して寝たきりになるだろ。 進行をくい止める治療法はない」と告げられました。その病気は「脊髄小脳変性症」といい、 運動機能を司る小脳や脊髄が萎縮して次第に働きを失っていく病気で、 国の認定する難病(特定疾患)の一つです。 「 食断ちでその病気を克服。1日青汁1杯だけで15年間・・・。あなたは信じますか?21歳で余命5年の難病に。 絶望の淵から断食ではい上がる。現在栄養学から言うと不思議で説明がつかないようです。 いろいろなテレビ、新聞、雑誌などの取材も受けられ又、映画化もされました。 平成23年(2011年)3月11日 東北大震災の凄まじい大津波の映像、 被災地の様子、親族、友人、知人を 亡くし、 住まいも、故郷も亡くした多くの人達が苦しみや失望感は私達が 想像できないものがあると思います。 又台風12号でも奈良、和歌山の被害をもたらしました。 このようなかってないような天災が日本を襲い、まだまだこれからも心配 される中、いつ自分たちが被災者になるかも知れない怖さ、辛さ・・・ をふと感じます。 「天を恨まず」 平成22年度 文部科学白書」の冒頭の部分には、東日本大震災で被災した 気仙沼市立階上中学校の卒業式で卒業生代表として読み上げられた 梶原裕太君の答辞が全文、記されています。 極めて異例な事だそうですが、悲しみの中で15歳の少年が示した決意、 今もなお、全国の人たちを勇気づけています。 「 自然の猛威の前には人間の力はあまりにも無力で、 私たちから大切なものを容赦なく奪っていきました。 天が与えた試練というには、むごすぎるものでした。 つらくて悔しくてたまりません。 しかし苦境にあっても私達は天を恨まず運命に耐え、 助け合って生きていくことが、これからの私たちの使命です。 途中、何度も歯を食いしばり、涙をこらえながら、天を仰ぎながら、彼は一つ一つの言葉を 絞り出していました。 その言葉に、その表情にどれだけの哀しみが内包されているのか。 そのような過酷な状況でも「天を恨まない」と言った高潔さ。この言葉に頭が下がりました。 嗚咽、涙ながらに答辞を読む梶原君の姿に、まず心がたまらない状態になるのです 震災では3人の友人を津波で失ったそうで、それを理解した上で「天を恨まず」という言葉を 使う梶原君の姿は、より一層メッセージとしての重みが、計り知れなく重いものに伝わってきます。 “ 決意”というものは、こういうものなのかもしれません。 現在、工業系の高等専門学校に進学した梶原くんは、当時を振り返って 「どうしてこんなことを」と思う反面「自分に文章を言い聞かせた」と。 「しおれることなく、大きな人間になり、再び故郷の復興に役立ちたい。 そういう人間に皆で一緒になっていこう」という思いが答辞には込められていた、 そう話しています。そして将来の夢は「技術を身に付け、内面的な人間性も磨き、 復興に役立てる人間になること。それが僕の使命だ!」と…。 自分がいかにぬるま湯の中で生活しているか、恥ずかしい気持ちになりますね。 それは「普通」という言葉にも置き換えられるし、 「平和」とか「幸せ」という言葉なのかもしれないけれど…。 「“天を恨まず”前を向いて」という決意は、今なお全国に広まっているそうです。 私もニュースを見て心を打たれました。被災地の皆さんが頑張っているのに、 自分は小さな事でくよくよと、何をしてるんだ! と叱咤激励しつつ、前向きに 一生懸命な姿は美しいなぁと思ったニュースでした。 土石流や御岳山の爆発・・・地震・・・などは大変だけれど・・台風などは自分で出来る限り予防を。 食料や衣類などを入れたリックを背負って避難所へ行くとか。。。・・・・。 「方丈記」に惹かれます。 動乱の中世に生きた神官の息子である鴨長明が中年になって出家し、4畳半ほど(方丈)の小さな庵で 書いた随筆 「 行く川のながれは絶えずして、しかも本の水にあらず。よどみに浮ぶうたかたは、 かつ消えかつ結びて久しくとゞ まることなし。 世の中にある人とすみかと、またかくの如し。 玉しきの都の中にむねをならべいらかをあらそへる、たかきいやしき人のすまひは、 代々を經て盡きせぬものなれど、これをまことかと尋ぬれば、昔ありし家はまれなり。 或はこぞ破れてことしは造り、あるは大家ほろびて小家となる。 住む人もこれにおなじ。 所もかはらず、人も多かれど、いにしへ見し人は、二三十人が中に、わづかにひとりふたりなり。 あしたに死し、 ゆふべに生るゝならひ、たゞ水の泡にぞ似たりける。 知らず、生れ死ぬる人、いづかたより來りて、いづかたへか去る。 又知らず、かりのやどり、誰が爲に心を惱まし、何によりてか目をよろこばしむる。 そのあるじとすみかと、無常をあらそひ去るさま、いはゞ朝顏の露にことならず。 或は露おちて花のこれり。のこるといへども朝日に枯れぬ。或は花はしぼみて、 露なほ消えず。消えずといへども、ゆふべを待つことなし」 という無常観、 平成9年、平成21年 実家(香里園)と私の家(梅ヶ丘)で最愛の父と母を看取りました。 「人生、襁褓(おしめ)に始まり、襁褓で終わり。」そして「おしめ」ぇだ〜と介護を通じ身をもって 体験しました。赤ちゃんはプラス成長、お年寄りはマイナス成長・・・・。 合掌 |
| 1973年 |
大阪歯科大学卒業 元同大学矯正学教室同門会会員 |
| 1979年 |
大阪市福島区に開業後、自然を求めて寝屋川市の生駒、飯盛山系の麓、東寝屋川にて開業 |
| 現在 |
元・やまなみ幼稚園、梅が丘小、府立寝屋川支援学校(小、中、高)園医、校医。 日本東洋歯科医学会、日本咀嚼学会、日本障害者歯科学会、日本総合医学会、 関西予防歯科研究会、日本ホリステイック医学協会、癒しの環境研究会、その他各会員。 元・大阪府学校歯科医会広報委員長・ 大阪府立高等学校歯科医会常務理事 ・寝屋川市介護認定審査会委員、 寝屋川ロータリークラブ会員(職業奉仕委員長など)、 市立「あかつき・ひばり園(障害児療育施設」: 昭和56年開設時より医療スタッフ. ワークセンター小路(障害者授産施設)を支える会会長、 医学博士 著書 「歯から始める健康医学」星雲社刊 1997.7 P217 「医学部歯学部に栄養学、自然医学の視点を」(東洋医学を通じ)1996.12 PWU刊・ 文献など [被爆顧みず救助に奔走の父」 2011.7.19 朝日新聞 朝刊 語りつぐ戦争 [母を看取る」 2010.12。 No1052号 月刊保団連(全国保険医団体連合会) 当ホームページの「歯から始める健康医学」に掲載。Dr武田の死生観。「母を看取る」拙文が掲載 [代替医療の病院選び。全国ガイド」 2009.2.23ナチュラル・オルタVol .12 ほんの木編 「お医者さんがすすめる代替医療」(帯津良一総監修) 学習研究社刊 2006年3月発行 歯科医療「病と生死・医療のあり方とは」 第一歯科出版 1999年秋号 「スタッフ教育あなたならどうする?」 デンタルダイヤモンド社(別冊) Vol、25/No342 「義母、癌について思うこと」月刊情報誌「健康の集い」自然健康法普及会 5周年記念号 「義母の逝去」月刊 健康食1990年269号 「現在医学の盲点」歯科ペンクラブ1998年No326号 「歯科医の入院体験 上・下」食べ物通信 家庭栄養研究会 No190、191 その他多数 最近の論文 病と生死、医療を見つめて。高歯会雑誌12号 学校歯科保健に関する会員アンケート調査について。高歯会雑誌16号(1)2005年 学校歯科保健に関する会員アンケートのまとめと考察について。高歯会雑誌17号(2)2006年 診療報酬改定について 2006.5.23 日本歯科新聞「 診療報酬の改定について「日常診療を阻害するような朝令暮改の診療報酬の改悪」 総合医学会・医事評論 2007年 講演会 「口の中の細菌について」大阪府立寝屋川支援学校 学校保健委員会 平成23年6月14日 [歯の講話」第68回学童歯磨き大会 インターネット参加 寝屋川市立梅が丘小学校 平成23年6月3日 職業講話「歯医者になって」 代行 秦真紀子 寝屋川市10中 平成21年3月 卓話[日本の医療について。その一」 寝屋川ロータリークラブ 平成19年4月 「学校歯科保健に関する会員アンケートの調査について」発表。大阪府立高等学校保健会 平成17.2.9 大阪府歯科医師会館 「障害者の歯科受診について」大阪府立高等学校職域合同部会 平成17.11.9 大阪府立教育センター 卓話 「歯をみる 」 寝屋川ロータリークラブ 平成17年 11月 「障害者の歯をみる」 ワークセンター小路(障害者授産施設) 平成18年5月 「歯から始める健康医学」藤井寺・富田林歯科医師会合同学術研修会・ 「歯から始める〜」 堺市西保健所 その他・・・ 趣 味 絵を描くこと(油絵、水彩、イラスト、他)。旅行、カメラ、菜園、アウトドア、陶芸(自称;武田一陶)、釣り、アートグラス バードウオッチング、木工(糸鋸工芸など)、民具、剣道(2段)、万華鏡、ステンドグラス、その他・・・・・・。 過去、非日常性を求め年に1〜2回 (主に5月の連休) 遠い旅に出ることがありました。 カンボジャのアンコールワットの古代の遺跡に感嘆したりと・・・・・・・・・・・。ベトナムでは掏摸(すり)にあい 腹が立つやら、がっくりする やら・ ・・。悲惨なベトナム戦争の傷跡。あの戦争博物館の展示には絶句。。。 又日本の戦後のお互い様と言い相手を思いやる貧しい情景をかいま見、思い出しました。 旅はここ数年、摩訶不思議に魅了された国、インドへ。人の多いのにはビックリ。まだ2000ぐらいの カースト制度があるとか。(帰国後 暫く下痢に悩まされました?)、 モンゴルでは地平線を見ながら道なき道を行きました。 無駄のない自然連鎖の生活を見聞し、感激したり、見習いたいなと思ったり・・・しました。 ストーブあれどゲル(丸い白い布のテント)の中は寒いのでしっかり 夜は防寒服を着て寝ました。 ゴビ砂漠の砂の粒子の小ささに驚きました。粉?のようで。 フランスへ、ゴッホの誕生地を訪れたり、モネの絵をしっかり勉強?しに行きました・・・。 昔、日本には油を使って絵を描く発想がなかつたのが分かりました。 歴史、文化を大事にする国だと感心。、中学2年の時、京都市美術館で印象派画家モネの赤、青、黄色など 使った素晴らしい色彩 の 「チュウリップ畑」の絵を観て 興奮。絵心がめらめらと彷彿したのを思い出します。 4年前、数ヶ月ホームステイをした北欧フィンランドの交換留学生ビビの母国へ行きました・・・ この国の男子、女子にはしっかりした 徴兵制の義務があります。 家族写真を見せてもらったとき「あれ?お兄ちゃ、丸坊主?やのん?」「2ヶ月前、1年間の徴兵、から帰っ て、き、た」と言ったので、驚きました 最近、ビビ( 3回目の来日の時に)に徴兵に行った写真を見せてもらいました。戦闘服を着て、顔は緑、 茶色などの顔料で草色(装飾)・・・。 又 冬は日の出が10時頃で日暮れが3時頃だとか・・・、・・・ 2011.8月にも兄と友人と3人で来日しました。映画監督を目指し大学へかよっているとか。 南アフリカの「アパルトヘイト」人種差別・のその後を見に行ったり、ジンバブエへ(当地で荷抜きあいました。 私の大きな黄色いスーツケースが・・・な・・ない・・・) この国では再三このようなことがあるようです。本当にがっくり・・・。 ジンバブエのビクトリヤフォールズ(世界の3大瀑布の一つ)に感激 。 又子どもの頃から 憧れだった野生のキリン、サイ、カバなどの写真を撮り、幼子のように心が弾みました。 一 眼レフカメラを持ち・・・。重たかった? ・・・でも・・・・荷抜きには二度とあいたくないな。 小学校の社会科で習った古代文明。やっと行った古代遺跡の宝庫、エジプト、大きな石が幾重にも 積み上げられた墓石の大きさに呆然?なんとでかいことか・・・。又車の車検はなし。 道路沿いのビル は1,2階建てて3階はは建てず、ほったらかし? トルコ美しい国ですがモスクの数々の建物・・・。、夜行列車のトイレにはまぃった・・・ その他・・・・・・・・。 文明史家の村山節氏によれば、。地球の文明には800年周期で東と西が交代。交互に盛衰すると。 宇宙全体のメカニズムがあるのでは?DNAのらせん状構造?と似て非なるもの。 私が好む「宇宙の二極対立の法則」だ。陰と陽・女と男・生と死・有と無・・・。 2013年4月より院長を交代。武田邦太郎が院長になりました 武田邦太郎のホームぺージ(ここをクリック)をご覧ください。 どうか今後とも何卒よろしくお願いいたします。 |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
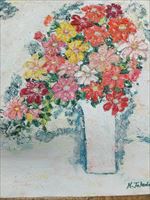 |  | 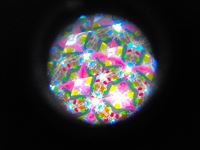 |
 |  |
|