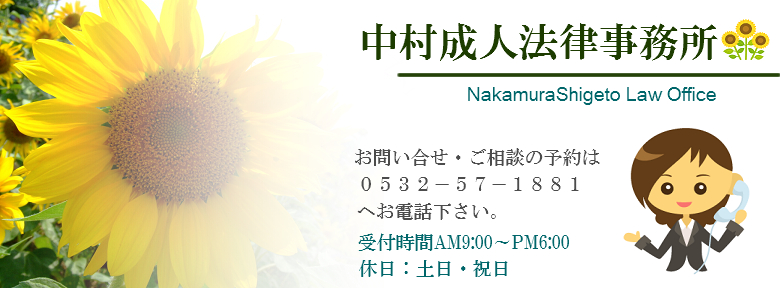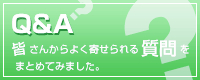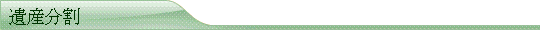
- Q
- 長兄から「父の不動産や預金の関係で判が要る。この書類に判をくれ。印鑑証明も5通取り寄せてくれ。」と矢の催促。もっと父の預金があったはずなのに色々変です。どうしたらよいでしょう。
- A
- 遺産分割では、相続人全員が遺産の明細を正確に認識しあうことが大前提です。それもしないまま書類に判を押したり、判を預けたりすることは、大変危険です。父の不動産が売却されたり、預金が払い戻されたりしたのに、あなたには何も渡されないといったことが起きたりします。他の相続人に任せるのではなく、主体的に関わる姿勢が大切です。
父の預金が不自然に少なくなっているのなら、金融機関に出向き、預金取引の明細書の提出を求めて下さい。多額の出金や定期の解約等を見つけたら、払戻請求書や定期預金証書等の開示を求めて下さい。
遺産の明細が隠されたり、無断払戻等が疑われる場合、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をし、裁判所から調査してもらった方が解決が早いと思われます。調停は「話し合いの場」です。「裁判沙汰」と敬遠する必要はありません。
- Q
- 先月、父が急死しました。遺言がないので、遺産分けをしたいのですが、母は認知症で判断能力がなく、兄は3年前に事業に失敗して行方不明、弟は小学生の子二人を残して2年前に病死しています。誰と協議したらよいのでしょう。
- A
- 遺産分割協議は相続人全員でする必要があります。ご相談のケースでは、お母さん、お兄さん、弟さんの二人の子供も相続人なのですが、それぞれに協議困難な事情があります。結論を申しますと、お母さんには成年後見人、お兄さんには不在者の財産管理人、弟さんのお子さんには特別代理人(一人については弟の奥さんが親権者として関わることも可能)をそれぞれ家庭裁判所に選任してもらい、選任された人と協議することになります。お母さんの成年後見人、お兄さんの不在者財産管理人にあなたがなることも可能ですが、遺産分割については、あなた自身と利害が衝突するため、さらに特別代理人を選任する必要が出て来ます。当初から、お父さんの相続と関係のない身内や知人、弁護士や司法書士などを選任してもらうことも考えられます。家庭裁判所は、遺産分割協議の内容が物言えぬ立場の人の権利を不当に害した形にならないよう慎重に配慮する運用をしています。
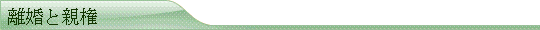
- Q
- 離婚話を進めているのですが、夫は、3才の男の子の親権を渡せと強行です。話合いに疲れたので、一旦、夫に親権を渡し、何年か後に親権の変更の話をしたいと思います。どうでしょうか。
- A
- 協議離婚の場合、夫婦は、話合いで親権者を決めることができます。しかし、一旦、決めた親権者を変更するには、家庭裁判所に申立をし、調停又は審判の手続を経なければなりません。すなわち、二人だけの話合いではできないのです。また、子供にとって親権者を変更する必要があるのかどうかも裁判所に吟味されることになります。
裁判所が親権者の指定・変更を行う場合、(1)乳幼児は母親を優先、(2)子の置かれた現状は尊重する、(3)物心ついた子の意向は尊重する、(4)経済面よりも子の精神面を重視する、(5)兄弟姉妹は一緒になどの基準をもとに判断します。子の福祉を考えたうえでの基準ですので、協議離婚で親権者を決める際にも尊重したいものです。
さて、「後から変更」ということですが、調停等が必要になるうえ、(2)の基準との関係で支障が生ずるおそれがあります。3才の子ですから、(1)、(4)の基準を前面に出して、今、初志を貫徹して下さい。
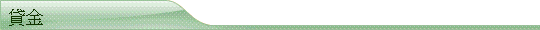
- Q
- 元同僚から「子供が専門学校に行くから100万円貸して欲しい。」と頼まれています。友達だから嫌とは言いにくいのです。高級車に乗っているし、借用書をとれば安全と思うのですが。
- A
- 銀行のカードローン、サラ金のATM、クレジットカードによるキャッシング等々、今の時代は、昔と違って、恥をかかずにお金を借りる手段がたくさんあります。逆に言うと、この時代、恥を忍んで個人に金を貸してくれと頼んで来る人は、そうした手段を使い果たした「よくよくの人」だと覚悟する必要があります。返済は危ないとみるべきでしょう。
借用書を作っても、払わない人は払いません。裁判所の判決が出ても払わない人さえいます。その人にめぼしい財産がなければ回収できないのです。高級車に乗っていてもクレジットで買ったかもしれません。その車はクレジット会社のものです。預金の差押には預金先が、給料の差押には勤務先が分かっている必要があります。お金のことであなたを悩ませる人、その人は本当の「友達」でしょうか?。
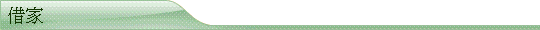
- Q
- 家主から「アパートを建て替えるから今年いっぱいで出てくれ。」と言われています。今と同じ家賃の物件はないし、75歳なので転居したくありません。出ないといけないでしょうか。
- A
- 家主が自分の都合で借家契約をやめる(解約、更新拒絶)には「正当事由」が必要です。あなたに契約違反がないのに一方的に「出て行け。」とはいえません。有効利用のための立退は、立退料を提供してどうにか認められるかどうかといった微妙なものです。同じアパートに住むほかの方とも連携をし、弁護士と相談のうえ、対応策を決めて下さい。立退に応じる場合、引越代、新築アパートへの優先入居(又は転出先の敷金・礼金・仲介手数料・家賃差額)、借家権価格や営業の補償などを求めることになります。立退に応じられない場合、「正当事由」が充たされないことを説明して家主に建替を断念してもらうことになります。あなたの生活の拠点がかかっている話です。自分一人で即断したり、家主から示された書類にすぐさま署名したりしないで下さい。
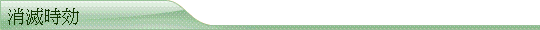
- Q
- 5年前、義弟の開店資金として500万円を貸しました。時効にかかりそうなので、商売をしている知人に聞くと、「毎月、請求書を送っていれば、大丈夫。」との返事。正しいでしょうか。
- A
- 大間違いです。請求(催告)は時効の完成を6か月延ばすだけです。6か月の間にあらたに裁判や支払督促などをしないと時効にかかります。内容証明郵便で請求した場合も同じです。「請求書を送っておけば時効にかからない。」は商売をしている方によくある誤解です。
裁判より安価で手軽な時効防止策はないでしょうか。1万円でも入金してもらう。債務残高を書いた書面に署名捺印してもらう。これにより時効の進行は止まります。時効にかかった後でも時効の主張を封じることができます。
開店資金のための貸金の時効は5年ですが、いつから5年と計算するのでしょうか。入金があるときは最終入金時。入金が全くないときは返済期限。返済期限を決めてないときは催告後相当期間経過したときからです。
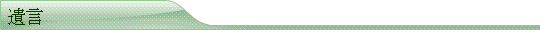
- Q
- 私と妻には子供がなく、私の財産は40坪の自宅があるだけです。両親は亡くなり、兄弟はいます。妻は「遺言をして。」といいますが、居住権もあるし、心配ないのではないでしょうか。
- A
- 遺言をしてあげた方が奥さんに親切です。遺言がないと、法定相続分は、奥さんが4分の3、兄弟が4分の1となり、4分の1に相当する分をお金で払えと奥さんが兄弟から要求されて困ることもあるからです。また、居住の実績があるからといって兄弟の相続分がなくなるわけではありません。兄弟には遺留分がないので、遺言により自宅をすべて奥さんに相続させることができます。
遺言は、口で言っただけではダメで、書面にする必要があります。自筆証書遺言と公正証書遺言がその典型ですが、安全・確実な公正証書遺言をお薦めします。公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言の内容を口授し、公証人が証書に作成します。病気などで公証役場へ行けないときは、公証人が自宅や病院まで出張してくれます。
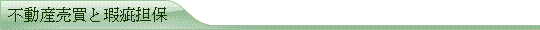
- Q
- 新居を建てるため昨年末に土地を買いました。ところが、着工前に地中に古い配管類が埋まっていることがわかり、撤去に数十万円かかるとのこと。売主・買主・仲介業者、誰の負担になるのですか。
- A
- 買主のあなたとしては、配管埋設を土地の瑕疵(欠陥)と評価し、売主が瑕疵担保責任を負うべきだと主張してゆくことになります。この責任は無過失責任で、売主が埋めたのでなくても、また、売主自身埋設を知らなかったとしも、責任を負うことになります。ただし、売買契約書上、「売主は瑕疵担保責任を負わない。」と特約されていることも多く、この場合、買主が負担をかぶることになります。なお、売主が宅建業者の場合は、このような特約は無効とされています。
このような土地を仲介した業者には責任はないのでしょうか。仲介業者が事情を知って仲介した場合は責任を負いますが、ボーリング調査等しないとわからないようなことだと調査義務違反の責任を問うことは難しいでしょう。
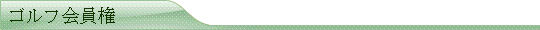
- Q
- 10年前に会社を定年退職し、退職金2000万円を預託金として払ってゴルフ会員権を取得しました。返還時期が来たので、返還を求めたら、理事会でもう10年延ばしたとの返事。老後の資金だったのに悔しいです。
- A
- 預託金は、返還時期を定めて、あなたがゴルフ場経営会社に預けたお金であり、本来、期限が来れば返すべきです。あなたの了解なく、ゴルフ場が一方的に延ばすことはできません。少数の裁判例を除き、最高裁も、多くの裁判例も、そう判断しています。
しかし、バブル期に開場したゴルフ場は、100億円を超す預託金債務を抱え、約2割の会員が延期を了解せず、返還困難というところも少なくありません。交渉だけではずるずる延ばしにされる危険があります。誠意がみられないのなら、早めに見切りをつけ、預託金返還訴訟に踏み切ります。その中で、できれば即金、ダメなら可能な限り短期の分割弁済の和解を成立させ、一刻も早く、回収に着手します。
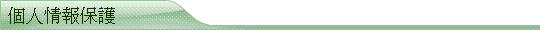
- Q
- 幼稚園児を持つ母親です。お隣の写真屋の奥さんが「七五三や入学祝のダイレクトメールに使いたいから、園児名簿を貸してくれない。」ってしつこいのです。貸すと個人情報保護法で処罰されますか。
- A
- 個人情報保護法は、本人の同意なく、個人データを第三者に提供したり、個人情報を目的外に利用したりすることを禁じています。しかし、その義務を負うのは、5000人を超す個人データを持つ「個人情報取扱事業者」に限られ、あなたがこれに該当することはありません。したがって、あなたが役所から勧告や命令を受けたり、処罰されたりすることはありません。他方、写真屋さんの方は、「個人情報取扱事業者」に該当すれば、個人情報の不正取得が問題となります。
いずれにせよ、法は、個人の権利を守るための社会常識をルール化したもの。たとえ適用がなくても、「そうした個人情報の利用は、幼稚園や園児・保護者の信頼を裏切る行為だから、私にはできません。」とお断りするのが、常識ある社会人だと思います。
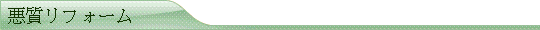
- Q
- A町の実家に一人で残して来た母親が悪質リフォームにひっかかり、クレジット契約を3社と結んでしまいました。これをどう処理したらいいのかということと今後の予防策をお尋ねします。
- A
- まず、契約書をご確認下さい。受け取った日から8日間はクーリング・オフ(無条件解約等)できます。契約書に不備があるときは、無期限にクーリング・オフできます。クーリング・オフが無理な事案でも、錯誤や公序良俗違反による無効、消費者契約法による取消や詐欺による取消の主張が可能です。リフォーム業者だけでなく、クレジット会社にも通知書を送り、口座振替をやめ、クレジット代金は払いません。リフォーム業者からの脅しやクレジット会社からの督促もあるので、弁護士に対応してもらいます。
行商人や御用聞が家々に頻繁に出入りした昔とは時代が違います。予防策は、お母さんによく言って、「知らない人の電話には応対しない。」「知らない人は家に入れない。」「インターホン越しに断わる。」を徹底してもらうことです。
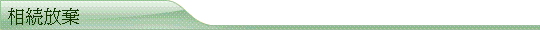
- Q
- 長年音信がなく、遠方のA市で借家暮らしをしていた父が死亡しました。私は、A市民病院の知らせでかけつけ、葬儀や借家の明渡し、未払家賃・医療費の清算をしました。1年後、父が金を借りたサラ金から私に督促が来たのですが、相続放棄できますか。
- A
- 借金も相続の対象となり、これを免れるには相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。しかし、あなたの場合のように、3か月以内に相続放棄しなかったのが、遺産が全くないと信じたためであり、かつ、父の生活歴や父との交際状態等から遺産の調査をしないのがもっともだと評価できるときは、例外的に借金の存在を知った時から3か月と計算することも可能です。
次に、父の動産類を廃棄したりしたことが遺産の処分に、未払家賃等の支払が相続債務の弁済にあたり、単純承認となって相続放棄できないのではといった心配もありますが、とりあえず相続放棄の申述をして下さい。申述受理証明書を示されれば、請求を断念するサラ金は多いはずです。
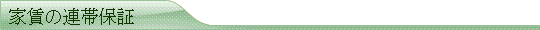
- Q
- 5年前、知人Aがマンションを賃借する際に連帯保証人になりました。契約書に書かれた期間は2年でした。ところが、先日、家主から「Aが家賃を3年分ためたから払え。」と私に催促。私に責任がありますか。
- A
- あなたとしては、自分が署名捺印した契約書の期間は2年だから、その後は知らないと言いたいところです。しかし、判例は、建物賃貸借において、期間後の継続は予測しうることだから、保証人は、原則として、更新後の家賃滞納にも責任があるとしています。
では、例外はどんな場合でしょうか。契約書に保証人の責任は2年に限ると書いてあった場合や家主の滞納放置が信義に反する場合などが考えられます。
滞納状況を保証人に伝えなかった家主の態度はどう評価されるのでしょうか。家主には滞納状況を保証人に伝える義務はないと解釈されていますが、長期滞納を知らせず、保証人がいろいろ手を打つ機会を奪ったと評価できるときは、保証人の責任を限定する事情になると思われます。
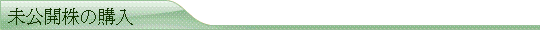
- Q
- 最近、複数の投資会社から、A社の未公開株の購入を勧める電話やダイレクトメールが来ます。A社のCMはよく見るので、一番安い値段を示している投資会社に申込をしようと思います。ただ先に大金を振り込むのが心配です。
- A
- 有名企業の未公開株を「上場間近」と称して過大な金額で売りつける被害が多発しています。A製薬、O製薬などOグループ、Y●K、書籍取次のN販などの株が標的とされ、各社は、自社のホームベージで注意を呼びかけています。
各「投資会社」が似たような値段を表示するため、それが「相場」と錯覚する人もいますが、違います。例えば、A製薬の場合、各「投資会社」が売り出した価格は1株1万5000円~2万円、A製薬の上場時の公募価格は1株2000円です。購入者は、7倍から10倍の値段で買わされたことになります。
こうした「投資会社」の多くは、証券取引法違反の無登録業者で、数か月で、担当者が辞めたとか、業務を他社に引き継いだと言い出すところも多いもの。株が送られて来たとしても、高い買物になるので、絶対に手を出さないで下さい。
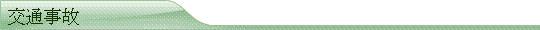
- Q
- 半年前に息子を交通事故で亡くしました。昨年の春に学校を卒業し、就職したばかり、独身でした。加害者の保険会社から示談の提案がなされたのですが、妥当な金額か判断がつきません。どうしたらよいでしょうか。
- A
- 死亡事故の損害は、慰謝料、逸失利益(将来得られたであろう収入から生活費を引いたもの)、葬祭費などからなりますが、保険会社の提示額が低いことがあります。例えば、独身男性の死亡慰謝料は、2000万円~2400万円ですが、1000万円台の提示がなされることもあります。また、若年者の逸失利益は、平均賃金を基礎に計算する手法が最近では支配的になって来たのに、低い現実収入を基礎にされ、1000万円以上安く計算されてしまうこともあります。さらに、事故態様により、過失相殺率の基準が示されているのですが、その適用や解釈の誤りを指摘できる場合も少なくありません。
このように専門的判断を必要とし、100万、1000万単位の不利益を受けることもあることですので、提示には即答せず、弁護士に損害額の試算をしてもらって下さい。弁護士に委任して交渉してもらうことも有効です。
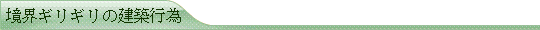
- Q
- 隣の人が境界線間近なところまで建物を建てようとしています。こんなことが許されるのでしょうか。また、対応はどのようにしたらよいでしょうか。教えて下さい。
- A
- 建物は境界線から50センチ離して建てなければなりません(民法234条1項)。この距離は、側壁や出窓等の固定的突出部分からの最短距離で測定します。違反者に対しては工事の禁止や変更を請求できますが、着工後1年経過すると、損害賠償請求しかできなくなります(同条2項)。したがって、直ちに施主・工事業者に建築内容を確認し、違反とわかったら、すぐ変更を求めることが大切です。建築内容を教えてくれないときは、役所で建築確認申請の図面を閲覧して知る方法もあります。不誠実な違反者には工事続行禁止の仮処分を裁判所に申し立てて対応せざるをえません。
以上の民法の原則は、建築基準法によって一部修正されています。同法65条は、防火地域又は準防火地域において、外壁が耐火構造の建物を境界線ぎりぎりに建てることを許しています。この点も調査したうえで対応して下さい。
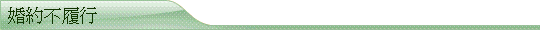
- Q
- 彼から「性格が合わないから結婚をやめる。」と言われました。結婚式場や新婚旅行の予約も済んでいます。裁判で結婚を命じてもらえますか。損害賠償を請求できますか。受け取った結納金はどうなりますか。
- A
- 結婚は自由な意思でなされるもの。法的手続で強制することはできません。しかし、婚約も契約です。正当な理由なく破棄した者は、損害賠償義務を負います。彼の婚約破棄に正当な理由があるかですが、互いを理解して婚約したのですから、いまさら「性格が合わない」は、正当な理由にならないと思います。
次に、賠償対象となるのは、式場や旅行のキャンセル料などの財産的損害と精神的苦痛に対する慰謝料。慰謝料の金額は、裁判例では30万円~500万円とばらつきがありますが、100万円程度が一つの目安と思われます。
受け取った結納金はどうなるのでしょう。結納金は、結婚を目的とした贈与ですので、結婚が成立しなかった場合、返すのが原則です。しかし、正当な理由なく婚約を破棄した者からの返還要求には応じなくてもよいとする裁判例が多数あります。したがって、あなたの場合、返さないという方針でのぞむことになります。
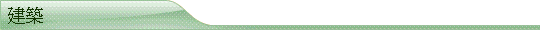
- Q
- 自宅を新築しようと思います。2500万円で工事を頼んだのに後から500万円の追加請求が来たなどという話も人から聞きます。どんな点に気をつけたらよいのでしょうか。
- A
- 追加請求は、瑕疵(欠陥)と並ぶ建築トラブルの代表例。「その工事は当初の金額に含まれていたはず。」「いや違う。」ともめることに。もめるケースは、(1)工事内容を確定せずに契約した、(2)見積書が粗雑、(3)見積書に「別注」を明記しない、(4)施主が施工中にどんどんグレードアップを要求した等、それなりの原因があります。(1)、(2)の防止策は、契約前に工事内容を詰めて設計図・仕様書を確定し、正確な見積書を作成させて納得したうえ、契約書に調印することです。(3)は、住宅設備機器(バス、トイレ、キッチン、洗面等)、照明、空調、水道工事(公道分)、水道工事負担金、設計料等がよく問題となります。防止策は、見積書を精査し、問題となりやすい点が工事金額に含まれるのかどうかを確認し、記録に残すことです。(4)の防止策は、グレードアップの要求の都度、追加金額の有無と金額を確認し、記録を残すことです。これらの記録は、双方のサインのあるメモ程度でも結構です。
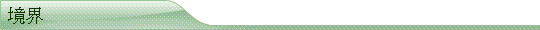
- Q
- 隣の人が頼んだ測量士が「お宅の壁が隣に入っている。建替時に引いて建てる旨の念書に判を下さい。」と言って来ました。私の家は20年以上建っており、納得できません。
- A
- 土地の境界は、登記簿や附属地図などで公的に確定された線であり、隣同士の合意や越境の実績で決めることはできません。真実の境界の見通しをつけるため、貴殿の側でも、土地家屋調査士(測量士)などの専門家に意見を聞く必要が生ずることもあります。
仮に、境界が先方の測量士の言うとおりだったとしても、貴殿は越境部分を時効取得している可能性があります。いわゆる越境型の場合、20年間、所有の意思で、平穏かつ公然と占有して来たとして、時効所得を認める裁判例は多数あります。そして、この場合、境界は先方が言うとおりでも、所有権の範囲は貴殿の言うとおりで、越境部分の所有者は貴殿ということになります。
先方の測量士がいう念書はどう評価されるでしょうか。時効の利益の放棄とみなされる可能性がありますので、取得時効の主張をしたいときは、署名捺印しない方が無難でしょう。