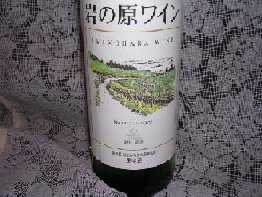岩の原葡萄園
〜日本ワインの父、起つ〜
外観
新潟の上越市周辺といえば言わずとしれた大稲作地帯。見事なまでに広がる水田は、日本が米の国であることを語ってくれます。
しかし明治時代、この稲作の地で一人、同じような風景を見ながら別のことを考えていた人物がいました。
その人物、川上善兵衛が造り上げたのが、この岩の原葡萄園です。丘のふもとに建てられてた瓦屋根の醸造所や販売所だけでなく、あちこちに善兵衛の遺業をしのぶ歴史館やワイン蔵が立ち並び、もちろん背後の丘一面には、葡萄畑が広がっています。
日本ワイン史に不滅の業績を残した醸造所の過去と現在を見ていきましょう。
歴史
北陸地方最古、日本でも有数の歴史を持つ岩の原葡萄園は、日本ワインの歴史を語る上においてけして外すことのできないワイナリーの一つです。日本ワインに興味がある人で川上善兵衛の名を知らない人はまずいないでしょうし、日本ワインを何度か飲んだ人で「マスカットベリーA」のワインを飲んだことがないという人もいないでしょう。
岩の原葡萄園の創始者、「日本ワインの父」と評されるようになる川上善兵衛が生まれたのは明治元年。生まれた川上家は北方村(現在の上越市南東)で屈指の豪農として名をはせており、善兵衛はその長男としてこの世に生を受けました。経済的には不自由なく成長した善兵衛は、見聞を広めるべく明治15年(1882年)に上京。ここで川上家とはもともと親交のあった勝海舟に訓等を受け、またこのとき初めて”葡萄酒”と出会います。慶応義塾大学にも入学して見識を広めようとした善兵衛ですが、既に父親が死去していたこともあり跡取りとしての責務を果たすよう母親に言われやむなく地元に戻ります。
郷里に帰った善兵衛は、かねてから考えていた小作人の生活の苦しさ、というよりは農民の貧しさを解決する方法を模索するようになります。荒地でも耕作でき、豪雪地帯ゆえ冬季に収穫期のこない植物を探した結果、行き着いた先は葡萄でした。そのため、二十歳になると、当時の日本のワイン醸造や葡萄栽培において第一人者の人々の元を訪ね歩き、その技術や知識を習得する旅に出ます。出会った人々には、カルフォルニアで葡萄栽培を学び日本にラブレスカ系葡萄(デラウェア、コンコードなど)を多く取り入れた小沢善平、フランスで醸造を学んだ土屋龍憲と高野正誠、蜂葡萄酒で財を成した牛久園の神谷伝兵衛など、日本ワイン史において外すことのできない人物が数多くいました。
明治23年、善兵衛は小作人とともに名園と言われた川上家の山を開墾し、数々の葡萄の苗木を植え葡萄栽培に取り組みます。ここに「岩の原葡萄園」のはじまりです。
事業は、試行錯誤を繰り返しながらもに進みますが、善兵衛はワインには向くが栽培が容易ではないヴィニフェラ種、その逆のラブレスカ種、この両者の長所をもち日本の環境で育つ品種の必要性を痛感するようになります(余談ですが、ヴィニフェラ種の中で比較的良好な結果が得られると善兵衛が記録している品種はメルロー。長野県のメルローの隆盛を暗示する記録です)。この経験から娘婿の川上英夫とともにワイン醸造のかたわら品種交配にも力を注ぐようになります。
その苦労が報われたかのように明治35年に東宮・有栖川宮の両皇族が見学に訪れ、明治37年の日露戦争の際には軍部が病院用の衛生材料として葡萄酒を大量に買い上げるなど、岩の原葡萄園で最良の時期が訪れます。ここで善兵衛は判断を誤りました。この一時的需要を永続的なものだと勘違いし、畑の拡張とさらなる増産を行い、結果、日露戦争の終結とともに岩の原葡萄園の経営状況は悪化しました。
この頃になると善兵衛は川上英夫に葡萄園の経営を任せ、専ら著作に力を入れるようなります。明治41年、善兵衛の経験をもとに葡萄栽培から醸造までを網羅した『葡萄提要』を刊行。この『葡萄提要』と昭和7年に刊行される善兵衛の知識の集大成ともいえる『葡萄全書』の著作は、戦前の葡萄栽培や醸造のバイブルとして多大な影響を与えた名著となります。
しかしこうした著作や研究の間に、善兵衛の経営能力の無さもあって岩の原葡萄園は廃園同然となってしまいます。昭和9年、この善兵衛のもとに、国産葡萄主体による「赤玉ポートワイン」の生産を検討していた寿屋(現在のサントリー)の社長、鳥井信治郎が訪れ、葡萄園の法人化と資金の供出を申し出ます。善兵衛のもつ技術や知識を見込んでの話で、借金は全て鳥井信治郎が清算する以外に研究への資金提供など破格としかいいようがない好条件で「岩の原葡萄園」は法人として再スタートしました。
こうして金銭面での心配が無くなった善兵衛は残りの生涯をほとんど品種改良の研究に打ち込むようになります。昭和15年にはその研究成果である22の川上品種を学会で発表。この中にマスカット・ベリーA、ブラッククイーンなども含まれており、ここで善兵衛の業績は揺るぎないものとなりました。
その後も若い頃と変わらず著作と品種の研究に没頭した善兵衛でしたが、昭和19年、肺炎のため73歳で死去。その業績が認められ始めた矢先のことでした。
現在の岩の原葡萄園は、戦前と同じようにサントリー出資の法人の一つとして営業を行っています。代表取締役には登美の丘ワイナリーの所長であったことでも知られる萩原健一氏が就任。川上品種より、国際レベルに通じるワインを造りだすという高い志をもって経営に取り組んでいます。
生産量は約50万本と純国産ブドウのみを使用するワイナリーとしては全国でもトップ10には入る驚異的な数値を誇り、全国のスーパーや酒販店で販売され、”岩の原”の名を知らしめています。
原料の葡萄は低価格のものは長野や山梨のものを使用していますが、フラグシップとなる深雪花などの中価格帯のワインは、自社畑の葡萄を使用しています。そして全ての赤ワインはベリーA主体で構成されているというのも、まさにこのワイナリーを体現する事実の一つといえるでしょう。
施設の概略
施設内に醸造器具がおかれており、多くの施設の見学は自由です。
道向かいの歴史記念館「紫水ふれあいの郷」の入館に限り、あらかじめ予約が必要なので、詳細は岩の原葡萄園にお問い合わせください。
販売店:ワインの試飲と購入のほか、このページの文章を書く際にも参孝にさせていただいた『川上善兵伝』(サントリー文庫)など、貴重な書籍も販売されています。
また、そのような堅苦しいことは抜きにしても、清潔感があるうえ、独自のお土産もの(深雪花ケーキなど)が多数販売されているので、けっこう買い物が楽しめるようになっています。こういったところはさすがサントリーが親会社、と思わせるものがあります。
初代園長の川上善兵衛もせめてこれくらい商売っ気があればこの葡萄園もあれほど苦難の歴史を歩まなかったのでしょうが・・・。
第二号石蔵:岩の原の第一号石蔵(非公開)と並び、現存する最古のワイン蔵で1898年に建造されました。上越市指定の文化財になっているほどの蔵ですが、驚いたことに”現役”です。
地下に作られた蔵の入り口は重々しい石の扉で、まさに歴史の迫力とでもいうべき雰囲気が漂います。中に入ると、ワインの芳香が鼻をつくので先ほどの”現役”という意味はすぐにわかるでしょう。蔵内に安置された大小様々な樽はワインで満たされ、出荷の時を待っていました。
内部では音声案内を含めて詳細な説明があるので耳を傾けて、この蔵の歴史を聞くと気分が高まります。
また、ワイナリーの貯蔵庫に何箇所か行った人ならば、ここには奇妙な空間があることがわかります。説明にもありますが、その空間は雪室と呼ばれる、雪を貯蔵しておく場所です。冬季は雪を貯蔵して蓋を閉じておき、春や夏に蓋を開けて、発酵作業時の冷却剤としてその雪を利用していました。現在のように温度管理機能付きステンレスタンクはもちろん、冷却用ジャケットもない、なにより低温長期発酵の重要性が世界中に伝播していたわけでもないこの時代にこのような手法を編み出した善兵衛の発想力には驚嘆せざるえません。
そしてこの雪室、CO2の発生量を削減して環境負荷を軽減することを目的に復活し、再び現役で活躍を始めています。もちろん昔のものをそのまま使っているわけではないですが、まったく同じコンセプトの施設が100年の時を越えて作られるというのは壮大なロマンです。
冷気ずい道:畑の行く途中で見学できる、”発見”された施設の一つです。明治28年に作られた全長40mにもなる地下に造られた石造りの細い道で、ワインの貯蔵庫に地下の冷たい空気を取り入れるために建設されました。
しかし、農民に仕事を与えるためという理由を差し引いても、貯蔵庫のワインの冷却のためにこのように大掛かりな施設を個人で建設していたのですから、明治期の岩の原葡萄園の経営が行き詰まってしまったのもやむなしかとも思えます。

直営レストラン
ワイナリーの販売所の向かいにレストラン「ラ・カーブ」があります。季節営業で4月〜11月中旬まで営業、定休日は毎月第三火曜日、営業時間は10:00〜15:00まで。平日はランチコースが設定されており、価格はだいたい1000〜1300円からとなります。コース以外のアラカルトはやや高めの値段設定。
料理は、フランスのビストロ(定食)のような欧風料理が主で、他にベーベキューもコースに含まれています。最低価格のコースでもデザートを含めなかなかしっかりしたレベルの料理を提供してくれるので、j数あるワイナリー直営レストランでも平日のランチ狙いならコストパフォーマンスの高い店の一つと思えます。
ただ一つ、それだけの料理を出しているにも関わらず、ここはなぜか屋外形式のレストラン。立地が新潟なのですから11月にもなったら、落ち着いて食事ができないほど寒いような・・・(^^)。
10名以上の団体の予約に限りディナーの受付も行っていますので、ツアーなどを企画している場合にはここの利用は一考の価値があります。
テイスティング
販売所で発売されている銘柄の多くが無料で試飲することができます。高価格の一部のワインが有料による試飲となります。
蛇足ですが普通の試飲カップかと思いきや手にとると、小型ながらもしっかりガラスのグラスなのにはびっくりします。
テイスティングコメントに関しては、参孝程度に読んでください。
フルーティーブラン:1031円。ナイアガラを原料とした甘口の白ワインですが、この品種のワインとしては少しおとなしい香りです。それほど個性的なワインではないので、ナイアガラの個性がそれほど好きでない人でも飲めます。ただ、金属香の余韻があったのでこの手の香りがあまり好きでない私にはあまり合わないワインでした。
フルーティールージュ:1031円。コンコードを原料としたやや甘口の赤ワインです。糖を多くは残していないので、さくさく飲めるワインという印象を受けます。また、フルーティーブランと同様、こちらもこの品種のワインとしては香りは少しおとなしめです。
余談ですが、公式ホームページの紹介には「リラクゼーション効果があるといわれているコンコード種の香り」のワインとして紹介されていました。言われてみると、なるほどコンコードの香りはアロマセラピーの香りにありそうとも思えます。
ブラッシュロゼ:1376円。マスカットベリーAによるブラッシュワイン(ロゼと白の中間)です。イチゴのような香りが、上立香と飲んだ際にも共通してイチゴの香りがあります。味わいはあまりインパクトがありません。
あまくちの赤:1376円。キャンベルアーリーを主体としたワインで、味わいは・・・まあ銘柄のままです(^^)。品種特性であるイチゴゼリーのような香りもしっかりでていますが、ブラックベリー系の重厚な香りもあります。タンニンもそれなりにあり、華やかさとほどほどの「重さ」が同居したかなりバランスのよいワインです。おすすめワインの一つで、ワイナリー内でも売れ行きナンバー1のようですが、販売所以外でお目にかかることはあまりないのが残念。
深雪花 赤:詳細は管理人のワイン記録に譲ります。岩の原葡萄園100周年を記念して作られた銘柄ですが、日本のベリーAのワインを代表する銘柄の一つです。ワイナリー内での試飲は有料となります。
善兵衛 2002 :ベリーAを主体(カベルネ・フランがわずかに入っています)とした、岩の原のフラグシップワイン。価格は6300円、グラスの場合は600円と高級ワインの価格帯。まず、ベリーAとはとても思えない濃厚な黒紅色に驚かされます。樽香の香りは充分にあり、またしっかりと果実の香りがあるので飲む前から期待が高まります。いざ飲むと、アタックはやさしめですが途中から樽の香りとベリーAとは思えない濃縮感のある味わいが口中に広がり、さらに余韻も樽香とベリー系の香りが長く残ります。
ベリーAながらも高級ワインの領域に踏み込んだワインなので、ワイナリーに行ったなら試飲だけでもしたいところです。
改めて銘柄を見てみると、岩の原の赤ワインは川上品種でも特にベリーAにこだわっており、川上品種でワイン用葡萄として一定の評価を得ているブラッククイーンはあまり前面に出ていないというのは興味深い点です。
日本ワインファンとしては全ワインを褒めたいところですが、個人的には「凄くよい、とはいえない」というワインがあったので、傾向をまとめてみます。
価格はスタンダードワインは1000〜2100円以内、とかなり買いやすい値段なのに好感がもてます。最高クラスの「善兵衛」はまずお目にかからないワインなので、一般市場で出会うワインはほぼこの範疇に入るといえます。
さすがベリーAの元祖だけあり赤は全て購入の価値充分です。中でも「深雪花」の赤はベリーAの最高峰のワインの一つとして飲んでおきたい銘柄です。営業部の方が「単純に2000円の赤ワインという範疇で飲んでも価値のある銘柄」とおっしゃっているだけあり、2000円代でもコストパフォーマンスは良いワインと思えます。また赤ワイン全般で、ベリーAのワインとしては骨格がしっかりとしたワインという印象を受けます。
残念ながら低価格のラブレスカのワイン、白ワインは赤ワインが良いこともあって比較してしまいあまり好印象を抱けませんでした。むしろベリーAのロゼやキャンベルアーリーのワインはコストパフォーマンスからみても充分なので、個人的にはこちらがおすすめです。
| 銘柄: |
深雪花 赤 |
| 生産元: |
岩の原葡萄園 |
| 価格: |
2100円(税込) |
| 使用品種: |
,マスカットベリーA |
| 備考 |
岩の原を代表する銘柄の一つ。
色は、ベリーAとしてはかなり濃厚なガーネット。香りは樽のヴァニラやロースト香のほかにカシスのような果実香。
香りは重厚ですが味わいはそこまで重くはなく、優しい味わいとともにベリーの甘い香りと樽のロースト香が口に広がります。その優しいなかにも凝縮感があり、ベリーAらしいなめらかなタンニンと、コクを感じます。
セニエ(醸造法の一つ)により、色と味に厚みをもたせているなど、かなり力が入っているだけあって、買う価値は充分。ラベルデザインも目を引くものなので贈答用も含めて、まず岩の原のワインはこの銘柄を購入してみることをおすすめします。
|
| 飲んだ日: |
2004年11月28日 |
発掘された冷気ずい道。40メートルを越える長大な
冷却用施設です。
| 銘柄: |
岩の原ワイン 赤 |
| 生産元: |
岩の原葡萄園 |
| 価格: |
1061円(税込) |
| 使用品種: |
マスカットベリーA、他 |
| 備考 |
色は、やや透明感のある鮮やかな赤。
香りにはベリー系の香り、グレープジュース(狐臭)、茎のような青い香りが確認できます。
アタックはやさしめで、含み香には甘いベリーの香りと少し青い香りが入り混じっています。タンニンはライトボディ程度ですが、ほどほどにあるので「赤ワイン」というジャンルには充分に入るレベルのもの。酸味はまろやかながらもしっかりしており、そこまで濃縮感はないこのワインにボディをもたせています。
樽は使っていない、または大樽の発酵と思われ、樽に由来するような香りはあまり感じ取れませんでした。
コストパフォーマンスに優れたワインで、値段的にもテーブルワインとして申し分ありません。インパクトなどはありませんが、香りもよく、味わいもバランスがとれたなかなかのワインに思えます。。 |
| 飲んだ日: |
2005年7月23日 |
葡萄畑
醸造所の後に迫る斜面にあるのが岩の原葡萄園の葡萄畑、とわざわざ説明する必要はまったくありません。山の斜面全体がまるまる葡萄の樹で埋め尽くされている光景を見れば何をかいわんやです。
この広大な畑、もともとは高田でも屈指の名園であった川上家の庭を善兵衛が葡萄畑とするために潰し、葡萄園にしたのが始りです。”岩の原”という名の示すとおり、かなり石の多い場所であったために開墾は困難を極め「岩の原を掘ると三日で鍬がダメになる」と言われたそうですから、想像がつくというものです。
しかも、この有名な畑、思いっきり北斜面というのも特徴。川上善兵衛も別に好きで日当たりの悪い北斜面を開墾したわけではないのですが、理想とされる南西向きの土地は自分の敷地になかったのでこれは止むを得ない選択でした。
現在の畑も斜面に沿って葡萄が栽培されており、垣根と棚の両方の栽培方法が採られています。興味深いことに棚栽培は明らかに生食用と異なる、密植栽培。斜面に狭い間隔で樹が植えられているので、優雅に葡萄狩りは楽しめそうにありませんが、一本の樹につく葡萄の量は制限されるので濃縮された果実が期待できる作りになっています。付け加えると、垣根の方も樹の間隔が狭く、こちらもかなり密植栽培です。
畑は自社だけで7ヘクタール以上と、かなりの広さ。栽培品種はマスカットベリーA、ブラッククイーン、さらに川上品種で現在栽培されているほぼ唯一の白葡萄であるローズシオター。他、いくつかヨーロッパ品種の葡萄も栽培されていますがまさに川上品種の博覧会場といっていい構成です。。
第二号石倉の入り口。明治に刻まれた文字がいま
も来訪者を出迎えます。
購入方法
ワインの販売は全国の酒販店やスーパー、ワイナリー内の販売店、公式ホームページからの通販で行われています。公式ホームページは親会社がサントリーのわりにはそれほどデザインを重視したものでないので、初めて見た方は少し驚かれるかもしれません。
ワイナリーアクセス
アクセスに関しては岩の原葡萄園の公式ホームページに説明されているのでそちらを御参照下さい。
総論
北陸、といより日本ワイン史に残る葡萄園の一つ。
善兵衛の傑作品種マスカットベリーAは、戦前から数多くの葡萄農家に恩恵をもたらしただけでなく、是非はともかく日本のワイン史において赤ワインというジャンルを支え続けてきた品種といっても過言ではありません。日本全国ほとんどの葡萄栽培地域でマスカットベリーAは栽培され続けている一事をとってもこの品種がいかに栽培適性が高い品種であったのかはわかります。
このベリーAについてはかの麻井宇介(浅井昭吾)氏は、”浅井昭吾のワイン余話”で『彼(注:川上善兵衛)が交配によって穫得しようとした特性は、ワインに与えるポテンシャルではなく、ブドウそれ自体の強健さと豊産性だったのですから。「マスカット・ベリーA」はまさにそのねらい通りのブドウとして、一時期、脚光を浴びたのです。』と醸造・生食兼用品種としてのベリーAの隆盛の理由と特性を鋭く見抜いています。
その”ワインに与えるポテンシャルではなく、栽培適性を重視”と評された葡萄から、国際級のワインを造るべく心血を注いでいるのが岩の原葡萄園なのです。
まず、赤ワインはコストパフォーマンスに優れたものが多いということが挙げられます。川上品種でも特にベリーAへのこだわりは尋常ではなく、全ての赤ワインがベリーAを主体としたワインです。味わいも「え、どこにベリーA入ってるの?」というものはなく、低価格のワインといえど、しっかりと重みのある果実香が感じ取れるのはさすが。とくに最高級ワインとなる「善兵衛」を飲むとベリーAでここまでのレベルにいくのかと認識を新たにするので、ワイナリーに行ったなら有料でも試飲してみるべきです。またこれほど高いワインを飲まなくても2100円の深雪花の赤を飲めば、高い志を持って挑んでいるだけのことはあると思い知らされます。
ただ白ワインは、赤と比べると、どうも相対的にインパクトに欠けるという印象が否めません。ナイアガラを使用したワインもそうですが、岩の原の白ワインは香りがおとなしく、また味わいもそこまで厚みがあるわけではないので、テイスティング程度に飲むとどうしても評価が低くなりがちです(白全般への評価は赤が良いだけになおさら気になる、という部分もあります)。
ちなみに、こうしたワインの原料たる川上善兵衛が心血を注ぎ込み作り上げた20種類以上の川上品種ですが現在は、マスカットベリーA、ブラッククイーン、ベリーアリカントAのほかはわずかにローズシオター、レッドミルレンニューム(琵琶湖ワインで栽培)が残るのみで多くの品種は栽培されていない、といっても過言ではありません。最も川上品種で成功したマスカットベリーAも、新たな高級生食用品種や栽培面積の減少により、生産量は減っており、今後も増えることはないでしょう。
善兵衛や川上英夫の苦労を考えると物悲しい気分にもなりますが、最近、岩の原葡萄園以外でもマスカットベリーAやブラッククイーンにワイン用葡萄として真剣に取り組むワイナリーが現れてその可能性を引き出そうとしているのは朗報です。
話が横にそれましたが、純粋にワイナリーとしての岩の原葡萄園は、前述のように理屈ぬきにしっかりしたワインを造っているのでおいしいワインが飲みたいという動機で行っても損はしません。マスカットベリーAに限れば、日本最高峰のワインを醸造している会社の一つということは断言できますし、正直あまり日照に恵まれていない畑から、よくこれだけのワインが造れると驚かされます。
ワインの品質以外でも見るべき場所も多く、レストランも内容は充分、販売所も清潔感があり独自のお土産も多いなど、観光で行っても充分に楽しめるワイナリーなので上越市に行く予定があるなら、訪れるのをおすすめします。
そして言わずもがなですが、このページを見ているような方は「訪れる必要がある」と断言できます。
新潟の豪雪地域で品種改良とワインに生涯を捧げた男、「日本ワインの父」川上善兵衛。彼の育て上げた葡萄と醸造所がいかに受け継がれ、現在の人々の努力で発展したのか。それを知ることは日本ワインを知るうえで少なくない意味があるはずです。
| 社名 |
(株) 岩の原葡萄園 |
| 住所 |
新潟県上越市大字北方1223 |
電話番号 |
025-528-4002 |
| 取寄せ |
オンラインショッピングあり |
HP |
http://www.iwanohara.sgn.ne.jp/ |
| 畑 |
自社畑あり |
ツアー等 |
訪問自由
テイスティング可(有料、無料) |
| 栽培品種 |
マスカットベリーA、ブラッククイーン、カベルネ・フラン、シャルドネ、ローズシオター、他 |
営業日 |
営業時間:9:00〜17:00
営業日:1〜3月は土日祝日休業 |
| ★ 2005年6月25日 |
備考:川上善兵衛が設立、国産葡萄のみ使用、親会社『サントリー』、歴史記念館「紫水ふれあいの郷」併設
直営レストラン「ラ・カーブ」あり(定休日 毎月第三火曜日) |
写真だと少しわかりにくいのですが、かなり高くまた
密植の棚栽培です。海外の棚栽培に近いかも。
試飲・販売所。オリジナルのお土産ものがかなり充実
しているのもここの特徴の一つです。