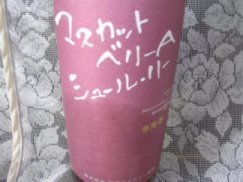島根ワイナリー
〜万年赤字工場、ドル箱となる〜
外観
出雲といえば、なんといっても思い浮かぶのは出雲大社。その出雲大社の近くに立つ巨大な建物が、営業でもっとも成功している第三セクターのワイナリーといわれる島根ワイナリーです。
あたりは葡萄園と田んぼと山々という緑深い中でひときわ目立つ、赤いレンガと白い壁の棟が目印です。
近づくと、平日・休日に関係なく、駐車場から大小の観光バスが、次々と出入りする光景を目にします。
あたりは農地だらけなのに、ここだけが別の世界、といってもよいこのワイナリー。しかし、このワイナリーがここまで来るのには、非常に険しい道のりがあったこともまた事実です。
歴史
島根県の葡萄栽培の歴史は意外に古く、慶応(江戸末期から、明治中期)に甲州の栽培が記録されたのがその始まりといわれます。大正時代から甲州よりも耐病性に優れ早熟のデラウェアに改植されていき、養蚕業の衰退もあって急速にその栽培面積を広げていきました。1960年頃にはジベレリン処理(種無し葡萄の生産に必要)、ビニール栽培の拡大が伴って早生による高付加価値の葡萄栽培を主力とする形態となります。こうして現在も島根では4月〜8月まで延々とデラウェアが収穫・販売され続けるようになりました。しかし、早生を狙ってのボイラーによる加温栽培は葡萄樹本体の寿命を縮めるばかりか、通常ではあまり罹患しないような病気にかかるという欠点も持ち合わせており、担い手不足も相まって島根での葡萄栽培は1985年をピークに下降線を辿っています。
島根ワイナリーはそんな栽培の歴史をもつ島根県の農協が母体となったワイナリーです。公式ホームページにもその歴史の概略について書かれています。ここでは私なりにその歴史を書いてみます。
戦後、前述のように島根県ではデラウェアを中心とした葡萄産業が栄えていましたが、産業規模が大きくなるほどに余剰生産物や病果が多くなっていきました。こうした葡萄を加工品として利用するためにサントリーの技術協力を得て1957年に島根県中央事業農業共同組合連合会により加工用工場が設立されたのがその起こりとなります。しかし、当時の生産施設は時代水準からみても貧弱なうえに、原料となるデラウェアがワイン醸造用に栽培されたものどころか、生食葡萄の余りと裂果や病気に侵された農業廃棄物だったため、ワインは控えめにいって粗悪品でした。1960年に共和発酵の技術協力を受け、1962年に「有限会社島根ぶどう醸造」と社名を改めて工場や施設を刷新したものの、農業廃棄物の最終処理場という状態は変わらず、ワインは売れ残り、在庫と赤字だけが増えていきました。
1974年、JA島根経済連に(現在はJA全農と合併しJA全農島根県本部に)その経営権が移っても経営は好転せず、増資もできない施設は老朽化の一途を辿りました。そして累積赤字が1億円を突破したところで、当然の帰結として経済連からこの不採算事業を廃止するべきであるという提案がなされ、工場は存亡の危機に立たされます。
ところがこれを聞いた地元生産農家が工場の復興に立ち上がりました。万年赤字工場ではあったものの農家にとっては30年もの間続いた貴重な葡萄の加工場であることにかわりはなく、さらにワインも以前より品質は向上し売上げも徐々に伸びていたのです。こうした農家とともに、今度はきちんと黒字経営ができるワイナリーにするにはどうすればいいのか熟慮に熟慮に重ねられ、そのための資金も調達されました。
1986年、社名を「島根ワイナリー」と改名し現在の場所にワイナリーを新設すると、汚名返上の快進撃が始ります。観光客を重視した施設には入場者が激増、1998年にははやくものべ入場者数が1000万人を突破。以降も年間100万人ペースでの来訪者がある一大観光施設へと変貌しました。年間売上高も凄まじく約25億円と、数あるワイナリーでも抜きん出た数値を誇ります。この売上げのうち3分の2はレストランやお土産の販売によるものであるところにも、島根ワイナリーの特色がでているといえるでしょう。
総生産本数は150万本とやはりかなりの量。マストや輸入ワインの使用については、島根ワイナリーの社員の方はないと言っていましたが、甘味果実酒などに使用しているのかどうかが不明なので詳しくは言及いたしません。
ワインのかなりの数はワイナリー以外の酒屋やお土産屋で売られており、地場産業として確かな地位を確立しています。販売している商品の中には甘味果実酒が少なくないのも特徴の一つです。
莫大な入場者を支えるよう、駐車場からありとあらゆる施設が収容人数が大きく作られており、現在の場所にワイナリーを設立した時の先見の明が光っています。その苦闘の歴史をみるとよくこれだけの施設を造る資金を集めることができたものだと、純粋に感心させられます。
営業的にもっとも成功したワイナリー、と評される島根ワイナリーは、今なお数多くの人が訪れる人気ワイナリーとしてその存在を知らしめています。
施設の概略
第三セクターのワイナリーのなかで、入場者向け設備の規模で、ここに敵うワイナリーは存在しないでしょう。広大な敷地にあますところなくいろいろな建築物が建てられ、中には歴史館や展示場など、かなり贅沢な使われ方をしているものまで。敷地内のあちこちにはベンチ、中央には噴水まで建造しているという景観設備の充実ぶりには目を見張らされます。
敷地に入れば見学順路があり、醸造設備はガラス越しに見学可能。ステンレスタンク、樽、ホーロータンクなど新旧様々な貯蔵・醸造器具があるので、このワイナリーの歴史の一端を垣間見ることができます。やはり生産量が多いだけあってかなり大型の醸造施設です。
ギャラリー・歴史館:同じ建物内にありその時々に応じて、色々な使われ方をしているエリアです。歴史館では、島根ワインの歴史がパネルで紹介されています。ギャラリーは広い意味で公の使われ方をする場所で、様々な団体のために絵画の展覧会や情報の発信の場として提供されています。展示内容はワイナリーの業務とは必ずしも関係しておらず、いい意味で第三セクターらしい設備です。
コーヒーハウス シャルドネ:白ワイン用葡萄品種の名を付けたも喫茶店。外側にテラスもあるので、晴れた日には日光にあたりながらのんびりくつろげます。
バーベキューハウス弥山:500席もあるバーベキューハウス。昼食を取るならばこちらのほうが向いているでしょう。最近はしゃぶしゃぶも始めています。
試飲販売所バッカス:試飲販売所・・・なのですが、普通のワイナリーの試飲販売所とはあらゆる意味において違いすぎるので唖然とさせられました。まず、広さが異常です。フロアを歩き回るだけでも相当な距離になります。
試飲についてはテイスティングの項で詳細は記載しますが、ひとことでいうならば「圧巻!」でした。
販売所ではこれ以上は集められないだろうというほどに島根県のさまざまなお土産がつまれ、ショーウィンドウもあるなどさながらデパートの地下食品売り場のよう。多くの中高年の団体客や、観光客で賑いその活気には圧倒されます。さらにこの喧騒を盛り上げてくれるのは、ワインやお土産がダース単位でフロアを行き交い、ダンボール箱が次々と発送されるか、バスに積み込まれていく光景。
ワイナリーの見た目もそうですが、中身ものどかな田舎の田園風景とは程遠い別世界が繰り広げられています。
加えて島根全体の観光案内もあるなど、観光施設としては完璧。
施設に関しては内容を概略だけ書くとオーソドックスですが、規模が大きくて普通の観光客重視のワイナリーとは比較になりません。
カルチャーショックを受けました(^_^)。

葡萄畑
ワイナリーの敷地に自社畑や、すぐ近くに契約栽培の畑があります。栽培品種はカベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、セミヨン、マスカット・ベリーAなど。ワイナリー周辺は海抜が低い平地で田んぼまであるので水はけは素人目にも問題があるように思えますが、あまり遮蔽物はないので日当たりは良好そう。もちろん、山側にも契約農家はあるようです。
自社畑ではかなりの数の苗木の育成が行われ、島根の土壌に適合する品種やクローンを研究しています。ここで良好な結果が得られた苗木が、契約栽培の農家に配られています。
また、少なくない面積で甲州葡萄も栽培されており、デラウェアと並ぶ島根ワイナリーの重要な品種となっています。
歴史の項でも説明したように、島根県の葡萄畑で目に付くのは平地で栽培されていることと、ボイラーなどの温熱装置付きビニールハウス栽培による畑が多いこと。山梨県・長野県など主要産地ではほとんど目にしない光景で、デラウェアの早生栽培などが主眼に置かれていることがわかります。
テイスティング
販売所バッカスに入ればすぐに試飲できる場所はわかります。
さて試飲をするかと試飲カップを手に取ると、大きいような・・・いや、明らかに大きすぎるサイズです。よくある小さい試飲カップの5倍は容積があります。
なぜこんな大カップなのかは、試飲所に置かれたワインをみればたちまちわかります。
左写真のように、周りに氷の張られたガラスのボールになみなみとワインが注がれ、これまた50mlはまとめてすくえる”おたま”のようなスプーンが添えられています。
周りを見ると、だいたいのお客さんは赤い顔をして上機嫌ですが、当たり前。試飲カップに遠慮せずにワインを注いで全銘柄飲んだら間違いなく酔っ払います。ある醸造家が「島根ワイナリーは、飲み屋だ」と表現したのもむべなるかなです。
ワインが少なくなると、これまた職員が一升瓶でどんどん補充していくのですから飲む方も補充する方も豪快!
お客の回転率がよくなければとてもできない荒業で、ワインの回転率がいいのと甘口ワインや甘味果実酒が多いこともあって、これだけ空気に接触している試飲方式といえど酸化のニュアンスのあるワインにはあたりませんでした。
ワインのサイズと比較すると、ワインの入ったガラスのボールが大きいことがわかります。
購入方法
ホームページからの注文を受け付けています。また島根県なら、あちこちで見かけます。ただし、有料試飲コーナーでしか飲めないワインに関してはワイナリーに直接問い合わせたほうがよいでしょう。
ワイナリーアクセス
アクセスに関しては公式ホームページを御参照下さい。
総論
悪戦苦闘の歴史を歩みながらも、それを微塵も感じさせない施設の充実と、圧倒的な集客力は他社の追随を許しません。観光客が求める要望をほぼ完璧に満たす、その運営手腕はさすがの一言。お隣の広島三次ワイナリーと似ていますが、島根の方が先輩なのでむしろ三次ワイナリーのほうがこちらを参孝にしているといえるでしょう。また、規模と集客力においても島根の方が圧倒的に上です。
お土産の販売には、そんじょそこらのドライブインなど相手ではないほどにスペース・人員が割かれており、しかもそれだけの労力が必要なのが納得できるほどに商品が回転していく光景には二の句がつげません。お土産の売り上げだけでかなり凄まじい金額になっているのは明らかです。ただ、ここまで一つの施設が売上げを伸ばしてしまうと、周囲のお土産売り場を圧迫しているのではないかとも推測されます。また、お土産を買って近所に配るといった慣習(といっていいのかわかりませんが)は、日本では世代を経るに従って少なくなっていることを考えると、同じ形・規模での経営があと10年以上続くかはやはり疑問です。
ワインの品質は私見ですが、まだ海外ワインを飲みなれた人をコストパフォーマンスで納得させえるものはない、と考えています。しかしながら、甘味果実酒などに隠れがちなカベルネ・ソーヴィニヨンなどを飲むと、本格ワインを指向する島根ワイナリーのもう一つの顔が見えてきます。わざわざヨーロッパ品種の苗木を育てて栽培していることは時代に合わせるという側面もあるのでしょうが、テーブルワインとしてのワインを目指しはじめていることの確かな証です。こういった部分をみると単純に「お土産用ワインだらけ」とはいえません。
その「お土産用ワイン」のほうも、主なターゲットである中高年層を意識し、ワインでなく特徴がよりわかりやすい甘味果実酒を生産するといった売り方などは「消費者が一番望むものを造る」という点からみれば非難されるべきものではありません。甘味をはっきりと感じさせる造りにしながらも、全体を軽く飲みやすくまとめているところをみると、お客をよく理解してものづくりを行っており、そこにはワイナリーの人間ならずとも見習うべき点が多く含まれているように思います。
・・・とまあ、自分でもかなり褒めちぎって書いているなあと思いますが、私が飲んだワインの中には迷惑料を請求したくなるようなワインがあったのは事実ですし、やっぱり個人的には買い続けたいと思うワインには出会えませんでしたが。
訪れる側からみるとこのワイナリーはなんといっても出雲大社がとても近いというのが最大にして(そしてほとんど唯一の)立地におけるメリットです。自転車で旅を続けた我々でも、確かに近いと思えたのですから車では問題にもならない距離です。
また、テイスティングの項でも書いたようにこれほど無遠慮にただでワインが飲みまくれるワイナリーはここしかありませんから、それを狙っていくというのもありかと思います(せめて一本は買って帰るべきですが)。また、お土産をどこかで買おうと考えている人なら、お土産の総合デパートのようなワイナリーなので行けばまず希望する島根県のお土産が見つかるのも利点です。
総論としては日本ワインファンはもちろん普段ワインを飲まない人でも、島根に行ったなら寄りたいところ。ワイナリーが目的にしろ、出雲大社が目的にしろ、どちらか一方に行くならばもう片方も必ずいきましょう。
| 銘柄: |
マスカットベリーA シュール=リー |
| 生産元: |
島根ワイナリー |
| 価格: |
1345円 |
| 使用品種: |
マスカット・ベリーA |
| 備考 |
あまり聞かない、シュール=リーを謳った赤ワインです。
色は暗い赤色で色素がよく抽出されており、ベリーAのワインとは見ただけでは思えません。香りは大根、ナフタリン、ロウソク、わずかですがイチゴも。
ワインの涙が複雑なので想像はしていましたが、エキス分が濃く口に含むとねっとりとした飲み口を感じます。アタックはやわらか、複雑味はまずまずで荒いながらもミディアムボディを名乗るのも納得の収斂味もあり、ライトなタイプのベリーAのワインとはまったく異なるワインであることを感じます。
アフターには、フランボワーズと新樽のような香りが少しありますが、樽につけているのではなくこれはシュール=リーによくあるアミノ酸の香りかもしれません。全体にソフトですが「飲んだ」という感覚が長く口中に残ります。
総合的に見てかなりパワフルなベリーAのワイン。醤油が強めの料理が向いているように思います。島根ワイナリーにいったら少なくとも有料試飲はしてみてほしい銘柄です。 |
| 飲んだ日: |
2005年3月2日 |
敷地内のビニールハウスで苗木の育成が行われています。意外かもしれませんが苗木の育成は他のワイナリーまず見られない光景です。
以下はテイスティングのコメントです。
島根わいん 白:840円。「わいん」といっていますが、甘味果実酒の表記があります。かなり甘口で推測ですがデラウェアがけっこう入っていると思わせる狐臭と味わいがあります。
島根わいん 赤:840円。同じく甘味果実酒。わりとシンプルですっきりした味わいの甘口。アルコール入りジュースという印象を受け、有名な赤玉スイートワインとは異なるタイプのワインになります。
葡萄神話 白:1030円。島根県産の甲州を主体とした中口ワイン。香りはあまり明瞭ではありませんが、クリーンな味わいです。ただ、クリーンすぎて個性に欠け、コメントしにくいワイン(^^)
葡萄神話 ロゼ :1030円。ベリーAを主体としたやや甘口ロゼワイン。明瞭なイチゴの香り、ややタンニンはあるものの含み香にとぼしくあまり個性がでていない味わいです。
葡萄神話 赤:1030円。ベリーAの赤ワインで中口〜やや辛口程度に糖分を残しています。色はよくでており、ガーネットのよう。香りにはイチゴ香があり、ベリーAのワインとしてはかなりタニック。含み香には果実香といっしょに軽いゴムのような香りもあります。個人的には好きな銘柄で、ベリーAのワインとしてはなかなかよいものではないかと思います。
他、山梨・長野以外では珍しい一升瓶ワインも販売されているのは意外でした。
以上は無料でしたが、これとは別に有料試飲もあります。
この有料試飲のカウンターはどこにも人ごみができる島根ワイナリーの安息の場ともいうべき場所で、ここだけは人が寄り付いていません。それどころか職員までいない、まさに無人地帯。仕方なく、近くで忙しげに働いていた職員に声をかけて有料試飲をしました。こちらはきちんとしたテイスティンググラスです。
甲州シュール・リー :1365円。島根県産甲州によるシュール・リー製法のワイン。そば殻のような香りで、ほとんど果実香がありません。味わいは辛口で酸味は強く、さらに苦味も強い印象を受けました。シュール・リーとしては味の厚みに乏しく、含み香には樽のようなスモーキーな香りがでているのに特徴があります。
マスカット・ベリーA シュール・リー:1365円。管理人のワイン記録を参照してください。このワインを含め、島根のベリーAは発色がよく、味わいも果実のフルーティーさがあるものが多いように思います。
セミヨン:3065円。シャルドネでなく、セミヨンというところが変わっている島根県産葡萄のみによるワインです。香りはフロールのような酸化熟成した香り。酸味はあまりないですが苦味がやや強く、含み香には朽木のような香りがあります。色が少し茶色が混じった黄色だったので、酸化していたのかもしれません。少なくとも私が飲んだワインは有料試飲どころか無料試飲でも遠慮したい味わいでした。
カベルネ・ソーヴィニヨン:3065円。島根県産カベルネのみによるワインです。樽香とカシス、ゴムのような香り。あまりタンニンもなく、ライトですっきりとした味わいの赤ワインで、やや薄く複雑味にはかけるので気軽に飲みたい味わい。
残念ながら気軽な値段ではありませんが。
銘柄比率でいくと低価格帯は甘口〜中口ワインのみで構成されています。また、島根県の葡萄栽培でもっとも重要な品種であるデラウェアの原料比率がかなり高い印象を受けます。
辛口ワインの銘柄の品質は、私個人は残念ながら満足いくものが少なかったように思います。やはり薄めで単純な味わいなものが多い、または白でも苦味が少し強い気がします。その中では個人的におすすめはベリーAを使用したワインで、全体に旨味が多くバランスも悪くありません。
主力たる低価格ワインは、辛口しか飲まない、ヨーロッパ品種以外はNO、といった人には容認しがたい内容ですが、飲みやすくすっきり造ってあり、購買層であるワインをあまり飲まない中高年の方々向けに、そつなく造ってあります。デラウェアなどはまずまず果実のフルーティーさもあり、ラブレスカの甘口ワインに抵抗がない私などは、これはこれでいいかなとも思います。
平日でもこの混雑。特に試飲(というには量が飲め過ぎる気がしますが)のエリアは人の山です。
| 社名 |
(株)島根ワイナリー |
| 住所 |
島根県簸川郡大社町大字菱根264番地2
|
電話番号 |
0853-53-5577 |
| 取寄せ |
オンラインショッピングあり |
HP |
http://www.shimane-winery.co.jp/ |
| 畑 |
自社畑あり 契約栽培畑あり |
ツアー等 |
見学自由
テイスティング可(無料・有料) |
| 栽培品種 |
マスカットベリーA、甲州、セミヨン、デラウェア、
カベルネ・ソーヴィニヨン、他 |
営業日 |
12月29〜.31日のみ休業
営業時間:9:30〜18:00
(5月〜10月) 9:30〜17:30 |
| ★ 2004年6月4日 |
| 備考:第三セクター、直営バーベキューハウス「シャトー弥山」あり、直営喫茶店「シャルドネ」あり |
ワイナリー近くのとある農家。画像中央に大きなボイラーがありますが、これを使った暖気による早生栽培が島根の主流です。