「原発事故、避難計画はたてられるか」
―東海村での講演会に参加
県議会では東海第二発電所のシビアアクシデント(過酷事故)を想定して避難計画を策定中ですが多くの課題を抱え困難に直面しています。このような中、本日15日、東海村で「原発事故、避難計画は立てられるか」という講演会がありました。県議会で傍聴に来ていました原発被害対策などの活動を行っているグループからご案内があり参加してきました。委員会での質問と県の答弁をお知らせし、事故時現地の最前線の声をお聞きしてきました。会場にいました村上前村長からも県議会での質問にアドバイスと激励をいただきました。参加者の強い眼差しを受け一層引き締めて原発の安全対策、防災対策に対処していきます。 (写真:村上達也前村長と)

消費税増税分はどこへ?
今、各地方議会では平成26年度の予算審議の最中です。県議会は休会でしたので議会報告でお伺いしていました。やはり消費税のことが話題に上ります。茨城県では増税分は約66億円です。これは全て医療・介護・少子化対策など福祉の充実にあてられます。消費税増税は賛否両論がある中で決まりましたがその使い道は福祉目的に限るとされていたことによります。
この点を地方議員の方々に報告したところ執行部から増税分の使途は聞いていないという議会がいくつかありました。知り合いの議員に問い合わせたところはっきり福祉に充当したというところと全く説明がされなかったところとまちまちでした。使い道の通知は総務大臣から県知事に知らされています。県内の市町村には県知事が周知するということになっています。この点について経過を明らかにするように求めていきます。
住民は消費税増税にあたって福祉に使うということで了解したわけです。各議会ではこれに明確に答えられなければなりません。
特定秘密保護法で自民党強行採決、
暴走ストップを!
昨年末の総選挙での自民党圧勝を受けて、2013年も政治の流れは変わりませんでした。東京都議会議員選挙では自民党公認の59人が全員当選、夏の参院選でも自民党が勝ち国会では安定多数となりました。現状では野党が束になってもかないません。
そこで出てきたのが特定秘密保護法案です。これは総選挙、参院選いずれの国政選挙でも自民党は公約としていませんでした。何をもって「特定秘密」とするのかですが、政府の一部で決めてこれをチェックする中立機関がありません。秘密とする要件の一つである「公共の安全と秩序のため」は国民生活全般に関わることが含まれるため、ときの政府が国民に知らせたくない情報をこれに該当するものと解釈すれば、ことごとく「特別秘密」に指定されてしまう懸念があります。
政府は、緊急性があると抗弁していますがそうであれば7月の参院選で公約として訴えるべきではなかったでしょうか。秋の官邸を取り巻く反対デモや報道を見ると自民党で大丈夫なのか、という不安の声が高まってきていると思います。
多くの国民が反対の声を挙げていましたが国会では強行採決されました。自民党の暴走はストップさせなければならないと思います。民主党は消費税を上げない、という公約を破って政権を失いました。自民党は公約にもない重要法案を強行しました。行きつく先は同じではないでしょうか?
特定秘密保護法と酷似する暴排条例
特定秘密法によく似た条例が茨城県にあります。それは暴力団排除条例です。名称から、警察が暴力団を排除し地域の安全を守ってくれるものと思っている方も多いのではないでしょうか。しかしこの条例は反対で、住民が暴力団を排除するために行動することを警察が支援するというものです。わたしは逆さまになっているのではないかと県議会で疑問を呈しました。
近隣の守谷市で2012年秋に暴力団が施設を建設しました。だれしも隣に暴力団が住んでいては気持ちのいいものではなく、不安がよぎるものです。出来るものなら移ってほしいというのが住民感情です。しかし、警察は法的には撤去できないという判断でした。警察は出来ないので「住民に自発的に撤去のため立ち上がってほしい」、そのためには応援するというのが警察の態度です。
「暴力団対策は警察が前面に出るべきだ」県議会で議論
法や警察ではできないことを住民がやるわけですから困難は明らかです。立ち退きの訴訟に持ち込んでも長期間かかることが想定されます。その間も住民は不安の中にいます。暴力団による使用が確認されていることから、県議会では建物の使用法について住民に危険を及ぼさないように警察が警告、指導、立入検査など適宜行い、使用を限定するなど少しでも住民が危惧を抱かないようにするためにも規制していくべきではないか、と質しました。しかし警察本部長は「排除対象者とは話し合わない」という硬直的な答弁でした。わたしは警察が前面に出て危険性の除去に取り組むべきだと主張しました。
法や条例でいう暴力団とは世間一般で言われている「ヤクザ」ではありません。集団的常習的に暴力行為を行うことを助長する恐れのある団体をいいます。そして暴力団の認定は警察のみが行い、だれが暴力団とされたかは本人にも知らされないというのが県議会の質問でわかりました。
実際に不法なことを行っていなくても警察が暴力団と認定すれば暴力団となってしまいます。さすがに今のところこのような執行はしていませんが、法や条例からは可能です。
警察のみが情報をもち、警察の裁量で暴力団と決めて取り締まりやすくする、そしてこれをチェックする機関もないということは特定秘密保護法とそっくりです。
低下する検挙率―県警の能力向上を追求
暴力団排除条例によって警察は大きな権限を得たことになります。警察の肥大化は予算の肥大化につながります。県では、行政部門は行政改革により人員を毎年削減していますが警察だけは増え続けています。条例が具体的にどのように適用されていくのか、暴力団を取り締まるものと思っていたことが、(特定秘密保護法のようにスパイ対策と思っていたことが)逆に市民生活が規制されるようなことにならないようにチェックしていきます。
一方、刑法犯の検挙率が落ちています。平成20年から比較すると6ポイントも減少しています。警察官は増えていても検挙率が低下しているのは警察の能力、捜査技法などにも問題があるといえます。私は3年前の県議選で「県も無駄な事業を止めさせ県民の生活向上にとりくみます」と訴えてきました。警察とはいえ例外ではありません。残り一年ですが、警察には税金を効率的に使い、住民の真の生活安全がはかられるようチェックし地域の要望を伝えていきます。
以上
盲ろう者通訳介助員派遣事業について
盲ろう者通訳介助員派遣事業について今開かれている決算特別委員会で質疑しました。以下議論の抜粋です。議事録は配布され次第掲載します。
平成25年 決算特別委員会での質疑抜粋 (25.11.14)
質問者 細谷 典男 委員
答弁者 茨城県障害福祉課長
Q1 盲ろう者及び通訳・介助員派遣事業の現状について
先日,私は盲ろう者の社会参加を支援されている方とお話しする機会がありました。
盲ろう者とは,目と耳の両方に障害を併せもつ方のことを言います。盲ろう者の方々は,「光」と「音」の双方が失われた状態で生活しているため,独力でコミュニケーションや情報の入手,移動ができないといったように,極めて困難な状態に置かれています。
しかし多くの盲ろう者の方々は,社会の中で精一杯力を発揮したいと望み,地域社会の一員として住民と交流し,生きている実感のある人生を送りたいと願っている、ということでございました。
このような盲ろう者の方々にとって,県が実施している「盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業」は,必要不可欠な事業であり,入院・退院や公的機関への移動など自立と社会参加を成し遂げるうえで,無くてはならない必須の支援であります。
そこで,先ず,県内には盲ろう者の方々がどの位おられて,通訳・介助員派遣事業の支援をどの程度受けておられるのか,現状をお聞きいたします。
A.答弁
委員ご指摘のとおり,盲ろう者の皆様方は,目と耳という人間の主要な二つの感覚機能に障害を併せ持つため,情報入手,コミュニケーション,移動など生活の様々な場面で困難が生じ,大変厳しい生活を強いられているものと認識しております。
ご質問へのお答えでございますが,先ず,本県の盲ろう者の人数でございますが,昨年度,視覚と聴覚の両方の身体障害者手帳を重複して所持されている方の実態調査を実施したところ,県全体で159名いらっしゃることが分かりました。
一方,通訳・介助員派遣事業の利用登録をしている盲ろう者の方でございますが,現在9名となっております。
なお,平成24年度の派遣事業の執行状況でございますが,110万9500円で,盲ろう者一人あたりの平均利用時間は年間約95時間程度となっております。
Q2.159人について
盲ろう者というのは、主に4つのタイプに分かれます。①全盲ろう・・・全く見えなくて、全く聞こえない、②弱視ろう・・・見えにくく、全く聞こえない、③全盲難聴・・・全く見えなくて、聞こえにくい、④弱視難聴・・・見えにくく、聞こえにくい
両方手帳を所持していないケースがあり実際はもっと多いのではないか、この支援事業を求めている人たちはもっといるのではないかとおもうがどうか
A.答弁
実際には,手帳交付対象とならない弱視や軽度難聴の方や,視覚と聴覚の両方に障害があっても両方の手帳を取得されていない方もいらっしゃると思いますので,人数は多くなるのではないかと考えております。
Q3. 利用時間の平均が95時間について
通訳介助者の移動時間はどのようにカウントされているのか。利用者にとって通訳介助の支援を受けた実際の時間が95時間という理解でよろしいか
A.答弁
95時間という時間数には,通訳介助者の移動時間も含まれておりますので,実際の通訳介助を受けた時間は,95時間よりも短い時間となります。
Q4. 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業の拡充について
ただ今お聞きした年間約95時間という派遣時間でございますが,実際利用する時間は何割か割り引かれます。私の印象としては,十分な時間ではないのではないかと思います。
一年間に約95時間以下しか外出や他の方々と交流ができないということは,ほとんどの時間を家の中で孤独に過ごさざるを得ないということであり,長く引きこもることで認知症にもなりかねないと言われております。
通訳・介助員派遣事業は,盲ろう者が生きていくうえで無くてはならないものであり,自立と社会参加を促進するために大幅な事業の拡充が必要ではないかと考えますが,いかがでしょうか。
A.答弁
今年度の盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業の予算でございますが,約18万円ほど増額し,129万円弱の予算措置をしております。
しかしながら,盲ろう者の当事者団体でございます「盲ろう者友の会」の方々からは,派遣事業の拡充等につきまして,大変強くご要望をいただいているところでございます。
また,先ほど県内の利用登録者は9名と申し上げましたが,調査では159名ありますので,実際にはもう少し多くの方がこの事業を必要としているのではないかとも推測しておりまして,リーフレットや市町村広報誌等の活用により更に周知を図ることで,利用登録者の増加も見込まれるのではないかと考えております。
今後,近県の実施状況や利用登録者の方々がどれくらいいて,それくらい派遣時間を希望しているのかなどを十分にお聞きしたうえで,なるべく盲ろう者の皆様のご要望に応えられるよう,通訳・介助員派遣事業の拡充につきまして努力してまいります。
Q5. 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業の拡充(要望)
盲ろう者と一口に言いましても,その障害の状態や程度は様々であり,盲ろうになるまでの経緯も一人一人違います。このため,通訳・介助の方法も一人一人のご希望に応じた支援が必要であります。通訳の手法も「音声」「要約筆記」「接近手話」「指点字」など個々の状況に合わせて行う必要があり、通訳者の養成も重要です。
この支援を求めている人々を掘り起こすということも必要です。全国盲ろう者協会の平成24年3月末の資料によると、茨城県には約500人の盲ろう者がいると言われています。両方の手帳保持者が159人ということでしたが、手帳交付まで至らない全盲でも難聴、耳は全く聞こえないが弱視、このような人々を掘り起し通訳介助の支援があることを知らせるのには、いま答弁いただきました周知と共に一層の対策が必要ではないかと思います。
茨城県では本年度は増額されたということですが関東各県と比較しても本県の予算措置は極めて乏しいといわざるを得ません。
県においては,来年度,通訳・介助員派遣事業の大幅な予算の拡充をしていただきますようお願いいたしますとともに,実際の派遣事業においては,利用者にとって使いやすいきめ細やかな対応をしていただくことを要望しまして,質問を終了いたします。
(11月14日記)
東海第二原発の行方、知事待ちの姿勢変わらず。ー県議会各派代表質問から
県議会開会中。昨日と本日は各派代表質問です。知事選直後の定例会とあって、まず6期目の県政運営を質すものからはじまっています。原発については相変わらず国の方針を受けて判断するという待ちの姿勢です。知事の言う減原発は脱原発への過程なのか、それとも容認なのか、本質に迫る議論がありません。東海第二原発は35年の運用で老朽化、UPZには96万人、非難など不可能で県庁も含まれます。廃炉以外にありません。日本で最初に原子の火をともしたのが茨城です。いまこそ茨城が原子の火を消さなければなりません。12月の定例県議会では質問することになっています。知事に「東海第2原発の廃炉」について態度を明確にするよう求めていきます。
茨城県議会第3回定例会始まる!地方交付税を徹底解明
本日から県議会第3回定例会が始まりました。これから議会模様を報告していきます。今日は議論がありませんでしたので地方交付税についてお知らせします。地方交付税は国から自治体へ送られるお金で、親からの仕送りのようなものです。都道府県で不交付団体は東京都のみでした。つまり親からの仕送りなしでも自立できるというものでそれ以外は多かれ少なかれ国からの仕送り頼りの財政運営です。
茨城県の地方交付税は1638億円でした。予算では1600億円と見積もっていたので38億円多かったということになります。今回の地方交付税は変則的に決定しました。政府は地方公務員も国に倣って賃金を引き下げるべきだと主張し地方交付税の算定は賃金を引き下げたとみなして削減するといってきました。今年は総務企画委員会でしたのでこの点について追求しました。①影響額は110億円引き下げられるという見通しを県はたてました。②この収入落ち込みをカバーするために総額96億円の賃金削減を行いました。少し足りませんがやりくりして本年度予算が決定しました。しかしふたを開けてみたら38億円増です。98億円も減らさなくてもよかったということになります。なぜこのような見込み違いが出てきたのか。すべて政府の鶴の一声で決められているからです。
地方交付税が決定される前に県の担当者を集めて算定会議という説明会が行われます。このとき担当者(県)から賃金削減の根拠を質したところ政府(総務省)は人員の増減などがあり一概に言えない、という程度のものだったということです。これで説明できるものかとおもいます。地方交付税は現状により決定されるべきで将来の政策を誘導するようなことであってはなりません。茨城県がどのような認識で交付税決定を受け入れたのか、算定の根拠は何か、などを追及する予定です。なお県内市町村の不交付団体は神栖市と東海村だけでした。
茨城県、東電に二回目の損害賠償請求
本日、茨城県は東電に対して2回目の損害賠償請求を行いました。請求額は約3億3千6百万円です。主なものは下水道復旧費約1億8千万円、放射線測定・機器購入費約1千2百万円、苅草処分費約3千万円、県施設入場料減収約6百万円、茨城空港施設使用料減収約4百万円などを算出しています。一回目は約9億円請求していますが1億数千万円しか支払われていません。
支払わない東電に誠意がないのか、県の請求が課題なのか、精査していきたいと思います。
取手駅西口交番建設工事、2度も入札不調
取手駅西口は開発区域になっています。この区画に県有地があり県施設が置かれるようになりますが、茨城県警の警察施設再編整備計画により交番とすることになっています。今年度予算では建設費用が計上され10月には完成という運びでした。
入札公告・同説明書によると、工事名=取手警察署(仮称)取手駅西口交番建設工事(電子入札対象工事)、工事場所=取手駅北区画整理事業13街区1-1番地1-2画地(取手市白山1丁目甲291番1)、工期は平成25年9月19日限り、というものです。
工事概要は、2階建て、訪問者用駐車スペース、1階には防犯ボランティアのミーティングも行える部屋を配置するなど東口駅前交番とは格段の違いの施設となっている。場所は6号線と西口・四谷橋方面との交差点であり取手西部方面にも機動的に対応できる模様。
参加資格として、竜ヶ崎事務所管内など県南区域に限定し地元にも配慮したものでした。予定価格は、31,227,000円、一般競争入札で開札日は5月22日でした。
しかし競争参加資格確認資料提出や入札説明書の閲覧などもなく、開札日には1社の応札もなく不調となってしまいました。
不調となった要因など徹底した分析もなく再入札を行いました。5月28日に公告し、工期を10月15日限りと延長し開札日を6月14日としました。1回目の不調から6日後の公告であり万全の対応とは言い難いものです。
参加資格などで変更した点は、参加要件を県内全域に広げたこと、技術者の配置については一級建築士または一級建築施工管理技士であったものを主任技術者と緩めたことぐらいでした。予定価格、工事内容は不調となった前回と同様でした・
3社前後から参加確認資料提出があったものの6月14日当日、全社辞退しまたも不調となりました。
不調の報を知って市内の建設業協会加盟の事業者に事情を聴き調査しました。工事単価の問題もありますが、それよりも人員の配置が厳しいというように感じました。
今回の参加要件は、格付けがAまたはSというものでした。建設工事の現状は景気回復基調と建設会社のこの間の淘汰で人手不足が顕著になっています。格付けの上の方から仕事が入っていく状況を勘案すればBランクまで一定の品質保証の条件を設定して拡げていかなければ同じ繰り返しになるのではないかとの提言も受けました。地域では治安の強化は求められているところです。3度目の失敗は許されません。県警本部会計課では入札条件の練り直しに入っています。工期は数ヶ月伸びることは必至です。
総務企画委員会で退職金改革、取手駅前振興について議論
県議会第一回定例会が2月28日から3月22日にかけて行われました。所属する総務企画委員会は3月12日、13日と開かれました。出資法人の退職金改革や、取手アートプロジェクトの活動を地域振興の観点から取り上げ質疑しました。詳細は[議会報告の項]に議事録を掲載しました。ご参照いただければ幸いです。
以上
地域の課題を県政へ 二年間の県議会活動報告
県議会議員として活動はじめて2年を経過しました(2010年12月選挙、2011年1月初登庁、2011年3月初の県議会定例会)。任期は4年ですから折り返しとなります。これからもみなさまのご要望を受け止め、地域活性化と住みよいまちづくりを目指していきます。
県議会では年に4回、定例会が開催されます。この議会ごとに「細谷のりお県政報告会」を行っています。報告会を中心に2年間の主な取り組みと県議会活動をご報告します。今後もご意見ご指導いただきますようにお願いいたします。
第1回県政報告会
日時 2011年4月3日(日)午後2時~4時
場所 取手福祉会館2階D号室
内容 茨城県議会第一回定例会報告(2月28日~3月22日)、東日本大震災における茨城県の対応、他
県議会開催中の3月11日に大震災が発生しました。議会審議を中断し、災害対策にむけて緊急決議を採択して終了しました。この時から震災による被害からの復旧・復興と原発対策が最重要テーマとなりました。
所属する文教治安委員会では、①教員の業務の軽量化、②人権にかかわる暴力団排除条例の適用問題、など取り上げました。
第2回県政報告会
日時 2011年7月3日(日)午後2時~4時
場所 取手市福祉会館3階講座室C
内容 茨城県議会第2回定例会報告(6月6日~20日)、文教治安委員会では布川事件の無罪判決を受けて再び冤罪を引き起こさないよう茨城県警の捜査体制の検証をもとめました。
予算特別委員会(6月16日)での質問要旨
①県南地域における児童生徒の放射線被害対策
県南地域がホットスポットとなっていることへの認識と対策
②若草大橋有料道路と道路公社の経営状況
有料道路の管理・人件費が通行料を上回っていることから早期無料開放を求めました。
③地震被害が甚大であった取手競輪場の展望について
第3回県政報告会
日時 2011年10月30日(日)午後2時~4時
場所 取手福祉会館2階小ホール
内容 茨城県議会第3回定例会報告(9月6日~10月4日) その他
講演 「松下政経塾の活動」 県議会議員 大谷 明氏(ひたちなか市選出、無所属)
定例会の主な審議は国の茨城県の震災対策を中心とする一般会計補正予算案と平成22年度の決算でした。所属する文教治安委員会での質疑では新聞報道もされた「科学スタンプラリー」事業の廃止(読売新聞9月27日付)や交通事故における捜査体制などについて質問しました。
今回はゲストとして大谷明・県議会議員に参加していただきました。大谷議員は松下政経塾29期生です。松下政経塾はご承知の通り、野田総理をはじめ多くの政治家を輩出しています。塾の理念、政治への志など活動報告とともに講演していただきました。
第4回県政報告会
日時 2012年2月24日(金)午後2時~4時
場所 取手福祉会館2階D号室
内容 平成23年第4回定例会(12月2日~22日)、最終日に議会人事が行われ議長、副議長を新たに選出、常任委員会の変更もあり土木・企業常任委員会に所属することになりました。
予算特別委員会(12月15日)での質問要旨
①災害時における建設業協会とのさらなる協力体制の構築について
東日本大震災時の防災協力協定事業者の対応をどのように評価するか、
発注者との連携の必要、 茨城県としてもBCP導入企業とBCPによる災害時対応の協議を地域経済の維持、受注機会確保、歩切撤廃について
②災害時の県保有のシステム管理運用について
東日本大震災時の「統合型GIS」および「IBBN」について、この度の震災での運用状況は?
災害対策や、政策判断に役立つ「統合型GIS」については、どのように利活用を図っていくのか。
③人事委員会勧告について
今後の課題として勧告された高齢期の雇用問題について、労使で問題意識を共有し,制度設計に向けて課題を設定し,徹底した労使協議を先行して行うべき、国家公務員と県職員との給与比較,地域手当支給率は不合理 人事委員会が3パーセントとした見解を明らかに。
第5回県政報告会
日時 2012年4月21日(土)午後1時30分~3時30分
場所 細谷のりお事務所 (取手市取手2-7-3 イーストヒルス゛ユウキ)
内容 平成24年第1回定例会(2月27日~3月22日)、出資団体の改革、水道料金の課題
土木部所管の出資団体、建築技術公社の問題を取り上げます。また農業ビニールなどのリサイクルを行っている園芸いばらき振興協会も調査しています。県水道事業も担当です。3月末には養護学校スクールバス委託で低入札があり調査の対象となりました。これらを主に報告しました。
第6回県政報告会
日時 2012年7月21日(土)午前10時~12時
場所 取手福祉会館2階D号室
内容 平成24年第4回定例会(6月4日~15日)
一般質問(6月8日本会議 午後1時より)での発言要旨
①公契約における県の基本的態度
②出資法人改革(茨城県建設技術公社、園芸振興協会リサイクル事業)
③東北2県のがれき処理について
第7回県政報告会
日時 2012年10月28日(日)午後 1時30分~3時30分
場所 ゆうあいプラザ 3F会議室
内容 茨城県議会第3回定例会報告(9月7日~9月28日)、取手二高の改築について
土木企業委員会での議論(県営公園の管理費負担などについて)の報告、県営公園の維持管理問題を共有する笠間市議会報告を石松俊雄市議会議員から行っていただきました。
議会報告会は、同様の内容で相馬公民館でも一回行いました。また利根町では「県政を知り考える会」の要請により昨年5月、7月、10月と懇談会をおこない議会報告を行っています。県議会第8回定例会は12月4日から21日の日程で行われました。報告会は2月に予定しています。
県政についてご意見・ご要望お寄せください。報告会はご要請いただければ随時実施していきますのでお気軽にお問い合わせください。
活動報告は紙面の関係で要点のみとなっています。議会の発言・県政の課題など詳細な2年間の議会報告を作成いたしますのでご要望の方はご一報いただきますようにお願いいたします。
(2013.1記)
県立取手二高の改築、始動!
日本大震災の影響もあり茨城県立取手二高は壁は亀裂が入る等大規模な修理が求められていました。安全面も含めて早期の対策を求めていましたが、この度全面改築されることになりました。校舎の老朽化と耐震補強も総合的に勘案して改築ということになりました。
取手市内で校舎建て替えとなり、関係者の希望がふくらむと共に地元でも地域が活性化してくるのではないかと期待が広がっています。 っては、設計はプロポーザルでおこない斬新なデザインを競い合いました。6事業者からの提案を土木部に設置した特別審査委員会(委員長:上野
淳 首都大学東京副学長)で審査しました。有識者(大学教授)3人、校長、県の5人で構成。10月22日,29日及び11月9日開催の 「平成24年度土木部プロポーザル」により11月19日最優秀事業者が選定されました。
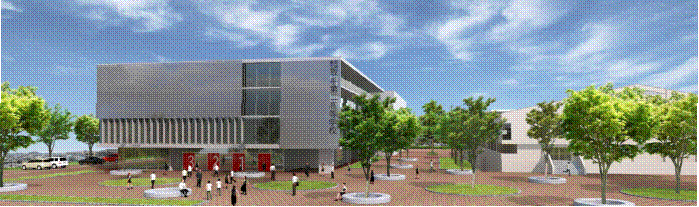
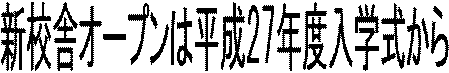
工事のスケジュールは、基本設計が平成24年12月 ~平成25年3月にかけて行われます。(基本設計予算約14百万円)この設計がプロポーザル方式で行われました。
最優秀事業者として、三上建築事務所・眞建築設計室建築関連業務共同企業体が選ばれました。代表構成員は(株)三上建築事務所 (水戸市)、その他の構成員として(株)眞建築設計室 (水戸市)が基本設計を受け持つことになりました。同企業体が示した外観図は4階建てでガラスの壁、校門からのアプローチなど今までの校舎というイメージから一歩進んでいるようにも思えます。
次に実施設計は平成25年4月 ~平成25年9月(予算約4千万円)にかけて行われます。実際の工事は平成26年3月 ~平成27年3月にかけて行われ、この間の授業は校庭に設置される仮校舎となります。新校舎に生徒を迎えるのは平成27年の入学式からとなります。工事名は取手第二高校管理普通教室棟改築工事。工事概要はRC造4階建て、延べ面積は4,000㎡程度です。概算事業費は8億8千万円を予定しています。
平成24年度には水海道一高、石岡一高が竣工
県教育庁では高校の建て替えについて、昭和45年以前に建てられたもので耐震についてIS値0.2以下のところから進めています。県南地域では本年度、水海道一高、石岡一高が竣工します。いずれも最先端を行く校舎となっています。
 【水海道一高の紹介】 【水海道一高の紹介】
21世紀をリードする単位制高校、その単位制高校の中で、全国の最先端を行く、素晴らしい校舎が茨城県に誕生します。そして、生徒の皆さんの進路実現のために、一層のバージョンアップが図られます。
皆さんの夢に飛び立つ空港が、海高に開港!
下:石岡一高

茨城県議会第3回定例会が開かれます!(2012年9月記)
県営公園維持管理費負担の公平性を求めます。
8月も終わりましたが暑さだけは変わりません。領土問題ではメルマガ、フェースブックを通して議論が出来ました。ご意見いただきましたことに感謝申し上げます。マスコミ・政党の論調は政府見解のほぼ焼き直しであり、一方的です。異論をはさむこともできずに世論が一方向に流されることに危惧し一石を投じました。
この問題は大きく言えば国家観、歴史哲学、天皇制に関わる問題です。地方政治のフィールドではありませんが今後も押しとどめなければならない動きが顕著になれば発言をしていきます。
茨城県議会第3回定例会(9.7~9,28)が開かれます。9月は平成23年度の決算も審議されます。今年所属しました土木企業委員会は大震災の影響もあり、道路、河川。橋梁。港湾など各施設の復旧復興事業が数多くありました。これらは政府の復興予算に裏づけられています。
一方土木部関連の通常の事業に道路維持管理があります。県内を網羅する県道の維持は日常的に行わなければなりません。道路建設と比べてもその重要性は変わりません。県には改修を求める地域の声が引きも切りません。しかし限りある道路維持予算では要望をすべて満足させるというところまでいかないのが現状です。
予算が足りないといってしまえば、そういうことなのですが満足に維持管理できなくなった原因があるはずです。
下記は、住宅を持とうとする人に費用は建設だけでなく中長期の家の一生のコストも考慮して住宅に係る総費用を考慮して臨むべきだというあるコンサルタントのご意見です。
「分譲マンションを購入すると、管理費のほかに、修繕積み立て費というのを毎月納めます。ご存じのように、これは修繕計画に沿って、将来の修繕を適切に行えるように、その費用を積み立てているわけです。
では、一戸建てはどうでしょうか。当然のことながら、だれかにルールを決められて、毎月いくらというように、修繕積み立て費が徴収されることはありません。しかし、戸建ても、マンションと同様に築年数が経てば、何らかの手を入れる必要が出てきます。
修理などで、お金が必要になったときに、手持ちの資金がまったくないということでは、大変です。そのときの費用も念頭に入れておかないと、手を入れないといけない時期を逸してしまい、建物に致命的な劣化を見逃すことになるかもしれません。
このような側面から考えていくと、家を建てたとき、いや、建てる前から、竣工後のメンテナンス費用について考えるべきだということがわかっていただけるでしょう。そして、その場合、竣工後15年、30年という長期的な視点で見るのと同時に、年間、月々という短期的な観点でとらえていくことが必要になります。つまり、毎月の家計費の中に、家を維持していくコストを計上して、管理していく感覚です。
上記は住宅について言っていますが「維持費が十分に捻出できなくなった公共施設」としてみると示唆に富んでいます。経済が右肩上がりで税収も増加している状況では建設しても、それほぼシビアな維持管理コストを考える必要もなかったでしょう。しかし現在は過去に建設した維持管理費が県財政に重くのしかかってきています。
9月2日の読売新聞に他人事とは思えない記事が、、、。「官庁も道路も中国マネー」という見出しが一面に踊っていました。太平洋に浮かぶクック諸島の中の一周32キロしかないラトロンガ島に大型体育館、サッカー場、教育省、司法省、道路舗装などが中国マネーで建設されているというものです。このような施設をつくって、しかも自前の資金ではなく、今後の維持管理はどのようにするのだろうと心配をしてしまいます。
日本には地方財政法があります。解釈はいろいろあると思いますが「地方は政府が目を光らせていないと勝手なことをやりかねない」「首長は4年交代であり将来にも責任を持ってもらわなければならない」、というような一面もあります。その観点から地方財政を「守る」ために政府が地方のお金の使い方にシバリをかけているものです。
地域主権という観点からは賛否両論ありますが、ラトロンガ島の施設のケースのように島の財政を考慮しない?建設は将来大変な重荷になると思います。つまり身の丈に合った地方の運営を行うということからは地方財政法のシバリは必要な面もあると考えます。
地方財政法は国の公共団体に対する財政負担についても規定しています。具体的には国が負担する例外は設けつつも「地方公共団体の事務を行うために要する経費は当該団体が全額負担することを原則」としています。これにより将来の見通しもなしに野放図に地方は事業ができないようになっています。
一方国の直轄事業について恩恵を受けている地方に一部負担させることが出来るという取り決めがありました。
国の道路などが例えば茨城県を通過する場合は茨城の地域も便利になるので、というような理屈です。この点について当時の橋下徹大阪府知事が不明朗な国交省の請求に異議を唱え改善を迫りました。また民主党を中心とする連立政権になり地方主権改革が進みました。その結果県財政には朗報がありました。
国営ひたち海浜公園の維持管理費を茨城県は45パーセント負担していました。しかし、これが国の施設であることから、全て国の負担となり茨城県には維持管理費を求めないということになりました。この結果県財政から支出していた年間約2億1千3百万円の負担が無くなりました。
国営ひたち海浜公園は政府と県の関わりです。一方県には偕楽園や笠松運動公園など22の県営公園があります。
県営公園の維持管理を調べていくと二重構造になっていることがわかりました。県営公園である以上県が管理することは当然なのですが、このうち6つの公園についてその維持管理費を地元市町村が半分負担をしていました。
県は地元と協定を締結して建設し維持管理費の負担も決めた結果としています。建設に当たっては地元要望を重視して計画決定したものという説明を断片的に受けました。
問題点としては
①
地元要望で建設した公園と県の主体的意志による公園と二種類存在することになるのか?この論理でいくと県営公園そのものが問われると思います。
②
地元要望ということについて、公共施設については利用や改善については日常的にあります。市の施設は市民の要望。県の施設は県民の要望をなるべく実現して使いやすくすることは当然のことと思います。県の施設でありながら利用者の要望を市の要望と置き換えて市に負担を求める根拠とすることはできないと思います。
③
地方財政法や負担の公平性の観点から問題があると考えています。
県議会では公園の整備なども私の所属する土木企業委員会の所管事項です。審議は9月20日を予定しています。議会で問題点を解明していきます。この課題は市議会時代から「身の丈に合った行政運営」を求めてきた立場からも明らかにしなければならないと思います。
県の施設でありながら維持管理費負担の半分を地元に強要するということは、例えば3つしかできない財政状況でも6つ建設できるというようなものです。あればあったに越したことはないでしょうが身の丈以上の財力が必要になります。
景気低迷、少子超高齢化、そして原発事故不安の中で政治に携わる一地方議員として、財政の縮小均衡を基本に少々不便になってもどこまで我慢できるか住民生活の理解も求めながら、財政の健全化を求めていきたいと思います。
公園整備についてはこれから委員会に向けて議論を行います。今後詳しい内容などお知らせしていきます。皆様からのご意見をお願いします。
|

