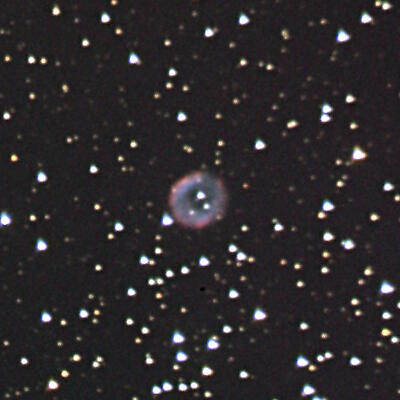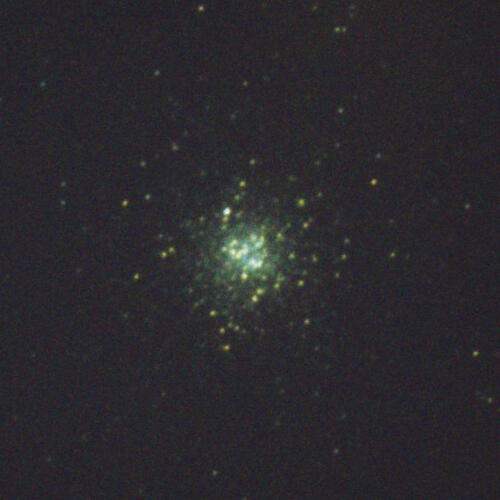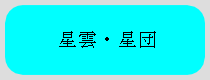
NGC�ԍ����ɕ���ł��܂��BIC�Ȃǂ͂��̌��ł��B��pCCD�̃t�B���^�[��
2012/10�ȍ~��Baader planetarium�ЁA���̐F�͂���ȑO��Meade(Dsi-Pro)�p���g�p�B
�F��RC 300mm + Canon EOS 6D �m�[�}���A���̐F�͉���NIKON D50���g�p�B
���ꂼ���F�������܂����B
�摜�����\�t�g�͂��ׂĂ�YIMG�Ȃǂ��g�p�B
�P�������c�ɐL�тĂ���̂̓A���`�u���[�~���O���s���Ă��Ȃ����߂ł��B
�L�ړ��e��摜�̖��f�ň��p�E���p�͂��f�肢�����܂��B
���̒��쌠�͂��ׂĐ������s�ɂ���܂��B