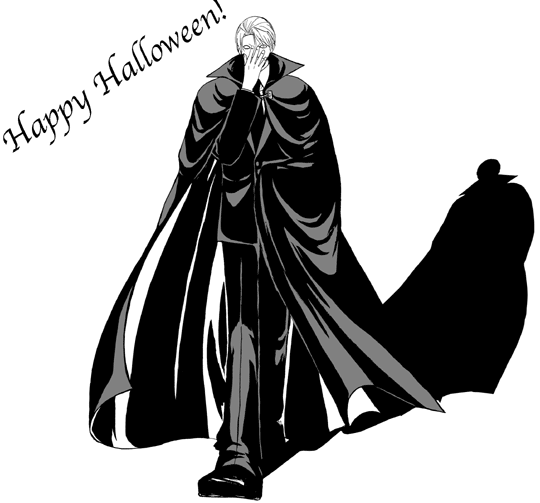|
夜天猫様サイト2周年お祝いSS
まったり散歩道 Tric or Treat |
文化祭準備の真っ最中に突然立ち上がった無謀企画『はばたき学園 ハロウィン』。それは理事長の鶴の一言で断行されることになった。生徒はもちろんのこと、教職員も提案者の理事長も仮装することになっているわけのわからない行事だ。 文化祭を目前に控えた吹奏楽部の顧問である氷室 零一の脳内には突如現れたハロウィンはどうでもいい行事として分類されている。間近に迫った文化祭の方がよほど重要な案件で、職員室で何人もの先生がどんな仮装をするか話をしていても全く気にも留めていない。 「…うん?」 ふと顔を上げた氷室は氷室学級のエース、 が職員室に飛び込んできたのを見つけた。常に自分のところに質問に来る の姿を見つけた氷室は手元の書類を片付けて、その訪れを待つ。 は氷室の姿を認めて、顔を輝かせるとそのまま真っ直ぐに氷室のところへと歩いてくる。 「氷室先生」 文化祭の準備中にも拘らず、質問に訪れる にやや感心していた氷室は、 が今日はその手にメジャーを持っているのを見つけて眉を潜めた。 「どうした、 ?質問ではないのか?」 「いえ、お知らせです。氷室先生はファントムに決まりました」 何の話か全く掴めなかった。 わけがわからなくて怪訝な表情をした氷室に は首を傾げる。 「オペラ座の怪人です。…知らないですか?」 「いや、知っている」 氷室の怪訝な表情は話題がわからないことだったのだが、 には全く通じていないらしい。氷室はオペラ座の怪人くらい知っている。 「だったら、問題ないですね。氷室先生はハロウィンに乗り気ではなさそうなので、クラスで多数決を取って決めました。衣装作るので採寸させてください」 ハロウィンの仮装のことだったのか、と氷室は一応理解できた。だが、何故ハロウィンで氷室が何の仮装をするかをクラスで決められなければならないのかは理解できない。氷室は の言ったとおりこの行事には最初から全く乗り気ではないので、特に何もするつもりはないのだ。 「私には必要ない」 氷室抜きの多数決で決めたというのにも苛立ちを覚える。自分の仮装を何故他人に決められなければならないのか。 が不満そうに唇を尖らせて、簡潔に断った氷室を強い漆黒の瞳で睨む。 「必要なくないです。この仮装はクラスごとに採点されるんですよ。氷室学級に敗北はありえませんから」 その熱のこもった漆黒の瞳にかける言葉がすぐには見当たらない。 『氷室学級に敗北はない』それは常々自分が言っていることだったが、氷室自身は積極的にハロウィンに参加するつもりはない。その及び腰な態度に気付いているのか、 の漆黒の瞳がきらりと煌いた。 「今のところ体育祭、期末試験の平均点と常勝ですから、当然今回も勝ちに行きますよ。…まさか担任の氷室先生が逃げ出すような真似はしませんよね?」 「…………」 じろりと睨まれて氷室は小さく溜息を吐いた。どうやら氷室に拒否権はないようだ。勝負事に燃える氷室学級のエースを止める手立てもない。今の氷室にできることといえば、流れに身を任せるだけだ。沈黙したまま、氷室は の言葉を聞く。 「当日はタキシードか黒のスーツで来てくれれば、マントと仮面はクラスで準備しますから。それくらいなら面倒でもないでしょう?」 「…そうだな」 氷室が為すべきことは当日黒のスーツで来るということだけに決まったらしい。理事長の一言で急に湧いて出てきたハロウィンのイベントは不愉快なものでしかなかったが、黒スーツくらいなら氷室にも準備できる。 「じゃあ、着丈と肩幅だけ測らせてくださいね」 熱く語っていた がひどく楽しそうにジャッという鋭い音を立ててメジャーを構えた。 嫌な顔をする氷室に全く構わず が氷室の背後に立つ。 ぴたっと背骨から肩までを測られる。 「先生、立ってください。それから、これを押さえててください」 言われるままに渋々立ち上がり、氷室は の指示通りに自分のスーツの上着とメジャーを指で摘んだ。手芸部の はこういうことになると俄然張り切る傾向がある。 職員室の注目を集め、氷室は大きな溜息を吐いた。ハロウィンに参加するつもりはなかったのに、 のせいで注目の的になってしまったようだ。 そして、ハロウィン当日。 氷室は職員室で溜息を吐いていた。職員室にはすでに仮装している先生方も何人かいる。 何が楽しくてそんな格好をしているのかわからない。手帳を見ながら本日なすべきことを確認していた氷室のところに氷室学級のエースが嬉々とした表情でやってきて、ずいっと紙袋を差し出してきた。これに着替えろということだろうと氷室は了承して受け取る。 「あ、きちんと黒いスーツ着てくれたんですね。…さ、着てみてください」 に言われたとおりに氷室は今日冠婚葬祭用の黒いスーツを着てきた。 その上から、 が作ったという黒いマントをつける。 足首まである黒い布がそれほど厚い生地でもないのに長くて重い。 「……重いな」 「先生の身長が高いからですよ。背が低かったら布の面積も小さいからそれほど重くないです。それから、これ。ファントムの仮面です」 氷室の不満はさらりと流して紙袋から取り出した白い仮面を が差し出した。氷室はそれを受け取って眺める。今すぐにつける必要性は感じない。 「これは後でいいだろう?」 「一応確認のために付けてみてください。…あ、眼鏡つけたままじゃ無理じゃないですか?」 「…無理だな」 氷室は眼鏡を外して仮面をつけてみる。 視界が悪すぎる。 氷室はすぐさま仮面を外した。これで一日いることは不可能だ。 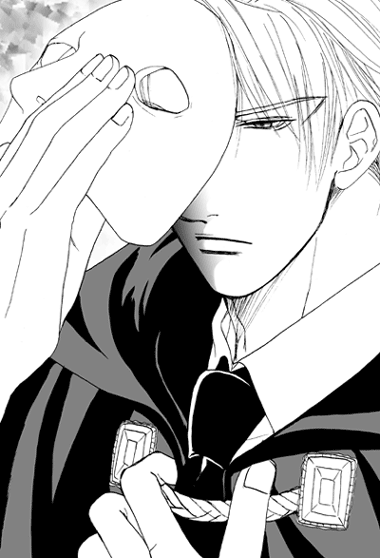 「悪いが眼鏡なしでは動けない。この仮面は無理だ。……どうした、 ?」 忽然と の姿見えなくなった。 視線を下げると、うずくまって床を叩いている姿がある。 氷室が声をかけると、ハッとしたように立ち上がって慌てて首を振った。 「いえ、何でもないです。……でも、採点される時だけは絶対に仮面付けてください」 「…それは何故だ?」 「犯罪的にカッコいいからです」 「…………」 こういう場合、どう反応するべきなのだろうか。 氷室はこめかみを押さえた。 は氷室の動揺を意にも介さず、『犯罪的にカッコいい』というのがどういうことか、熱心に説明し始めた。 「バサリと動きに合わせて大胆に翻る黒いマントは先生の長身にめちゃくちゃハマってるし、本来は醜い顔を隠すための仮面も先生がつければ、外れた時に見える素顔が心臓爆発するほど素敵に見えるんです。せっかくの顔なんですから、こんな時くらいは役立ててください。別に愛想振りまけなんて氷室先生にはできなそうな難しいことは頼みませんから。眼鏡をちょっと外して仮面をつけてくれるだけで良いんです。簡単でしょ?」 「…簡単と言えないこともないが…」 「採点の時は忘れず、絶対に、仮面はつけてくださいね」 はそう言い残して去って行く。 仮面を手に氷室は大きく溜息を吐いた。正直気が進まない。 氷室が溜息を吐くと同時に「あ!」と手を打って、くるりと振り向いた がにこりと笑った。 「氷室先生、仮装したら早くお菓子を準備しないと悪戯されちゃいますよ?」 その一言に氷室はざっと青ざめた。 ハロウィンのことなんて極力頭から排除していたせいでそんな物は持っていない。 普段は持ち込みを一応禁止している菓子類。 氷室は普段口にしない菓子類。 飴の一つも持っていない今日、生徒と顔を合わせるわけにはいかない。 きっと好き放題に悪戯されるだろう。 こんなお祭り騒ぎの日に生徒が絶対に近付かないような場所はどこだろうか。 氷室は眉を寄せて思案する。お祭り騒ぎとは正反対の場所がいい。 フッと頭に過ぎったのは進路指導室。そこに隠れていようと氷室は踵を返す。 風を受けてぶわりと大きく翻ったマントがひどく重たく感じた。 バタバタと慌しい足音が近付いて来る。 進路指導室に潜んでいる氷室は眉を寄せた。 『廊下を走るな』と注意したいが、それをすると自分がここに隠れていることがわかってしまう。苦々しいものを噛み締めながら氷室は気分を落ち着かせるために立ち上がって、資料を手に取った。 いきなりドアが開いた。 本棚の前で資料を読んでいた氷室は目を見張った。 魔女の格好をした が荒い息をしながら、進路指導室に飛び込んできたのだ。 黒い三角帽子、スカートの裾はギザギザで変な形の靴を履いている。そして、まるで氷室と揃いのような黒マントをつけていた。 全身黒のせいか の白い磁器のような肌が際立って見える。走ったせいか頬が薔薇色に上気し、心なしか漆黒の瞳が潤んでいるようだった。化粧でもしているのか、いつもよりずっと赤く見える唇がゆっくりと動いて氷室の名を呟いた。 「……氷室先生」 奈津実に追いかけられて逃げ込んだ進路指導室に先客がいるなんて は全く考えていなかった。 自分がドアを開けた反動で進路指導室の中の空気が大きく動いて、窓の前に立っていた氷室の黒いマントが風をはらんで翻る。驚いたように振り返った氷室と居丈高に揺らめくマントがあまりにもよく似合っていて息を呑んだ。 …グッジョブ、私!… 氷室の仮装を半ば強引にファントムに決めたのは だ。氷室の説得なんてクラスの誰もやりたがらない仕事なのをいいことに自分の趣味を押し付けたのである。 マントだけなら吸血鬼でもよかったが、仮面をつけた方が氷室のカッコよさがより強調される。朝、職員室で試着してもらった時にそれを強く感じた。本来醜さを隠す仮面の下から氷室の素顔が出てきた時には鼻血噴いて倒れるかと思ったくらいだ。 バタバタと廊下を駆ける足音を耳にして はハッと我に返る。 氷室のマント姿を前に放心している場合ではなかった。急いで逃げなければ奈津実に追いつかれてしまう。 は氷室のすぐ近くの窓が大きく開いているのを見つけて、窓に飛びついた。ここを乗り越えて、外に出れば少しは時間稼ぎになるはずだ。 「コラ、何をしている!?」 窓枠に足をかけたところで後ろから氷室に羽交い絞めにされるようにして止められる。 ここで掴まるわけにはいかないのだ。 は氷室を振り切ろうとして、腕の内で暴れる。しかし、いくら暴れてみたところで氷室の腕からは逃れられない。 は抜け出そうともがきながら必死で氷室を説得する。 「なっちんに追いかけられているんです。花椿先生の作った小悪魔なんて着たくないんです。あんな胸元が大きく開いてて、スリットの入ったミニスカートなんて絶対にイヤなんです。お願いですから、行かせてください」 「……この辺ねっ!?」 奈津実の声が廊下から響いてきた。先程の の声が廊下に響いたらしい。 はビクッとして、必死に逃げ出す算段をするが、どんどん近付いてくる足音から察するに氷室の腕から脱出した上で が逃げ出すだけの猶予はない。 頭からすっと血の気が引いていく。 脳裏には花椿お手製の小悪魔衣装を着せられた自分が思い浮かぶ。せっかく魔女の衣装にして、マントだって氷室とお揃いに作ったのに、苦労が水の泡だ。 絶体絶命。もうダメだ。 がくりと項垂れた の喉元にあるマントと帽子の結び目に氷室の指がかかった。 シュルと音がして、 のマントが重力に任せてふわりとその場に落ちる。 わけがわからなくて驚いて顔を上げた の動きに合わせて三角帽子がぽすっとその場に落ちた。 目を瞬く の前に真っ黒の世界が広がる。 氷室に腕を引かれるまま、 は黒に呑みこまれた。 氷室がマントの内に隠してくれたのだと理解したのは氷室がドアに背を向けるように資料のある本棚に向かって立ってくれてからだった。見つかるのが怖くて、真っ黒に包まれたこの状態が不安で は唯一縋りつける存在である氷室にぴたりと寄り添う。 「静かにしていなさい」 に聞こえる程度の大きさで囁かれた氷室の声は直接脳に響くような感じで、頭の芯がぐらぐらする。 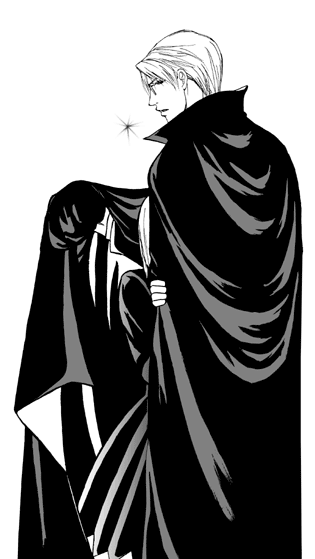 氷室が の頭上で資料を広げるのと、バンと大きく音を立てたドアが開くのはほぼ同時のことだった。 「うるさいぞ。静かにしなさい」 「……ヒムロッチ?…… 、見なかった?」 予想通り奈津実の声が響いてきて、 はびくりと身体を竦ませる。本当に見つからないかドキドキして、目の前の氷室に思わずしがみつく。 トクトクと脈打つ氷室の鼓動にほんの少し安心すると同時に の鼓動は早まってくる。 「…………」 ゆっくりと呆れたように息を吐いた氷室が資料を閉じて、腕を動かす。 見つかるのではないかと思って、ぎょっと目を見開いた の耳に奈津実の声が飛び込んできた。 「… のマント!ここから逃げたってことは……理事長室ね」 小さく は息を呑んだ。その通りだ。ここから外に出て、理事長室から校舎の中に入ってやろうと考えていた。どうやら奈津実には の行動パターンがバレバレらしい。 「 といい、君といい、行儀が悪い」 氷室の苦々しい声に奈津実が窓枠を乗り越えようとしていることがわかる。 これ以上氷室に動かれたら が奈津実に見つかってしまう。 は氷室にしがみつく手に力を入れた。 「 と同じく見逃して。じゃあね」 とぉっ!と掛け声をかけながら窓枠を乗り越えて外に出たらしい奈津実の足音が小さくなっていく。 その足音が聞こえなくなって、 はゆっくり安堵の息を吐いた。 「ハァ…緊張した」 そう呟きながらほんの少し氷室から離れる。 それと同時にすうっと冷たい空気が氷室と の間を通った。 一気に寒くなったことで寄り添っていた氷室が温かかったことを知る。 もうちょっとあのままいたかった。 思わずそう考えた はぐっと息を呑んだ。 今更ながら自分のした行動がどういうものだったのか、理解する。 こっそりと氷室の様子を伺うが、氷室は奈津実に見つからなかったことに安堵しているだけで、氷室のマントに が包まれた状況を気にしている様子は全くない。 「……もう、大丈夫だろう」 「ありがとうございます。助かりました」 氷室が手を動かすとばさりと黒い世界が動いて の目の前に色彩に溢れた現実の世界が現れた。 恥ずかしさにまともに氷室の方を向くことができず、 はくるりと氷室に背を向けて、手櫛で髪を整える。 「……早く君もここから出て行きなさい」 氷室の迷惑そうな口調にほんの少し落ち込みながら は窓辺に落ちているマントを拾う。それをくるりと翻して羽織りながら は首を傾げた。 ハロウィンの日に進路指導室でしなければならないことなんてあるのだろうか。仮装の採点をする時には氷室に来てもらわないとならない。 「……先生は?」 「私のことは良い。早く行きなさい」 つまり、用が終わるまではここにいるということだろうと結論付ける。 はい、と返事しながらマントの紐を結んだ はハッとしたようにポンと手を打って、顔を上げた。 せっかくのハロウィンだ。 には計画していたことがある。氷室にお菓子をもらうのだ。 小さな野望を思い出した は氷室に向かってパッと手を差し出す。 「…えーと、じゃあ……せっかくなので『Tric or Treat』しちゃいます」 「…………」 しかし、氷室は無反応だった。 いつもの無表情で を見下ろすだけ。 微動だにしない。 「…………先生?…お菓子くれないと悪戯……しちゃいますよ?」 お菓子をもらおうと手を差し出したまま、困って首を傾げた にやはり氷室は何も言わず、動きもしない。 悪戯を甘んじて受けるということだろうか、と考えて首を傾げた はハッとした。 お菓子一つで追い払おうにも、肝心のお菓子を持っていないのだ。 ハロウィンについては『黒いスーツ』を準備してもらうように頼んだが、お菓子を準備しなければならないことについては当然準備するものとして は一言も言わなかった。 の責任でもある。 氷室がハロウィンに乗り気ではないことはよく知っていたのだから。 氷室に悪戯したい生徒なんて山ほどいるだろう。 自分以外の誰かが氷室に悪戯するなんて考えただけでも堪えられない。 溜息を吐いた氷室の目の前で、 はくるりと踵を返した。 「氷室先生」 突然身を翻して、進路指導室から出て行った が慌しい足音させて再び進路指導室に駆け込んできた。廊下を全力疾走したらしい に氷室は溜息混じりにお小言を言う。 「廊下は走らないように…どうした、忘れ物か?」 「はい」 ニヤッと笑うその顔は悪戯を目の前にした楽しそうなものだ。 氷室にお菓子がないことを悟って、どうせ何か悪戯を仕込んできたのだろう。 「氷室先生、『Tric or Treat』!」 「…………」 「やっぱりお菓子ないんですね。……悪戯しちゃいますよ?」 「…………」 だいたい『Tric or Treat』と言われると困るから、氷室はわざわざ人目につかない進路指導室にやってきたのだ。 本棚の資料を手に氷室はやや乱暴な動作で椅子に座った。 勝ち誇ったように悪戯すると言われても氷室に為す術はない。 自分の不手際に怒りを感じるしかない。完璧主義の氷室には耐え難い失態なのだ。 むっつりとしたまま座って資料に視線を落とした氷室に が近付いてきた。 ほんの少し考えるように顎に人差し指を当てた を見て、氷室は眉を潜めて訝る。 何を企んでいるのか は氷室の眼鏡をゆっくりと外した。 「な、何を、君はっ!?」 「仮面つけるには邪魔ですから」 丁寧に眼鏡の蔓を折りたたんで、指導室の机の上… に手渡された白い仮面の隣に置く。 仮面をつけさせるのが の悪戯だということだろうか。 今日一日つけておくには視界が悪い、と言ったのが不満だったのだろうか。 そんなことを考えながら眉を潜めた氷室の肩にそっと の手が置かれ、心地良い重みが加わる。振り返ろうとした氷室のこめかみに温かくて柔らかなものが触れた。 ちゅっと小さな音を立てたそれが何かなんて考えるまでもない。 ぎょっとして目を見開く氷室の耳に楽しそうな の声が聞こえてくる。 「あ、口紅ついた」 「…き、君はっ!」 こめかみを押さえて を睨むが、全く意にも介していないようで、やった!と拳を握っている姿が目に入った。 「仮面つけたら見えませんからそんなに怒らないでくださいよ。それより、氷室先生も言ったらどうですか?『Tric or Treat』って私に」 「何故だ?」 「いいからいいから……ね?」 これ以上馬鹿馬鹿しいことにはならないだろう。氷室は諦めて の悪戯に付き合ってやることにする。全てはお菓子を忘れた自分の責任なのだ。 「……『Tric or Treat』?」 「はい、どうぞ」 が机の上にすっと小さな紙袋を差し出す。 氷室が紙袋を開けて覗くと中には飴玉がギッチリと詰まっていた。 苦い笑いが漏れる。 先程は教室までこれを取りに行っていたのか、と理解すると、一見破天荒に見える彼女の気遣いがよくわかる。 「……すまないな」 「氷室学級のエースですから。たまには担任のフォローもしちゃうんです」 は窓辺に落ちたままの黒い三角帽子を手にとって氷室に向き直る。 はにかむような、恥ずかしそうな笑顔で が指先を伸ばした。 白くて細い指先がそっと氷室のこめかみに触れる。 先程 に悪戯された場所が熱を持つ。 「…これね、先生が私に恋する魔法なんです。今日の私は魔女ですから」 が悪戯っぽい視線を向けて小さく笑う。その笑顔から何となく目を離せない。 三角帽子を被りなおして、魔女の衣装をきちんと着込んだ は氷室にも教室に顔を出すように言うと、来た時と同じように風のように去っていった。 やれやれ、と呟きながら頬杖を突いた氷室の指先がこめかみに触れる。 その瞬間、蘇ったのは温かくて柔らかな感触とひどく楽しそうな明るい声。 『あ、口紅ついた』 カッと顔が熱くなる。 楽しそうに笑う可愛い魔女の魔法にかかったような気がするのは今日がハロウィンのせいだろう。 明日にはいつもの自分に戻るはずだ、と自分に言い聞かせるようにした氷室は軽く溜息を吐いて、机の上に置きっぱなしの白い仮面に手を伸ばす。 赤面した顔と口紅の赤を誰にも見られないようにするにはちょうど良い。 「……今日、だけだ…」 白い仮面をつけたファントムは悪戯避けのお菓子を持って、立ち上がった。 カツカツと響く足音はいつもどおり測ったように正確で、教室に向かって真っ直ぐに歩く。 校内のあちらこちらから響く『Tric or Treat』にファントムの黒いマントがわずかに揺らぐ。白い仮面の下のファントムがやや動揺していることを知る者はいなかった。
|
|
|
|
|