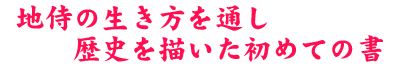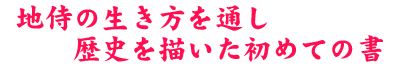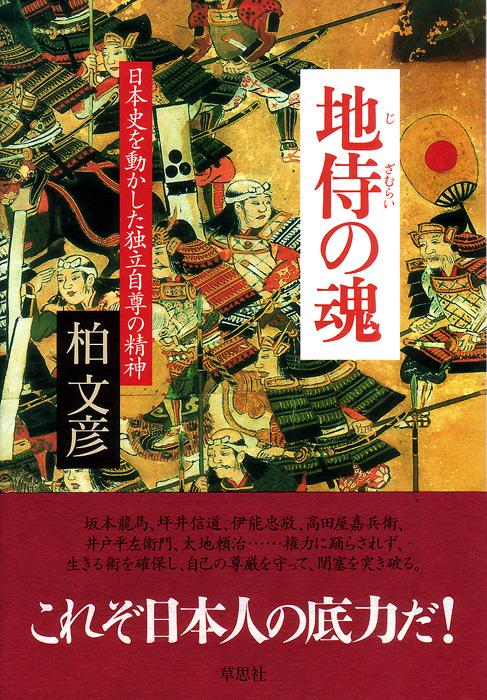
発行元 草思社
四六判 上製 256頁
定価 1890円(本体1800円)
5月1日発行 |
地に足のついた生き方がここにある
無気力、夢と理想の喪失、将来に対するそこはかと無い不安。これは昨今、我々に突きつけられる重く気鬱な現実である。背景として、先行きの読めない世界情勢、格差社会の出現、社会生活すべてにわたってのモラルの低下などがあげられる。
閉塞した時代を打破するもの、それはいつも人間であった。
中世、地侍と呼ばれる人たちがいた。武装した小領主、地主である。彼らは領地(生産手段)と地位(尊厳)を守るために、ある時は武田に属し、北条に転じ、またある時は徳川に従うなどした。しかし、それはあくまでも主体的にである。地侍──彼らこそが中世、戦国期の武士団の中核だったのである。そんな彼らも秀吉の時代、宮仕えの武士として歩む《領地(生産手段)を放棄する》か、百姓として生きる《武装(自衛力)を放棄する》か、選択を迫られた。これが兵農分離策である。
近世(江戸時代)が近代(明治時代以後)の基盤となったといわれる。すべての準備が江戸時代になされていたというのである。そして、その地の塩、背骨となったのが地侍の裔である上層農民と下級武士、自立した商人であった。彼らの独立自尊の魂と剛直な精神こそが近代を拓いたのである。
今混迷する時代、江戸期の彼らの生き方を顧みることは、我々に力強く生きるヒントを与えてくれるのではないだろうか。
序章 戦国――影の主役
見限られた武田勝頼/私の土地、公の土地/武装する有力農民たち/耕作者であり経営者/地侍を知悉していた織田信長/秀吉の兵農分離策
第一章 大地を拓く――天下統一前後の大開発
供給が追いつかぬ市川家の事業/五郎兵衛、新田を開発する/一円支配と土木技術の蓄積/拓かれていく各地の沖積平野/長州志士のルーツ/冷遇された大梶七兵衛/山中鹿之介の後継者“槍の新十郎”/素性の知れぬ近世大名
●市川五郎兵衛(いちかわ・ごろべえ)1572~1665
信濃国佐久(長野)で新田開発
●大梶七兵衛(おおかじ・しちべえ)1621~1689
出雲国松江藩(島根)で植林・新田開発
●亀井茲矩(かめい・これのり)1557~1612
因幡国鹿野城主(鳥取)となった戦国武将
第二章 挽歌――武装集団の潰滅
世渡りの達人・藤堂高虎/“治水の神”と西島八兵衛/誇り高き人々の義務/京の牢人・渡辺勘兵衛/不覚人・塙団右衛門/金銀に執着した侍たち/隷属するものの悲哀/仕組まれていた島原の乱
●藤堂高虎(とうどう・たかとら)1556~1630
伊勢津藩主(三重)となった戦国武将
●西島八兵衛(にしじま・はちべえ)1596~1680
津藩士。讃岐高松に派遣され溜池を築造
●渡辺勘兵衛(わたなべ・かんべえ)1562~1640
晩年は悠々自適に過ごした戦国武将
●塙団右衛門(ばん・だんえもん)1567~1615
大坂の役でも活躍した戦国の豪傑
第三章 時代を摑む――新たな事業を起こす
地下水脈、流れは絶えず/海の地侍、太地に生きる/最新捕鯨法のすべてを公開/安芸の牡蠣船、大坂に進出/時代を見据えた“企業化”/“心中ブーム”はなぜ起きた/哀歌、生活苦の下級武士
●太地頼治(たいじ・よりはる)1623頃~1699
紀州太地(和歌山)の鯨方宰領
●小林五郎左衛門(こばやし・ごろうざえもん)?~1687
広島湾での牡蠣養殖の創始者
●河面仁左衛門(こうも・にざえもん)?~1695
広島で牡蠣船を仕立てて大坂に進出
第四章 景気失速――はじけた元禄バブル
繁栄の世から不況の世へ/弓ヶ浜に綿花咲く/新税制導入者の深謀と遠慮/川崎宿で苦労した田中丘隅/将軍吉宗に献上された書/地方巧者を求める大岡忠相/山陰を救った“いも神さま”
●米村所平(よねむら・しょへい)1642~1727
弓ヶ浜に綿花産業を興した鳥取藩士
●田中丘隅(たなか・きゅうぐ)1662~1730
農政家、治水事業家。『民間省要』を著す
●井戸平左衛門(いど・へいざえもん)1672~1733
石見国大森(島根)代官。薩摩芋を導入
第五章 再建への道――不況の中の企業家たち
嫌われた春日局、歓迎された白象/武蔵野を開拓した北条・武田の遺臣/幕府も思い知った民間人の企業家精神/苦闘する紀州藩から将軍へ/山河を彩った櫨の紅葉/誉れに生きる田中善吉/甲州の“いも代官”中井清太夫
●川崎平右衛門(かわさき・へいえもん)1694~1767
武蔵国多摩の名主、農政家。のち代官
●田中善吉(たなか・ぜんきち)1694~1767
紀州藩の地士、商人。製蝋業を興す
●中井清太夫(なかい・せいだゆう)生没年不詳
代官。甲州(山梨)に馬鈴薯を導入
第六章 探査の時代――北方の大開発
市えん様に上酒醸造の打診/利益率の高い江戸での土地投資/忍の浮城、石田三成の蹉跌/「家産の三分の一を公益に供すべし」/落ち延びて僻遠の地に土着/伊能忠敬に師礼を尽くした上田宜珍/田沼意次の失脚と蝦夷地調査/冒険商人・高田屋嘉兵衛
●伊能忠敬(いのう・ただたか)1745~1818
上総国(千葉)出身の天文家、測量家
●吉田市右衛門(よしだ・いちえもん)1739~1813
武州下奈良村の名主、篤志家
●上田宜珍(うえだ・よしうづ)1755~1829
肥後高浜村(熊本県天草町)の庄屋、陶業家
●高田屋嘉兵衛(たかだや・かへえ)1769~1827
淡路島出身の蝦夷地開発者。北前船船主
第七章 嵐の前夜――鎖国下の“知”の蓄積
行き場を失った者たちの憤怒/家系図の秘めた威力/“生き菩薩”と呼ばれる医師・坪井信道/最新医学に出合い一念発起/緒方洪庵に受け継がれゆくもの/医師の品格を高めた師と弟子/弄石家、本草家、好事家の群れ
●坪井信道(つぼい・しんどう)1795~1848
江戸三大蘭方医の一人。門下に緒方洪庵ほか
●木内石亭(きのうち・せきてい)1725~1808
弄石家。『雲根志』を著す
●木村蒹葭堂(きむら・けんかどう)1736~1802
大収集家。造り酒屋を経営
●小野蘭山(おの・らんざん)1729~1810
本草植物学者。幕府医学館で講義
第八章 維新――先駆け奔った地侍たち
先駆けた清河八郎/武市半平太と中岡慎太郎/坂本龍馬の柔軟性/独立自尊の長州と薩摩/榎本武揚の“一分”/日本人よ、地侍であれ!
●清河八郎(きよかわ・はちろう)1830~1863
庄内藩郷士。尊攘派志士の先駆け
●武市半平太(たけち・はんぺいた)1829~1865
土佐勤皇党の創始者、剣客
●中岡慎太郎(なかおか・しんたろう)1838~1867
土佐藩の大庄屋、陸援隊を組織
●坂本龍馬(さかもと・りょうま)1836~1867
土佐藩郷士、海援隊を組織。「船中八策」発案
●土方歳三(ひじかた・としぞう)1835~1869
武蔵多摩出身、新撰組副長。五稜郭で戦死
●榎本武揚(えのもと・たけあき)1836~1908
五稜郭で戦った幕臣。明治の軍人、政治家
|