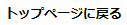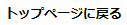
37擭傇傝偺暉堜崑愥偱偺奐敪偟偰偒偨梈愥憰抲偺忬嫷
 |
僐儞僋儕乕僩婎慴峐寭梡棙梡偱偺抧拞擬梈愥乮挀幵応乯
丂26擭娫丆崱夞偺崑愥偱傕挀幵応梈愥偲偟偰幚梡揑偵栤戣偑側偔傕愥傪傛偔梟偐偟懕偗偨丏梈愥柺愊摉偨傝弞娐億儞僾偺栺4倂/噓偺丆揹擬梈愥偺1/40偺徚旓揹椡偱偁傞丏暉堜導棫戝妛怑堳廧戭偺僐儞僋儕乕僩婎慴峐乮挿偝35m乯48杮偺拞嬻偵挋悈偟丆曻擬娗杽愝挀幵応400噓偐傜偺椻悈傪峐掙偵傑偱億儕僄僠儗儞娗偱憲傝丆椻悈偼峐撪挋悈偵弌偰丆備偭偔傝偲峐摢偵廃埻偺抧拞擬傪摼側偑傜棳傟傞丏崅壏偲側偭偨弞娐悈偼挀幵応偵栠傞丏暯惉2擭塣梡偝傟偰埲棃丆栚偯傑傝偟偨扽巁僇儖僔僂儉偱棳検寁傪奜偡側偳偺儊儞僥僫儞僗傪彍偒丆僔乕僘儞慜偺揰専傕堦愗柍偔愥傪徚偟懕偗偨丏梈愥偺僐儞僋儕乕僩楬柺傕傂傃妱傟偼慡偔尒傜傟側偄丏愊愥僙儞僒偼悢擭慜夡傟丆晹昳偑挷払偱偒側偔側傝丆廧柉偺曽偑庤摦偱塣揮偟偰偄傞丏栚帇塣揮偱偼柍懯側塣揮偲側傞偙偲偐傜崑愥偱偼梟偗偵偔側傞偑丆崱夞偼堦帪揑偵愊愥偑偁偭偨傕偺偲巚偆偑丆彍愥偺屻傕柍偔愥偼徚偊偰偄偨丏廧柉偺曽偐傜偼傛偔梟偗偰彆偐偭偰偄傞丏26擭宱夁偱弞娐億儞僾偼偄偮夡傟偰傕巇曽偑側偄偲巚偭偰偄傞丏弞娐億儞僾偼庢傝懼偊偰傕10枩墌傕偟側偄偩傠偆丏愊愥僙儞僒偼丆夋憸張棟僞僀僾20枩墌偑奐敪偝傟偰偄傞丏崙撪嵟弶偺偙偺幚徹僔僗僥儉丆巤岺偵傕拲堄偑峴偒撏偒丆26擭傎傏僩儔僽儖側偔丆悢抣僔儈儏儗乕僔儑儞傕帵偡傛偆偵丆崑愥偵傕嫮偄偙偲偑帵偝傟偨丏

| 
|
暉堜導棫壒妝摪偺婎慴峐寭梡棙梡偺抧拞擬梈愥乮曕摴)丂偙偙傕梟偗偰偄偨丏4擭慜偵愊愥僙儞僒偺拞偺抴鍋傪彍偄偰暅婣偱偒偨愊愥僙儞僒偩偑丆愥偱幬傔偵岦偄偨偑丆偆傑偔惂屼偟偰偄傞偲偺偙偲丏4擭慜偵丆摦偄偰偄偨偑塣揮帪偺峐掙偐傜偺楻悈傪夞楬傪戝婥奐曻宯偐傜戝婥枾暵宯偵偡傞偩偗偱柍偔偟丆楻悈偡傞偐傜偲掲傔偰偄偨峐傕棙梡偱偒傞傛偆偵偟偨丏偨偩偟丏扽巁僇儖僔僂儉偺愅弌偱娗楬偑栚偯傑傝偟偨峐偑偁偭偰丆壱摥偟偰偄傞峐偼巤岺峐偺6妱傎偳丏偙偺悢擭偺尋媶偱丆宂巁僜乕僟傪嬐偐偵揧壛偡傞側偳偱扽巁僇儖僔僂儉愅弌傗楻悈偼柍偔偣偨丏弞娐悈偑悈偱偼搥寢偺姦椻抧偱傕梈愥柺偲峐擬尮偺拞娫偵擬岎姺婍傪憓擖偡傞偙偲偱幚巤壜擻丏壒妝摪傕嶰榊娵傕愝旛夛幮偺儊儞僥僫儞僗偼偍偙側偭偰偄側偄丏導棫恾彂娰偼儊儞僥僫儞僗埾戸傪偟偰偄傞偑娗楬偑挿偔嬻婥敳偒側偳偵嬯楯偟偰偄傞丏愊愥僙儞僒偑曗廋偝傟偢偵丆庤摦偱塣揮偝傟偰偄傞偙偲傕偁偭偰偐廫暘側梈愥偵偼帄偭偰偄側偄丏

|

|
曕摴柍嶶悈梈愥幵摴嶶悈偺僙僢僩梈愥乮抧壓悈嵞棙梡梈愥乯16亷偺抧壓悈傪曕摴偵杽愝偝傟偨曻擬娗偵棳偟曕摴偺愥傪梟偐偡丏梟偐偟偨屻偺7亷偲側偭偨抧壓悈傪幵摴偵嶶悈偟偰徚愥偡傞丏偙偺曕摴柍嶶悈梈愥幵摴嶶悈偺僙僢僩梈愥偼徍榓61擭偵昅幰傜偑崙撪嵟弶偵幚巤偟偨丏偦偺屻搶杒埲撿偺愥崙偺搒巗晹偱嵟傕戙昞揑側梈愥偵晛媦偟偨丏戝愥捈屻偼梈愥偑捛偄偮偐側偐偭偨偑丆偦偺屻偼幨恀偺傛偆偵曕摴傕傎傏梟偗偰偄偨丏尰応偵傛偭偰丆傎傏梟偗偰偄傞僒僀僩偲梋傝梟偗偰偄側偄僒僀僩偑偁偭偨丏梟偗偰偄側偔偰傕愥偑崀傝巭傫偱幵摴偼嶶悈偝傟偄側偐偭偨丏昅幰偑奐敪偟偨僔僗僥儉偱偼梈愥曕摴偺愊愥傪姶抦偡傞傛偆偵惂屼偟丆愝寁偺巇條傕偦偺傛偆偵婰偟偨丏偟偐偟丆慡崙偵晛媦偟偨僔僗僥儉偼崀愥僙儞僒偱偺惂屼偱丆偙傟偱偼戝愥偱偼楬柺偵愥偑巆偭偨忬懺偱丆愥偑崀傝巭傓偲塣揮掆巭偲側傞丏抔朳偡傞偺偵丆幒壏偱柍偔奜婥壏偱惂屼偡傞傛偆側傕偺偱丆愊愥僙儞僒偺奐敪傪30擭慜偵丆婇嬈傗崅愱偲嫟摨偱昅幰傜偼奐敪偟偨丏奐敪偟偨愊愥僙儞僒偼曕摴梡偑70枩墌偱幵摴梡偺庱怳傝僞僀僾偑500枩墌偱丆崀愥僙儞僒偺30枩墌偵斾傋傞偲崅壙偩偑丆僔僗僥儉慡懱偺悢愮枩墌偐傜偡傞偲偦偺愡悈岠壥偑2攞偱丆桪傟偨擻椡岦忋偐傜偡傞偲愊愥僙儞僒偼桪傟傕偺偱丆抧壓悈梘悈偺揹婥戙偱傕10擭傎偳偱彏娨偱偒傞丏嶐擭偐傜夋憸張棟僞僀僾偺愊愥僙儞僒偑巹偺尦怑応偺儊儞僶乕偵傛偭偰偺奐敪丆巗斕偝傟偨丏偙偺夋憸張棟僞僀僾偺愊愥僙儞僒偱曕摴偺梈愥忬嫷傪尒偰惂屼偡傟偽戝愥偱偼愥偑崀傝巭傫偱傕墑挿偱丆崀偭偰傕愊傕傜側偄帪偼塣揮掆巭丆嬐偐側崀愥偱偼娫寚塣揮偱丆愡悈偲愡揹偲側傞丏梈愥偼僯僢僠側偺偱丆愱栧惈傪崅傔偰傕庴拲検偑曐徹偝傟側偄丏傑偨丆敪拲幰偑愱栧惈偺昡壙傪忋庤偵峴偆偙偲偑弌棃側偄偙偲傕偁偭偰丆梈愥傪傛偔暘偐傜側偄僐儞僒儖偑庴拲偡傞丏偦偟偰丆懡偔偼梈愥娭楢儊乕僇乕傗巤岺嬈幰偵愝寁傪壓惪偗丆娵搳偘偡傞偙偲偑栤戣偺攚宨偱偡丏偙偆偟偨攚宨偑偁傞偐傜偙偦丆岞嫟惈偺崅偄昅幰傜偑尋媶奐敪偡傞堄媊偑偁傞丏偙偆偟偨攚宨偼丆奐敪偟偰傕丆憤崌揑偵椙偄僔僗僥儉偑晛媦偡傞偺偱偼柍偔丆壓惪偗偺摿掕偺儊乕僇乕傗婇嬈偵棙塿偵側傞偺傕偺偑晛媦偝傟偰丆嵟揔側傕偺偑嵦梡偲偼昁偢偟傕側偭偰偄側偄丏
 |
 |
 |
儂僥儖偺尒偊傞幨恀偺暉堜墂杒曕摴(壞偺拁擬傪孮峐岠壥偱弶搤傑偱捠忢抧拞傛傝10亷崅傔傞乯偼丆戝愥偱拁擬偼側偔側偭偰丆傑偨崀愥僙儞僒惂屼偱崀愥帪埲奜偼塣揮偑掆巭偱丆梈愥柺偼墯傒偑尒傜傟傞掱搙偱攋抅偟偰偄偨丆摨偠曽幃偺岾嫶傕丆梈愥偼偙偺戝愥偵偼懳墳偱偒側偐偭偨丏慜屻偺嶶悈梈愥偵斾傋偰尒楎傝偟偰偄偨丏峾彴斉嫶偱楬柺搥寢偑偟偽偟偽惗偠傞偙偲偲婛懚偺堜屗傪堜屗孈嶍偑婯惂偝傟偨嫶偺撿偱巊梡偟丆偙偺嫶偼壞偺擬傪拁擬偟偨僔僗僥儉偵偟偨丏楬柺傪忢帪侽亷埲忋偵曐帩偡傞惂屼偱丆捠擭偱偼拁擬偺敿暘傪徚旓偟偰偄傞偙偲偐傜丆楬柺偵悈暘偑柍偄偲偒偼塣揮傪掆巭偡傞惂屼偵偱偒傟偽梈愥擻椡偼岦忋偡傞丏愊愥僙儞僒偱塣揮偝傟偰偄傞偑丆偙偺戝愥捈屻偼3亷偺弞娐悈壏偱偁傞偙偲偐傜60倂/噓乮1帪娫偱怴愥0.6cm偺梈愥乯弌椡偱偁偭偨丏婫愡娫拁擬偼丆37擭傇傝偺戝愥偵傑偱懳墳偝偣傛偆偲偡傞偲愝抲旓偑崅偔側傝偡偓傞丏抧拞擬傕戝愥偩偲抧拞偺壏搙偑掅壓偡傞偑丆婫愡娫拁擬傎偳偺壏搙掅壓偵偼側傜側偄丏抧壓悈棙梡偼丆柍恠憼側偺偱丆戝愥偱傕擻椡偺掅壓偼側偄丏偨偩偟丆怺偝12m偺抧壓悈懷悈憌偺悈埵偑掅壓偟丆昅幰傜偑幚徹帋尡拞偺暉堜巗怷揷偱偼抧壓悈弞娐曽幃偺抧拞擬擬尮彴抔朳僔僗僥儉偼梘悈偱偒側偔偐偭偨丏怺偝6m偺懷悈憌偼悈埵掅壓偑側偔偰丆梘悈傪愗傝懼偊偰塣揮偼宲懕偱偒偨丏暉堜巗壨憹偱傕嶐擭丆16m偺怺偄堜屗悈埵偑掅壓偟丆愺偄堜屗偲僒僀僼僅儞偱宷偄偱偄偨偙偲偱丆偦偺悈埵嵎偱曻擬娗撪傪抧壓悈偑弞娐偟丆柍摦椡偱梈愥偑偝傟偨丏