− 防空頭巾 − |
 |
私の小さい頃の思い出に防空頭巾がある。井口町の我が家から双葉幼稚園に行く時は必ず防空頭巾を携帯していた。空襲警報がなると真先に防空頭巾をかぶり地に伏して手で耳や目をふさぎじっとしている。火の粉があがったら近くの防火用水でぬらし逃げるとも教えられていたように思う。
昭和20年4月になると高知の街もいよいよ危ないということになって、仁淀川の上流吾川村久喜という田舎に疎開し、父とは別れて暮らした。7月4日の大空襲で父の勤めていた造り酒屋も全焼した。40キロ離れた田舎からも、高知の空が真赤になって、村人は高知が焼えゆうと口々に言って東の空を見ていたが、安否が心配されていた父はまもなく無事という報が入って安堵したことをおぼえている。高知の街は一瞬、火の海と化し。水にぬらした防空頭巾のおかげで助かったという人もいたが、せっせと掘らされた防空壕は何の役にもたたず。黒こげの死体の折り重なる死の壕になったのである。
桐生悠々が1941年9月「信濃毎日新聞」で「関東防空大連習を嗤ふ」というタイトルで軍部の愚鈍を批判したことが高知の街を含め全国の都市で現実となったのである。この愚鈍は今も続いている。
(西森茂夫) |
− 奉公袋 − |
 |
「奉公」とは「戦場の労苦を偲び」私生活を2の次3の次として「公け」のために「奉仕」しましようという趣旨である。「興亜奉公日」は「国民精神総動員運動」の一環として1939年(昭和14年)9月1日から毎日1日をそう呼ぶことに決めた。
「日本軍隊用語集」(寺田近雄著、立風書房)には次のような解説がある。1890年(明治23年)に明治天皇が国民に示した道徳律「教育勅語」の中に「一旦、緩急あれば義勇公に奉じ…」とあり、ひとたび国家の一大事となれば勇気をもって死力を尽して国に奉仕することを高度のモラルと定めた。昭和の国民的スローガンにも「滅私奉公」の言葉があり、すべての私心を捨てて国に奉仕する合言葉でもあった。この場合の公は、皇室でも国民でも人類でもなく国そのものである。
さて奉公袋だが、これは一種の軍人用のポシェット・ハンドバッグで、赤紙がきて召集された新兵や在郷軍人たちは、ハンで押したように手に手にこの袋をぶら下げて兵営におもむいた。縦四〇センチ、横二〇センチばかりの綿やメリヤス製の布袋で、口が麻ひもで締めくくられるようになっている。色は軍服に似た緑色あるいは褐色で、表面に「奉公袋」の文字と氏名書き入れ欄が印刷されていた。中身には、召集令状・印かん・筆記具・入営後に不要となった衣服を送り返す油紙・麻ひも・荷札といったところが相場であった。軍隊の経験がある再役者は軍隊手帳・下士官適任証などの証明書、ときには勲章や従軍記章も入っている。兵営に入ると、奉公袋の中身は個人的ロッカーである木製の手箱に移し預金通帳は班長に預ける。現金や印鑑などの貴重品は奉公袋をふた回りほど小さくした貴重品袋に入れて首からぶら下げる。奉公袋と貴重品袋とは色も形も同じ大小で一対となる袋だが、貴重品袋の存在は軍隊内に意外に窃盗が多かったことを物語っている。
今、日本政府の有事法制化の動きが再び「滅私奉公」の精神を復活させようとしている。 |
− 日満露支交通国境大地図 − |
 |
(大阪毎日新聞社編纂) 昭和10年1月3日発行(第18566号付録)
日本領土は赤、満州は紫、ソ連は緑、中国は黄に色分けされている。(スケール 110
X 78) |
− 外套 − |
 |
| 元901海軍航空隊海軍二等整備兵曹、シベリア抑留中着用外套 |
− 千人針 −
<千人針の中には、日の丸が血で書かれた物や、
お守りが30ほど入っている物もある> |
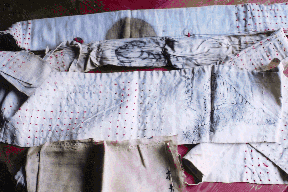 |
千人針は、出征兵士が無事に帰還できることを祈って多数の女性によって作られました。日中戦争開始とともに全国的に広まりました。日清・日露戦争の頃には、すでにハンカチほどの布に糸で結び目を作るという行為はおこなわれていたようで「千人結」と呼ばれていました。
婦人会活動に取り入れられ、作り手は出征兵士の縁故者ばかりでなく、多数の千人針が作られ戦地へ送られるようになりました。しかし、戦況が激しくなると、規制されたこともあり、あまり作られなくなりました。
千人針の起源は、無事に帰還して欲しいという願いを大勢の人の力に頼った合力祈願がはじまりで、これにさまざまな民間信仰が付随して発展したものと考えられています。
寄せ書きした日の丸も「死線を越える」という思いを込めて兵士に贈ったといいます。これも大勢の力でもって無事生還を願ったもののひとつといえるでしょう。「虎は千里を走り千里を帰る」との言い伝えから寅歳の女性は自分の歳の数だけ縫うことができました。このほか、千人針の布に十銭・五銭の穴あき硬貨を縫いつけたが、これは「死線(四銭)を越えて苦戦(九銭)を越えて」の語呂合わせで生まれたものであります。
戦地では出征兵士は戦地で、千人針や家族・親類から渡されたお守りなどを腹に巻いたり、帽子に縫いつけたりしました。千人針を銃弾よけではなく、腹巻きとして使用していた人もありました。
千人針やお守りを付けていると「守られている」と心強く感じた人もあれば、シラミやノミの巣となった千人針を身につけることに抵抗を感じた人もありました。千人針の布を梅酢につけて乾かすと、戦地で水が無くなったときや胃腸病で苦しんだときにかんで助かったこともあったそうです。
千人針を女性が作るという点では、沖縄の兄弟の旅立ちに際しては常にオナリ神(姉妹)が守っているという考え方、さらに兄弟の旅立ちにはオナリ神の髪を守り袋に入れ、オナリ神が身に付けていた手ぬぐいを渡す習俗などが、千人針に通じるのではないかと考えられています。沖縄では、千人針も妻ではなく姉妹が中心となり作っていたそうです。 |
| |
NEXT
|