−
愛国婦人会高知県支部・
大日本国防婦人会のたすき − |
 |
北清事変の翌年、1901(明治34)年に奥村五百子によって「愛国婦人会(愛婦)」はつくられた。
民間団体であったが在郷軍人会とともに軍を背後から支えた一大組織であった。主婦のシンボルの白い割烹着に会のたすきをかけ、出征兵士の湯茶の接待、傷病兵の慰安、遺族の援助に駆け回り、平時に入っても戦争後の不況に苦しんでいる主婦等に内職を世話したり、社会福祉団体の性格も備えていた。
1930年、文部大臣訓令「家庭教育振興に関する件」で「大日本連合婦人会(連婦)」がつくられ、満州事変後の軍国ムードに乗って、1932年「大日本国防婦人会(国婦)」が関西を中心につくられた。国婦はエリート意識がないだけにみるみる会員を増やしていった。
この3つの婦人団体は互いに競い合いながら、軍事援護、愛国貯金などに乗り出した。千人針集めや前線へ慰問袋を送る運動だけでなく、街頭に立って洋髪の女性に"パーマネントは止めましょう“のビラを渡してプレッシャーをかけたり、和服の長い袂をハサミで切り落とす実力行使も見られ、お上の威光をカサにきての振る舞いが多くなり、"泣く子も黙る婦人会“とも言われるようになった。
1937年、日中戦争開始ともに「国民精神統動員中央連盟」が発足。1940年には「大政翼賛会」が発足して、生活必需品の統制が相次いだ。1942年、3婦人団体は「大日本婦人会(日婦)」に統合され、翼賛会傘下に入った。
政府は1938年2月、「家庭報告三綱領・実践14項目」を発表。皇民教育を全面に出し、貯蓄奨励から食事・服装にいたる実践項目を示し、国民生活の隅々まで絡め取ろうとした。1942年5月には「戦時家庭教育指導要綱」(母の戦陣訓)を発表。婦人団体の方でも「戦力増強婦人総決起運動申し合わせ三条」を出し、「誓って飛行機と船に立派な戦士をささげませう」「一人残らず決戦生産の完遂に参加協力いたしませう」「長袖を断ち、決戦生活の実践に蹶起いたしませう」と言うまでになった。
新聞、雑誌、ラジオもまた国を護るための死を美化し、母を聖化した。『家の光』や『主婦之友』は、座談会で「今まで大事に育ててきた子どもに『死ね』と一言いうて送り出す強さが日本を支えている」とのべさせ、戦争協力にやっきとなった。
2000万人の女性を組織したといわれる日婦が、部落会、町内会、隣組と一体となって戦争遂行に果たした役割は大きなものがあった。 |
− 誓神州護持の血書 − |
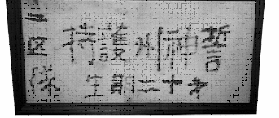 |
仙台にあった陸軍予備士官学校で、1944(昭和19)年の卒業式に際し、生徒が教官におくった血書。68×35cmの額に収められている。
神州とは神の国、日本のこと。多くの若者が「神州不滅」を信じ、現人神であった天皇を中心にした国家のため命を捧げた。敵艦に体当たりする「特攻精神」も同根の「狂気の精神」、人間の命を大事にする人間思想は微塵もなかった。
大東亜戦争の呼称は、支那事変(日中戦争)も含めて、対米英戦を呼ぶことにする閣議決(昭和16年12月12日)によるが、この戦争も「聖戦」とされた。
日本軍は皇軍と呼ばれ、軍歌には「神兵」の言葉がある。昭和17年4月、ビクターから発売されたレコード「空の神兵」は、その1月にセレベス島のメナドに降下した海軍落下傘部隊、2月に南スマトラのバレンバン間近に強行降下した陸軍空挺隊などの日本軍パラシュート部隊をうたったもので、歌詞は感銘直裁で美しく、曲もすぐれていて、たちまちのうち全国で愛唱されるようになった。
しかし、「神州不滅」を信じたたかった皇軍の内実は、「三光作戦」であり、女性に対する性暴力であり、細菌兵器や毒ガスの使用であり、人間を食らうという犯罪者集団であった。戦争の責任者の追求とともに、なぜこうなったかその原因をさぐらなければならない。 |
| |