−高知空襲で焼けた貯金箱のお金− |
 |
去る2003年4月20日、高知空襲で焼けた貯金箱のお金が草の家に寄贈された。寄贈者の西山芳恵さん(高知市中水道)によると、この貯金箱は高知市本町1丁目で高知空襲を受けた。
爆弾の熱で貯金箱のお金が溶け、約1kgの固まりになった。表面に書かれた「一銭」、「昭和十三年」、「大日本」などの文字が鮮明に読めるお金もある。溶けてしまったお金は、空襲当時の爆弾の威力、被害の状況を物語っている。 |
−血糊のついた軍服− |
 |
この軍服は1937(昭和12)年、上海近郊の羅店鎮の攻防戦で負傷した中隊長○さんの着ていたものである。
上海の喉元にある羅店鎮白壁の家を攻めた和知部隊(44連隊)は中国兵の激しい抵抗にあって立ち往生。死傷者続出の激戦となった。当時の新聞は和知部隊の勇蒙果敢ぶりを大々的に報じたが実相は悲惨極まりないものであった。(1991年中国平和の旅でこの地を訪れ、現地の住民の聞き取り調査をした。記録は草の家ブックレットNO1「前事不忘 后事之師」にある)
中隊長だった○さんが草の家にこの軍服を資料として保存活用してほしいといってもってきて下さったとき私は聞いた。「夏の暑いときこんな軍服を着ていたのですか。写真でみる限り兵士はユニホームでたたかっていますね」「いやこの軍服をきて正装したのは、包囲され自分の部隊は最後だと思い。この軍服を行李から出し、部下の兵士に靖国の杜で会おうと挨拶をし立ち上がったところを中国兵に狙撃されたものだ」と答えた。弾丸は右腕を貫通し、腹部に達したが千人針を腹に二重三重にまいていたので助かったとのことであった。 |
−レコード「出征兵士を送る歌」− |
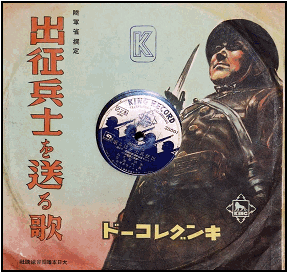 |
「出征兵士を送る歌―わが大君に/召されたる」
日中戦争2周年を記念して、1939年大日本雄弁会講談社は「出征兵士を送る歌」の作詞・作曲を公募した。後援は陸軍省。1等賞金1500円に、作詞12万8592点、作曲1万8617点が応募。生田大三郎作詞・林伊佐緒作曲に決定した。11月3日、永田絃次郎・長門美保の歌でキングから発売。 |
−小学生の作品− |
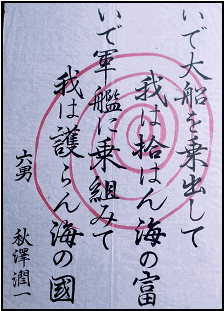 |
いで大船を乗出して 我は拾はん海の富
いで軍艦に乗組みて 我は護らん海の國
六男 秋澤潤一
達筆で書かれている小学生の作品、戦争に利用された教育の姿を赤裸々に見せてくれる。1941年、文部省が発行した手本の教師用指導書、「テホン(上)教師用」(大阪書籍)の内容を見よ。最初に「藝能科指導の精神」が書かれている。
「一 皇国の道の修練
藝能科教育の要旨は、先づ第一に皇国の道に側つて初等普通教育を施し国民の基礎的錬成をなすにある。・・・」
憲法や教育基本法の改悪が迫ってくる最近の情勢に示すことが大きい資料である。「心の教育」に代弁される教育現場の反動化、保守化から子どもたちを守るために抵抗すべきだ。 |
−戦時中の伝単(でんたん)− |
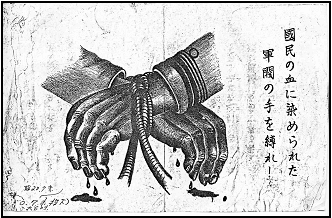 |
「国民の血に染められた軍閥の手を縛れ!」
1945年7月末、投下された伝単に書かれている文章で、アメリカ・イギリス軍が日本軍兵士にむけ作ったものである。戦争の時代には「ビラ」、「チラシ」という言葉とともに「伝単」も日常語の一つであった。「伝単」は中国語をそのまま日本語に読み替えた言葉である。
日本軍とアメリカ軍の心理戦に使われた伝単は、日本陸軍参謀本部がアメリカ軍を含め、外国軍にむけ作ったものと、アメリカ・イギリス軍が日本軍、日本本土の市民にむけ作ったものなどがある。アメリカ軍が日本兵士にむけた伝単を見ると、自軍の圧倒的な兵力を誇示、日本軍の兵力不足をつく、日本軍の敗色濃し、理性にうったえる、「生命の大切さ」をうったえる、投降をうったえる内容などがある。
日本の市民にむけた伝単は、敗北の情勢、日本軍指導部批判、自由への呼びかけなどの内容が書かれている。草の家が所蔵している戦時中の伝単は、もう一つの戦争、心理戦の様子を物語っている。(参考文献:紙の戦争伝単、エミール社、1990年) |
| |
NEXT
|