−
1937年(昭和12年)の新聞スクラップ − |
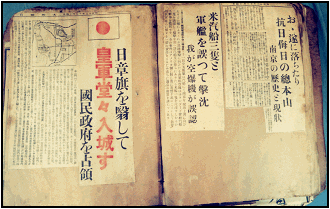 |
当時の社会像を何よりよく反映している新聞スクラップ。 1937年10月から12月までの大阪毎日新聞と高知新聞の記事が整理されている。いくつかの目立つ記事の題目を書いて見れば次のようだ。
和知部隊の南翔攻略祝賀の大提燈行列
今夜六時から擧行 主催
高知新聞社
高知市主催で大祝賀會を開催(11月13日)
皇后陛下 戦死 殉職者へ畏し御歌を賜ふ
御紋菓と御ともに(12月1日)
南京城外に殺倒す
紫金山麓の敵陣を占領
先鋒部隊 中山陵前に突出(12月9日)
閑院宮殿下、靖国神社参拝(12月12日)
日章旗を翳して皇軍堂々入城す
国民政府を占領(12月14日)
新聞記事を読んだら日本軍の中国侵略の過程を良く分かることが出来る。特に注目されることは上の写真を見れば分かるように戦争と係わるすべての記事の書き起こしに大きく日の丸が描いてある(白黒の新聞の中で唯一に赤色の日の丸)点だ。一方当時の新聞記事の中で天皇と係わる記事は何より明らかに天皇の戦争責任を証明している。 |
−灯火管制用電灯カバー− |
 |
灯火管制は、すべての灯火を消滅あるいは遮蔽することにより、来襲してくる敵機の攻撃目標をまどわそうとするものである。太平洋戦争がはじまり空襲の危険度が高くなるにつれて、灯火管制用電球や電灯カバーなどいろいろと考案され、各家庭にそれらの設置が厳しく指導された。なお、防空用具として備え付けるよう指導されたのは、家庭用として、防火用水、バケツ、ホース、防火用砂、筵、火叩き、水柄杓、作業服、非常袋、救急剤、防空頭巾、防毒面、隣組に対しては防火貯水槽、軽便ポンプ、シャベル、梯子などであった。(「戦前戦中」用語ものしり物語、北村恒信、1991、光人社、180-182より)
|
−出征兵士を送る幟− |
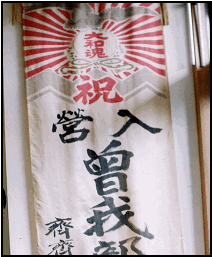 |
赤紙がきて兵士が入営するときこういう幟や日の丸を揚げて見送った。
この幟の大きさは40cm×162cmあり、上部にトビの絵、その下に大和魂、祝、入営、名前(曽我部致雄)、チチハル駅友会と書かれている。
草の家が所蔵している幟には全て「祝」という字があり、天皇のため死ぬことをたたえた当時の状況がわかる。しかし国民のなかには自分の息子を戦地におくるのを忍びず、かくれて泣いていた母親もいた。いずれにせよ戦時中は本心を表わすことはできなかった。 |
−戦時中の子どもの雑誌− |
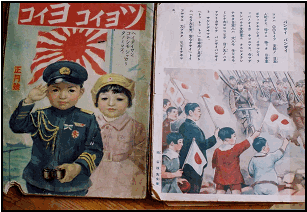 |
「ツヨイコ ヨイコ」第13巻第10号、(1944年、小学館発行)
戦時中1932年から毎月に発行された子どもの雑誌のタイトルである。1944年正月号の表紙には赤色の鮮明な軍艦旗の横に次のような言葉が書いてある。
「ヘイタイサン、コトシモ シッカリ タノミマス」
本の中身を見ると最初の頁には戦争遊びをしている子どもたちの絵(絵:山下大五郎)とともに次の詩が書いてある。
アノ ハタヲ ウテ
アメリカヲ ウテ、
イギリスヲ ウテ、
カチヌク オシャウグヮツノ
トツゲキ ダ。
この他には、占領地フィリピンでのことを描いた「ニッポンタウノ ハナシ」(作:尾崎士郎、絵:田代光)、大本営海軍報道部海軍少佐の浜田昇一が監修した絵巻物語「ニッポンマル」(作:山本和夫、絵:黒崎義介)、折り紙「ヤサシイ
グンカン、ツクリカタ」(作:芳谷まさる)などが載せている。子どもの雑誌だと思わないくらい全ての内容が侵略戦争を美化する話である。特に絵のなかでは数多く描いている鮮明な日の丸が目立つ。
有事法制の成立に続いて、教育基本法の改悪を通して子どもに「愛国心」「日本人としての自覚」を強要する政府、自民党の動きが強くなっている。
戦時中の子どもの雑誌は、子どもの“心まで戦争に動員”させた恥ずかしい過去を今日も語っている。 |
−帝国在郷軍人会特別会員徽章と表札− |
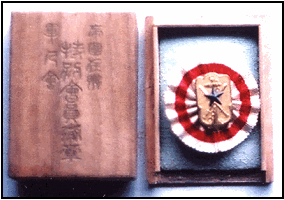 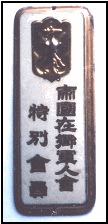 |
在郷軍人は現役として旧帝国陸海軍に属していていない予備役(後備役 帰休兵)などの退役した軍人で、平時は一般人として生活しながら、定期的に「教育招集」や「簡閲点呼」を行い、戦時には必要に応じ招集され軍務に付いた。在郷軍人会は、1910年(明治43年)“帝国在郷軍人会”として設立され、各町村には分会が置かれ、第2次世界大戦中は軍国主義教育や大政翼賛体制を地域社会で下支えする役割を果たしていたが、1945年8月15日の敗戦、旧帝国陸海軍の解体にともない、1946年解散された。
「帝国在郷軍人会特別会員徽章」は会員が服の胸につけていたバッチである。徽章の左下にある写真は在郷軍人会会員の家につけられた表札である。表札には「帝国在郷軍人会特別会員」と書いてある。 |
| |
NEXT
|