− 皿
支那事変(1937年)戦争記念 − |
 |
| 帝国万歳の文字が四隅にある(30cm×30cm) |
− 1937年(昭和12年) 12月17日、南京占領を祝う入場式の絵柄襦袢 − |
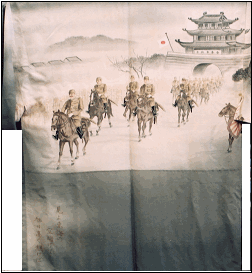
|
| 1937年12月13日、激しい攻防の末、南京を日本軍が占領。日本国内ではちょうちん行列をして中国首都占領を祝った。しかしこのとき南京大虐殺事件は進行していた。 襦袢には「見よ東海の空あけて」の歌詞も染められている。 |
− 軍隊手帳 − |
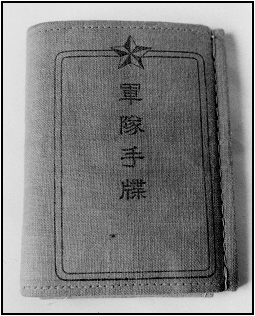
|
入営すると必ず貰う一種の身分証明書。
ここに階級の昇進や部隊の配置換えの時書き入れて貰う。兵役服務中はずっとついてまわった。
草の家にある高橋讓の「軍隊手牒」をみると最初のところには「軍人勅諭」がとくに朱色の活字で印刷してある。この「勅諭」は、明治天皇が軍人に対して下した〈訓戒〉である。それは、「一、軍人は忠節を尽すを本分とすへし」からはじまる「五ケ条」の〈訓戒〉と、それに先行する〈前文)、あとの〈後文)、この3部構成になっていて、最後の日附けは明治15年1月4日である。その次にも大正元年7月31日、昭和元年12月28日などの勅諭が続いて書いてある。
その次は「軍隊手牒に係る心得」、「應召及出征時の心得」が書かれてある。
ところで、この「軍隊手牒」の中でも、とくに多くのページを占めているのが「戦陣訓」の部分で、全文は22ページに及び、「勅諭」とは別の、写真植字に似た小さめの美しい字体の活字で印刷されている。
とくに「戦陣訓」の中の「第八 名を惜しむ」の、
「生きて虜囚の辱を受けず、死して罪禍の汚名を残すこと勿れ」
の一項が、多くの悲劇を生んだことも否定できない。
たしかに、この一項にこだわりすぎたため、またこの一項について執拗に教育されたため、死ななくてもよかった兵隊や非戦闘員が死んだ事実は少なくなかったはずである。そこに〃軍隊残酷物語”を見出す考え方を非難し得る人が何人いるか。別の項(「英霊」)にも書いたが、不名誉な死に方をした廉で、遺骨の入った箱が荒縄でがんじがらめにされていたという例もあるくらいだから、死んでも「辱め」からは解放されないわけである。(三国一郎、戦中用語集、1985、岩波親書No.310、170−173)
その次には兵隊個人の履歴欄がある。 |
− 鉄兜(てつかぶと) − |
 |
もともと鉄製のかぶとは刀槍の斬り合いや飛んでくる矢から頭を防ぐものだが、やがて銃器の発達につれて重い甲胄を着ていては動きが鈍く、よい標的になるばかりで戦術も運動戦となり、軍装もそれにつれて軽快になってきた。
1914年(大正3年)、第1次世界大戦が始まると弾薬の破壊力は強力となり、ふたたびその破片やふりそそぐ土砂から頭を守る必要が出てきた。これが近代の鉄かぶとであり、その条件は銃の直撃貫通は止むを得ないが流弾や土砂には耐えられる強さ、量産がきく鉄製で重さ1キロ程度のものとされた。
材質や硬度、デザインなどはお国ぶりに合わせて各国軍独特の型となったが、性能は大同小異である。ドイツ語でHELMET、英語では他の防暑用ヘルメットなどと区別して、STEEL
HELMET、フランス語ではかぶとと同じCASQUEという。
それまで鉄かぶとのなかった日本軍でも世界大戦の戦訓をふまえて、さまざまの試作品を作り出した。この段階で仮の名称を鉄兜または鉄甲と呼んでいたが、試行錯誤の未にようやく1930年(昭和5年)、はじめての国産第1号を作り出した。
制式名は九〇式鉄帽で、これより鉄かぶとは俗称となる。
海上戦闘を仕事とする海軍は鉄帽の開発に熱意が薄く、1932年(昭和7年)の第1次上海事変の陸戦隊などはイギリス軍の鉄帽を輸入して装備している。
(寺田近雄、日本軍隊用語集、1992、立風書房、195-196)
|
− 憲兵腕章
− |
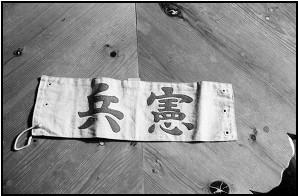 |
憲は日本国憲法や大西洋憲章の憲で、字も重々しく模範・手本・命令などの意味がある。これに兵をつけた憲兵は兵語辞典によると、「陸軍の一兵科にして軍人の犯罪を取締り軍紀を維持する軍事警察にかかわる兵科」となる。
ニッポン・ケンペイは軍国主義・帝国主義・侵略主義の代名詞のようにいわれ、残虐・冷酷・暴力の暗いイメージが定着した。戦前から憲兵は治安警察の「特高」とともに、軍人だけにかぎらず国民全体の思想言動に目を光らせて、“憲兵隊に引っぱられた”という噂は“警察に引っぱられた”よりも重々しく、かつヒソヒソと耳うちされて町内に伝わった。戦争に入ると占領地の治安が憲兵の仕事となり、ゲリラやスパイの摘発はもちろんのこと、敵意をもった住民への取り締り、捕虜の管理にいたるまでその行動は峻烈可酷をきわめた。
憲兵の服装にみる特徴は、憲兵マントと憲兵腕章である。憲兵マントはフランスの巡査が着ていたような短マントで、憲兵腕章は1923年(大正12)に制定され、幅12センチの白線地に憲兵と赤書きしてある。また憲兵には上級下士官のみに許されていた軍刀、長靴、拳銃が兵の身分でも支給され、着用、携帯した。軍刀は俗に曹長刀ともいわれた下士官軍刀で、以前はサーベル型の32年式軍刀、1934年(昭和9)以降は94式軍刀であった。拳銃は口径8ミリの14年式および94式自動拳銃で、時には馬で、時にはサイドカーに乗って巡察した。
(寺田近雄、日本軍隊用語集、1992、立風書房、56:北村恒信、戦前戦中用語ものしり物語、1991、光人社、145-146) |