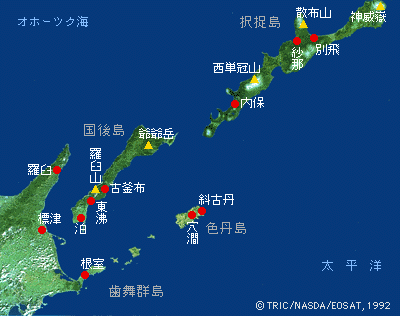
↑ 「北方領土の基礎知識」より(アドレスはコラムの最後に)
北方領土は、いま(中編)
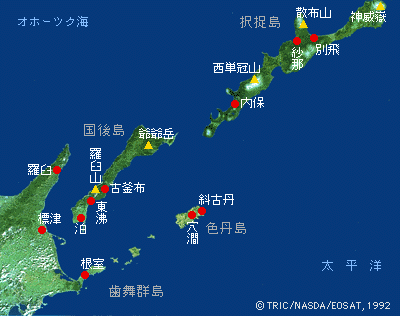
↑
「北方領土の基礎知識」より(アドレスはコラムの最後に)
【歯舞諸島】(はぼまい・しょとう)
歯舞。アイヌ語で「流氷のある島」。
歯舞群島、とも呼ばれる。根室半島の陥没により、離島となったと言われている。
大小20個ほどの島からなっていて、根室半島に最も近いのは「貝殻島」。
北海道の陸地から、わずか3.7kmの所にあるが、ここにはロシア国境警備隊の建造物がある。
戦前に日本が造った灯台も、根室側から見えるそうだ。
終戦時には852世帯、5,281人の日本人が住んでいたが、現在は警備員以外は無人である。
よって、主だった都市はなく、全体的に草原に覆われている。
【色丹島】(しこたんとう)
「色丹」はアイヌ語で、「大きな集落のある地」。
国後や択捉に比べて一回り小さく、歯舞諸島にまぎれ込んでいる。
この島は、なんといっても湾である。北欧でよく見られる、入り組んだ入江のフィヨルドが
ここでも見られる。(日本人は見られないが)
海抜300m程度の、なだらかな平原が続く。
気候は、四島とも概して悪い。
低気圧の通り道であるため、霧が晴れず、風も強い。だが、北海道ほど冬の寒さは厳しくない。
終戦時(敗戦時)の人口は、206世帯、1,038人。
現在は、ロシア人が2,300人ほど居住しており、北部に二つの集落(斜古丹、アナマ)があるという。
斜古丹(ロシア名:マロクリリスコエ)には、ホテルと百貨店もある。
アナマ(ロシア名:クラボザボツコエ)にはサッカー場がある。
ホテルといっても、誰が宿泊するんだろう。
ところで、この島には、1995年1月には3,746人の定住者がいたという。
しかし前年(1994年)に起こった北海道東方沖地震で、極東随一の規模と言われたカンヅメの加工工場が崩壊し、操業不能となったことから路頭に迷い、ロシア本土に戻る住民が多発した。
そのため、2年間で2,300人にまで人口は減ったそうだ。
色丹島周辺では、地震以降の電気料金が大幅に値上げされたらしく、住民の生活難に拍車をかけているのみならず、燃料である重油の不足で停電も多いという、惨憺たる状況だという。
また、地震による廃屋の撤去費用も出せず、放置されている所も多いようだ。
2つあった病院も地震で崩壊し、1995年10月には日本政府の人道援助で、プレハブの診療所が建設された。
日本政府は、この手の「人道援助」なるものを数多く手がけており、日本国のイメージアップに躍起になっている。
【国後島】(くなしりとう)
「国後」は、アイヌ語で「草の島」。
北海道、知床半島と根室半島にはさまれる感じで、細長く伸びる島である。
特に知床半島に近く、知床の温泉から国後島が一望できるくらいである。
逆に、国後のロシア人たちは、知床で夏に行われる「花火」を見物しようと、海岸沿いに集まるほどだという。
本当に北海道に近く、これがロシア領なのかと目を疑うほどだ。
とはいえ、知床半島に面した海岸線には、都市はまったくない。
国後島は、前2島と対照的に活火山帯であり、1973年には北部山岳地帯で大噴火している。
平野はほとんどなく、河川の流れは急だという。
温泉が15箇所あるそうだが、現在使われているのは1つだけである。
人口は、1945年の敗戦当時は1,327世帯、7,364人。
現在は3,800人ほど。もちろんロシア系住民であり、日本人は皆無。
主な都市は、戦前から栄えていた古釜布(ふるかまっぷ)、東沸(とうふつ)、泊(とまり)など。
東沸には、メンデレーエフ飛行場もある。
また、北方領土への「入国審査」ができるのも、この島だけである。
アクセスは、きわめて悪い。
島南部の古釜布−泊の間には林道のようなものがあるが、北部へのルートはなく、
山間部あるいは海岸沿いの断崖絶壁の間を、六輪駆動車で通行しなくてはならない。
戦前は、島北部にも集落はあったが、現在ではすでに自然に還っているようだ。
旧集落では、土を掘り起こすと「大日本麦酒」(戦前のビール会社)のビンが出てきたり、日本語の文字が入った食器が出てくるそうだ。
そして、山間部にはヒグマが数多く生息。その遭遇率は、北海道・知床半島の2倍だという。
食料が豊富で、なによりハンターがいない。そのため、数も多く、体も大きい。
都市間を結ぶ林道以外のアクセスは無いに等しいため、島北部では手付かずの大自然が残っている。
日本にこの島が返還されたら、おそらく「展望台」などがつくられ、観光客らが押し寄せることだろう。
さて、都市部はどうか。
歯舞諸島・色丹島・国後島は、ロシアでは「サハリン州・南クリル地区」とされている。
人口3,600人の古釜布(ロシア名:ユジノクリリスク)には、その地区の行政府がある。
島の人口のほとんどが、この古釜布に住んでいる。
ほかには音楽学校や、「日本人とロシア人の友好の家」という宿泊施設があるらしい。
それにしても、日本人がいない「友好の家」というのは、どうかと思うが。。
この古釜布を見た人の話によると、
「港には廃船が沈んだまま」
「拿捕されてつながれている日本漁船が、すごくきれいに見える」
「島内の商店は、品揃えはいいが物価は意外と高い」
のだそうだ。
そして、やはり1994年の、北海道東方沖地震で被害を受けている。
この地震では釧路市でも震度6(当時)を記録したが、北方四島はさらに震源に近く、
釧路以上の揺れがあったものと思われる。
ロシア製の集合住宅ゆえ、建物が少なからぬ被害を受けたことは想像に難くない(失礼)。
病院は復旧したが医薬品が足らず、日本による人道支援を受けている。(だめじゃん。)
「ナ・ルベジェ」(国境にて)という新聞が週2回発行されており、テレビも3チャンネルある。
【択捉島】(えとろふとう)
エトロフ。ロシア語ではない。アイヌ語で「岬のあるところ」。
エトロフ。「捉択」でもなければ、「促捉」でもない。どういう根拠で、この当て字になったのか。日本に帰属されれば、この島の北端が「日本最北端」(北緯45度33分)となる。
広さは鳥取県ほどもある。
千島火山帯にあるため、例によって火山活動が激しい。温泉もある。
1800年には、この島の北端に「大日本恵登呂府」と書かれた標柱が建立されている。
ただ、これはロシアにとって不利な柱であるため、撤去されている可能性もある。
戦前の人口は3,608人。現在は8,300人。
この島はサハリン州・クリル地区とされている。(ほかの3島は南クリル地区)
都市は、いくつか点在している。行政の中心地である紗那(しゃな、ロシア名:クリリスク市)。人口2,200人。
漁村で港湾施設のある内岡(なよか、ロシア名:キトブイ)。
漁村の有萌(ありもい、ロシア名:ルイバキ)。
水産加工業の別飛(べっとぶ、ロシア名:レイドボ)。人口1,500人
滑走路2,200mの滑走路がある、かつての軍事基地、天寧(てんねい、ロシア名:ブレベスニク) 。
天寧の近くには、日本人が「真珠湾攻撃」のときに使用した単冠湾(ひとかっぷわん)もある。
紗那には、1981年頃に開館した「日本博物館」がある。
動物の剥製や元島民の生活用品が展示されている。
日本人が入れず、おまけに開館した年も分からぬ日本博物館とはいかがなものか。
またこの街には、北方四島ではおそらく唯一の、レーニン像がある。
かつて、紗那には日本の郵便局があったが、今ではロシアが、その建物を使って郵便局をやっている。
水産加工場は最新設備を導入し、生産を行っており、経営状態は良好のようだ。
震災の影響もさほど受けておらず、北方四島の中では、最も経済的に安定した島であるようだ。
とはいえ、冬に漁業はできず、5月初旬までは集落単位で孤立してしまうらしい。
ところで、ロシア側の固定資産管理はお粗末なようで、
天寧の空港は、コンクリートの間から雑草が茂っているという。
おまけに、戦闘機の残骸が放置されているようだ。
択捉島では、「クラスヌイ・マヤーク」(赤い灯台)という新聞が週2回発行されている。
テレビも、国後島と同じく3チャンネルある。
以上が、四島の概観である。
最後に、ロシアの状態などをからめて見ていきたい。