 |
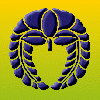 |
 |
| まる九字 | 下がり藤 | まる九字 |
 |
 |
|
| まる丸字 | ||
 |
||
時に分かれた大分市宗方の安東家も現在まで使用されていることから、
当初から表紋として使用されていたものと思われる。
戦に明け暮れた時代背景から、同士打ちを避ける意味から下がり藤の紋から
まる九に変えて使用したと思われる。
鎌倉以前には、まる九は本来、裏紋または女紋として使用されていたのでは
と思われ、藤原の九条家の女性が安東家に婚姻したことで女紋としていた?
のではと推測される。
また、一方では上の墓石にあるようにまる丸字であり、まる九と使い分けを
していたのかもしれない。
こちらの方が、安東氏の豊後入国以前のルーツ解明に根拠が生まれる。
安東氏は別姓を丸氏であったとすると、豊後入国以前は関東の安房国を発祥
とする丸氏とつながる。このことで千葉県安房郡丸山町町史では以下の
ように解釈している「大井城のことであるが、その所在を丸山町大井と
館山市大井のいずれにするか、また双方とするかなど論議のわかれる
ところである。問題の発端は、元禄十三年(1700年)水戸彰考館の
丸山可澄が、紀州三浦家本に拠って編集した「正木家譜」の正木時綱
の条の記述にある。
すなわち、「安東氏(丸別号)保大井城攻之時綱遂抜矣。而後郡郷悉服。」と
あることによる。正木時綱は相州三浦氏の出で、安房に来て里見氏の援助に
より正木氏の初代となった人物であるが、この家譜ではその出自や事績、
里見義豊にかんする事項についての誤りが見られ、引用の部分についても
問題がある。安東氏は丸氏の別号ではなく、館山市安東(安房郡の東部に
由来する地名)に拠った中世の豪族で、丸氏とは別の系統に属するものと
考えられ、大井の地を領し、同所の手カ雄神社の社殿を造営したことも知ら
れている。」
正木氏の出自はともかくとして、安東氏が大井城を支配していたところを
正木時綱が攻めて、以後、郡郷を悉(ことごと)く支配したことに違いはない。
大井城が館山市の大井城なのか、安房郡丸山町大井なのかは今後の論議
とするとして。
水戸彰考館の丸山可澄の言う安東氏の別号を丸氏とすることは、豊後安東
氏の家紋からしてこれを否定するものではないと思われる。
また、豊後入国初代安東常輝、2代安東左近将鑑常宗、3代常任、常之、
常秀と坂東の上総の支配者が名乗った「常」を歴代名乗っている。
このことからも安東氏が安房、上総、と関係あることが裏付けられる。
丸氏は源頼朝が石橋山の戦いで敗退して、安房にたよった際から、頼朝に
協力した経緯があり、以後、頼朝の家臣として千葉常胤を筆頭に抜擢されて
いったことは「吾妻鏡」などの史実誌にあるところである。
また、岡山の系図調査では一人者であられます清水さんの調査によりますと
岡山県の土橋安東家で使用されている家紋は「まるに丸」とのことです。
これには、非常に興味あることです。
通常家紋は植物や図柄を用いるのが一般的で、漢字、数字でも一、二、三
ぐらいがありますが、九は熊野の九鬼水軍ぐらいです。
同じ安東の氏で家紋が「まるに丸」と「まるに九」は関係ないとは思えません。
鎌倉初期に豊後に入国した安東氏と美作に入国した安東氏(千葉氏に随行
した)が同族であった可能性を否定しがたい事実と思われます。
熊本市薬園町にある久本寺境内にある肥後細川藩の家臣の墓石にある
家紋は豊後安東氏の祖(大野郡大野町安藤)にある墓石家紋とまったく
同じ「まるに丸」であります。
豊前細川藩に安東氏が仕えその後肥後熊本に入国したことを立証し、
これは豊後安東氏が耳川の合戦以降関が原合戦に至って衰退していくに
あたり、末代子孫のために新しい主君に仕えた証でもあります。
言い伝えによれば、安東の祖は旭将軍であり、その証に家紋を「まるに丸」
としたとある。漢字「旭」のくずし字は九に点を右に打つにである。
確かに墓石には皆、点が右であり、否定しがたい。
その旭将軍とは源氏の木曽義仲がそう呼ばれていた。
義仲は元々武蔵国が本国であるが、のちに信濃に行き木曽氏を名乗った
この義仲に仕えていた、宮六位兼仗国平は長井斉藤別当実盛の外甥で、
(実盛は平家に属し)平家滅亡の後、囚人となり、 始め上総権介廣常(平)
に召し預けられ、廣常誅戮せらるるの後、 中原親能に預けらる。
「しかるに勇敢の誉あるによって親能子細を申して能直に付せしむと云々」
この阿津賀志山の合戦ででてくる宮六位兼仗国平に仕えていたのが、
安藤次であり、安藤四郎である。
中原親能は嫡男大友左近将監能直が初陣であるために百戦練磨の国平
に助太刀を要請したのである。
このとき阿津賀志山の背後よりの戦法をとったのが、国平である。
以後、安東氏が大友氏に仕え豊後入国するのである。
安東家紋付