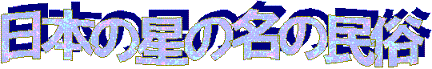 |
|
はじめに・野尻抱影氏の著書『日本星名辞典』[1973,東京堂出版] ・内田武志氏の著書『日本星座方言資料』[1949,日本常民文化研究所] ・桑原昭二氏の著書『星の和名伝説集-瀬戸内はりまの星』[1963,六月社]
呼称について
対象とする範囲【天体】星座を構成する主な星(恒星)が主体です。さらに、一部金星や木星などの惑星、彗星、流星、月と接近する不特定の星も 含めて分類の対象としました。 【時代】主に1970年代以降の調査記録を対象としているため、日本の星の名が利用された時代として、近世末から昭和初期ころ までが想定されます。農・林・漁業を基本とした生業や暮らしに星が重要な役割を担っていた時代であり、ここに掲載した呼称の 多くは、そうした時代の人びとが星を自然物の一つとして捉え、活用を図ることを目的に命名したものです。 【地域】北海道から沖縄県まで、全国各地に伝承された星の名が対象ですが、西日本における記録はその大半が2012年以降の 調査によるものであり、いわゆる伝統的な星名は少ない傾向を示しています。
表記について
解説の内容【意味】星の名の読みを「ことばの意味」として表したものです。語尾に(転訛形)とあるのは、本来の意味が変化した読み方と なっていることを示しており、同じ表記であっても実際には微妙なニュアンスの違いが認められることがあります。 【星座名】天文学上の星座および呼称の対象となる星について、固有名あるいはバイエル記号、フラムスチード番号などで示しました。 ただし、一部標準和名で表記したものがあります。 【伝承地】現地調査によって記録された星の名の伝承地域を、北から南へ都道府県別に示しました。調査記録が豊富な地域では、 その分記載された呼び名も多い傾向にあります。しかし、一部のローカル的な星名を除けば、伝承地に記載がなくてもその星名が 利用されていた可能性は十分に考えられることを付記しておきます。 【分類】本書の特徴の一つは、すべての星の名について以下のような分類を行ったことです。これは、天文学的な属性と暮らしに かかわりの深い項目の組み合わせにより構成されており、解説ではそれぞれの星名について、第1類から第2類、第3類までを 順に表記しています。 〈第1類〉:天文学的な属性 星の名が形成された天文学的要素として、どのような属性が注目されたのかを示し、①時・季節、②位置関係、③色、④明るさ、 ⑤配列、⑥方角、⑦数、⑧動きで分類しました。 〈第2類〉:民俗分類Ⅰ 星の名の意味が環境や暮らしのどのような領域と深く結びついているのかを示し、①自然、②生業、③生活、④人、⑤知識で分類 しました。 〈第3類〉:民俗分類Ⅱ 民俗分類Ⅰの項目について、さらに具体的な要素に細分化したものです。分類Ⅱでは、地形・地理・気象・天文・生物・農業・ 漁業・交易・用具・衣食住・行事・信仰・娯楽・家族・行動・人名・感覚・数詞・状態・従属・その他の21項目を用いています。 その他の説明【天文データ】星座名や等級などの表記は以下に示す文献を参考としました。 ・『全天恒星図(新版)』広瀬秀雄、中野繁(著)[1966,誠文堂新光社] ・『フィールド版・スカイアトラス』村山定男(監訳)、白尾元理(訳)[1991,丸善] ・『天体観測ハンドブック』大田原明(著)[1995,誠文堂新光社] ・『天文年鑑2005年版』天文年鑑編集委員会(編)[2004,誠文堂新光社] |
