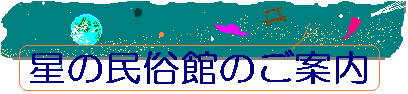は じ め に
星の民俗館は、1974年から2019年にかけて星の民俗に関する調査を実施し、その間の聞き
とりによる記録を分類整理し、蒐集資料とともに一般に公開することを目的としています。
日々の暮らしや仕事において、私たちが太陽や月、星とどのようにかかわってきたのかを振
り返ることは、決して意味のないことではありません。とはいえ「星の民俗」といっても、
いったい何のことかと思われる人も多いことでしょう。
天文学や物理学など科学的な対象としての「宇宙」は、人類にとって永遠なる未知の世界
です。その一方で、私たちは無意識のうちに神話や伝説の世界で、あるいは日常の暮らしを
背景とした「もうひとつの宇宙」とともに生きてきました。そうした何気ない話題にスポット
をあて、自然とともに生きた人びとの想いを探求したのが「星の民俗館」なのです。
日本人と星
かつて、日本人は星に対してほとんど関心をもっていなかったと考えられた時代がありま
した。近世までは、ごく一部の史料で星に関する記述が散見される程度であり、そうした捉
え方も無理からぬことであったのです。しかし、その後の民俗学を中心とした常民文化の調
査が進展するなかで、日本では広範で豊かな「星の文化」が育まれてきたことが明らかとな
りました。現在ではむしろ、日本人ほど星というものを自然の一部として純粋に捉え、そし
て利用した民族も少ないのではないかと考えられるほどです。
星(太陽や月などを含む)の民俗は、日本で生まれた星の名前(和名)を始めとして、言
い伝えや俚諺などの伝承、星にまつわる信仰、行事や有形文化財にいたるまで、幅広い項目
を対象としています。従来は、これらを一元的に扱う取り組みがほとんどみられませんでし
た。ただし、日本の星名に関しては全国的な研究が進められ、既に体系化されています。星
に関する多くの著作を遺された野尻抱影氏は、その第一人者としてよく知られています。な
かでも、日本で命名、伝承された星の名(呼び名)を積極的に蒐集し、それらを集大成され
た業績は特筆すべきものがあります。また、内田武志氏や桑原昭二氏なども優れた業績をの
こされています。さらに、各地で独自の調査・研究に取り組んできた方々や現在も継続して
いる研究者は少なくありません。
当館の調査は、単に星の名を記録するだけでなく、それが生業や暮らしのなかでどのよう
に利用されてきたのかという点を重視した取組となっています。それでも、全国各地に埋も
れた星の伝承や有形・無形文化財の潜在性を考えれば、これまでに掘り起こされた記録はほ
んのごく一部に過ぎません。星の民俗の世界は、私たちが思い描いていた以上に奥深い領域
に及んでいるのです。
展示について
当館では、このような「人間と宇宙の文化誌」を対象として、人びとが星や太陽や月とど
のような関わりをもって生きてきたのかという点に着目しました。したがって、展示の構成
については、それらを分かりやすく解説することを重要な基盤としています。
展示室は、星の民俗に関する有形資料を中心に、解説や星の旅の随想などで構成されてい
ます。展示資料は、ごく一部を除きすべて当館の調査データをもとに構成したものです。
地域的にはほぼ日本全国をカバーしていますが、調査密度は地域により偏りがあります。特
に西日本の各地あるいは関東甲信以外の内陸部の記録は、まだまだ十分なものではありませ
ん。
記録について
公開するデータは、星の民俗館が調査した記録に基づくものですが、日本の星の民俗をす
べて網羅したものではなく、また展示内容も記録のすべてではありません。ここに展示され
ていない星名や伝承、行事、習俗、文化財等については関連するそれぞれの文献や資料を参
照してください。
また、当館では星の民俗に関する各種資料の収集も重要なテーマの一つとなっています。
かつての生活用具や生産用具を始め、信仰・行事等に付随する有形資料、そして無形文化財
を記録した映像資料など、次代への遺産として継承すべく活動中です。
|