
|
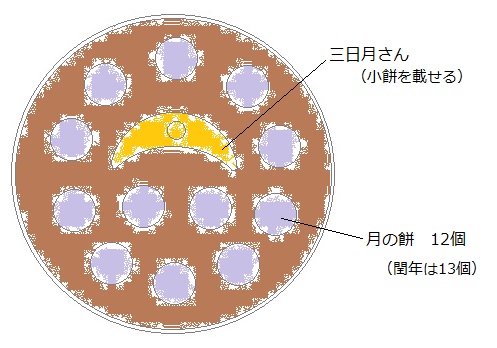
|

|
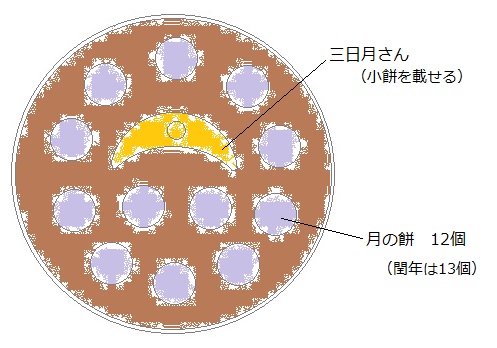
|
日本では、日月星の文化も星の名や伝承などと同様に多彩な一面をもっています。それらは、信仰や行事、文化財などに
代表されるように昭和の時代まで各地に存続していましたが、信仰・行事においては、本来の素朴な営みはほとんど
姿を消しつつあります。一方、有形民俗資料として貴重な存在である遺跡や建造物、石造遺物などは現在も健在です。
規模や形はさまざまですが、ともすれば忘れられがちなこれらの遺物を、日本の天文民俗文化にかかわる貴重な文化財として
位置付ける取り組みが求められています。信仰・行事も含めて、そこに内包された意義を正しく理解し後世に伝えることは、
自然と人の暮らしの関係について見つめ直す格好の機会となるでしょう。 |
対象とする範囲【天体】太陽、月、一般的な星などを分類の対象としました。 【時代】主に1970年代以降の調査記録が対象となります。したがって、信仰・行事など伝承の背景は近世から明治、大正、 昭和の時代を想定するのが適当と考えられます。 【地域】対象は全国ですが、項目により東日本の記録が主体となります。
展示について【展示内容】実態の聞き取り記録や現地取材をもとにまとめてあります。 【調査地】自治体名は基本的に調査当時の区分にしたがっていますが、必要に応じて新旧の併記を行っています。 |