| No |
漁具・漁法の名称 |
対象漁 |
漁具の構造・図 |
漁具・漁法 |
漁 期 |
地方名・由来・歴史・その他 |
| 1 |
ピンコ釣り |
鮎 |
 |
・竿釣り;超硬先調子
・寒狭川(現在の豊川中流部)猿橋付近で行われている。 |
6月〜9月 |
・見釣り・玉釣り
・釣り竿をピンコ・ピンコと力強く引き上げることで鮎を掛ける様からこの名が付いたものと思われる。
・明治43年12月〜45年2月にかけて長篠発電所が作られたが、その時九州方面より出稼ぎに来ていた工夫により伝えられたと言われている。 |
| 2 |
友釣り |
鮎 |
 |
・竿釣り;好みによるが一般に中調子
・みち糸は昭和35年頃までは「スガ糸」と呼ばれた40〜60番の絹糸、ハリスには馬の尾が最良とされていた。 |
6月〜9月
下りに入る直前まで釣れる |
・縄張り(餌となる良い垢;川藻が付く所)を持ち、外部からの進入を拒む習性を利用した釣りで、侵入させる鮎(友・親・おとり)を付けることからこの名が付いたものと思われる。
・江戸時代にはこの記述が見られることからそれ以前から有るものと思われる。 |
| 3 |
流し針 |
鮎 |
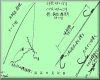 |
・竿釣り;超硬先調子
・チャラ瀬(浅くて適度な流れ)の、鮎の付きそうな場所に入れ、鮎の掛かるのをじっと待つ。 |
9月上旬より |
・糸(針の付いた仕掛け)を、流した状態で鮎が掛かるのを待つ所からこの名が付いたものと思われる。
・仕掛けの先端に、木片(マッチの棒3本)を付けるのだが、これが水の流れに沿って左右に泳ぐように流れるのが良い。 |
| 4 |
ガリ |
鮎 |
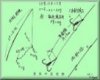 |
・竿釣り;超硬先調子
・チャラ瀬で川底を探るように引き回す。
・秋、朝夕のまずめ時、下り鮎の群れたところをねらって行なわれる漁法。 |
9月上旬より |
・ゴロ引き・ガリピン
・頭を指でガリガリ引っ掻く様に似て、川底を引き回し釣るところからこの名が付いたものと思われる。 |
| 5 |
ハヨ釣り |
カワムツ
オイカワ |
 |
・竿釣り;先調子
・餌釣りが主体(青虫、サシ、ミミズ、カゲロウの幼虫 |
時無し
最盛期は夏場
|
・冬場のものが脂がのっており美味と言われる。
冬の静かな日溜まりで、そっと釣るのである。
丸々と太り骨も柔らかい。 |
| 6 |
ヤマメ釣り
アマゴ釣り |
ヤマメ
アマゴ |
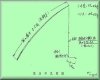 |
・竿釣り;硬調、先調子
・餌釣りが主体(イクラ、ブドウ虫、カゲロウの幼虫)基本的にはその川に棲む川虫が最良とされる。 |
冬場
(一般に2月1日が解禁日が多いようである) |
・シラメ釣り;放流する海産の養殖魚の肌が白いところからこの名が出た様である。
・大変用心深い魚で、静かに、人の気配を消して釣るのがコツと言われる。 |
| 7 |
毛針釣り(1) |
ハヨ
鮎 |
 |
・竿釣り;硬調、先調子
・深場を持った適度な流れの中で静かに釣る。 |
・夏場 |
・ハヨ毛針;カワムツ、オイカワ
・アユ毛針;鮎:本川では10センチ前後の小さなものしか釣れないが、天竜川では15〜20センチのものが一日に数十匹釣れることもあるという。 |
| 8 |
毛針釣り(2) |
ヤマメ
アマゴ |
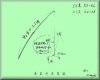 |
竿釣り;硬調、先調子
・滝下の落ち込み、流れのある浅場の岩陰を人の気配をどれだけ消して釣ることが出来るかが、釣果ににつながる。 |
・春先・秋口
・朝夕のまずめ時が最良とされる。 |
・用心深い上に、動きは敏捷である。
・先合わせではずすのは良いが、後合わせは警戒心を持たせるので最悪といわれる。
・小川の木の下などを狙うので、小さく鋭く合わせることである。 |
| 9 |
ルアー釣り |
ヤマメ
アマゴ
サツキマス
ハス
|
 |
・竿釣り;全体に腰の強いものが好まれる。
・疑似餌釣りなので先合わせとする。
|
・春先・秋口 |
・湖に沈むスプーンをマス(トラウト)が口にして遊ぶのを見て考案されたものといわれている。今では各種の疑似餌が有る。
・生き餌を好み、性格が単純で食性が旺盛なものほど良く釣れる。 |
| 10 |
夜釣り |
鯉
ウナギ
ナマズ |
 |
・投げ釣りによる置き竿
・夕方日が沈んでから、2・3時間か、朝日が昇る前1・2時間。 |
・春先3月頃から秋口10月頃 |
・春先の冬ごもりから醒めて食性の出たときと、秋の冬ごもりに向かって食性の出たときがよい。
・藤の花の咲く頃が釣り時と言われている。
・鯉釣り ・ウナギ釣り |
| 11 |
ふて針 |
ウナギ
ナマズ |
 |
・夕方深場の流れが緩やかな所へ仕掛け、朝明るくなって巣の穴に戻る前に引き上げる。
・月夜はダメ |
・夏場6月から9月に掛けて行われる。 |
・針一本の比較的短いものを「ふて針」、複数の針で長いものを「ナガノ」と呼び分ける所もある。
・川の中に「ふてて置く」沈めておくの意味。 |
| 12 |
掻き出し |
ウナギ |
 |
・水鏡や水中に潜り、ウナギの住みか(穴)に差し入れ、糸だけを残し、一呼吸置いた後、力強く一気に掻き出す:引き出す。 |
・夏場7月中旬より9月上旬 |
・ものを掻き出す様よりこの名が付いた。
・毒針;ウナギ針以前に、木綿針の太いものや針金の中央部を縛ったものを用いており、餌の腹の中に針を仕込むことからこの名が付いたものと思われる。 |
| 13 |
ズズゴ |
ウナギ |
 |
・雨降りで川が笹濁りになったとき、小川や、滝の落ち込み付近で釣る。餌は銜えているだけなので、はなす前に網で素早く掬うのがコツ。 |
・春先田植えの頃から秋口 |
・餌に蚕のマユを使い、ウナギの歯が引っかかり外れにくく工夫したものも有った。
・昔、田んぼの脇でやったら、水しぶきを上げて食いに来たのを思い出す:海野久栄談 |
| 14 |
モリ |
ウロハゼ
ウナギ
ナマズ |
 |
・水鏡で見て突く。
・水中に潜って突く。 |
・夏期
7月から9月 |
・ヤス・鉄砲
・水中鉄砲と呼ばれたヤスの部分が外れるものもあったが、危険と言うことで禁止されてから久しい。 |
| 15 |
引っ掛け |
アユ |
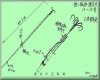 |
・水鏡で見て引っ掛ける。
・水中に潜って引っ掛ける。 |
・9月上旬より |
・潜り
・熟練を必要とする。
・泳ぐ魚を水中で引っ掛ける様よりこの名がある。 |
| 16 |
笠網漁 |
アユ
カワムツオイカワ
サツキマス
|
 |
・遡上する鮎が、滝を越そうと飛び跳ねるものを笠に似た網で受け捕らえる。 |
6月1日より9月上旬 |
・新城市出沢区の鮎滝に伝わるおよそ350年の歴史がある伝統漁法で、市の文化財指定も受けている。
・網の形が笠に似ているところから名がある。 |
| 17 |
濁り掬 |
アユ
雑漁 |
 |
・雨が降って、水かさが増し濁った時、岸の雑木の中に逃げ込んでいる魚を掬い上げる。 |
・春先から秋口 |
・川が濁ったときにすくい上げるところからこの名がある。 |
| 18 |
伏せ網 |
ウロハゼ |
 |
・水鏡で見て、上から網をかぶせる。 |
・夏期
7月から8月 |
・対象漁を上から網をかぶせるようにして捕獲する様よりこの名がある。
・網の名称;エビ掬
・対象漁俗名;スナハミ |
| 19 |
投網 |
アユ |
 |
・川底が平で、流れの少ない浅場で、魚影の濃い所へ投げ入れる。 |
・秋口
9月上旬より
・朝夕のまずめ時がよい。 |
・網が広く、円形に、水平に打ち込むのが良い。
・熟練が必要。
・網を投げ入れる様よりこの名がある。 |
| 20 |
霞網 |
アユ |
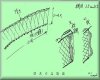 |
・一般に5・6人で組み、川岸より網を仕掛け、魚を追い込み掛ける
・水深1m前後の浅場
|
・9月上旬より |
・霞網;糸が細くて魚の目に霞が掛かったようで見えない。
・瀬網;浅い川瀬にに掛ける
・蒔き網(巻き網);船を使って大きく蒔く(巻く) |
| 21 |
巻き網 |
アユ
コイ
ウグイ |
 |
・一般に5・6人で魚の群を巻き込んで捕る
・船を使うこともある |
・9月上旬より |
・魚の群を網で巻き込んで捕らえる所から、この名が付いた。
・ぼい込む道具として竹の先に金属を付けガチャガチャ音がするようにしたものが使われた。 |
| 22 |
四つ手 |
アユ
オイカワ
カワムツ |
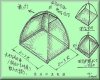 |
・一方向が開いた網に追い込む |
・春先より秋口 |
・四つの持つところ(手)があるところからこの名が付いた
・一間四方の大きなもので、四方が塞がったものをあらかじめ仕掛けて置き、滑車を使うなどして吊り上げる物も有った:林仲治談。 |
| 23 |
ウナギツボ |
ウナギ |
 |
・ウナギが夜餌をとりに出て、通りそうな川底に、入り口を川下にして仕掛ける。
・夕方仕掛け、朝明るくなる前に上げる。 |
・夏期
7月から8月 |
・月夜はだめ
・元々は真竹で作られていたのでこの名があるが、杉の板で箱にした物もある。いずれも良く枯らした物が用いられる。 |
| 24 |
ウゲ(1) |
ウナギ |
 |
・ウナギツボと」同じ |
・夏期
6月〜8月 |
・全てが、竹細工となっており、相当な熟練が必要と思われることから、竹細工師でウナギの好きな人、漁師が考案したのではないかと思われる。 |
| 25 |
ウゲ(2) |
コイ
フナ |
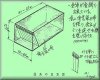 |
・コイは通り道や餌場が決まっていると言われその道筋、特に餌場に入り口を川下に向けて仕掛ける。
・朝のまずめ時 |
・春先より秋口 |
・阿部正六談 |
| 26 |
テンモク |
オイカワ
カワムツ |
 |
・浅い川底に仕掛ける。
・水の流れに注意し入り口を下に向ける。 |
・夏期
7月〜8月 |
・口部の形状が、抹茶茶碗の天目に似たところよりこの名が付いたと思われる。
・前進は、擂り鉢や壺に寒冷紗をかぶせた物で捕っておりそれが原型と思われる:阿部正六談。 |
| 27 |
ハルメ捕り |
ハルメ |
 |
・雑木の枝葉を丸めて、滝壺に沈めて置き、頃合いを見て引き上げ網で掬う。 |
・春先から夏場 |
・椎の小枝が一番という。他にソバの茎を束ねたものが良かったという:阿部正六談。
・ハルメ:ウナギの15〜20㎝のものの俗名 |
| 28 |
夜ぼり |
ウナギ
雑漁 |
 |
・夜浅場へ餌を求めて出る魚や、体を休めている魚を捕る。
・一般に支流で行う。 |
・夏期
7月〜8月 |
・夜に行う漁法で、遭難も多く、特に電気を使うものは電波妨害も有り、禁止されているところもある。 |
| 29 |
|
|
|
|
|
|