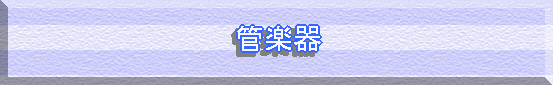
[戻る]
トップメニュー
バリトン・サックス(セルマ・MkⅥシルバー)
村松フルート
セルマ・テナーサックスMkⅦ
ヤナギサワ・テナーサックスT-5
ニッカン・テナーサックス
ニッカン・テナーサックス・ジャンク
バリサク修理
セルマ・アルトサックスMkⅦ
ヤマハ・アルトサックスYAS-62
ヤマハ・ソプラノサックスYSS-61
ヤマハ・フルート
ヤマハ・クラリネットSEカスタム
都山流尺八
ヤマハ・フルートⅡ
ヤマハ・ホルン
バリトン・サックス 2006/1/5
 今日はバリトンサックスです。この楽器は私の物ではありません。
バンドリーダーがあるところで「えー!!うそじゃろー」というような値段で買ってきたものです。
楽器はフランスセルマのMkⅥのシルバーのようで、
ホームページの小さい写真にある貫田さんのテナーとまるで兄弟のようです。
その当時音は出てはいたのですが、キーカバーのハンダが取れていたのが一カ所、
A♭とFのキーが少し漏れていたこと、一番下のAのキー
(他のサックスはB♭までしか出ないが、バリだけはAまで出る)
は右手の小指も一緒に押さえないと音が出ない。といったさまざまな問題をかかえていました。
今日はバリトンサックスです。この楽器は私の物ではありません。
バンドリーダーがあるところで「えー!!うそじゃろー」というような値段で買ってきたものです。
楽器はフランスセルマのMkⅥのシルバーのようで、
ホームページの小さい写真にある貫田さんのテナーとまるで兄弟のようです。
その当時音は出てはいたのですが、キーカバーのハンダが取れていたのが一カ所、
A♭とFのキーが少し漏れていたこと、一番下のAのキー
(他のサックスはB♭までしか出ないが、バリだけはAまで出る)
は右手の小指も一緒に押さえないと音が出ない。といったさまざまな問題をかかえていました。
左親指のAキーですが、これはほとんどのクッションコルクが永い年月でへたったもので、
コルクを4カ所貼り替えたら直りました。E♭のキーカバーのハンダはずれですが、
サックスのキーカバーは単なる保護のために付いているのではなく、
タンポの開き具合つまり音程の調整もしている結構重要な役目を持っています。
テナーもそうですが、E♭のキーはよく物にあたりやすくよく取れるところです。
しかもカーブに近く、管体の肉厚が厚いためハンダ付けのしにくい所です。
今回も苦労してバーナーでハンダ付けをしました。
さて、タンポの隙間ですが、なかなか見ただけではわかりません。
そこで写真Dのような器具を使って(2本あるのではなく、点灯したときとそうでないときの比較をしてある。)
楽器の中に蛍光灯をつっこみタンポの隙間を見ます。
アルトとテナーなら上からつっこみ写真Bのように隙間を見ることができますが、
バリでは上からつっこむ事が出来ません。
プロはどこかばらしてつっこんでいるようですが、見たことがないのでよくわかりません。
そこで写真Eにあるような器具を作りました。Dはただの蛍光灯の点灯回路で職場
にあったあり合わせの材料で15分くらいで作ったものです。
Eの方は白色LEDを8個直列にして100Vで直接点灯したものです。
ただ保護抵抗を入れ直列に点灯したのでは交流の半周期しか点灯していないことになり少し暗くなるだろうと思い、
1Aの整流用ダイオード4個でブリッジを組んであります。
なんとか明るさも確保しタンポの隙間からでも管の中につっこめるのですが、最大の欠点は向きがあることです。
蛍光灯なら360°OKですが、LEDでは一方向しか照らせません。
しかもLEDを立てて使っているため思ったほど細くならないのです。
これではクラリネットやフルートで使えるかどうかあやしいところです。
まだまだ改良が必要です。ちなみに写真Cはばらしている途中の楽器と私の楽器用七つ道具です
この楽器はまだまだ本調子ではありませんが、金をかけずに修理するにはこれくらいが限界だろうと思います。
[TOP]
村松フルート 2006/1/15
 私は学生時代(高校と大学)吹奏楽部でフルートを吹いていました。一番最初は何でフルートに決まったかは忘れま
したが、おそらく部内の事情だったのだと思います。男子校だったのでフルートもクラも全員男子でした。この楽器は2代
目で初代は高校時代親に買ってもらったYAMAHAのカレッジモデルでした。この楽器は大学時代アルバイトでためた金で購入しました。
30年以上前の話です。村松が2代目になってすぐのころの楽器で、
あまり高くない楽器ですがこのころはまだすべて手作りの頃でした。
私は学生時代(高校と大学)吹奏楽部でフルートを吹いていました。一番最初は何でフルートに決まったかは忘れま
したが、おそらく部内の事情だったのだと思います。男子校だったのでフルートもクラも全員男子でした。この楽器は2代
目で初代は高校時代親に買ってもらったYAMAHAのカレッジモデルでした。この楽器は大学時代アルバイトでためた金で購入しました。
30年以上前の話です。村松が2代目になってすぐのころの楽器で、
あまり高くない楽器ですがこのころはまだすべて手作りの頃でした。
初代の村松には歌口に付いている歌口の断面の形をしたMのマークは付いていません。
今では20万以下の楽器はあまり作ってないようですが、
そのころは2万円台で手作りのフルートがありました。
他の楽器にも共通することですが、
この頃の楽器には製造番号が刻印されていないようでこの楽器にも刻印はありません。
大学3年・4年で授業が少なくなってくると、授業がない日も学校に行って朝から練習をしていました。
[TOP]
セルマ・テナーサックスMkⅦ 2006/1/21
 この楽器は現在私がメインで使っているフランスセルマMkⅦテナーサックス(製造番号M265134)です。
1975年頃新品を手に入れた物でMkⅥから変わってあまり間もない頃のものだろうと思います。
この楽器は現在私がメインで使っているフランスセルマMkⅦテナーサックス(製造番号M265134)です。
1975年頃新品を手に入れた物でMkⅥから変わってあまり間もない頃のものだろうと思います。
taoで一度調整をしてもらったことはありますが、タンポの交換などほとんど自分で調整をしています。
現在のコンデションが購入以来最高だと思います。
今までサックスのパートは1番から5番まで全部経験がありますが、
今は4番を吹いています。
4番はアドリブソロなどがないので特に個人練習をしなくてもなんとかなるので気は楽ですが、
テンション音が多いので吹いていて気持ちよくないことと、個人練習をさぼりがちになり、上達しないなどが問題です。
[TOP]
ヤナギサワ・テナーサックスT-5 2006/1/22
 私の予備の楽器ですが、現在同じバンドのメンバーに貸し出し中です。
楽器は初期のYANAGISAWAで型番T-5、製造番号672367で、おそらく'70年頃の物と思います。
私の予備の楽器ですが、現在同じバンドのメンバーに貸し出し中です。
楽器は初期のYANAGISAWAで型番T-5、製造番号672367で、おそらく'70年頃の物と思います。
この楽器はある雨漏りのひどい倉庫の中で雨ざらしになりケースは朽ち果て、
楽器は全体緑青で真っ青だったのをただで譲り受け3万円と3ヶ月の期間をかけて再生したものです。
もちろんタンポも全部交換し、
錆びて動かなくなっていた芯がね(キーに使ってある細く長いボルト)やスプリングも一部交換しました。
ラッカーもすべてはがしたので見かけはぼろぼろですが思いの外音はよいです。
コンデションもまずまずで最低音まで楽にだせます。
セルマのキーに近いので持ち替えたときの違和感があまりなくメインの楽器としても十分使えると思います。
ただ、ネック管のオクターブ機構の芯がねが錆びて動かなかったので、自分で工作して修理したため、
とても不細工になっています。
新しいネックを買えば良いのですがそこまで金をかける価値があるのかどうか考慮中です。
H29年4月14日(2017年) ヤフーオークションで売れました。
[TOP]
ニッカン・テナーサックス 2006/1/25
 またまたテナーサックスです。
この楽器はYANAGISAWAと同じ所でケースは朽ち果て本体は真っ青になっていたのをただで譲り受けたものです。
楽器はNIKKANの古い楽器で、
No020 668165N。YANAGISAWAの修理に部品を取ったので1年くらいジャンクのまま放置しておりました。
またまたテナーサックスです。
この楽器はYANAGISAWAと同じ所でケースは朽ち果て本体は真っ青になっていたのをただで譲り受けたものです。
楽器はNIKKANの古い楽器で、
No020 668165N。YANAGISAWAの修理に部品を取ったので1年くらいジャンクのまま放置しておりました。
この頃の国産の楽器はほとんど部品を外国より輸入して作っていたので、
ネジはすべてインチネジで芯がねその他ネジ類はすべて使い回しができます。
最近のYAMAHAやYANAGISAWAはミリネジを使っているので使い回しは出来ません。
ところがその後同じバンドのそのころ4番を吹いていたKさんにもう一本ジャンクテナーをいただき
同じNIKKANだったので完成させることができました。
やはりタンポはすべて交換し芯金やバネも一部交換し半年がかりで3万円くらいかけて完成しました。
YANAGISAWA同様見かけは悪いですが音はよく出ます。
ただ、キーの間隔や形がセルマとずいぶん違うので、吹きこなすには慣れが必要です。
[TOP]
ニッカン・テナーサックス・ジャンク 2006/1/29
 またまたまたテナーサックスです。
前述と同じ型のNIKKANなのですが、年式はだいぶ違うようでこの楽器には製造番号の刻印がありません。
キーや芯がね、ネジ類はすべて同じなのでYANAGISAWAに取られて欠品となっていた部品をすべて補う事ができました。
ネックがないことやへこみが大きいことなどから、この楽器の再生はまず無理であろうと思われます。
まだ取れる部品が沢山あるので、大事に保管しておこうと思います。
先日書きましたようにセルマのネジとも互換性があります。
またまたまたテナーサックスです。
前述と同じ型のNIKKANなのですが、年式はだいぶ違うようでこの楽器には製造番号の刻印がありません。
キーや芯がね、ネジ類はすべて同じなのでYANAGISAWAに取られて欠品となっていた部品をすべて補う事ができました。
ネックがないことやへこみが大きいことなどから、この楽器の再生はまず無理であろうと思われます。
まだ取れる部品が沢山あるので、大事に保管しておこうと思います。
先日書きましたようにセルマのネジとも互換性があります。
[TOP]
バリサク修理 2006/2/4
 先日修理したバリトンサックスですが、持ち主がいつ手放すかわからない状態だったので、
実を言うとあまり本気で修理していませんでした。
それでバリ担当のYさんに駄目出しをされました。
先日修理したバリトンサックスですが、持ち主がいつ手放すかわからない状態だったので、
実を言うとあまり本気で修理していませんでした。
それでバリ担当のYさんに駄目出しをされました。
持ち主も売り出す気が無いようなのでもう一度入念に調整することにしました。
LEDで開発したバリ用のライトですがやはり暗くて調子悪かったので、
蛍光灯のライトを長さが半分の4Wの管球を買ってきてCのホールより写真にあるようにつっこみました。
短いので再々移動させなくてはなりませんが、LEDよりはだいぶあかるく、
方向を気にせずできるので調子はよいです。
調整が終わり自分で吹いた感じではまずまずだと思いますが、
こんどの練習でYさんにお伺いをたてたいと思います。
[TOP]
セルマ・アルトサックスMkⅦ 2006/2/18
 これはアルトを吹いていたときのメイン楽器でアメリカセルマのMkⅦです。
アメセルのMkⅦは日本人には体力的に吹きこなせないのではということで、
当時はほとんど輸入されておらず、幻の名器といわれていました。
これはアルトを吹いていたときのメイン楽器でアメリカセルマのMkⅦです。
アメセルのMkⅦは日本人には体力的に吹きこなせないのではということで、
当時はほとんど輸入されておらず、幻の名器といわれていました。
最近ビンテージブームで中古の楽器が輸入されるようになり、ごくたまに見ることがあります。
製造番号はN313113でラッカーは90%程度残っており私自身最近テナーばかり吹いているので古いわりには外観上も傷んでおりません。
6年くらい前taoで購入したものですが、その時だいたい同じ値段でフラセルのMkⅥが置いてあり、
吹き比べてみました。MKⅥはやはり枯れたダークな音で通好みだなーと思いましたが、私はテナーはともかく、
アルトは明るいキラキラした音が好きで、フラジオが出しやすかったこのMkⅦの方に決めました。
MkⅦはⅥに比べてキーが大きく特にテナーでは一番下のB♭は手の小さい日本人にはきつい物がありますが、
アルトではテナーほどではありません。今私が持っている管楽器ではこれが一番値段が高かったです。
[TOP]
ヤマハ・アルトサックスYAS-62 2006/2/19
 この楽器は20年前防府のバンドで吹いていたころ
同じバンドのMさんがセルマを買ったので安く売ってあげようといわれ3万円で買った物で、
6年前セルマを買うまでメインで吹いていた楽器です。
この楽器は20年前防府のバンドで吹いていたころ
同じバンドのMさんがセルマを買ったので安く売ってあげようといわれ3万円で買った物で、
6年前セルマを買うまでメインで吹いていた楽器です。
したがって25年くらい前のYAMAHAのプロモデルで型番YAS-62製造番号005374です。
古いなりの錆びは出ておりますがYAMAHAはセルマに比べると塗装ははるかにしっかりしており、
ラッカーもほとんど取れておりません。
コンデションもまずまずで、いつでも本番使用可なのですが、やはりセルマに比べると、
音の太さと言いますか芯の堅さと言いますかちょっと違うような気がします。
でも、聞いている人にはきっとわからないでしょう(笑)。
こだわる人はこのわずかな違いに大金をかけるものなのです。
見かけ上のセルマとの大きな違いは、
CのキーカバーがB♭のそれとつながっているのがYAMAHAで別々に付いているのがセルマです。
古いYANAGISAWAやコーンのサックスは、BとB♭のホールが裏側に付いていたりします。
[TOP]
ヤマハ・ソプラノサックスYSS-61 2006/2/25
 今日はソプラノサックスです。サックスという楽器は小さくなるほど音程が不安定です。
ソプラノサックスの上には渡辺貞夫が吹いているソプラニーノサックスという楽器もありますが、
あまりの不安定さにほとんど使われておりません。
まるでピーピー豆で音楽をやるようなものです。
今日はソプラノサックスです。サックスという楽器は小さくなるほど音程が不安定です。
ソプラノサックスの上には渡辺貞夫が吹いているソプラニーノサックスという楽器もありますが、
あまりの不安定さにほとんど使われておりません。
まるでピーピー豆で音楽をやるようなものです。
ソプラノサックスも音程は半分勘で吹くような楽器で音感のしっかりした者でないと吹きこなせません。
この楽器は25年くらい前徳山の十字堂で買った物でYAMAHAの初期のプロモデルYSS-61で製造番号は3690です。
必要があって買ったわけではなく、コンパクト性から持ち歩くおもちゃにちょうどいいかなと思い買いました。
おもちゃにしては少し高価ですがこのころは独身貴族で物の値段など考えていませんでした。
沖縄に出張していた頃は1年以上の長期だったためテナーを持って行き現地のビッグバンドに参加していましたが、
その他の短期出張にはいつも持ち歩いていました。本番ではたぶん1度も吹いてないと思います。
[TOP]
ヤマハ・フルート 2006/4/23
 またヤフオクで楽器を買ってしまった。
写真のフルート、たしかにきたない。私はこの歴史を感じるような楽器が好きだ。
またヤフオクで楽器を買ってしまった。
写真のフルート、たしかにきたない。私はこの歴史を感じるような楽器が好きだ。
この変色のしかたは銀メッキではないかと思うのだが、ケースや楽器自体はヤマハにしては安っぽい。
届いたときはキーがあちこち変形していてまったく音が出なかったが、
例のLEDを使った管楽器修理用ライトで内側から照らしながら修理するとよく出るようになった。
音質はまあまあで特に高音域が出しやすいのはヤマハの楽器の特徴だが、
低い音の響きはやはり前から持っていた村松の方が一枚上だと思う。
[TOP]
ヤマハ・クラリネットSEカスタム 2006/7/8
 先日ウインドシンセを書いたので続きで、もう少し書き残している管楽器についてアップします。
写真は普通サイズのB♭クラリネットです。
先日ウインドシンセを書いたので続きで、もう少し書き残している管楽器についてアップします。
写真は普通サイズのB♭クラリネットです。
クラにはサックスと同じくらい移調楽器があり、一番良く使われるものがこのサイズです。
他に吹奏楽ではオクターブ下のバスクラ、ちょっと短いE♭(エス)クラ、
オケではバスクラよりちょっと短いE♭のアルトクラ、
バスクラよりもっと長くて金属管でできたコントラバスクラというのもあります。
コントラバスクラは私自身アンサンブルコンテストの中国大会で松江女子が使っていたのを一度見たきりです。
まるで化学工場の配管みたいだと思いました。
この楽器は岩国のリサイクルショップに出ていた物ですが、
YAMAHAのSEカスタムといって結構よい楽器ですがすごく安く出ていたので買ってしまいました。
私自身はおもちゃ程度に吹いていたのですが、現在大学4年生の娘が中学校の3年間吹奏楽部でこの楽器を吹いていました。
ちなみに彼女は高校3年間はバスーンという変わった管楽器を吹いていました。
サックスのパートをやっているとクラへの持ち替えが結構あります。音は出せるのですが、
なんせ円柱楽器なもので運指がサックスと全く違い、なかなか上手く吹きこなせません。いずれ吹きこなしたい楽器です。
[TOP]
都山流尺八 2006/7/30
 尺八です。木管楽器ならぬ竹管楽器ですが、これも管楽器です。
30年前大学の友人にたのまれ、ピアニカ(鍵盤ハーモニカ)と取り替えたものです。
二十数年前尺八の制作もやっている村松一眺先生と知り合い、そのころ管理が悪く、
ひびが入った尺八の修理をたのんだのがきっかけで尺八を習い始めました。
尺八です。木管楽器ならぬ竹管楽器ですが、これも管楽器です。
30年前大学の友人にたのまれ、ピアニカ(鍵盤ハーモニカ)と取り替えたものです。
二十数年前尺八の制作もやっている村松一眺先生と知り合い、そのころ管理が悪く、
ひびが入った尺八の修理をたのんだのがきっかけで尺八を習い始めました。
私の結婚式の司会を頼んだ程親しくして頂いたのですが、仕事の関係で尺八の方は2年くらいでやめてしまいました。
学生時代ずっとフルートをやっていたおかげで音は最初から出せたのですが、楽譜がなかなか読めませんでした。
今でもあまりよめないのですが、写真の後ろに立ててあるお経のようなものが尺八の楽譜で、ロツレチで書いてあります。
甲高いとか、めりはりをつけるというのは尺八用語で、甲というのはオクターブ上を表し、
めりは半音下げる、はりは半音上げる意味になります。
尺八はキーがありませんので半音はあごの角度で調整して出します。
尺八はみなさんご存じのように一尺八寸の長さのものが普通なので尺八といいますが、
一尺六寸管や二尺管も尺八と呼ぶようです。キーは一尺八寸管を全部押さえた状態でDの音ですが、
指で言えばフルートのDと同じなので、ピッコロと同様にCの音は出なくてもC管と言って良いでしょう。
表に穴が4つ裏に一つあり順番にDFGACの音となります。ちなみに下のDFGはフルートと同じ運指です。
二尺管はB♭管なのでソプラノサックスと同じ運指同じ高さの音となります。
尺八には琴古流と都山流という大きく二つの流派があり楽譜の読み方、歌口の形が少し違います。
私の持っている尺八は都山流であり、習ったのは琴古流です。私のつれあいは琴を習っていたとかで、
楽器はでかい顔してたんすの上にいますが、まだ本格的に弾かれているのを見たことがありません。
2人で春の海をセッションできればよいなーと思っています。
[TOP]
ヤマハ・フルートⅡ 2013/1/6
 またヤフオクで楽器を買ってしまった。と前回フルートを買ったとき書きましたが、またまた買いました。
またヤフオクで楽器を買ってしまった。と前回フルートを買ったとき書きましたが、またまた買いました。
2011年ころマイブームで尺八を作っていました。そのころインターネットで尺ルートなるものがアメリカにあることを知りました。
作っているのは日本人のようですが、売っているのはアメリカ中心のようです。
私も以前より、半音階が自由に吹ける尺八がほしいなーと思っていました。
この楽器なら音は尺八で半音階も自由に吹けるのではないかと、自作することを決意しました。
今持っているフルートを使い頭部管だけ作ることも考えましたが、はめ込みがうまくいきそうにありません。
この2本には愛着があるし、つぶすには忍びなく、新たにフルートを1本買い足すことにしました。
いつものヤフオクで落札したのですが。前に落札したyamahaのfl211と全く同じ楽器で
前回も数千円で落札したのですが、今回はそれよりももっと安く落札できました。しかも音も前の楽器よりよく出ます。
そういう次第で急きょ前回のフルートをつぶすことにし写真のようになりました。
一番左が前回落札したfl211で中心のものが今回落札したfl211、右のものが40年前より持っている村松です。
音はEキーシステムの付いてない村松は低音の響きはよいのですが、やはり高音が出にくいです。
しかも頭部管のみ銀メッキで、あとは洋銀製、キーは見たとおり赤さびが出ています。
今回落札したyamahaが安物ですが外見、高音の出しやすさなどから一番吹きやすい楽器となりこれを吹いています。
[TOP]
ヤマハ・ホルン修理 2015/5/21
私の自分持ちの楽器ではありませんが、ホルンの修理レポートをします。
この楽器は学校の楽器です。今年は私がここに来て初めてホルン奏者が3人になりました。
とりあえずマイ楽器が1人いましたので楽器はたりたのですが、予備がありません。
こわれてぼろぼろになったホルンが2台ありました。
修理にだせばよいのですが、これだけぼろぼろですと最低でも5万円はかかります。
最近では5万円も出せば、無名のメーカーの楽器が手に入ります。
しかし、無名のメーカーの楽器はいまいち信用できません。
こんな理由で修理をしてみることにしました。
今までにもサックスの修理などで楽器のハンダ付けをしたことはありますが、
電気の配線のハンダ付けと違い、とてもむつかしいです。


まずはパイプの凹出しです。写真を見てください。
左がマウスピースパイプで材料がとても薄いためつぶれた上に穴も開いていました。
こういう細いパイプの凹出しには右の写真のような道具を使います。
8mmから13mmくらいまでの色々な大きさのボールをつなげたものです。
これを中に入れたり出したりしながら中から凹んだところを出していきます。
もちろんこれも自作です。中のワイヤーはギターの弦です。
穴はホームセンターで買ってきた厚さ0.5mmくらいの銅板をハンダ付けしました。

ばらばらになっていたためお互いを支える柱も壊れたり無くなったりしていました。
これも真鍮の丸棒を旋盤で削り出し両端に銅板をハンダ付けして作りました。写真の矢印の2本です。
格好はあまりよくないですがしっかりとくっつき、がっちり固定できました。


左が修理前、右が修理後です。楽器の左上も微妙に凹んでいたのをたたき出しています。
これは少し先端を曲げた鉄の丸棒を、万力に固定しておき、内側からもみ出すというかこすり出す感じで凹出しします。
これも専門の道具があるらしいのですが、ないものは作らなければしょうがないので作りました。
こういった作業は道具や治具を作るのに時間の大部分をつかいます。
[TOP]
[戻る]
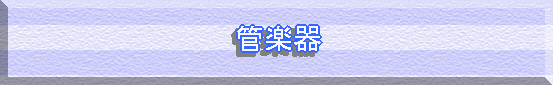
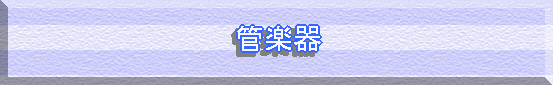
 今日はバリトンサックスです。この楽器は私の物ではありません。
バンドリーダーがあるところで「えー!!うそじゃろー」というような値段で買ってきたものです。
楽器はフランスセルマのMkⅥのシルバーのようで、
ホームページの小さい写真にある貫田さんのテナーとまるで兄弟のようです。
その当時音は出てはいたのですが、キーカバーのハンダが取れていたのが一カ所、
A♭とFのキーが少し漏れていたこと、一番下のAのキー
(他のサックスはB♭までしか出ないが、バリだけはAまで出る)
は右手の小指も一緒に押さえないと音が出ない。といったさまざまな問題をかかえていました。
今日はバリトンサックスです。この楽器は私の物ではありません。
バンドリーダーがあるところで「えー!!うそじゃろー」というような値段で買ってきたものです。
楽器はフランスセルマのMkⅥのシルバーのようで、
ホームページの小さい写真にある貫田さんのテナーとまるで兄弟のようです。
その当時音は出てはいたのですが、キーカバーのハンダが取れていたのが一カ所、
A♭とFのキーが少し漏れていたこと、一番下のAのキー
(他のサックスはB♭までしか出ないが、バリだけはAまで出る)
は右手の小指も一緒に押さえないと音が出ない。といったさまざまな問題をかかえていました。 私は学生時代(高校と大学)吹奏楽部でフルートを吹いていました。一番最初は何でフルートに決まったかは忘れま
したが、おそらく部内の事情だったのだと思います。男子校だったのでフルートもクラも全員男子でした。この楽器は2代
目で初代は高校時代親に買ってもらったYAMAHAのカレッジモデルでした。この楽器は大学時代アルバイトでためた金で購入しました。
30年以上前の話です。村松が2代目になってすぐのころの楽器で、
あまり高くない楽器ですがこのころはまだすべて手作りの頃でした。
私は学生時代(高校と大学)吹奏楽部でフルートを吹いていました。一番最初は何でフルートに決まったかは忘れま
したが、おそらく部内の事情だったのだと思います。男子校だったのでフルートもクラも全員男子でした。この楽器は2代
目で初代は高校時代親に買ってもらったYAMAHAのカレッジモデルでした。この楽器は大学時代アルバイトでためた金で購入しました。
30年以上前の話です。村松が2代目になってすぐのころの楽器で、
あまり高くない楽器ですがこのころはまだすべて手作りの頃でした。 この楽器は現在私がメインで使っているフランスセルマMkⅦテナーサックス(製造番号M265134)です。
1975年頃新品を手に入れた物でMkⅥから変わってあまり間もない頃のものだろうと思います。
この楽器は現在私がメインで使っているフランスセルマMkⅦテナーサックス(製造番号M265134)です。
1975年頃新品を手に入れた物でMkⅥから変わってあまり間もない頃のものだろうと思います。 私の予備の楽器ですが、現在同じバンドのメンバーに貸し出し中です。
楽器は初期のYANAGISAWAで型番T-5、製造番号672367で、おそらく'70年頃の物と思います。
私の予備の楽器ですが、現在同じバンドのメンバーに貸し出し中です。
楽器は初期のYANAGISAWAで型番T-5、製造番号672367で、おそらく'70年頃の物と思います。 またまたテナーサックスです。
この楽器はYANAGISAWAと同じ所でケースは朽ち果て本体は真っ青になっていたのをただで譲り受けたものです。
楽器はNIKKANの古い楽器で、
No020 668165N。YANAGISAWAの修理に部品を取ったので1年くらいジャンクのまま放置しておりました。
またまたテナーサックスです。
この楽器はYANAGISAWAと同じ所でケースは朽ち果て本体は真っ青になっていたのをただで譲り受けたものです。
楽器はNIKKANの古い楽器で、
No020 668165N。YANAGISAWAの修理に部品を取ったので1年くらいジャンクのまま放置しておりました。 またまたまたテナーサックスです。
前述と同じ型のNIKKANなのですが、年式はだいぶ違うようでこの楽器には製造番号の刻印がありません。
キーや芯がね、ネジ類はすべて同じなのでYANAGISAWAに取られて欠品となっていた部品をすべて補う事ができました。
ネックがないことやへこみが大きいことなどから、この楽器の再生はまず無理であろうと思われます。
まだ取れる部品が沢山あるので、大事に保管しておこうと思います。
先日書きましたようにセルマのネジとも互換性があります。
またまたまたテナーサックスです。
前述と同じ型のNIKKANなのですが、年式はだいぶ違うようでこの楽器には製造番号の刻印がありません。
キーや芯がね、ネジ類はすべて同じなのでYANAGISAWAに取られて欠品となっていた部品をすべて補う事ができました。
ネックがないことやへこみが大きいことなどから、この楽器の再生はまず無理であろうと思われます。
まだ取れる部品が沢山あるので、大事に保管しておこうと思います。
先日書きましたようにセルマのネジとも互換性があります。
 先日修理したバリトンサックスですが、持ち主がいつ手放すかわからない状態だったので、
実を言うとあまり本気で修理していませんでした。
それでバリ担当のYさんに駄目出しをされました。
先日修理したバリトンサックスですが、持ち主がいつ手放すかわからない状態だったので、
実を言うとあまり本気で修理していませんでした。
それでバリ担当のYさんに駄目出しをされました。 これはアルトを吹いていたときのメイン楽器でアメリカセルマのMkⅦです。
アメセルのMkⅦは日本人には体力的に吹きこなせないのではということで、
当時はほとんど輸入されておらず、幻の名器といわれていました。
これはアルトを吹いていたときのメイン楽器でアメリカセルマのMkⅦです。
アメセルのMkⅦは日本人には体力的に吹きこなせないのではということで、
当時はほとんど輸入されておらず、幻の名器といわれていました。 この楽器は20年前防府のバンドで吹いていたころ
同じバンドのMさんがセルマを買ったので安く売ってあげようといわれ3万円で買った物で、
6年前セルマを買うまでメインで吹いていた楽器です。
この楽器は20年前防府のバンドで吹いていたころ
同じバンドのMさんがセルマを買ったので安く売ってあげようといわれ3万円で買った物で、
6年前セルマを買うまでメインで吹いていた楽器です。 今日はソプラノサックスです。サックスという楽器は小さくなるほど音程が不安定です。
ソプラノサックスの上には渡辺貞夫が吹いているソプラニーノサックスという楽器もありますが、
あまりの不安定さにほとんど使われておりません。
まるでピーピー豆で音楽をやるようなものです。
今日はソプラノサックスです。サックスという楽器は小さくなるほど音程が不安定です。
ソプラノサックスの上には渡辺貞夫が吹いているソプラニーノサックスという楽器もありますが、
あまりの不安定さにほとんど使われておりません。
まるでピーピー豆で音楽をやるようなものです。 またヤフオクで楽器を買ってしまった。
写真のフルート、たしかにきたない。私はこの歴史を感じるような楽器が好きだ。
またヤフオクで楽器を買ってしまった。
写真のフルート、たしかにきたない。私はこの歴史を感じるような楽器が好きだ。 先日ウインドシンセを書いたので続きで、もう少し書き残している管楽器についてアップします。
写真は普通サイズのB♭クラリネットです。
先日ウインドシンセを書いたので続きで、もう少し書き残している管楽器についてアップします。
写真は普通サイズのB♭クラリネットです。 尺八です。木管楽器ならぬ竹管楽器ですが、これも管楽器です。
30年前大学の友人にたのまれ、ピアニカ(鍵盤ハーモニカ)と取り替えたものです。
二十数年前尺八の制作もやっている村松一眺先生と知り合い、そのころ管理が悪く、
ひびが入った尺八の修理をたのんだのがきっかけで尺八を習い始めました。
尺八です。木管楽器ならぬ竹管楽器ですが、これも管楽器です。
30年前大学の友人にたのまれ、ピアニカ(鍵盤ハーモニカ)と取り替えたものです。
二十数年前尺八の制作もやっている村松一眺先生と知り合い、そのころ管理が悪く、
ひびが入った尺八の修理をたのんだのがきっかけで尺八を習い始めました。 またヤフオクで楽器を買ってしまった。と前回フルートを買ったとき書きましたが、またまた買いました。
またヤフオクで楽器を買ってしまった。と前回フルートを買ったとき書きましたが、またまた買いました。



