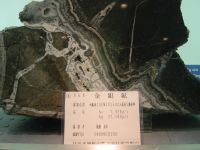| 日立鉱山のあゆみ |
| 明治38年 | 久原房之助(くはらふさのすけ)が日立鉱山を創業する。 |
| 明治39年 |
久原房之助が小平浪平(おだいらなみへい)を日立鉱山に招き、機械修理や開発を任せる。
明治40年 中里発電所が送電を開始。製錬所で使用する機械の電化が進む。 |
| 明治40年 | 中里発電所が送電を開始。製錬所で使用する機械の電化が進む。 |
| 明治41年 |
大雄院(だいおういん)に大規模な製錬所を開設。銅の生産量が飛躍的に増加する。
このころから、鉱山周辺の村に煙害が拡大する。 |
| 明治43年 | 小平浪平が5馬力モーターを開発する(大正9年に独立。日立製作所の創業となる)。 |
| 明治44年 |
煙害が特に激しい入四間(いりしけん)地区で、関右馬之允(せきうまのじょう)が代表となり住民運動を開始。
日立鉱山とともに被害の実測や農業技術の検討などを行う。 |
| 大正4年 | 大煙突が完成。煙害が激減する。大規模な植林事業を展開。大島桜は昭和6年までに260万本を植林する。 |
| 大正6年 |
共楽館を開場。この年、銅(国内の34%)、金・銀とも全国第1位の生産量を記録する。
大島桜の苗木に接ぎ木して育てた約2,000本の染井吉野を、学校や道路などに植林する。 |
| 昭和19年 | 軍需景気により、従業員数が 7,835人とピークに達する。 |
| 昭和56年 | 鉱石量が減少し、日立鉱山が閉山する。 |
| 平成5年 | 大煙突が地上57mを残し、倒壊(とうかい)する。 |