| 東北地方太平洋沖地震! |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
平成23年3月11日午後2時46分頃、東北・三陸沖を震源とする、国内観測史上最大のマグニチュード9・0の極めて強い地震が発生しました。この「東北地方太平洋沖地震」は、宮城県などの東北地方に壊滅的な被害を及ぼすなど各地に大きな爪あとを残しました。 日立市でも震度6強を観測し、沿岸部では津波により家屋が損壊するなど大きな被害を受けました。また、市内全域で断水、停電するなど市民生活にも大きな影響をもたらしました。 3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震は、市民生活に甚大な被害を与え、私たちの日常を一瞬にして変えてしまいました。被害を受けられた市民の皆様に、心からお見舞いを申し上げます。 地震発生後、本市においては災害対策本部を設置し、避難所の開設や電気・ガス・水道などのライフラインの復旧に全力を挙げて取り組んでまいりました。 また、この間、支援物資の提供などに多大なるご支援、ご協力を賜りました国・県・自治体をはじめ市内外の多くの皆様に対し、深くお礼を申し上げる次第です。 さて、このような厳しい状況の中、さくらまつりは中止となりましたが、本市においては春を明るく彩る桜の季節を迎えようとしております。市の花でもある桜は、煙害や戦災といった幾多の困難の中、先人達が、知恵と勇気、そして不撓不屈(ふとうふくつ)の志を持ち、守り、育て、受け継いできた大切な財産であります。 そのように本市にとりまして特別な意味を持つ桜に思いを巡らせながら、感動することで新たに生きる勇気を得るとともに、改めて皆様と共に力を合わせ、この未曾有の危機を乗り越えてまいりたいと考えております。 市民の皆様には、しばらくの間、ご不便をおかけするかと思いますが、一日でも早く市民生活が安定し、生活再建が推進されますよう、全力を尽くしてまいりますので、温かいご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。 日立市長 樫村千秋 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
 | 波により大きな被害を受けた沿岸部(水木町)。 |
 | 津波に持ち上げられた車があちこちに(みなと町・久慈町)。 |
 | 漁港では漁船が打ち上げられました(川尻港)。 |
 | 浸水する会瀬地区。 |
 | 道路のひび割れが地震の大きさを物語ります(大みか町)。 |
 | 河原子海岸の津波被害。 |
 | 地震の影響によりガソリンの供給が低迷。 |
 | 地震直後、多くの市民が避難所へ避難しました(日高中学校)。 |
 | 多くの自衛隊員が日立市で救援活動を行いました。 |
 | 断水のため、給水所には長い列が出来ました(十王支所)。 |
 | 多くの救援物資が届けられました。 |
 | 水道の復旧に向けた配水管工事。 |
 | 水道の復旧に全力で取り組みました。 |
住民の避難状況の推移
と き 避難場所数 避難人数
3月11日(金) 69か所 13,607人
3月12日(土) 45か所 12,509人
3月14日(月) 31か所 2,422人
3月15日(火) 27か所 1,380人
3月17日(木) 24か所 878人
3月18日(金) 17か所 677人
3月19日(土) 11か所 556人
3月21日(祝) 9か所 354人
3月30日(水) 3か所 81人
家屋の被災状況と建築物の応急的な危険度調査状況
津波による家屋被災状況
| と き | 避難場所数 | 避難人数 |
|---|---|---|
| 3月11日(金) | 69か所 | 13,607人 |
| 3月12日(土) | 45か所 | 12,509人 |
| 3月14日(月) | 31か所 | 2,422人 |
| 3月15日(火) | 27か所 | 1,380人 |
| 3月17日(木) | 24か所 | 878人 |
| 3月18日(金) | 17か所 | 677人 |
| 3月19日(土) | 11か所 | 556人 |
| 3月21日(祝) | 9か所 | 354人 |
| 3月30日(水) | 3か所 | 81人 |
家屋の被災状況と建築物の応急的な危険度調査状況
津波による家屋被災状況
と き | 避難場所数 | 避難人数 |
|---|---|---|
35 | 50 | 483 |
建築物の応急的な危険度調査状況
危険判定 | 要注意 | 被災程度の小さいもの |
|---|---|---|
65件 | 251件 | 478件 |
道路などの被災箇所件数
●道路 約300件
●河川 約40件
●公園 約40件
(平成23年3月28日現在)
「東北地方太平洋沖地震」の概要
国内観測史上最大のマグニチュード9.0
平成23年3月11日午後2時46分18秒、三陸沖の深さ24kmを震源とする地震が起きました(東北地方太平洋沖地震)。
この地震を起こした断層は、岩手県沖から茨城県沖にかけての長さ約450km・幅約200kmの大きさで、地震の規模を表すマグニチュードは9.0と、これまで日本付近で観測された地震の中で最大のものでした。
このマグニチュード9.0という数字は、世界で観測された中でも4番目の大きさです。
この地震により、宮城県で震度7の揺れを、宮城・福島・栃木・茨城県で震度6強の揺れを観測したほか、北海道から九州にかけて揺れが観測されました。
日立市でも、震度6強の揺れを観測し、これまでに市で観測された最大震度5弱をはるかに上回る強い揺れの観測となりました。
この地震を起こした断層は、岩手県沖から茨城県沖にかけての長さ約450km・幅約200kmの大きさで、地震の規模を表すマグニチュードは9.0と、これまで日本付近で観測された地震の中で最大のものでした。
このマグニチュード9.0という数字は、世界で観測された中でも4番目の大きさです。
この地震により、宮城県で震度7の揺れを、宮城・福島・栃木・茨城県で震度6強の揺れを観測したほか、北海道から九州にかけて揺れが観測されました。
日立市でも、震度6強の揺れを観測し、これまでに市で観測された最大震度5弱をはるかに上回る強い揺れの観測となりました。
この地震により津波が発生し、震源に近い三陸沿岸には、地震発生直後に津波の第1波が到達しました。
茨城県の沿岸でも、地震発生から約30分後の午後3時15分に大洗で第1波が観測されています。
津波の高さは、岩手県や宮城県沿岸で最大で10mを超えました。
日立市では、東京大学の現地調査により、4m以上(久慈町のなぎさ公園で4.2m、川尻港で4.4m)の津波が押し寄せていたことが分かりました。
本震のあとも、日立市で19日に震度5強の揺れを観測するなど、余震を数多く観測しています。
茨城県の沿岸でも、地震発生から約30分後の午後3時15分に大洗で第1波が観測されています。
津波の高さは、岩手県や宮城県沿岸で最大で10mを超えました。
日立市では、東京大学の現地調査により、4m以上(久慈町のなぎさ公園で4.2m、川尻港で4.4m)の津波が押し寄せていたことが分かりました。
本震のあとも、日立市で19日に震度5強の揺れを観測するなど、余震を数多く観測しています。
*これらのデータは、3月28日現在のものであり、今後の調査で変更となる場合もあります

緊急消防援助隊として10人の消防隊員が福島県へ派遣されました
 |
| 緊急消防援助隊として10人の消防隊員が福島県へ派遣されました |
福島第一原発から周囲20㎞~30㎞圏内における医療機関及び老人福祉施設から他施設への搬送活動を実施するため、日立市から10人の消防隊員が派遣されました。
|
|
|
3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震で、日立市は震度6強の非常に強い揺れを観測し、大津波警報が発表されました。 市内では、幸いにも死者や行方不明者はいませんでしたが、地震や津波で多くのかたが負傷し、家屋や道路が損壊しました。また、電気や水道などのライフラインも大きな被害を受け、約10日間供給が止まりました。 余震は減少傾向にありますが、まだ油断は出来ない状況です。 もしもの場合に備え、各家庭で地震・津波へのいっそうの備えをお願いします。 |
|
 |
非常持ち出し品の例 |
|
食料品や飲料水、ラジオ、懐中電灯、貴重品、医薬品などをすぐに持ち出せるようにまとめておきましょう(上図参照)。 今回の地震では、激しい揺れで倒れた家具により、けがをしたかたもいます。震度5強の地震でも、タンスなどの重い家具が倒れたり、テレビが台から落ちたりします。家具を固定したり、置く場所を変えるなどの対策をしましょう。 また、いざというときすぐに行動出来るように、日頃から、避難場所や避難ルートを家族で確認しておきましょう。 |
|
|
大きな地震が起きても、慌てて飛び出したりせず、まず安全な場所に身を隠し、揺れがおさまってから行動しましょう。 また、コンロやストーブなど火の始末も忘れずにしてください。 |
|
|
市では、今回の震災では発生当初からさまざまな手段を使って、市民の皆さんに情報を発信しました。 市内の被害状況、ライフラインの復旧状況、被災者の生活支援情報などを「市役所からのお知らせ」にまとめ、毎日、避難所など地域の皆さんに届けました。また、ケーブルテレビやラジオ(コミュニティFM)、市のホームページでも情報提供を行いました。 震度や津波などの緊急情報は、防災無線戸別受信機や屋外放送塔でそのつど発信しています。津波警報が発表されたときは、海岸部にいるかたは速やかに近くの高台へ避難してください。 今後も、防災無線やケーブルテレビなどで流れる市からの情報に、注意をお願いします。 |
|
|
避難するときには、出来るだけ近所で声を掛け合い、いっしょに避難するようにしましょう。 災害時には、特に高齢者や独り暮らしのかたは地域の支えが必要です。 |
|
 |
|
度重なる余震により、地盤が緩み、弱くなっている可能性が高いため、雨による土砂災害の危険性が高まっています。 大雨警報が発表されたときには、特に土砂災害に注意してください。 土砂災害ハザードマップで避難場所を確認するなど、災害に備えましょう。 |
 東日本大震災記録誌「東日本大震災日立市の記録3・11からの出発」を発刊します
東日本大震災記録誌「東日本大震災日立市の記録3・11からの出発」を発刊します
東日本大震災における日立市の被災状況や災害対応を風化させることなく後世に残すとともに、将来の災害に対する備えとするため、被災写真や市民の体験談、小・中学生の作文などを記録誌としてまとめました。
1部500円で販売しています。また、各図書館・交流センターなどで閲覧することも出来ます。
1部500円で販売しています。また、各図書館・交流センターなどで閲覧することも出来ます。
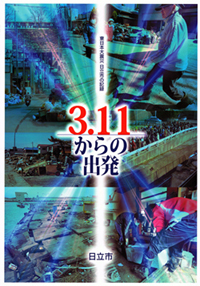
記録誌の概要
|
|
| 生活安全課・総務課・各支所 | |
| 500円 | |
| 生活安全課防災対策室 内線340 |
津波災害に備えて
~11月5日は「津波防災の日」~
知っておこう!!津波から逃げるために!!
津波はいつ発生するかわかりません。津波が発生した時にどこに避難するのか、自宅や職場の近くの避難場所や避難経路を事前に確認しておきましょう。また、日頃から3日分以上の食糧・飲料水などの備蓄、非常持出品を準備しておきましょう。
 地震の揺れを感じたら
地震の揺れを感じたら
強い揺れや、弱い揺れであっても、長い時間の揺れを感じたら、すぐに高台や高い建物など安全な場所に避難しましょう。
 避難は徒歩で
避難は徒歩で
自動車による避難は、交通障害の原因になったり、避難支援活動の妨げになるおそれがあります。津波からの避難は、原則として徒歩で避難しましょう。
 率先して避難しましょう
率先して避難しましょう
「周囲の人が避難しないから大丈夫」ということはありません。自ら率先して避難行動をとることが他の地域住民の避難を促します。
 想定を過信しない
想定を過信しない
地震や津波は自然現象であり、想定を超える可能性があります。「浸水想定区域外だから大丈夫」「津波警報が出ていないから大丈夫」ということはありません。
 避難したら
避難したら
津波は数時間続いたり、第1波より第2波、第3波の方が大きくなることがあります。津波警報などが解除されるまでは、海岸には絶対に近づかないでください。

津波により破壊された河原子海岸南浜の防波堤
あの日を忘れない…

平成23年3月11日 日立市は過去に体験したことのない震度6強の大地震に襲われた
ライフラインは寸断され、市内69箇所の避難所には、最大1万3千人以上の市民が避難した
あの日、市内を見渡すと、そこには昨日と違う世界があった
市民生活は困難を極めた
しかし、多くのかたがたからの温かい支援の手や、お互いが助け合うことで、私たちは被災の苦境を乗り越え、日常を取り戻すことができた
あれから5年あの日を、あの想いを、私たちは忘れない
ライフラインは寸断され、市内69箇所の避難所には、最大1万3千人以上の市民が避難した
あの日、市内を見渡すと、そこには昨日と違う世界があった
市民生活は困難を極めた
しかし、多くのかたがたからの温かい支援の手や、お互いが助け合うことで、私たちは被災の苦境を乗り越え、日常を取り戻すことができた
あれから5年あの日を、あの想いを、私たちは忘れない
地震発生
平成23年3月11日(金曜日) 14時46分 東北三陸沖を震源とするマグニチュード9・0の地震(名称:平成23年東北地方太平洋沖地震)が発生しました。
日立市では、歴史上最大となる震度6強を記録し、沿岸部一帯に高さ4メートル程の津波が押し寄せました。
この地震による家屋の被害は、1万8千386件(うち全壊は436件)にのぼり、また、交通機関が不通となり帰宅が困難となった人を含め、最大約1万3千人が69箇所の避難所に避難しました。
日立市では、歴史上最大となる震度6強を記録し、沿岸部一帯に高さ4メートル程の津波が押し寄せました。
この地震による家屋の被害は、1万8千386件(うち全壊は436件)にのぼり、また、交通機関が不通となり帰宅が困難となった人を含め、最大約1万3千人が69箇所の避難所に避難しました。
ライフラインが止まった
電気、都市ガス、水道は震災当日から停止し、市民生活は困難を極め、給水所には水を求める人で長蛇の列ができました。(下写真は市役所で給水を待つ人々) *電気は3月16日、都市ガスは3月18日、水道は3月21日に市内全域の復旧が完了。

自主防災
災害発生後すぐに、各地区コミュニティ組織では自主防災活動(避難所開設準備などの初動対応と、炊き出しや学区内パトロールなどの災害支援活動)を実施しました。3月11日以降19日までに各地域において約600人が地域のために活動しました。
園・学校も被災
幼稚園、小・中・特別支援学校は3月18日まで休園・休校となり、くじ保育園、河原子幼稚園、水木小学校は地震による被害が甚大だったため、近隣の園や学校での保育や授業を余儀なくされました。
がれきがまちにあふれた
推定総量4万5千トンの、災害廃棄物(ブロック、大谷石、家屋の解体木くずなど)が排出されました。

久慈サンピア日立脇の臨時集積所に集められた災害廃棄物
原発事故からの避難者
3月12日、福島第一原子力発電所1号機原子炉建屋付近での爆発事故を始めとした、一連の原子力発電所の事故により、住み慣れた土地を離れることを余儀なくされた、最大211人の福島県からの避難者を受け入れました。
支援の手が続々と
3月15日、日立市社会福祉協議会と市は災害支援ボランティアセンターを設置。6月21日のセンター閉鎖までの間、希望する世帯に延べ594人のボランティアを派遣しました。また、自衛隊や他市町村からの応援、義援金などたくさんの温かい支援が日立市に寄せられました。
私たちにできること
東日本大震災を教訓に、私たちは、食料や飲料水などの備蓄、防災マップや津波ハザードマップの見直し、津波避難階段や津波避難場所の整備など、自助、共助、公助のそれぞれの面から、多くの取組を進めてきました。
また、災害時に大きな力となる「人と人との絆」を深めていくため、学校や、コミュニティ、関係機関などと合同で取り組む防災訓練も毎年実施しています。
安全で安心なまちをつくるため、私たちはこれからも、震災の記憶を風化させず、教訓として後世に伝えること、そして、一人ひとりが行う防災の取組を継続させながら、自助、共助、公助の連携をいっそう強めていくことが必要です。
また、災害時に大きな力となる「人と人との絆」を深めていくため、学校や、コミュニティ、関係機関などと合同で取り組む防災訓練も毎年実施しています。
安全で安心なまちをつくるため、私たちはこれからも、震災の記憶を風化させず、教訓として後世に伝えること、そして、一人ひとりが行う防災の取組を継続させながら、自助、共助、公助の連携をいっそう強めていくことが必要です。
震災発生後の経過(主なもの)
|
平成23年 3月11日(金曜日) | 14時46分 平成23年東北地方太平洋沖地震(災害名称:東日本大震災)発生。 |
| 15時14分 大津波警報発令 | |
| 災害対策本部設置後速やかに避難所を設置(最大69箇所。避難者は最大約13,000人。同年3月31日最後の避難所閉鎖) | |
| 県知事に自衛隊派遣を要請 | |
| 3月12日(土曜日) | 福島第一原子力発電所1号機原子炉建屋付近で爆発 |
| 3月14日(月曜日) | 福島第一原子力発電所3号機原子炉建屋付近で爆発 |
| 3月15日(火曜日) | 福島第一原子力発電所2号機で爆発 |
| 日立市災害支援ボランティアセンター設置(同年6月21日閉鎖) | |
| 3月16日(水曜日) | 福島県からの避難者受け入れ開始(避難所開設。避難者は最大211人。同年4月11日に避難所閉鎖) |
| 市内全ての電気復旧 | |
| 3月18日(金曜日) | 市内全ての都市ガス復旧 |
| 3月21日(月曜日) | 市内全ての上水道復旧 |
| 3月29日(火曜日) | 被災者支援総合相談窓口を市役所本庁及び各支所に開設(同年8月31日閉鎖) |
| 5月12日(日曜日) | 市内10か所で空間放射線量率測定開始 |
| 11月10日(木曜日) | 市立幼稚園・保育園、小・中・特別支援学校の除染作業開始(平成25年度に完了) |
東日本大震災に関する取組
市では、大震災から5年を迎えるに当たり、震災関連の取組を実施します。
◆防災行政無線による追悼放送(黙祷) 3月11日(金曜日) 14時46分~
◆シェイクアウト訓練(県北臨海3市同時開催)・防災行動プラスワンコンテスト 3月11日(金曜日) 12時~ *訓練に併せて独自に取り組んだ防災行動の内容と写真を募集します(詳細は市ホームページを御覧ください)。
◆震災写真パネルの展示 3月7日(月曜日)~13日(日曜日) 日立駅情報交流プラザ、4月1日(金曜日)~9日(土曜日) 日立シビックセンターアトリウム
◆防災行政無線による追悼放送(黙祷) 3月11日(金曜日) 14時46分~
◆シェイクアウト訓練(県北臨海3市同時開催)・防災行動プラスワンコンテスト 3月11日(金曜日) 12時~ *訓練に併せて独自に取り組んだ防災行動の内容と写真を募集します(詳細は市ホームページを御覧ください)。
◆震災写真パネルの展示 3月7日(月曜日)~13日(日曜日) 日立駅情報交流プラザ、4月1日(金曜日)~9日(土曜日) 日立シビックセンターアトリウム
災害に強いまちづくりの実現を目指して
~震災後の市の取組について~
今年の3月11日で、東日本大震災から5年が経過しました。
平成23年9月に策定した震災復興計画は、平成26年3月末に終了し、市では、被災住宅修繕工事費補助や災害時非常用持出袋の配布、学校施設をはじめとする公共施設の耐震化などの復旧・復興事業を実施し、おおむね完了することができました。
また、東日本大震災の経験を踏まえ、市は災害に強いまちづくりを目指し、さまざまな取組を実施しました。
平成23年9月に策定した震災復興計画は、平成26年3月末に終了し、市では、被災住宅修繕工事費補助や災害時非常用持出袋の配布、学校施設をはじめとする公共施設の耐震化などの復旧・復興事業を実施し、おおむね完了することができました。
また、東日本大震災の経験を踏まえ、市は災害に強いまちづくりを目指し、さまざまな取組を実施しました。
情報通信体制等の強化
- 津波監視カメラシステムの整備(写真(1))
- 戸別受信機の全戸配備完了、屋外放送塔の増設
被災者救援体制等の確立
- 福祉避難所の整備
- 給水場所の拡大
避難所の運営体制と環境の整備
- 防災備蓄倉庫の整備(写真(2))及び食料、生活物資等の備蓄
地域・市民の防災力の向上
- 非常用持出袋、家庭版防災ハンドブックの作成と全戸配布
- 津波ハザードマップの改訂と全戸配布
- 防災マップの改訂と全戸配布
- コミュニティ版防災ハンドブックの作成、配布
- 津波避難、海抜等表示看板(写真(3))の整備
*防災関係事業の詳細は、市ホームページを御覧になるか、問い合わせてください。
| 問合せ | 生活安全課 内線337 |
|---|
 |
 |
 |
| 震災前 | 震災後 | |
| 情報通信体制等の強化 | ||
|---|---|---|
| 防災行政無線(屋外放送塔) | 92基 | 101基 |
| 防災行政無線(戸別受信機) | 52,232台 |
78,000台 (全戸配布) |
| 津波監視カメラ | - | 8台 |
| 被災者救援体制等の確立 | ||
| 給水所 | 6か所 | 22か所 |
| 福祉避難所 | - | 27か所 |
| 避難所の運営体制と環境の整備 | ||
| 防災備蓄倉庫 | - | 64か所 |
| 地域・市民の防災力の向上 | ||
| 海抜表示看板(電柱などへ設置) | - | 2,270か所 |
| 津波避難場所 | - | 1か所 |
| 災害時協力井戸登録数 | - | 271か所 |
あの日から6年
-災害への備えを点検しましょう-
復興
復興
平成23年3月11日、三陸沖を震源とするマグニチュード9・0の地震により、本市では過去最大となる震度6強を記録しました。
巨大地震と津波により、建物や生活インフラなどに甚大な被害が出ました。
この震災を教訓とし、市では、防災機能を備えた池の川さくらアリーナの建設をはじめとする、災害に強いまちづくりを進めてきました。
震災以降、全国で土砂災害や台風による河川の氾濫、地震などの災害が発生しています。
この機会に、再度、家庭でできる災害への備えを点検しましょう。
巨大地震と津波により、建物や生活インフラなどに甚大な被害が出ました。
この震災を教訓とし、市では、防災機能を備えた池の川さくらアリーナの建設をはじめとする、災害に強いまちづくりを進めてきました。
震災以降、全国で土砂災害や台風による河川の氾濫、地震などの災害が発生しています。
この機会に、再度、家庭でできる災害への備えを点検しましょう。
 |  |
| 新庁舎 | 水木小学校 |
 |  |
| 池の川さくらアリーナ | 津波避難階段 |
当時の状況を振り返る
東日本大震災では、日立市にも津波が到来し、甚大な被害を及ぼしました。
電気、都市ガス、水道のライフラインは震災直後から停止し、皆さんの生活にも多大な影響を与えました。
電気、都市ガス、水道のライフラインは震災直後から停止し、皆さんの生活にも多大な影響を与えました。
 家屋の被害状況
家屋の被害状況
| 被害状況 | 交付件数 | うち津波が原因によるもの | 津波以外のり災によるもの |
|---|---|---|---|
| 全壊 | 424 | 13 | 411 |
| 大規模半壊 | 675 | 132 | 543 |
| 半壊 | 3,217 | 449 | 2,768 |
| 一部損壊 | 13,249 | 165 | 13,084 |
| 合計 | 17,565 | 759 | 16,806 |
*状況は平成24年3月31日現在
 避難の状況
避難の状況
避難所 最大69箇所
避難者 最大13,607人
避難者 最大13,607人
 ライフラインの復旧状況
ライフラインの復旧状況
| 電気 | 3月16日復旧 |
| 都市ガス | 3月18日復旧 |
| 上水道 | 3月21日復旧 |
| 下水道 | 3月18日復旧 |
 防災関係事業の進捗状況
防災関係事業の進捗状況
| 震災前 | 震災後 | |
| 情報通信体制等の強化 | ||
| 防災行政無線(屋外放送塔) | 92基 | 101基 |
| 防災行政無線(戸別受信機) | 52,232台 | 78,000台 (全戸配布) |
| 津波監視カメラ | - | 8台 |
| 被災者救援体制等の確立 | ||
| 給水所 | 6か所 | 22か所 |
| 福祉避難所 | - | 27か所 |
| 避難所の運営体制と環境の整備 | ||
| 防災備蓄倉庫 | - | 65か所 |
| 地域・市民の防災力の向上 | ||
| 海抜表示看板 | - | 2,270か所 |
| 津波避難場所 | - | 1か所 |
| 災害時協力井戸登録数 | - | 271か所 |
 |
水道の復旧の様子 |
被害を最小限にするために
-まずは、自分の身を守ることから-
-まずは、自分の身を守ることから-
自助
災害が発生したとき、被害を最小限に抑えるためには、自分のことは自分で守る「自助」が防災の基本になります。
いざというときに困らないよう、非常持出品の準備や家具の固定など、身のまわりの安全対策を行いましょう。
いざというときに困らないよう、非常持出品の準備や家具の固定など、身のまわりの安全対策を行いましょう。
 |
| 東連津川を遡上する津波 |
 家庭でできる災害への備え
家庭でできる災害への備え
 |
1 避難所を確認する
家の近くの避難所と避難所までの道のりを確認しておきましょう。家族が離ればなれになったときの 集合場所を決めておくこともたいせつです。 |
 |
2 危険箇所をチェックする
家具が倒れないように固定しているか、倒れた場合でも入口を塞ぐことがないか確認しましょう。 家の外では、避難経路を塞ぐものがないか確認しましょう。 ブロック塀などの補強も効果的です。 |
 |
3 非常用持出品をチェックする 非常食、飲料水、ヘルメット、上着や下着、 保険証のコピーなど必要だと思うものは簡単に持ち出せるよう、 バッグにまとめておきましょう。 機器の保存状態や食べ物の消費期限の確認もたいせつです。 |
 |
4 防災無線を確認する 防災無線は常にスイッチを入れておきましょう。 気象警報などが発表されている場合には、 防災無線のスイッチが「入」になっているか確認しましょう。 |
 災害に対する日頃からの心構えがたいせつです
災害に対する日頃からの心構えがたいせつです
地震発生直後から避難所対応に従事し、当時住んでいた実家に帰ったのは、次の日の昼。実家では、地震の後、すぐにお風呂の水を汲んでおいたおかげで、生活用水として使うことができました。また、プロパンガスとカセットコンロがあったおかげで、簡単な食事をとることができました。
日頃から災害のことを頭の片隅で考えておくことで、災害に対応する力は大きく変わります。「これは災害時に使えるな」と思うものは備蓄しておいたり、役立つ知識を覚えておくことがたいせつです。
災害はいつ起こるかわかりませんので、備えは万全にしておきましょう。
日頃から災害のことを頭の片隅で考えておくことで、災害に対応する力は大きく変わります。「これは災害時に使えるな」と思うものは備蓄しておいたり、役立つ知識を覚えておくことがたいせつです。
災害はいつ起こるかわかりませんので、備えは万全にしておきましょう。
 |
|
生活安全課 防災対策室
髙畠友宏主事 |
 ご家庭や職場で!シェイクアウト訓練にご参加ください!
ご家庭や職場で!シェイクアウト訓練にご参加ください!
震災の記憶を忘れず、防災の教訓としていくため、市ではシェイクアウト訓練(一斉行動訓練)を実施します。
いざというときに備え、自分自身の身を守る方法を身に付けておくためにも、ぜひ、ご家庭や職場などでの皆さんの参加をお願いします。
とき 3月11日(土曜日) 14時30分から約1分程度
内容 防災行政無線から、訓練の実施を呼びかけますので、地震による揺れを感じたという想定で、
その場で約1分間、安全確保行動【DROP(まず低く)COVER(頭を守り)HOLD-ON(動かない)】をとってください。
屋外の場合は、より安全な場所へ移動してください。
その他
訓練後の14時46分に、追悼放送を行います。
1分間の黙とうにご協力ください。
いざというときに備え、自分自身の身を守る方法を身に付けておくためにも、ぜひ、ご家庭や職場などでの皆さんの参加をお願いします。
とき 3月11日(土曜日) 14時30分から約1分程度
内容 防災行政無線から、訓練の実施を呼びかけますので、地震による揺れを感じたという想定で、
その場で約1分間、安全確保行動【DROP(まず低く)COVER(頭を守り)HOLD-ON(動かない)】をとってください。
屋外の場合は、より安全な場所へ移動してください。
その他
訓練後の14時46分に、追悼放送を行います。
1分間の黙とうにご協力ください。
災害時の「避難準備情報」などの名称が変わりました
平成28年台風10号による水害では、岩手県でグループホームが被災し、入所者が亡くなるという痛ましい被害がありました。
この被害の原因の一つには「避難準備情報」の意味することが伝わっておらず、適切な行動がとられていなかったことが挙げられます。
国は、こうした事態を重く受け止め、高齢者などが避難を開始する段階であるということを明確にするため、「避難準備情報」などの名称を変更することとしました。
なお、突発的な災害の場合、市町村長からの避難勧告などの発令が間に合わないこともあるため、身の危険を感じたら躊躇(ちゅうちょ)なく自発的に避難をしましょう。特に、津波については強い揺れまたは長時間ゆっくりとした揺れを感じた場合、気象庁の津波警報などの発表や市町村長からの「避難指示(緊急)」の発令を待たずに、居住者などが自発的かつ速やかに避難所へ避難することが必要です。
この被害の原因の一つには「避難準備情報」の意味することが伝わっておらず、適切な行動がとられていなかったことが挙げられます。
国は、こうした事態を重く受け止め、高齢者などが避難を開始する段階であるということを明確にするため、「避難準備情報」などの名称を変更することとしました。
なお、突発的な災害の場合、市町村長からの避難勧告などの発令が間に合わないこともあるため、身の危険を感じたら躊躇(ちゅうちょ)なく自発的に避難をしましょう。特に、津波については強い揺れまたは長時間ゆっくりとした揺れを感じた場合、気象庁の津波警報などの発表や市町村長からの「避難指示(緊急)」の発令を待たずに、居住者などが自発的かつ速やかに避難所へ避難することが必要です。

| (変更前) | ||||
| 避難準備情報 | 避難勧告 | 避難指示 | ||
 |  |  |
||
| (変更後) | ||||
|
避難準備・ 高齢者等避難開始 | 避難勧告 | 避難指示(緊急) | ||
|
|
|
||
| 問合せ | 生活安全課防災対策室 内線340 |
|---|
あの日から7年 忘れない、風化させない
 平成23年3月11日、三陸沖を震源とするマグニチュード9.0の地震により、本市では過去最大となる震度6強を記録しました。
平成23年3月11日、三陸沖を震源とするマグニチュード9.0の地震により、本市では過去最大となる震度6強を記録しました。巨大地震と津波により、建物や生活インフラなどに甚大な被害が出ました。
震災以降も全国で、さまざまな災害が発生しています。
震災の記憶を風化させることなく、災害について、もう一度考えてみましょう。
震災を風化させない 日頃からの心構え
避難所・避難経路を確認する
 災害時、どこに避難すればよいのか。避難する際は、どの道を通るのか。防災マップなどであらかじめ確認しておきましょう。
災害時、どこに避難すればよいのか。避難する際は、どの道を通るのか。防災マップなどであらかじめ確認しておきましょう。
家族の連絡方法を決める
家族が離れている時間帯に災害に遭遇した時のために、「災害用伝言ダイヤル(171)」を利用するなど、連絡方法を決めておきましょう。
家庭で食料品などを備蓄する
 基本的な備蓄は、1人3日分と言われています。食料品をはじめとした生活必需品を少し多めに購入しておくことも、簡単な備蓄の方法です。また、自動車のガソリンなども常に半分以上入れておくことも、災害の備えとなります。
基本的な備蓄は、1人3日分と言われています。食料品をはじめとした生活必需品を少し多めに購入しておくことも、簡単な備蓄の方法です。また、自動車のガソリンなども常に半分以上入れておくことも、災害の備えとなります。
自分が住んでいる地域を知る
防災マップやハザードマップなどで、自分が住んでいる地域にどのような危険があるのか確認しましょう。
地域の防災訓練に参加する
市内にはコミュニティごとに自主防災組織があります。自主防災組織が実施する防災訓練に参加しましょう。
 災害時、どこに避難すればよいのか。避難する際は、どの道を通るのか。防災マップなどであらかじめ確認しておきましょう。
災害時、どこに避難すればよいのか。避難する際は、どの道を通るのか。防災マップなどであらかじめ確認しておきましょう。家族の連絡方法を決める
家族が離れている時間帯に災害に遭遇した時のために、「災害用伝言ダイヤル(171)」を利用するなど、連絡方法を決めておきましょう。
家庭で食料品などを備蓄する
 基本的な備蓄は、1人3日分と言われています。食料品をはじめとした生活必需品を少し多めに購入しておくことも、簡単な備蓄の方法です。また、自動車のガソリンなども常に半分以上入れておくことも、災害の備えとなります。
基本的な備蓄は、1人3日分と言われています。食料品をはじめとした生活必需品を少し多めに購入しておくことも、簡単な備蓄の方法です。また、自動車のガソリンなども常に半分以上入れておくことも、災害の備えとなります。自分が住んでいる地域を知る
防災マップやハザードマップなどで、自分が住んでいる地域にどのような危険があるのか確認しましょう。
地域の防災訓練に参加する
市内にはコミュニティごとに自主防災組織があります。自主防災組織が実施する防災訓練に参加しましょう。
東日本大震災の写真・映像の提供をお願いします
 東日本大震災から7年が経過します。
東日本大震災から7年が経過します。震災の記憶を風化させず、教訓として後世に伝えるため、市内の被害の様子などを撮影した写真・映像の提供をお願いします。
提供いただいた写真などは、地域の防災訓練での展示や、市の広報などで使用させていただきます。
提供方法
撮影場所・年月日、撮影者氏名、住所、電話番号を明記し、郵便(CDなどに記録)かEメールでお送りください。
注意事項
- 写真等の版権は市に帰属します。
- 提供された写真や記録媒体は返却しません。
問合せ及び送付先
生活安全課 内線 340
〒317-8601 助川町1丁目1番1号 Eメール anzen@city.hitachi.lg.jp
〒317-8601 助川町1丁目1番1号 Eメール anzen@city.hitachi.lg.jp
シリーズ防災(23)
災害に備えて備蓄しよう
3月11日で東日本大震災から9年がたちました。また、昨年の台風で近隣市町村においては、被害を受け避難所生活を送られた方もいました。
ライフラインが復旧し、支援が開始されるまでおおむね3日分(できれば1週間分)の備蓄が必要であるとされています。近年では、日頃利用している食料品や日用品を少し多めに保有し、日常生活で使用するたびに買い足し補充をする「ローリングストック(日常備蓄)」という方法も注目されています。生活の一部に備蓄品を取り入れ使用することで、賞味期限などの管理もできるため、食料品を無駄にすることも少なくなります。
また、スマートフォンなどの情報収集機器の普及に伴い、モバイルバッテリーなどを準備しておくことも大事になってきました。災害はいつ発生するか分かりません。常日頃から水や食料品、燃料や工具など備蓄品を揃え、万が一に備えましょう。
【備品リストの参考】
| 食料品 | 缶詰やレトルト食品、チョコレートやあめなど |
|---|---|
| 水 | 大人1人当たり1日3リットル |
| 燃料 | 卓上コンロ、固形燃料、予備のガスボンベなど |
| 工具 | ロープ、バール、はさみ、のこぎりなど |
| その他 | 簡易トイレ、毛布、寝袋、食器類、使い捨てカイロ、マスク、シート、照明器具、筆記用具、モバイルバッテリーなど |

