 市内に14,000本を超える市の花、桜。日本さくら名所百選に選ばれている「かみね公園・平和通り」をはじめ、4月上旬から、市内一円を美しく彩ります。 その「桜」には、市民と日立鉱山とが手を取り合い、市民・企業の共生の原点となった物語が秘められています。 今号では、「桜」にまつわる歴史を紹介するとともに、その歴史を基に描かれた新田次郎の小説『ある町の高い煙突』の映画化などについてお知らせします。
 日立鉱山が創業する前の鉱山は「赤沢銅山」と呼ばれていました。佐竹氏がこの地域を治めた江戸時代以前から約300年を越える歴史があるとはいえ、規模的には地方の群小鉱山の一つに過ぎませんでした。 1905(明治38)年、久原房之助(くはら ふさのすけ)が赤沢銅山を買収、村名の「日立」からとって「日立鉱山」と改称し、近代的な鉱山の経営に乗り出しました。 (写真は本山採鉱所の本鉱入り口)
日立鉱山は、当時の最新技術を使った探鉱により、鉱床を次々と発見。銅の埋蔵量の豊かさを確信した久原は、他鉱山の鉱石を買い入れて製錬することを視野に入れた、大規模製錬所を天童山大雄院の寺域に1908(明治41)年に建設し、1912(大正元)年までに合計10座の溶鉱炉を完成させました。 しかし、日立鉱山が発展する一方で、排出される煙の量が増加。周辺地域の農作物や草木が枯れるなど、銅鉱山の技術的宿命であった煙害が発生しました。 周辺住民に対する補償は、会社の誠意ある対応によって初めは順調でしたが、入四間(いりしけん)など、製錬所に近い集落における被害は深刻を極めました。
 日立鉱山の庶務課長であった角 弥太郎(かど やたろう)は、煙害などの問題を地元とともに解決する組織である地所係を設置しました。 さらに、1908(明治41)年、伊豆大島の噴煙地帯にオオシマザクラが自生することに着目した角は、鉱山の社宅周辺でオオシマザクラの試験植栽を行いました。 また、試験研究機関として、1909(明治42)年に農事試験場を設置しました。この試験場は、煙と植物の間の因果関係を探り、適正な補償に役立てるとともに、優秀な耐煙性植物の開発や苗木の育成などに大きな役割を果たしました。 (写真は村松村(現東海村)の農事試験場)
 一方、久原は高い煙突により煙を高空へ拡散させることを考えます。 久原は火山が高く煙を噴いてもさほど煙害をもたらさないことと、日立鉱山の前に携わった小坂鉱山での経験から、煙突を高くすれば、悪天候の場合を除いて、煙はほぼ地面に降りることなく空中に拡散すると確信していました。 しかし当時、煙害を軽減する最良の方策は、「煙をできるだけ希釈し、低い煙突から排出して、狭い範囲にとどめること」であると、学者・政府・業界の全てが信じていました。久原は、部下の反対論を退け、政府を説得し、「日本の鉱業発達のための一試験台」として、大煙突の建設に踏み切りました。 1914(大正3)年12月20日、当時世界一の高さである「155.7メートルの大煙突」が完成しました。 翌年3月、大空に煙が吐き出されると、製錬所周辺にたれこめていた煙が消え、これを目にした角は後に「手の舞ひ足の踏むところを知らぬ喜び」と感激を表現しています。その後、大煙突と下記制限溶鉱の対策があいまって、煙害は激減しました。(写真は建設中の大煙突)
農事試験場では、煙害に強い樹木の研究が続けられ、オオシマザクラなどの苗木育成にも成功していました。1914(大正3)年に農事試験場で栽培したオオシマザクラの苗木は、約120万本と報告されています。 大煙突建設によって煙害の状況が一変すると、角はただちに自然環境を回復させるために、オオシマザクラ、ヤシャブシ、スギ、ヒノキ、クロマツなどの植林を開始しました。およそ18年にわたる植林の面積は延べ1,200町歩(約1,190ヘクタール)に達し、植えられた苗木は、500万本を超えます。そのうちオオシマザクラの植林面積は合計595町歩と報告され、260万本が植林されたと推測されます。 日立鉱山による植林とともに、周辺地域の希望者に対する苗木の無償配布も大規模に行われました。1915(大正4)年度の日立村ほか17か村に対する29万本の配布をはじめ、1937(昭和12)年までの23年間に、約500万本の無償配布が行われました。そのうちオオシマザクラの苗木は72万本におよびます。 260万本のオオシマザクラっていったいどれくらい・・・  およそ1キロメートルの道のりにソメイヨシノが約120本植えられている平和通りで換算すると・・・。 2,600,000÷120≒21,666.66666… 平和通りの約21,700倍、つまり距離にして約21,700キロメートルになります。 これは日立市からアメリカのニューヨークまで(10,714キロメートル:Google調べ)を往復できてしまう距離なのです!
 オオシマザクラの苗木がうまく育つようになると、農事試験場の担当者は、この苗木にソメイヨシノの苗を接ぎ木して、大量の苗木を作りました。角はこの桜の美しさに着目し、1917(大正6)年頃、社宅や学校、道路、鉱山電車線路(大雄院〜現在の日立駅付近)沿いなどに約2,000本の桜を植えさせ、これが市内の桜の原点となりました。 日立市の桜は、その美しさの背景に、地域の煙害克服の歴史と、環境回復への悲願のもとに懸命に努力を重ねた人々の歴史が秘められているのです。(写真はオオシマザクラ)
|
||||||||||||||||||||||
 |
鉱毒水騒ぎで経営が安定していなかった赤沢銅山を1905(明治38)年に買い受け、日立鉱山として創業。新しい技術を導入して、短期間で四大銅山の一つに数えられるまでに発展させた。煙害問題が表面化し一時は経営の重荷になったが、1914(大正3)年の大煙突築造、気象状況により操業を調節する対策などでこれを見事に乗り切った。 |
 |
新田次郎の小説『ある町の高い煙突』の主人公のモデル。1911(明治44)年、23歳という若さで、入四間の住民代表「入四間煙害対策委員長」となる。補償交渉にあたり、被害の実態を調査・研究した上で要求案を提出、また鉱山側とともに被害の実測や農業技術向上に積極的に協働するなど、公平かつ平和的な解決に奔走した。 |
 |
日立鉱山側の煙害対策の中心人物。日立に着任する前、小坂鉱山で煙害を経験。自分の使命は煙害問題の解決にあると覚悟していた。「煙害による損害は、鉱業主が進んで賠償の責を果たさなければならぬ」という基本方針を立て、地元との共存共栄を理想として交渉にのぞみ、被害者側との信頼関係と交渉のルールを確立した。 |

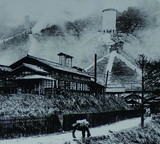

 新田次郎氏の小説『ある町の高い煙突』の映画化が、今年の年末から来年年明け頃の公開を目指して進められています。
新田次郎氏の小説『ある町の高い煙突』の映画化が、今年の年末から来年年明け頃の公開を目指して進められています。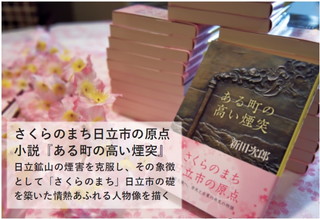





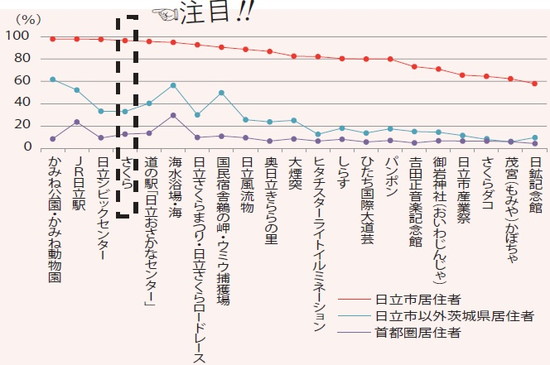
| 日時 | 4月14日(土曜日) 8時〜 *雨天中止 |
| 内容 |
Aコース=鞍掛山〜神峰山(往復)
*先着50人Bコース=鞍掛山〜神峰山〜御岩神社(御岩神社からは路線バスを利用) *ジオネット日立による「煙害と桜の歴史」などの解説付き。 持ち物=昼食、飲み物、雨具など(動きやすい服装、靴で参加を) |
| 参加料 | 100円(保険代) |
| 日時 | 4月14日(土曜日) 14時〜 *荒天中止 |
| 内容 |
コース=久慈漁港〜日立沖〜久慈漁港
*先着50人持ち物=防寒着、雨具など |
| 参加料 | 1,500円(保険代など) |
| 申し込み |
(1)(2)とも、3月12日(月曜日)の10時から、申込書(日立市観光物産協会のホームページからダウンロードできます)に必要事項を記入し、
ファックスで、日立市観光物産協会 ファックス 0294-24-7980へ |
| 問合せ | 日立市観光物産協会 電話番号 0294-24-7978 |






 |
|
 |  |
映画は来春全国で公開予定です |
|