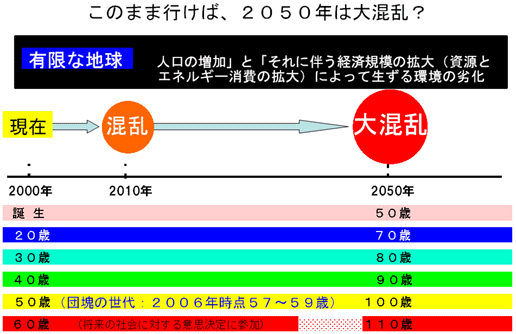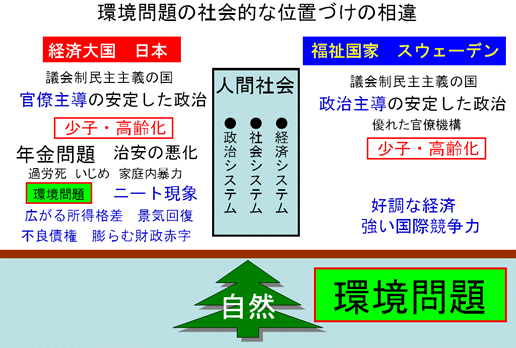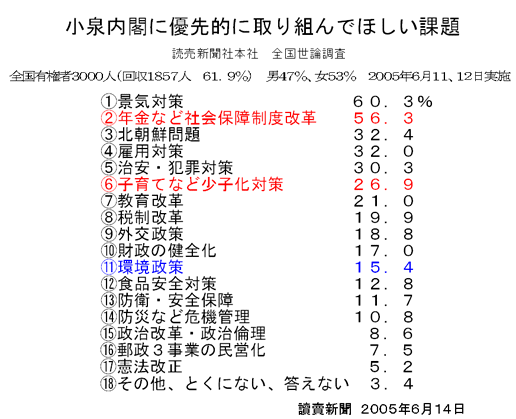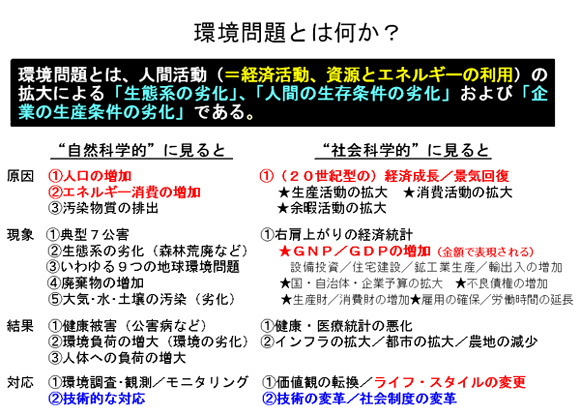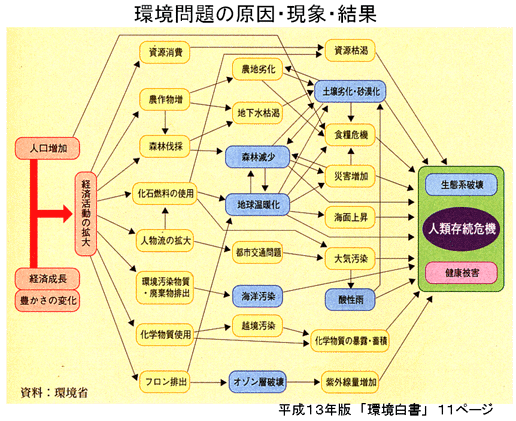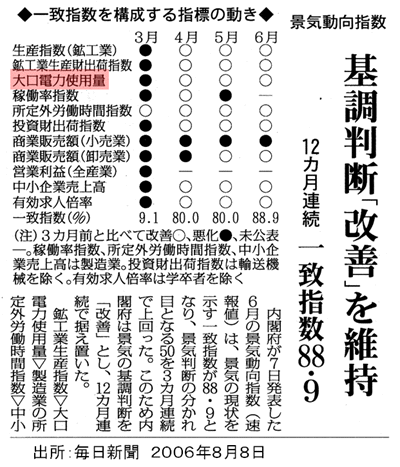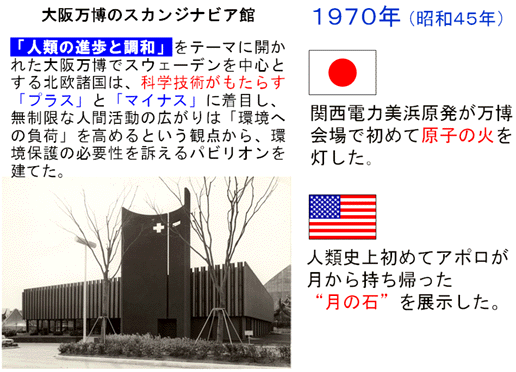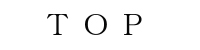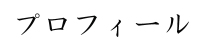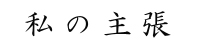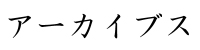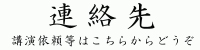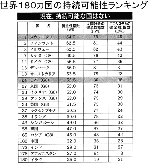私の環境論では、環境問題の解決とは金額で表示される「経済成長(GDPの成長)」をとめるのではなく、「技術開発の変革」と「社会制度の変革」によって資源・エネルギーの成長を抑え、20世紀の大量生産・大量消費・大量廃棄に象徴される「持続不可能な社会」を、21世紀の安心と安全な希望のある「持続可能な社会」に転換することを意味する。
□20世紀の経済成長は「資源・エネルギーの消費拡大」だったが、21世紀型の経済成長は資源・エネルギーの成長を抑えて達成しなければならない。
|
□
93年の「環境基本法」の制定
日本で「環境基本法」が制定されたのは、国連環境計画(UNEP)の「世界環境報告1972~92」が発表された翌年の93年でした。それから10年後の2003年9月12日付の朝日新聞は、「鈴木環境相は12日の閣議後記者会見で、公害対策を中心とした環境基本法を、積極的な環境の再生と改善のための枠組みに転換することを視野に入れた検討を開始する考えを明らかにした」と報じています。
このことは13年前、私がスウェーデンの環境政策の専門家として、衆議院環境委員会中央公聴会に公述人として招かれたときに指摘したとおり、環境基本法が現実の変化に対応できない不十分な法律であったことを示唆するものだと思います。
1993年5月13日、「環境基本法案等に関する衆議院環境委員会中央公聴会」に出席を求められた私は、この法案について、つぎのような趣旨の意見を述べました。
この法案はきわめて不十分である。新法をつくるよりも先にすべきは、行政の縦割構造にメスを入れることである。この新法は「公害対策基本法」に置き換わるが、公害対策基本法のもとでつくられた「大気汚染防止法」や「水質汚濁防止法」などはそのまま残るので、行政の許認可の根拠法は変わらない。この法案の最大の欠陥は、他省庁がかかえる開発志向型の法律群(たとえば、リゾート法、都市計画法、国土利用計画法など)にほとんど影響しない点にある。
今日の環境問題を招いているのは、数多くの開発志向型の法律に基づく経済活動の拡大である。「審議の上、速やかに可決されることを期待する」とあるので、私は反対である。
日本とスウェーデンの環境問題に対する現在の「認識の相違」や「対応の相違」は21世紀初頭には「決定的な相違」となってあらわれてくるだろう。
詳細はhttp://www.maroon.dti.ne.jp/backcast/archives/19930513.pdfを参照。
|
あれから13年たった2006年、「環境問題」に対する日本とスウェーデンの考え方の相違は、当時よりもさらにはっきりしてきました。両国の間には、環境問題に対する認識や行動に20年以上の開きがあるといっても過言ではないでしょう。
□
「環境問題」に対する社会的な位置づけの相違
私の環境論から見た日本とスウェーデンの「環境問題の社会的な位置づけ」の相違を下図に示します。
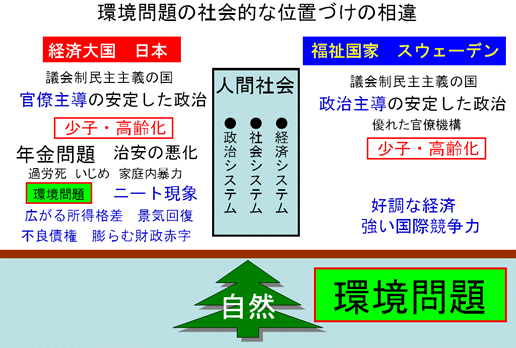
日本では環境問題を、人間社会に起こる数多くの困った問題の一つとして理解してきたので、つねに環境問題よりも年金問題や景気回復、不良債権の処理といった経済・社会問題(図の左中に例示した社会現象)のほうが優先されてきました。一方、スウェーデンでは環境問題を、人間社会を支えている「自然」に生じた大問題(図の右下)と考えてきました。ですから、人間を大切にする「福祉国家」のままでは環境問題には耐えられないことに気づいたのです。そこで、人間を大切にする「福祉国家」を、人間と環境の両方を大切にする「緑の福祉国家」へ転換していこうとしているのです。
スウェーデンでは、ここに例示した日本の経済・社会問題はほとんど問題にならないか、あるいはすでに解決ずみといってよいでしょう。
日本の「環境問題」に対する社会的な位置づけは、2005年6月に読売新聞社が行なった世論調査「小泉内閣に優先的に取り組んでほしい課題は何か(複数回答)」という問いに対する回答結果からも示唆されます。
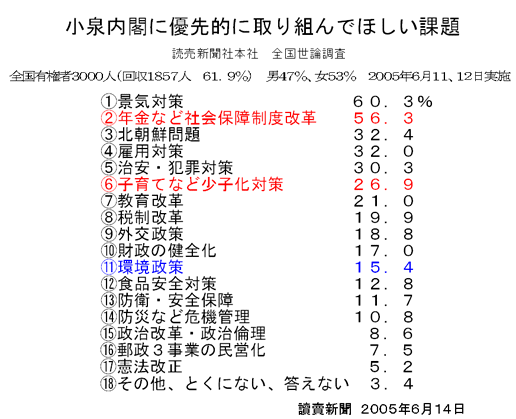
政治が決めた「これまでの50年」:「最貧国」から「福祉国家」へ
100年以上前、日本の明治20年代中頃、スウェーデンはヨーロッパで最も貧しい国でした。あまりにも貧しいがゆえに、当時の人口350万人うち3分の1くらいが移民として米国に渡ったと言われています。
スウェーデンは自然条件が厳しかったうえに、国内で石油や石炭、天然ガスなどの化石燃料が乏しく(この状況は現在も同じです)、ほかのヨーロッパ諸国に比べて工業化が遅れたからです。この50年間でスウェーデンは、ヨーロッパの「最貧国」から現在のような「福祉国家」になりました。
1889年に結成されたスウェーデンの社民党は1932年に政権に就いて以来、「福祉国家の実現」を国のビジョンとして掲げ、76年の連立政権(中央党・自由党・保守党の中道・保守連立内閣)誕生までの44年間、長期単独政権を維持してきました。長期単独政権を維持するなかで、絶対多数(国会の議席の過半数の確保)は1回だけで、あとは比較多数のままで、連立政権を組むこともなく、単独政権を守りつづけました。スウェーデンの経済発展は社民党の44年にわたる長期単独政権の結果によるものでした。
一方、日本の経済発展は、自民党の38年にわたる長期単独政権のもとになされたものです。要約すれば、社民党の44年にわたる長期単独政権が20世紀の「福祉国家スウェーデン」を、自民党の38年にわたる長期単独政権が20世紀の「経済大国日本」をつくりあげたと言えます。
□
政治が決める「これからの50年」:「福祉国家」から「緑の福祉国家」へ
環境問題への対応で世界の最先端を行くスウェーデンの環境戦略を特徴づけるのは「環境問題の明確な社会的位置づけ」ができていること、そして「政治のリーダーシップ」です。まず政治家が「ビジョン」を掲げ、そのビジョンを実現するために「整合性がある包括的で柔軟な法律あるいはガイドライン」と「政策」を国会で審議し、可決したうえで、政策目標達成の手段として法律を活用していること、さらに政策目標達成の進捗状況を国会でフォローしながら、たえず見直しが行なわれている点にあります。
人間を中心に考えれば「少子高齢化問題」および「環境問題」などの「将来不安」こそ、政治の力で解消すべき最大の対象であることは間違いありません。
2001年10月、国際自然保護連合(IUCN)は世界180カ国の「国家の持続可能性」ランキングを公表しました。この調査でスウェーデンは「人間社会の健全性」と「エコシステムの健全性」のバランスが最もよくとれていると評価され、1位にランクされました。日本は24位、米国は27位。しかし、この時点で「持続可能性あり」と判断された国は皆無でした。
このような未来予測を前にして、これからの50年、みなさんは「これまでどおりの経済成長の維持あるいは拡大」を求めるのでしょうか、それとも、「持続可能な社会への転換」を求めるのでしょうか。
日本の首相の施政方針演説では前者を、スウェーデンの首相の施政方針演説では後者をめざすことが、はっきりと方向づけられています。小泉純一郎首相は2002年2月4日の施政方針演説で、「改革なくして成長なし」と語り、「持続的な経済成長」の必要性を明示しました。
このように、小泉首相のビジョン(政治目標)は「持続的な経済成長」(つまり、20世紀の経済社会の延長上にある「経済の持続的拡大」)です。その意味で、21世紀初頭に発足した小泉・連立内閣は「行き詰まった20世紀経済を再生するための内閣だった」と言えるでしょう。
2001年4月の小泉・連立内閣発足以来、政府の「経済財政白書」のサブタイトルが2001年の「改革なくして成長なし」に始まって、2005年が「改革なくして成長なし Ⅴ」であったことからも、この内閣が従来の経済拡大路線を着実に踏襲していることは明らかです。一方、スウェーデンのペーション首相は96年9月17日の施政方針演説で「緑の福祉国家への転換」を21世紀前半のビジョンとして掲げました。
これからの50年の両国の将来像は、現時点ではきわめて対照的です。大変不思議なことに、日本では、「少子・高齢化問題」は国民の関心が高まり政治の課題となってきましたが、市場経済社会を揺るがす21世紀最大の問題である「環境問題」は、国政レベルの選挙の争点にもなりません。この現実と、両国の政治家や国民の意識の相違は何を意味しているのでしょうか。スウェーデン人と日本人の視点はどこがどう違うのでしょうか。
□
スウェーデンを軽視する日本
スウェーデンにできて日本にできない問題に直面すると、「スウェーデンは人口900万だが、日本は1億2000万、それに経済規模も違うし……」という反応を示す識者が、日本にはかなり多くいます。
900万人と1億2000万人の人口の差、1%と16%の世界経済に占める割合の差は、たしかにスウェーデンが日本に比べれば、人口や経済の規模でまぎれもない小国であることを示しています。「両国の共通の問題」を同じ方針や手段で解決しようとするときには、人口が少ない小国のほうが有利なのは当然です。しかし、日本がいまだ完全に処理しきれていない不良債権問題がスウェーデンでわずか1年で解決したのは、「スピード」、「政党間の協力」、「透明性」など明らかに日本にはなかった発想や方法論によるものです。
このような基礎的な分析なしに、人口規模が違いすぎるとか経済規模が異なるという表面的な言い訳は成り立ちません。スウェーデンをすべてまねしよう、という議論に対してなら、「人口や経済規模にこれだけ差があるのだから、そっくりまねることはできない」というのは正しい判断だと思います。
しかし私は、世界に共通する環境問題、エネルギー問題、そのほかの経済・社会問題に対して、スウェーデンがほかの先進工業国とは一味違う先進性のある取り組みを展開するのは、人口の大小や経済規模の違いというよりむしろ、「国民の意識」と「民主主義の成熟度」の問題だと思います。
□私ももちろんそうだが、「スウェーデンに学ぼう」と提案している論者が主張したいのは、すぐれた先見性と資質をそなえた国が具体化した「概念」、「ルール」、「制度」、「技術」などの合理性を、さまざまな角度から徹底的かつ真剣に検証することによって、将来の日本の社会の方向性を見極めよう、ということである。
そして、「合理性がある、好ましい」と判断した事例に対しては、日本の現状からその方向に向かうにはどうすればよいかを考えることである。
|
新スウェーデン・モデル「緑の福祉国家」
スウェーデンは米国と同じように、日本に比べると個人の自立性が高く、自己選択、自己決定、自己責任の意識が強い国です。20世紀のスウェーデンは、国や自治体のような共同体の公的な力や、労働組合のような組織の力を通して、個人では解決できないさまざまな社会問題を解決してきたのに対し、米国は個人の力による解決に重きを置いてきました。米国は個人の力に根ざした競争社会であるのに対して、スウェーデンは自立した個人による協力社会「緑の福祉国家」をめざしています。
次の図は「現在の福祉国家」を「緑の福祉国家」に転換する具体的な枠組みを示したものです。

95年1月1日に、スウェーデンはEUに加盟しました。EUに加盟したスウェーデンの理念と行動はEUの環境戦略をリードし、その経験は2000年3月のEUの「米国に対抗する新しい経済モデル策定の合意」の基礎に生かされています。
2000年1月に提案された「第6次EU環境行動計画案」は、2001年から2010年までの10年間のEUの環境戦略を方向づけるものですが、その内容は、スウェーデンが88年に策定した「90年代の環境政策」と題する国のガイドラインに、きわめて類似しています。スウェーデンは環境分野でEUの10年先を行く、といっても過言ではありません。
ですから、いま、スウェーデンが国家目標として掲げている「緑の福祉国家への転換」は、「旧スウェーデン・モデル」が賛否両論はあったものの、世界の福祉政策にとってのモデルであったのと同じように、21世紀前半の「持続可能な社会のあり方」を先駆的に提案するものと言ってよいでしょう。
希望の船出
96年9月17日、乗員・乗客884万人を乗せたスウェーデン号は、「21世紀の安心と安全と希望」を求めて、周到な準備のもとに目的地である「緑の福祉国家」へ向けて出港し、現在、順調に航行を続けています。
航行中、予期せぬ難問に遭遇し、場合によってはグローバル化の荒波に呑み込まれ、沈没してしまうかもしれませんが、順調に行けば、目的地に到着するのは2025年頃とされています。
これまで述べてきたように、スウェーデン政府は2020年頃までに「緑の福祉国家を実現する」という大きなビジョンを持っています。スウェーデンは93年から現在に至るまで好調な経済を維持しながら、主な環境問題を解決した新しい社会である「緑の福祉国家」を次世代に引き渡すことをめざして、力強い一歩を踏み出したところです。
このビジョンの実現を加速する目的で2005年1月1日に発足した「持続可能な開発省」のホームページに「緑の福祉国家」についての記述がありますので、その要旨を記しておきます。ご興味のある方は直接、下記のアドレスにアクセスしてみてください。
※2006年9月のスウェーデンの政権交代に伴い下記のアドレスはリンクが切れております。
「緑の福祉国家」というビジョンの実現のために、政府は新しい技術を駆使し、新しい建築・建設を行ない、新しい社会にふさわしい社会・経済的な計画を立て、そして積極的なエネルギー・環境政策を追求しています。このビジョンの最終目標は現行社会の資源利用をいっそう高めて、技術革新や経済を促進させ、福祉を前進させてスウェーデンを近代化することです。
緑の福祉国家の実現によって、スウェーデンは「社会正義をともなった良好な経済発展」と「環境保護」を調和させることができるでしょう。現在を生きる人々と将来世代のために。国際社会を見渡したとき、スウェーデンは発展の最先端に位置しているので、現在強い経済成長を経験している国々に、「エコロジカルに持続可能な社会の開発」の考えを伝える立場にいます。
現行社会の近代化は、地球の資源がすべての人々にとって十分であることを保障する近代化でなければなりません。
参照 http://www.maroon.dti.ne.jp/backcast/archives/MOSD.pdf
http://www.sweden.gov.se/sb/d/2066
(↑現在の「環境省」のホームページ)
|
|