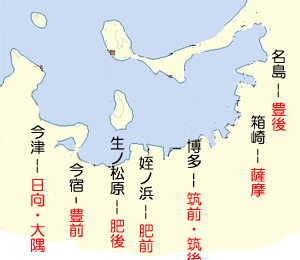13世紀初め、チンギス・ハンはアジアからヨーロッパにまたがるモンゴル
帝国をうち建て、その孫の皇帝フビライは国名を「元」と改め、日本に使者
をおくってきましたが、鎌倉幕府はこれに応じなかった。
1274年(文永11)蒙古の襲来を受けた鎌倉幕府は、1276年(建治2)
に博多湾の海岸線に石築地(いしついじ)を築いて再度の来襲に備えた。
防塁は、博多湾の今津から香椎まで20kmにわたって築かれているが、
今津は大隅国と日向国、今宿は豊前国、生の松原は肥後国、姪浜は
肥前国、博多は筑前国と筑後国、箱崎は薩摩国そして香椎は豊後国と
九州9か国の分担を割りあて、所領面積一反(10アール)につき1尺
(30センチ)、(50万石であれば約3km)一斉に工事にかかるように命
じている。約30kmに渡り建造
3月から8月までのわずか6か月で完成させる計画となっていた。


これまでの発掘調査で、それぞれの地区によって築き方が異なつて
いることがわかってきた。今津地区では、高さ3m、上の幅2m、下の幅
3mの台形に築いているが、玄武岩のところはすべて石だけであるのに
対して、花崗岩の部分は前と後を積み上げてその中に砂を入れている。
玄武岩と花崗岩が交互に連続して続いているのは、所領(領地の広さ)
に応じて築いた工事区間の長さを反映している。
生の松原は石積みの幅が1.5mと狭いが、後を粘土で補強している。
西側は花崗岩で、東側は砂岩で築いているが、その接点が肥後国と肥前
国の分担の境界を示しているのではないかと考えられている。
また防塁の前にある別な石積みは、防塁が少し埋まってからのもので、
修理のために築いたことを示している。
1281年(弘安4)の2回目の蒙古襲来では蒙古軍は上陸していないので、
元寇防塁は大きな役割を果たしたと考えられる。
元寇防塁は、昭和6年国の史跡に指定さた。