

島津軍との合戦の戦死者 1万人
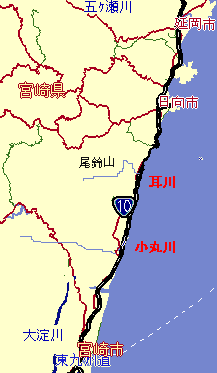 |
拡大 | |||
 |
昭和8年2月国史蹟名称天然記念物(文部省指定) 天正6年11月島津氏と大友氏による壮絶な戦いが高城川(現・小丸川)を挟み行われた。西の関ヶ原と言われる九州を2分する高城川の合戦である、高城川から耳川(日向市)までの両軍の戦死者の数2万人、この戦いに勝利した《島津家16代島津義久》敵味方の区別なく葬り供養する様に《高城主・山田新助有信》に命じた。 命を受けた山田新助有信は手厚く葬ると共に、島津の菩提寺である福昌寺と周辺の寺から300余名の僧侶を呼び寄せ大施餓鬼の法要を行い卒塔婆を建て(豊後塚)と名づけ、この合戦で敢得なく散華した両軍の戦没者の霊を弔った。 天正12年高城川の合戦から7年目に、島津義久は再び豊後塚に7回忌の大施餓鬼を行うように、高城主・山田新助有信に命じた、命を受けた山田新助有信は「六地蔵塔」の建立を計画、天正13年2月彼岸日に六地蔵が刻まれた供養塔を建てた。これが後に、土地の人々がよんでいる【宗麟原供養塔】である。 ※この竿石には「本来無東西 何処有南北 迷故三界城 悟故十方空」と刻まれている |
|||
| 天正6年9月(1578年)大友宗麟は日向に切支丹国を築くべく、第二次日向国に向けて 出兵した。同年臼杵城を出発し、日向国延岡の務志賀(現延岡市無鹿)に本陣を置いた。 時に宗麟49歳。今回の出兵に家臣団のなかでも反対の声が多かった。 この度の相手が鎌倉以来の名門島津氏が直接の相手であり、遠征の隙をねらって 中国の毛利氏が再び九州へ侵攻してくることや、肥前(佐賀)の竜造寺氏がそれに 呼応して、攻めてくることが懸念されたからである。 十月下旬、四万三千の大友軍は延岡より宮崎平野を南下した。 十一月十日耳川の合戦では島津軍は財部城に引いた。 この頃島津軍の大軍も薩摩を出発。大友軍はまず小丸川沿いにある高城(現児湯郡 本城町)に攻撃をしかけた。高城は山田有信がわずか五百の兵で城を守っていた。 しかしながら、城の守りは固く大友軍は容易に落とすことができなかった。 そこに島津本隊軍が到着し、ここに小丸川を挟み両軍は対峙し、激しい戦いの火蓋 が切って落とされた。そこを高城に籠る城兵に背後を突かれ、加えて指揮の乱れで 大友軍は総くずれとなり、この高城河原での戦で大友軍は主な武将をはじめ三千の 兵を失うことになった。大友軍は耳川まで後退するに島津軍の勢いに圧倒され、 二万の兵が戦死するありさまであった。安東幸秀は傷ついた一族と共に、後詰めの 大役を仰せ付かり、奮迅の戦い振りで寄せ来る島津軍を追い払い、大友軍の日向 脱出を助けた。小丸川から耳川河原までの七里(約28km)の児湯平原一帯は 両軍の屍(しかばね)が累々としていたという。遮蔽物が無い平坦な地形が劣勢の 大友軍には尚更不利であった。 これを耳川の合戦といい、安東一族から出陣したうち六名がこの地で討死した。 この戦を境に大友の力は急速に落ちて言った。 |
||||
|
安東幸秀行状記には「天正六年八月中旬大友宗麟より豊後、肥前、筑前の軍勢を 催し日向国ご発足のお触れあり。この時幸秀は一族十余人の首領としてお供に 従った。斯くて豊後勢は日向国務志賀に着陣、ここに宗麟公御本陣を据えた。 諸軍勢の手分けあり安東氏は高城に向かう。高城に押し寄せ、数日手立てを尽く しければ、城主島津中務大輔も籠城危難と見えるところに、島津太夫義久の 大隈、薩摩両国の勢を催し、日向に押し入る旨、宗麟公聞き、豊後勢耳川に引き 陣を張った。豊後勢耳川を渡りて合戦の時、宗麟公田原紹忍の意趣を窺い、 老攻の軍配を御用なきにより味方悉く敗北して、ご一族、外様勇将数を尽くして 討死す。幸秀は小佐井左京、摂津式部、摂津形部と四人一所になり戦いしが、 味方総敗軍となりる故、心ならずも諸軍勢と共に落ち行く所に、勝ち誇りたる 薩摩歩卒二三十煙嵐を巻いて追いかける。 四人望む所と返し、合わせ馬より下立てに槍引っ提げ、無二無三に突き立つ れば追い来る軍兵大半討死し、残りし卒は四方に逃げ散り、敢えて近付く ものもなし。 心静かに耳川を渡り御本陣に落ち付けり」とある。 |
||||
| 筑前の立花道雪はこの戦に参陣していなかったのは、豊後の背後の脅威、 毛利氏の備えのために、筑前に在陣して牽制していたのであって、決して日向出陣 を拒んだ訳ではない。これは豊後の宗麟の側近であった吉岡宗観、臼杵鑑速 が亡くなり、田原紹忍が側近として仕えていたが、「大友家ノ依頼トモナルベキ 道雪ヲ六箇敷者ニ思ヒ中国大切ノ押トテ」といって、援軍要請をしなかった。 これらの「軍儀で吉弘鑑理は薩摩との戦を控えるべきと進言し、もし出陣するので あれば道雪を呼ぶべきと言うも通らず、斉藤鎮実も鑑理に賛成し、席を立った。 他の忠臣も心元無い気持ちであった。」と立花家の十時摂津守が藤川徹斉に 軍話として云うとある。 |
||||
| 安東氏は戸次鎮連の元で奮迅 | |||
| 安東式部少輔 | 他安東家6名 | ||
| 以下は佐伯宗天の指揮の元で討ち死にした武士 | |||
| 佐伯 掃部助 | 長田 左京亮 | 塩月 内記 | 本越 右近 |
| 泥谷 監物 | 柴田 園書 | 塩月 大学 | 柴田 惣左衛門 |
| 柴田 左吉 | 柴田 三左衛門 | 泥谷 喜左衛門 | 柴田 甚助 |
| 泥谷 伊予守 | 泥谷 内膳 | 泥谷 雅楽助 | 泥谷 右京 |
| 泥谷 五兵衛 | 佐田 民部 | 佐田 弥八郎 | 佐田 五左衛門 |
| 塩月 源左衛門 | 神志那 左近 | 塩月 弥兵衛 | 広末 市之助 |
| 河原 大蔵 | 菅 弥兵衛 | 広末 興左衛門 | 柏江原 阿弥 |
| 龍護寺 | 河俣寺 | 宗得 | かいそく坊 |
| 阿南 猿之介 | 阿南 半介 | 城弥 四郎 | 城弥 九郎 |
| 深田 十郎兵衛 | 深田 又四郎 | 泥谷 勘左衛門 | 長田 将監 |
| 橋迫 右馬介 | 戸敷 新次郎 | 橋迫 円書 | 戸敷 興四郎 |
| 森田 三介 | 森田 善四郎 | 木屋 勘解由 | 高司 次郎左衛門 |
| 佐用 玄蕃 | 佐用 弥十郎 | 宮脇 藤七兵衛 | 泥谷 三郎 |
| 矢野 興一兵衛 | 寺田 相模 | 塩月 刑部 | 後藤 出羽守 |
| 塩月 勘解由 | 岡倍 市之助 | 河邊 六郎 | 河邊 勘六 |
| 臼井 隼人佐 | 河邊 大造 | 盛岡 大蔵 | 由布 右馬介 |
| 盛岡 蔵人介 | 平井 内記 | 飛田 宮内 | 盛岡 左馬之丞 |
| 安藤 藤内兵衛 | 盛岡 藤左衛門 | 河邊 七郎 | 安藤 織部 |
| 中野 主税介 | 松浦 嶋之介 | 御手洗 玄蕃 | 高木 織部 |
| 才田 興三兵衛 | 寺嶋 大介 | 末松 左近 | 津井 左馬介 |
| 神毛 蔵人 | 矢野 左介 | 後藤 新次郎 | 吉良 大介 |
| 才野 市兵衛 | 大津 喜兵衛 | 高畑 左京亮 | 宮脇 宮内 |
| 塩月 大蔵 | 江藤 大和守 | 泥谷 十兵衛 | 津井 舎人佐 |
| 佐井 左介 | 長田 源五兵衛 | 狩野 左京亮 | 狩野 源三郎 |
| 染屋 新十郎 | 中野 藤十郎 | 染屋 平十郎 | 谷口 興四郎 |
| 出納 新兵衛 | 古市 又四郎 | 古市 四郎五郎 | 古市 孫十郎 |
| 古市 又次郎 | 古市 興五郎 | 古市 新兵衛 | 古市 又左衛門 |
| 古市 孫左衛門 | 古市 忠左衛門 | 古市 四郎兵衛 | 古市 藤十郎 |
| 小倉 惣左衛門 | 坊万力 | 池邊 吉左衛門 | 高畑 興五郎 |
| 上岡 之大力 | 藤原 徳力 | 兵士 市大夫 | 岡 宮之介 |